コヨバ(エバーフレッシュ)の育て方

育てる環境について
コヨバ(エバーフレッシュ)は、熱帯の植物ですので、日光にあたるのを好みます。耐陰性もありますが、日光にあてないで栽培を続けると葉の色が変色したり、落葉したりしてしまいます。すぐに、枯れてしまうということはありませんが、なるべく、日光をあててあげることをおすすめします。
春から秋など日差しが多く、暖かい季節には日光にあてましょう。ただし、日差しが強すぎると葉が開かないこともありますので、直射日光は避けたほうがよいでしょう。また、耐寒性にいは弱い品種となっていますので、冬場は室内に置き、できるだけ日光が当たる場所がよいとされています。
屋外で栽培をしている場合には、最低気温が15度を下回ったら、屋内に入れましょう。羽状複葉の葉をとなっていますので、とてもボリューム感のある植物です。それが魅力的な観葉植物ですが、葉が生い茂りすぎた、木の高さが高くなりすぎたと感じた場合には、迷わず剪定しましょう。
剪定することで一定の高さと幅を保つことができます。剪定の他にはとくに栽培中の作業は必要ありません。あるとすれば、落葉した葉を取り除くくらいです。育て方としてはとても楽な植物と言えます。
観葉植物を気軽に育てたい人におすすめの植物です。また、春から秋には丸い花が咲きます。花を咲かせたい場合には、木漏れ日のような日差しがあたる場所で栽培しましょう。花の咲いた後には、実がなりますので、花と共に実がなるのも楽しむのもおすすめです。
種付けや水やり、肥料について
コヨバ(エバーフレッシュ)の種付けは5月から6月が最適です。種付けをしたい場合には、ホームセンターなどで苗かタネを購入して、この時期におこないましょう。苗の場合には、すぐに観葉植物として楽しむことが可能です。
水やりについては、生育期である5月から9月には鉢の土の表面が乾いてきたらたっぷりとあげます。夏は水をよく吸い乾きやすいので、毎日水やりをすることになります。土の乾燥については常にチェックをする必要があります。コヨバ(エバーフレッシュ)は乾燥を嫌う観葉植物となっていますので、
土が乾き過ぎないようにしましょう。また、空中の湿度を好みますので、霧吹きなどで、葉に水分を与えます。霧吹きによる水やりは年間を通して必要な作業となります。秋になり寒くなってくると、水を吸わなくなってきます。水を吸わなくなってくるのは気温が15度を下回る頃になります。
鉢の土の乾燥もしにくくなりますので、水やりの頻度が減ってきます。秋から冬にかけては、土が乾燥したら水をあげましょう。また、乾燥させすぎると日中でも葉が開かなくなります。葉が開いていると葉から水分が蒸発するため、水分が不足すると閉じてしまいます。
そのような状態になったら、早めに水をあげる必要があります。肥料については、花を咲かせたい場合には、4月から10月にかけて花用の緩効性化成肥料を施します。花を咲かせない場合には、観葉植物用の肥料を使用しましょう。冬については、肥料は必要ありません。
増やし方や害虫について
ふやし方は2種類あります。まずはタネまきで増やす方法ですが、時期は5月から6月になります。コヨバ(エバーフレッシュ)は花を咲かせると果実がなりますので、その果実を利用します。まず、よく熟した果実の皮をむき、中に入っているタネを取り出します。
取り出したばかりのタネの周りはヌルヌルしています。ヌルヌルがなくなるまでよく水で洗いましょう。洗ったタネを土に植えます。発芽には1~2ヶ月かかりますので、気長に待つ必要があります。発芽し、小羽が完全に開いたら、移植します。次に、さし木でふやす方法ですが、時期は5月から8月になります。
栽培中の作業として育ちすぎた枝を剪定しますので、その剪定した枝を利用するのが便利です。元気そうな枝を選んで10~15cmに切り分けて、下の方の葉は切り落とします。残った葉は半分にカットしましょう。用意ができたら、挿し穂の半分を赤玉土にさし、明るい日陰で栽培します。
この際、さし床が乾燥しないように注意しましょう。2~3ヶ月で初根しますが、すぐには移植しないでさらに栽培し続けます。そして、さし床に根がはったら移植します。栽培中に注意が必要な病気は炭そ病になります。春から秋に発生しやすくなっています。
発生を確認したらすぐにその部分を除去します。また、注意が必要が害虫はカイガラムシとハダニになります。時期を問わず、いつでも発生しますので、見つけたらすぐに駆除しましょう。カイガラムシについては発見したら、駆除後、スミチオンなどを散布しておくことをおすすめします。
コヨバ(エバーフレッシュ)の歴史
マメ科コヨバ属の植物である、コヨバ(エバーフレッシュ)は日本においては、原産地である南アメリカのボリビアから沖縄の生産者が輸入したことが栽培の始まりといわれています。日本に原生している植物ではないのです。園芸用に販売するために輸入されたようです。
栽培が始められた当時は、正式な名前が分からず、販売するためにエバーフレッシュという名前をつけました。その名前が現在も使われています。その後正式な学名を探し、類似種のPithecellobium confertum(アカサヤネムノキピトヘケロビウム属)という学名が与えられました。
しかし、よく調べてみると、ボリビア原生のはずが、Pithecellobium confertum(アカサヤネムノキピテケロビウム属)は東南アジア原生ということが分かり他の学名を探すことになりました。学名が違うということがわかり、ニューヨーク植物園がウェブ上に公開している品種から、
Pithecellobium sophorocarpum var. angustifolium(ピテケロビウム属の変種アングスティフォリア)であるということがわかったのです。この品種はボリビア原産であることからほぼ間違いないとされています。
なお、現在は、このピテケロビウム属からコヨバ属に移されています。コヨバ属の植物は南アメリカに12種存在していますが、観賞用に栽培されているのはコヨバ(エバーフレッシュ)のみとなっています。
コヨバ(エバーフレッシュ)の特徴
コヨバ(エバーフレッシュ)はマメ科コヨバ属の植物です。園芸では主に観葉植物として栽培されることが多くなっています。コヨバ属は12種あるのですが、コヨバ・アルボレアの変種アングスティフォリアという品種が観葉植物としてよく栽培されています。
この植物はエバーフレッシュという名前で呼ばれることが多いので、園芸店などで購入する場合には、コヨバではなくエバーフレッシュという名前で探すとよいでしょう。
コヨバ(エバーフレッシュ)は常緑性で日陰でもよく育ちます。
そのため、屋内で緑を見たい方におすすめの観葉植物です。いつでも緑を楽しむことができます。その葉は羽状複葉で、一つの葉に小さな長楕円形の葉がいくつも並んでいます。同じような羽状複葉の植物としてはオジギソウがあります。また、特徴的なのは葉が就眠運動をするという点です。
通常、葉は開いたり閉じたりという変化をしないのですが、この植物の場合、夜になると葉が閉じてしまうのです。そして朝になるとまた開きます。夜になると葉がとじる葉が閉じるのは、夜間に葉から水分が蒸発するのを防ぐためといわれています。
まれに、昼間も葉を閉じることがありますが、これは就眠運動ではなく水分不足のサインです。生息地である南アメリカでは、30mを超す木もありますが、観葉植物として販売されている木の高さは10cm~200cmで低木です。部屋の緑として、屋内にも置くことができるので、このくらいの高さになっているようです。
-

-
ペラルゴニウムの育て方
和名においてアオイと入っていますがアオイの仲間ではありません。フクロソウ科、テンジクアオイ属とされています。よく知られて...
-

-
アザミの仲間の育て方
アザミの仲間の種類は多く、科属はキク科アザミ属です。生息地で言うと、日本に多く見られるのは、日本が原産国であるためです。...
-

-
コウバイの育て方
楽しみ方としても、小さなうちは盆栽などで楽しみ、大きくなってきたら、ガーデニングということで、庭に植えるということもでき...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
ヨルガオの育て方
ヨルガオというものは朝顔の仲間でもあるもので、熱帯アメリカ原産であり寒さに弱いものですので、一年草として扱われているもの...
-

-
ホヤ(サクララン)の育て方
花の名前からラン科、さくらの科であるバラ科のように考えている人もいるかもしれませんが、どちらにも該当しない花になります。...
-

-
シェフレラ・アルボリコラ(Scefflera arboric...
台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低...
-

-
柑橘類(交雑品種)の育て方
柑橘類は遡ること3000万年という、はるか昔の頃から、インド東北部を生息地として存在していたものです。中国においては、4...
-

-
カラスノエンドウの育て方
古くは食用にも好まれていました。カラスノエンドウはマメ科ソラマメ属の植物です。ソラマメや、さやえんどうのような実をつけま...
-

-
アブチロンの育て方
アブチロンはアオイ科の属の一つで、学名はAbutilonです。別名としてウキツリボクやショウジョウカ、チロリアンランプと...




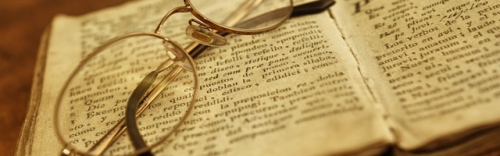





マメ科コヨバ属の植物である、コヨバ(エバーフレッシュ)は日本においては、原産地である南アメリカのボリビアから沖縄の生産者が輸入したことが栽培の始まりといわれています。