ドクダミの育て方

ドクダミの育てる環境について
ドクダミは栽培するのではなく放置しておけばどんどん増えると言う人も多いものですが、ここでは自然に群生するドクダミではなく観賞用としての八重咲き品種、斑入り葉の五色どくだみです。どちらも自然に群生しているものと同じく自制力が強い事、生命力が高いことなどからもそれほど難しい事は有りません。
ラーリーフとして栽培をしたい人も多く、どうやって育てれば良いのか解らない人も多いのです。関東地方などにおいては、植え付け時期は4月頃で、開花となるのは5月の半ばから7月の初旬頃になります。鉢植えによる肥料は植え付けを行った時期から5月の下旬頃に行うのが特徴となります。
育てる環境は幅広い環境に適しているのも特徴となりますが、日向や日陰、乾燥地や湿気が在る場所など関係なく、どこでも栽培が可能な万能の植物と言えます。しかしながら、日陰の湿地と乾燥地とでは成長のバランスは事なるため、育てる環境は何処でも良いと言う事ではありません。
日陰が多くなる湿地の場所では徒長した形で成長をし、乾燥した場所では草丈が低くなり、花つきが悪くなります。日当たりが良い場所は節間が詰まった状態になり、バランスのよい草姿となりますし、花も綺麗に咲いてくれます。
観賞用の斑入り葉などの場合も、環境を変えると特徴となる斑模様が濁るような感じになってしまいますので、日当たりが良い場所で栽培を行う事で斑の分が綺麗に表現できる葉を作り出すことが出来ます。
ドクダミの種付けや水やり、肥料について
植え付けは4月になって行う事になりますが、観賞用のどくだみはこの時期にホームセンターや園芸ショップ、インターネットの通販サイトなどで購入が可能になっています。また、10月になった時点で植え替えを行って上げることになりますが、植え替えを行う時には花つきを良くさせるためにも緩効性化成肥料の置き肥を施してあげます。
尚、この肥料は春時期に行えば良いでしょう。水やりは、庭への地植えの場合は殆ど必要がありませんが、鉢植えの場合は、用土を見て乾いたら、水をたっぷりと与えてあげます。これは極端に用土が乾燥してしまうと、花が咲き難くなってしまうので注意が必要だからなのです。
また、受け皿に水をためて、腰水栽培を行う方法もお勧めです。利用する用土は、一般的に草花用として利用する培養土などで良く、土質についても選ぶことなく育てることが可能になります。尚、ドクダミは良く茂る事からも、
育成を妨げてしまう恐れがあるため、適度な間引きをしていく事は大切です。全体的に太陽の光が十分に注ぎ込ま割れるよう間引きをしてあげて、開花を終えた時は切り戻ししてあげます。このように、特別な世話をしなくても成長をしてくれますが、
綺麗な花を咲かすためには幾つかのポイントを抑えて世話をしてあげることが大切です。斑模様の葉を持つもの、八重咲きのものなどはしっかりと世話をしてあげることで綺麗な花を咲かせたり、濃淡が明確になるまだ模様の葉を作り出します。
ドクダミの増やし方や害虫について
植え付けや植え替えなどについては、冬の厳寒期でなければいつでも行う事は可能です。但し、植え付けや植え替えにおける最適な時期と言うのは4月や10月となりますので、このタイミングを逃さないようにします。また、ドクダミは地下茎を長く伸ばして広がる性質が在りますが、
草むしりをする時などドクダミの地下茎があまりにも長くて途中で切れてしまうと言う経験をされている人も多いものですが、このような性質が在りますので地植えを行う場合などでは場所を考えた上で植え付けを行う事が大切です。
尚、地下茎はどんどん伸びていきますので、広がりを防止する目的で地中に遮る囲いを設けてあげるのも良い方法です。育て方や増やし方と言うのは特別何かをしないといけないと言う事はなく、自生する物などの場合は自然に増えて行きます。
草むしりをして途中で切れてしまった地下茎などでも自然と増えるといいますし、逆に増えてしまうと絶やす事が難しくなるほどの生命力を持ちます。尚、観賞用として人気のある斑入り葉については、先祖返りとなり、一般的な緑葉の芽が出る事もあり、
これについては早目に取り除いておくことがポイントとなります。肥料についても、他の植物違って殆ど上げる必要が無いなどの特徴を持ちますが、植え替えを行う時などは置き肥を施しておく事で花つきが良くなります。尚、害虫については殆ど影響を及ぼすものが付くことは在りませんので特別な防除を行う必要も有りません。
ドクダミの歴史
ドクダミは、ドクダミ科ドクダミ族の多年草であり、ギョウセイソウやジゴクソバ、ドクダメとも呼ばれています。ギョウセイソウと言うのは「魚腥草」、ジゴクソバは「地獄蕎麦」、ドクダメは「毒溜め」と言った中国語で現されており、「魚腥草」は魚の野菜の葉と言う意味を持つベトナム語のザウザプカーやザウジエプカーと同じ意味合いを持つと言います。
ベトナムでは古くから魚料理などの臭みを消す時に使われていると言いますが、日本国内に生息しているものと比べると臭気はそれほど強くはないと言います。また、「魚腥草」は中国語であり「腥」は生臭いと言う意味を持つ言葉ではあるのですが、ドクダミは生臭さを全て取り除くほどの強い臭気を持つ植物でもあるのです。
最近は、ドクダミを栽培して薬草として利用する人もいると言いますが、栽培するといってもそのまま放置しておけば群生すると言う家も多く在ります。歴史の中では、これを薬として利用している時代も有り、現代においても健康茶として有効成分が利用されていたり、傷などの治療薬として利用するケースも有るなど、薬としての有効成分を多く含む植物です。
古くから解毒作用、利尿作用を持つとして十薬の名で薬草として利用されている薬草でもあり、中国の中ではドクダミは家庭薬として常備されているとも言われています。また、生息地は国内においては全国各地であり、南は沖縄県から北は北海道にまで分布をしています。尚、原産国と言うのは東アジア、東南アジアなどになります。
ドクダミの特徴
ドクダミの最大の特徴は強い臭気にあります。また、草むしりをしている時など、ドクダミを抜こうとした時、あまりにも長い根により途中で切れてしまうと言う経験を持つ人も多いかと思われますが、地下茎がとても長い植物でもあるのです。
この地下茎は奥深くに在り、土の中を自在に生えめぐらせており、繁殖力が高く事やちぎれた地下茎でも繁殖すると言う生命力を持つ植物です。尚、ドクダミには解毒や利尿などの効用が在り、古くから十薬の名で薬草として使われ続けています。
茎や葉には独特の臭いが在りますが、これを薬草として利用する段階では強い臭気は消えており、有効成分だけがしっかりと留まると言う性質もあります。食材として利用する地域や国も有ると言いますが、臭気については乾燥や加熱する事で無くなるため、
日本では山菜として天ぷらで料理が行われることも有りますし、中国の西南部では「折耳根」と言った呼び名で呼ばれ、四川省、雲南省などの地域では葉や茎を食し、貴州省では根を野菜として利用すると言います。尚、根は少し水で晒してから唐辛子を利用して辛味みある和え物にして食されていると言います。
所で、ドクダミには白い綺麗な花が魅力だと言う人も多いものです。群生している中に咲いている白い花は清楚であり可憐なイメージを持ちますが、花が咲く時期と言うのは入梅の時期であり、観賞用のドクダミを栽培する人などは、八重咲き品種、斑入り葉の五色ドクダミと言った種類に人気が高まっています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ジャーマンカモミールの育て方
タイトル:ブルーハイビスカスの育て方
-

-
カラタチの育て方
今から約1300年前に伝来していて、和名の由来はからたちばなという言葉が略されたとする説が実在しています。ただ、からたち...
-

-
タチバナモドキの育て方
タチバナモドキはバラ科トキワサンザシ属の常緑低木です。名前の由来は橘(タチバナ)を同じ橙色をしていることから橘もどきとな...
-

-
ブロッコリーの育て方
サラダやスープ、炒めものにも使えて、非常に栄養価の高い万能野菜であるブロッコリーは、地中海沿岸が生息地といわれています。...
-

-
マユミの育て方
マユミはニシキギ科に属しますが、ニシキギという名称は、錦のような紅葉の美しさから名づけられたと言われています。秋になると...
-

-
レモンの育て方
レモンの原産地や生息地はインドのヒマラヤ地方とされ、先祖とされている果物は中国の南部やインダス文明周辺が起源です。そして...
-

-
いちごの育て方
いちごの歴史は古く、すでに石器時代から食べられていました。南米や北米が生息地になり、野生の果実は甘味が少なく大きさも小粒...
-

-
きゃべつの育て方を教えます。是非、挑戦してみて下さい。
きゃべつは涼しい所を好み低温に強い作物です。また、冬を越して作られる品種は甘みが強く、生食でも加熱しても食べる事が出来ま...
-

-
ポテンティラの育て方
この花の科名としてはバラ科になります。キジムシロ属、ポテンティラ属ともされています。あまり高くまで成長することはなく、低...
-

-
ヤシ類の育て方
ヤシ類の特徴としては、まずはヤシ目ヤシ科の植物であることです。広く知られているものとしてはココヤシ、アレカヤシ、テーブル...
-

-
フルクラエアの育て方
フルクラエアはリュウゼツラン科の植物で原産地は熱帯や亜熱帯地方の乾燥地帯なので日本には自生していません。またこの品種には...




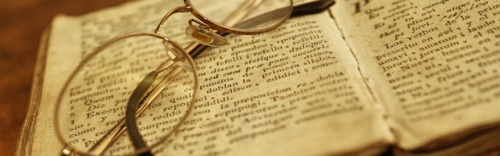





ドクダミは、ドクダミ科ドクダミ族の多年草であり、ギョウセイソウやジゴクソバ、ドクダメとも呼ばれています。