フラグミペディウムの育て方

育てる環境について
フラグミペディウムの育て方の難易度は少々高めと言われていますが、これは日本の気候と原産国などの気候に違いが有ることなどが挙げらます。例えば、中南米から南米北部を原産とするものなどの場合、これらの地域と言うのは1年を通じて雨が多い地域であり、
日本にも梅雨と言う雨が多い季節は在るものの、それ以外の季節は中南米や南米北部とは異なり、乾燥する季節も含まれており、気候により変化が日本には有ることからも育て方において難易度が高いと言われているのです。また、水を好む植物でもあり水やりはとても重要な要素となります。
耐寒性が弱いため、冬越しを上手に行ってあげないと枯れてしまったり、乾燥している時期などに水やりを忘れてしまうと枯れてしまう事も在るなど管理を徹底する事が栽培におけるコツになっています。尚、プラグミペディウムは一般的には、比較的地味な色彩の花を持つ品種が多いのですが、
近年、オレンジ色や赤色系と言った鮮やかなものも増えており、人気が高くなっています。但し、これらの苗木と言うのは普通の園芸ショップなどでは入手が難しい事も在り、洋ランを販売している専門店などで入手が可能なケースも有ります。
植え付けや植え替えと言うのは、4月頃から7月頃と9月頃に行い、肥料については鉢植えの場合は、これらと同時期に与えていきます。日当たりや水はけがが良い環境での栽培となりますが、先ほども説明を行ったように乾燥には十分注意を要する草花です。
種付けや水やり、肥料について
冬場の栽培環境は乾燥に対する管理を徹底します。また、冬場は部屋の中など、温かい場所に置いて管理をしていき、10度を下回ると株が弱ってしまうので注意が必要です。窓辺などのようなカーテン越しに置いておくことで、日光の光を当てる事が出来ます。
春から秋にかけは、室外での栽培を行う事が出来ますが、直射日光を当てるのではなく、50%ほどの射光を行なって育成させていきます。尚、品種によっては暑さに強いものもありますが、気温が高い時には乾燥を防止する目的において水やりが必須で、
シャワー灌水を行ってあげる事で元気な状態を維持する事が出来ます。また、品種によっては、腰水をして栽培が可能なタイプも有りますが、何れの品種においても新鮮な水を常に与えると言う管理は必要ですし、夏の暑い時期などは水が温まらないように注意する事が大切です。
鉢植えなどの場合は、日向に置いておくことで鉢の内部が高温になり、土は乾燥してしまいます。土が乾燥してしまう事でフラグミペディウムは弱ってしまいますし、鉢内部も乾いてしまう事も在ります。尚、鉢の内部まで乾燥してしまうと、葉先が枯れてしまったり、
全体的に弱弱しい状態になりかねないため、鉢内部の土の温度が上昇しないようにするためにも直射日光に当てずに、遮光50%を心掛ける事と、日中の水やりは水を高温にさせてしまって鉢内部を高温化させてしまう要因となるため、水やりについては朝と夕方にたっぷりと与えて上げるように管理をしていきます。
増やし方や害虫について
フラグミペディウム類似していると言われている同じラン科の植物でもあるパフィオペディラムと比較をすると、フラグミペディウムは肥料を好む品種が多いのが特徴です。春から秋までの間は、1週間から10日に一度の割合で、規定の倍率に薄めた液体肥料を施してあげます。
尚、用土は栽培を行う方法などにより異なりますが、素焼きで出来ている鉢を利用して栽培を行う場合などは、底部分に多めの軽石をひいてあげて、プラスチック製の鉢の場合は、日向土の小粒でもある砂礫質の用土を使います。これらの用土を使う事で、
常に湿り気と言うものを与えてあげて乾燥を防ぐ効果をえることができます。また、これらの用土は通気性を高めてくれる効果も期待出来ますが、風通しが良い場所に置いて管理を行う事も大切です。植え替えや植え付けの適している時期は4月から7月と9月であり、
最も適しているのは5月頃になります。増やし方としては株分けで可能になっており、5月頃に株分けを行うことで増やすことが出来ます。大きくなった株を探して、3芽から4芽で1株になるように鋏を使って切り別けてあげます。後は通常の植え替えと同じように、
鉢に植え付けて上げる事で、増やすことが出来るのです。因みに、8月は真夏日が続くため、この時期の植え替えは控える事が大切です。フラグミペディウムは、病気や害虫の心配は殆ど無いと言いますが、それでも全くないわけではなく、新芽が腐ってしまう事が有ります。
これは腐敗性による病気であり、フラグミペディウムの病気の一つと考えておくことが大切です。尚、新芽が腐ってしまった場合は、腐った部分を綺麗に除去し、新鮮な水を与えてあげることで発芽を促すことが出来ます。
フラグミペディウムの歴史
フラグミペディウムは常緑性のランの仲間であり、メキシコからペルーやブラジルなどを原産としており、これらの生息地には15種類が存在していると言います。花の一部分が袋状になっているのが特徴であり、ラン科の植物でもあるパフィオペディラムに類似していると言われています。
パフィオペディラムは蘭の中ではメジャーな存在であり、様々な交配種が存在しています。しかし、フラグミペディウムにはそれほど多くの品種があるわけではなく、パフィオペディラムと比べるとそれほど有名ではないと言う話も有ります。
しかしながら、フラグミペディウムにはピンク色をした花弁をもつものや朱色をした花弁をもつもの有り、パフィオペディラムと比べると魅力を感じる人が多いため、人気種と言われているのです。パフィオペディラムの名前の由来と言うのは、フラグマ(隔壁)、ペディロン(スリッパ)に由来していると言われており、
雄蕊の下の膨らんだ器官を子房と呼び、果実になる部分が隔壁により3つに分かれている事や、花弁の一部分がスリッパのような袋状になっている事からこのような呼び名が付いたと言われています。尚、この花にはペルー北部を生息地とする、
赤みが強めのオレンジ色の花を咲かせるベッセアエ、エクアドルを生息地とする、淡い黄緑色で紫色の筋が入っているハートウェギィ、グアテマラ、ベネズエラ、ペルーなどを生息地とするカウダツム、コロンビアに生息する、淡いピンク色の花を咲かせるシュリミィなどの仲間が有ります。
フラグミペディウムの特徴
メキシコからペールにかけて、ブラジルなどを原産とするフラグミペディウムの最大の特徴は袋のような形をした花で有り、アマゾンなどを原産とする食虫植物のような印象を持つ草花です。また、フラグミペディウムの名前は隔壁及びスリッパと言う意味を持つ言葉から由来されており、
子房が隔壁により3室に分けられており、花弁の一部分でもある唇弁の部分がスリッパのように見える事から、このような呼び名が付いたと言われています。尚、この花は細長い葉を持ち、左右交互に葉を出しながら成長していくのも特徴で、表面には光沢があり、厚みを持つ葉が特徴です。
茎は極端に短いのも特徴で、茎は葉の間に埋もれた状態になっています。開花の時期と言うのはフラグミペディウムの品種により異なり、不定期に開花する種類も在ると言います。一般的には、葉の付け根部分から花茎を伸ばして行き、先端に2輪から複数の花を咲かせるのが特徴です。
尚、草丈は30センチから1メートルを超えるものもあり、珍しい花の形や葉の形状をしている事からも、庭などで栽培をする人も多い草花です。品種により生息地も異なるのですが、ベッセアエはペルー北部、ハートウェギィはエクアドル、カウダツムはグアテマラやベネズエラ、
ペルー、シュリミィはコロンビアがそれぞれ原産と言われる品種になります。尚、花の色は品種により様々であり、主な花色としては緑色、茶色、ピンク色、オレンジ色などが有り、これらの色に加えて、黄緑色に紫色の筋が入っている品種も在るなどの特徴を持ちます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セッコクの育て方
タイトル:シクノチェスの育て方
-

-
ヒメジョオンの育て方
ヒメジョオンは、北アメリカが原産の植物で、明治維新で日本が揺れているころに、入ってきて、以来日本中に広がり、色んな家の庭...
-

-
ウスベニアオイの育て方
ウスベニアオイは、アオイ科の多年草で成長すると2mほどの高さにもなる植物で、直立した円柱形の茎に手のひらのような形をした...
-

-
チンゲンサイの育て方
チンゲンサイの原産地は、中国の華中、華南といった地域が原産地ではなかったかと考えられています。アブラナ科で原種とされるも...
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
ニオイバンマツリの育て方
ニオイバンマツリはナス科の植物で南アメリカが原産となっています。生息地はブラジルやアルゼンチンなどの南米の国々となってい...
-

-
緑のカーテンに最適な朝顔の育て方
ここ数年毎年猛暑が続き、今や日本は熱帯よりも熱いと言われています。コンクリートやアスファルトに覆われた環境では、思うよう...
-

-
ダンギクの育て方
中国や朝鮮半島、台湾、日本が原産地となるダンギクは、30センチから80センチほどになる山野草です。日本では九州や対馬地方...
-

-
レモンマートルの育て方
レモンマートルはオーストラリア原産のハーブの一種です。ハーブといっても高さ20mと大きく育つため、低木や草花といった一般...
-

-
ハナショウブの育て方
ハナショウブとは6月の梅雨の時期に花を咲かせる花弁の美しいアヤメ科の多年草です。原産は日本や中国などのアジア圏になります...
-

-
ライラックの育て方
ライラックの特徴としてあるのはモクセイ科ハシドイ属の花となります。北海道で見られる事が多いことでもわかるように耐寒性があ...




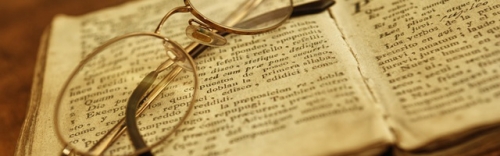





フラグミペディウムは常緑性のランの仲間であり、メキシコからペルーやブラジルなどを原産としており、これらの生息地には15種類が存在していると言います。花の一部分が袋状になっているのが特徴であり、ラン科の植物でもあるパフィオペディラムに類似していると言われています。