チャボリンドウの育て方

育てる環境について
アルプスの標高が高い場所が原産の植物の為、育て方として重要になってくるのが、あまり暑くならない環境です。寒さには強い植物ですが、暑さには弱く、温暖な気候の場合、育てにくい植物となります。一年草ではなく、多年草で、種を撒く以外に、脇芽やランナーによってその数を増やしていくという特徴があります。
気温があまり高くならず、生息地に似た環境であれば、自然に増え、育てやすい植物となりますが、温暖な地域で育てたいと考えた場合、夏を上手く越せるかどうかが重要になってきます。暑いからといって、必ず全滅をするという訳ではありませんが、暑い環境の中、育てていくと、
枯れる原因となり、その数を増やしていく事ができなくなります。長く楽しみたい、数を増やしながら楽しみたいと考えるのであれば、暑くない環境を用意する事が大切です。暑くない環境を作る際、日陰に置いておけば良いと考える人もいますが、
日当たりを好む植物の為、日が当たらない日陰での栽培はお勧め出来ません。それよりも、遮光によって日差しを和らげ、そしてよい風通しを作っておく事がお勧めです。高温多湿の環境は、枯れてしまう原因ともなってしまうので、梅雨明け等、
高温多湿になりやすい時期から、しっかりとした暑さ対策、湿度に関する対策等を心がけておく事がお勧めです。冬の寒さには強い植物ですが、雪の中で育つ植物の為、乾燥には弱いという特徴があり、冬は乾燥対策が重要になってきます。
種付けや水やり、肥料について
チャボリンドウの種を植える場合、1月から2月頃に植えてきます。種から育てるという人も少なくありませんが、株分けによって増やしていく事も出来る植物です。栽培中の水やりは、季節に合わせて行っていきます。高温多湿を嫌う植物なので、高温多湿状態を作らないように、
春と秋は、朝に水やりを、そして夏場は、夕方以降の涼しい時間帯になってきたら、たっぷりとみずを与えていきます。そして、冬場に気をつけなければいけないのが乾燥です。元々、冬場は、雪の下で過ごしていた植物です。雪の下というのは、水分がしっかりとある、乾燥とは無縁の状態となります。
ですから、冬場に乾燥をさせると、枯らしてしまう原因となってしまいます。冬に雪が降る地域は、原産地と似た環境と言える為、そのまま雪の下で冬を越させるようにすると良いでしょう。ですが、冬場に雪が殆ど降らず、土が乾燥しやすい地域の場合、土が乾燥しないように、
土の表面が乾いてきたタイミングでの水やりを繰り返していく事が大切です。これにより、枯れない状態で冬を越し、雪解けと言われる季節になった時に、青色の綺麗な花を咲かせる事になります。肥料は、与え方によって花つきが変わってきます。
春の芽が出始めから、梅雨頃まで、そして秋頃から冬頃までは液体肥料を与えていきます。花が咲き終わってから、夏の初め頃までは、りん酸が多めの肥料を与えるようにする事で、花つきの良い状態を作っていく事が出来ます。
増やし方や害虫について
1月から2月頃に種を撒く事によっても、増やしていく事が出来ますが、既に育てている株があるならば、株分けによっても増やしていく事が出来ます。株分けは、4月頃、もしくは10月頃、植え替えの際に、同時に行うようにしていく事がお勧めです。
株分けはランナーの中でも、根が出始めているものを選んで、切断し、新たに植え付けていきます。ただ、無理に株分けをしようとすると、株自体を炒めてしまう原因となってしまいます。株分けを考えているのであれば、現状で出来る株分けを考えていくのではなく、
まずはランナーをしっかり増やし、株分けをしやすい状態まで栽培した時点で、植え替え、株分けをしていく事がお勧めです。ランナーが増え、株分けしやすい状態を作っておく事で、元の株や新たな株に負担が少ない状態で、チャボリンドウを増やしていく事が出来ます。
チャボリンドウは、ランナーを上手く増やす事が出来れば、株を増やしやすいという特徴がある植物ですが、害虫の被害に遭いやすい植物でもあります。アブラムシをはじめ、ナメクジやイモムシ、バッタ等、様々な害虫がつきやすい植物です。葉っぱだけではなく、
根の周辺にも害虫がつきやすく、栽培中は、害虫がいないかしっかりと確認しておく事も大切です。害虫がいた場合、早めに駆除や対策をする事で、被害の拡大を防ぐ事が出来ます。この他、病気にもかかりやすい為、栽培中は、変化がないか、しっかりと確認しておく事が大切です。
チャボリンドウの歴史
チャボリンドウは、アルプスやピレネー山脈の草地原産の常緑の多年草です。チャボといえば、茶色を基調とした鶏の色をイメージする人も多いでしょう。ですが、このチャボリンドウは、とても美しい青色の花を咲かせる事が特徴のリンドウです。
その青色は、真っ白なアルプスの景色の中に美しく映える為、エーデルワイスとアルペンローズと並ぶ、アルプスの三大名花としても有名です。チャボリンドウと呼ばれる事もありますが、この他、アルペンリンドウ、アルペンブルー、ゲンチアナ・アコーリスという名前でも呼ばれる事があります。
この中でも、特に呼ばれる事が多いのが、アルペンリンドウです。とても美しい花を咲かせる事で有名な植物ですが、このチャボリンドウはアルプス山脈等の中でも標高1200mから3000mと、とても標高が高い場所が生息地の植物です。その為、寒さには強いという特徴がありますが、
暑さにはやや弱く、温暖な気候の中で育てるには向かない事もある植物となります。美しい青色は、庭を彩るのに最適ですが、実際に植える場合、このチャボリンドウを上手く栽培出来る環境等も重要となってくる為、温暖な地域の場合、植木屋やホームセンター等では、
販売されていない事が多くなります。実際に、購入をして、栽培をしたいと考える場合、ホームセンター等に出向くよりも、ネットで植物を販売している店舗をこまめに確認しておく方が、購入出来る可能性が高くなります。
チャボリンドウの特徴
チャボリンドウの特徴は、その美しい花です。一般的なリンドウは、青紫から白に近い色合いで、花びらは先端が尖った物が多くなります。更に、ひとつの茎に対して、いくつもの花を咲かせていくというものが多くなります。それに対して、チャボリンドウは、茎が伸びた先に、一輪だけ綺麗な花を咲かせます。
小型のリンドウといわれる事もありますが、それは、草丈が10cmから15cmと、低めである為、小型といわれる事になります。ただ、草丈自体は低めですが、草丈に対して花は大きく咲く為、とても存在感があります。更に、その花の色合いが、とても鮮やかな青、もしくは青紫色をしている事が特徴です。
白色のものも存在しますが、人気は青から青紫にかけてのものとなります。アルプス山脈の白色の中で映えると言われる、青に近い色合いはとても美しく、そして、その美しさを更に強調しているのが、花びらの存在感です。日本で多く見られるリンドウの花びらは、
先が尖り、スッキリとした印象の花びらが多くなります。それに対して、チャボリンドウは、花びらが横にも広めで、淵の部分は、適度なフリルが付いた状態で、大きく開いた状態のものは、ラッパのような形状となっています。
それにより、美しい色合いが、より映える状態となっています。その花は、葉っぱに比べて大きく、存在感がある為、鉢植えとして育てる場合、多くの花を咲かせる事が出来れば、とても印象的な鉢に仕上げていく事も出来ると人気の花になっています。
-

-
アデニウムの育て方
アデニウム/学名・Adenium/キョウチクトウ科・アデニウム属です。アデニウムは、南アフリカや南西アフリカなど赤道付近...
-

-
ゴボウの育て方
ゴボウは世界の中でも食べるのは日本だけとも言われています。しかし、食物繊維が豊富に含まれている事からも便秘の解消などに最...
-

-
トキワサンザシの育て方
真赤な赤い実と濃い緑の葉を豊かに実らせるトキワサンザシは、バラ科の植物で、トキワサンザシ属です。学名をPyracanth...
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...
-

-
ウスユキソウの育て方
ウスユキソウは漢字で書くと「薄雪草」と書きますが、この植物はキク科ウスユキソウ属に属している高山植物です。因みに、ウスユ...
-

-
ホウレンソウの育て方
ホウレンソウの特徴としては、冷涼な地域などや季節に栽培されると育ちやすいということで、冷え込んだりすると柔らかくなり美味...
-

-
ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存...
-

-
ボタンの育て方
牡丹の原産は中国の西北部だと考えられています。この地域では、もともとは観賞用ではなくて、薬として用いられていたそうです。...
-

-
ジャックフルーツの育て方
果実の大きさは世界最大として知られています。世界最大の実をぶら下げているのは、太い幹です。大きな実をぶら下げているだけあ...
-

-
大きなサツマイモを育て上げる
サツマイモは特別な病害虫もなく農園での育て方としては手が掛からないし、家族でいもほりとして楽しむことできる作物です。




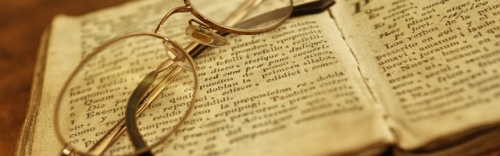





チャボリンドウは、アルプスやピレネー山脈の草地原産の常緑の多年草です。チャボといえば、茶色を基調とした鶏の色をイメージする人も多いでしょう。チャボリンドウと呼ばれる事もありますが、この他、アルペンリンドウ、アルペンブルー、ゲンチアナ・アコーリスという名前でも呼ばれる事があります。