ケラトスティグマの育て方

育てる環境について
ケラトスティグマは多年草の草花として知られている他、やや大型のサイズの物に関しては低木に分類されることもあります。原産地は中国西部、ヒマラヤ、エチオピアであり、20センチくらいの小さなものから1メートル程度のサイズまで幅広く成長します。
耐寒性に優れており、耐暑性にも優れているという特徴があるために比較的育てやすい草花として知られています。園芸用の植物としては初心者でも扱いやすいものであると言えるでしょう。青紫に咲く花が美しい品種であり、観賞用に育てられている姿を良く見る品種です。
割と環境に適応しやすい丈夫な植物ですので殆ど放任でも問題はないと言えるでしょう。日向から半日蔭まで様々な環境に適応し、水はけのよい場所であれば栽培は簡単であると言えるでしょう。石畳の酢地間にあるわずかな土の部分からでも育つほど生命力にあふれている品種であるため、
庭で育てるのであれば手間のかからない植物であると言えるでしょう。しかし鉢植えで育てるのであれば一定の世話は必要です。特に乾燥には注意し、冬の時期に葉鉢植えの中が凍結しないように注意して見ておく必要があると言えるでしょう。そこまで冷える環境下においては防寒対策が必要になります。
もう一つ注意すべき点があるとすれば肥料のやり過ぎと水のやり過ぎでしょう。丈夫な植物ではありますがこの湯無環境が続くと根腐れしやすくなってしまいます。この点については適切な育て方を理解して間違いのないようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
植え付けに関しては春から秋までいつでも対応が可能です。生育期中であれば問題はないですが、寒くなる時期に関してはしっかりと根付かせるために無理に動かさない方が良いと言えるでしょう。庭に植える場合には植える場所に腐葉土を混ぜて良く耕しておくと良いでしょう。
根がしっかりと付くまでは乾燥させることのない様にするのもポイントです。水やりはある程度こまめに定期的に行う必要があるでしょう。鉢植えで育てることも容易ですし、コンテナや花壇の様な環境にも利用しやすいものであると言えます。色々な大きさに仕立てることが出来るので希望に合わせて調整しましょう。
植え替えをするのであれば根詰まりを予防するという目的で行うのが良いでしょう。従って庭に植える場合には植えっぱなしで特に何もする必要がないと言えます。そのため非常に手のかからない植物です。ルリマツリモドキは地下茎を介して広がる性質が
ありますので時には間引きを行ったり、地中に枠を入れる等必要に応じて生息範囲を制限しておくと言う対応も有効であると言えるかもしれません。低木状に育つケラトスティグマの場合には基本的に他の樹木と同じような取り扱いになると良いでしょう。
鉢植えの場合には根詰まりを起こして花の付きが悪くなるという症状を呈する前に対応することが推奨されます。そのため1~2年程度に一回は植え直しをした方が良いと言えるでしょう。肥料に関しては殆ど心配する必要はないレベルです。
増やし方や害虫について
ケラトスティグマを増やそうとするのであれば主な手段としては3種類程がります。さし芽をすることが望ましい倍もありますし、株分けや種まき絵も増やすことが出来ます。この内さし芽は容易に増やせることが出来るという点で優れており、
5月から9月の育成期間中に元気の良い若芽を切ってさすことで新しい株を育てることが出来ます。またケラトスティグマは株分けにも対応します。4月から6月、または9月から10月の期間に限定して株分けの対応をすることも可能になります。そして三つ目の手段が種まきです。
時間がかかりますのであまりお勧めの手段ではありませんが、自然に繁殖する場合にはこの種によって増えているので、その仕組みを利用して育てることもできるでしょう。しかしながら種が実るのはケラトスティグマの中でもウィルモチアナム等一部ですので、
種が容易に得られない品種の場合にはさし芽等の対応の方が良いと言えるでしょう。成長を阻害する病気や害虫についてですが、病気に関してはこれと言って心配が必要な病気はありませんのである程度は安心できます。しかしながら水分過多、また栄養過多による根腐れには注意を払いましょう。
害虫に関してはアブラムシに対して警戒しておく必要があると言えます。アブラムシが付くと株を弱らせてしまう性質がありますので付いていることが確認出来次第除去して行く対応を取らなくてはなりません。付きやすいと言うほどではありませんが、付くことがありますので警戒しておきましょう。
ケラトスティグマの歴史
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。高さ20~30センチ程度に成長する草花状の品種は地下茎が発達して丈夫に育ちますのでグランドカバーの目的のために栽培されることもあります。
中には大きく育つものもありますので品種に応じて育て方を工夫すると良いでしょう。コバルトブルーに咲く花は小さく、かわいらしい見た目になっています。花が次々と咲く中で花がらが残ってしまう性質がありますので少々見た目良く保つことが難しいのがもったいないところではありますが、
花壇を彩る脇役としての存在感は十分であると言えるでしょう。ケラトスティグマは別名をルリマツリモドキと言い、よく似た品種にルリマツリと呼ばれるものがあります。この品種の近縁種であるためにモドキという名前が付いていますが、
地下茎でつながっている非常に丈夫な植物として環境を美しく保つための働きをこなしてくれるものであると言えるでしょう。日本においては近代になって導入された花であり、歴史の長い花であるとは言い難いものに分類されますが、それでも比較的目にする機会の多くなってきている花であると言えます。
ケラトスティグマは園芸用の植物として、美しい花壇や庭を彩る植物として広く導入されている品種として有名な存在になってきているということが出来るでしょう。この様な役割を果たすことからお庭の名脇役としての評価を得ることが出来た花としても知られています。
ケラトスティグマの特徴
ケラトスティグマには8種類ほどの品種があります。大きく分けて冬に地上に出ている部分が枯れてしまう草本性のものと茎が残って低木の様な状態になるものの二種類に分けることも出来ます。そんなケラトスティグマの内、最も一般的な種類としてはルリマツリモドキと言う品種が知られています。
これは中国西部を原産とする耐寒性の宿根草であり、地下茎を伸ばして広がるのが特徴になっています。茎や葉がこんもりと密集するように成長し、そこに青い色をしたかわいらしい花を咲かせます。開花時期が比較的長いのが特徴であり、花壇の縁取りによく利用される他、グラウンドカバープランツとしても利用されます。
低木状になる種類のケラトスティグマに関してはグリフィチーとウィルモチアナムと呼ばれる品種が良く栽培されています。日本ではブータンルリマツリ、アルタイルリマツリと言う名称で呼ばれることもあります。これらは草丈が十分にありますので花壇の中央や後方に植えられることもあります。
これらはよく似ていますが、前者はやや大型で枝が少なく秋に花をつけるのに対し、後者は枝分かれが多く初夏から秋にかけて花が咲くと言う違いがあります。ケラトスティグマに良く出てくる日本名のルリマツリですが、
このルリマツリと言う品種はブルンバゴ属と呼ばれる別の品種になります。非常に紛らわしい関係性がありますが、こちらは南アフリカを主たる生息地としているつる性の低木です。
-

-
アオドラセナの育て方
アオドラセナはリュウゼツラン科の観葉植物です。そして鉢植えで植えるのに適していて、育て方は初心者の方でも十分簡単に育てる...
-

-
フロックスの育て方
フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の植物の総称で、現時点で67種類が確認されています。この植物はシベリアを生息地と...
-

-
植物の育て方にはその人の心があらわれます。
自宅で、植物をおいてあるところはたくさんあります。お部屋に置いておくと部屋のイメージがよくなったり、空気を浄化してくれる...
-

-
ジュズサンゴの育て方
花期は夏から秋頃になります。果実が見煮るのは9月から11月頃、ヤマゴボウ科の常緑多年草です。葉は互生し、長卵形をしており...
-

-
オクラとツルレイシの作り方
オクラは別名アメリカネリといい、アフリカ原産の暑さに強い野菜でクリーム色の大きな美しい花の後にできる若さや食用にしてます...
-

-
にんにくの育て方
にんにくは、紀元前3000から4000年以上前から古代エジプトで栽培されていたもので、主生息地はロシアと国境を接している...
-

-
シシウドの育て方
シシウドの原産地は日本になります。別名をウドタラシと言うのですが、猪独活ともいった名前が付いているのが特徴です。夏の暑い...
-

-
オクラの栽培オクラの育て方オクラの種まきについて
オクラはプランターなどでも手軽に育てることが出来るということもあり、とても人気があります。オクラのの栽培やオクラの育て方...
-

-
バイカウツギの育て方
バイカウツギは本州から九州、四国を生息地とする日本原産の植物になり、品種はおよそ30~70種存在し、東アジアやヨーロッパ...
-

-
シダルセアの育て方
シダルセアは、北アメリカ中部、北アメリカ西部が原産国です。耐寒性はある方で、乾燥気味である気候の地域を生息地として選びま...




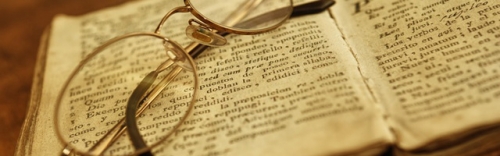





中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科で属名は、ルリマツリモドキ属(ケラトスティグマ属)と分類されており、和名は、ルリマツリモドキなどと呼ばれています。