スパラキシスの育て方

育てる環境について
スパラキシスは南アフリカの比較的暖かい地域を主な生息地としている植物の一種です。咲かせる花は非常にカラフルであり、スパラキシスの中には複数の色で構成さえる花も少なくありません。成長すると15センチから80センチ程度までは成長するのが特徴であり、
白や赤、ピンク、オレンジ、黄色、紫、茶色等の様々なカラーの中からいくつかが組み合わされて花が咲く仕組みの植物となっています。多くの職部と同じくスパラキシスも日当たりのよい環境を好みます。また水はけが良い環境である必要があるでしょう。
日本における寒さはスパラキシスにとってはかなり深刻なものになりますが、暖かい地域であれば育てやすいと言えるでしょう。寒い地域の場合には主に植木鉢での栽培とし、冬の時期は室内に入れるなどの対応が必要になりますが、関東地方よりも南の暖かい地域においては
戸外で栽培することも不可能ではありません。育て方を決める際の重要な判断基準となりますので慎重に考えましょう。一般的に霜が降りるような環境であれば屋外に植えるのは望ましくないでしょう。その様な場合には鉢植えで栽培し、
リスクの高い時期には軒下で風雨をしのぎながら育てるような対応であることが必要になります。植木鉢の場合には土壌は自分で作るのが良いでしょう。水はけと通気性を両立する土壌として、赤玉土6に対して腐葉土3、軽石1と言った構成の土壌を用意すると良いでしょう。この様な環境で良く育ちます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けに関しては9月から11月にかけての時期の行うのが良いでしょう。この時に使用するのは一般的に求婚であり、丁寧に育てれば大きく育ちます。一方鉢植えの場合には5号鉢に対して7=8球ほどスパラキシスを植えると良いでしょう。
深さは球根一つ分として、一定の間隔をあけて植えて行くと良いでしょう。鉢植えを利用する場合には毎年行う必要がありますが、庭に植えている場合には3年に一回程度植え替えを行えば十分であると言えます。水やりは重要ですが、湿った城rタイのまま長く放置されないような環境であることが重要です。
基本的には表面の土が乾いたら水を与えるようにしましょう。但し冬は若干乾かし気味に管理しておく必要があります。春になったら成長とともに必要とする水分が大幅に増えますので水やりの量を増やしていくと良いでしょう。花が咲いて葉が黄色く変色するようになってきたら水やりを中止しましょう。
その後は断水で夏越しとなります。育て方としては健康な球根を採るための方法をしっかりと身につけておく必要があります。ただやみくもに水を上げれば良いというものではないということ知っているかいないかで結果が大きく変わるでしょう。
スパラキシスを成長させるために肥料としては、元肥として緩効性化成肥料を土壌と用土の両方に混ぜ合わせておくことが有効であると言えます。鉢植えを使って栽培している場合にはさらに丸の成長期に合わせて液体肥料を2週間に一回程度追肥するのが良いと言えるでしょう。
増やし方や害虫について
スパラキシスを増やそうとする場合には基本的には球根を活用した増やし方が推奨されます。まずは分球ですが、この方法は親玉の上の茎に付いてる子球を利用して育てる者です。この子球を蓄えておき、秋になったら地面に植えて育てると言うのが基本的な対応です。
この子球は非常に多くの数をつけますので、個数に関して必要以上に心配することはありません。美しく咲き乱れる花の美しさを見ていると静かに待っているのが正解であったと感じることが出来るのがスパラキシスの特徴でもあります。もう一つの増やし方としては種まきがあります。
自然環境ではこの様な増え方の方が基本にはなりますが、この種まきによる方法で得ることが出来る成果は3~4年ほど将来になるでしょう。そのため園芸用の増やし方としては非常に時間がかかりすぎるものであると言えるでしょう。主にこの二種類の栽培方法によってスパラキシスが日々増やされているのです。
この様な植物を栽培する際に心配しなければならない内容にはいくつかありますが、その中でも植物の病気と害虫に関しては気を配っておくべきものであると言えるでしょう。しかしスパラキシスに関しては幸運にもその様な害虫や病気のリスクが殆どないというのが評価となっています。
そのため育てやすい品種であると言えるでしょう。しかし、どのような環境でも変わらずに育てることが出来るというものではありません。虫害がないというのは栽培する人にとってはうれしいことであると言えます。
スパラキシスの歴史
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いていることからそれなりに日本でも親しまれてきた歴史を持っている花であるということが分かります。カラフルで美しい見た目のスパラキシスはこれまでも
多くの人にその美しさが認められてきており、多くの人の目を集めてきたものであると言えるでしょう。観賞用に適した品種であり、日本においても南の方に位置するエリアであれば庭に植えて楽しむことも出来ます。花壇や鉢植えに植えて見て楽しむだけではなく、
切り花にも使用される特徴を持っている花でもあります。花が咲く時期が非常に短く花が落ちてしまうという特徴があるので本来は向かないのですが、生け花など一瞬の美しさを追求する分野においては素材の一種として利用されてきました。
非常に色鮮やかで目を引く植物であるという特徴はこの様な場所でもその真価を発揮しています。スパラキシスは球根を作り上げる植物であるということから、他の球根性の植物と同様に沢山の球根が作られて取引されてきたという歴史も持っています。
園芸用の植物としてはこの球根を活用してどんどんその数を増やしていくという仕組みを利用しています。自生しているスパラキシスの場合にはためを振りまいてその数を増やしているのが一般的ですが、生命力にあふれたスパラキシスは人の手を借りなくてもその歴史の1ページを積み重ねています。
スパラキシスの特徴
スパラキシスは南アフリカを原産地とする半耐寒性の植物として知られています。球根を作るタイプの植物であり、原産地である南アフリカにおいて6種類ほどの品種が確認されている植物です。3月下旬から5月にかけて細長い葉の間から細い茎を伸ばしてはっきりとしたコントラストの花を穂状に咲かせて行くのが特徴の植物です。
日本において最も見かける機会が多いと考えられるのはスパラキシス・トリカラーと呼ばれる品種の交配種でありいくつかの色の花が混交するという特徴を持っている花であると言えるでしょう。このトリカラーという言葉の意味は3種類の色と言う意味であり、
多くの場合花弁の中心が黄色と黒で彩られ、それに加えて花弁の主たる色の3色によって構成されることになります。この花は球根一つから2~3本の茎が伸び、3~6輪の花をまばらに付けるのが特徴になっており、4日ほどで終わってしまう花の寿命は非常に短いと言えますが、次々に咲いてくれる仕組みがありますのでおよそ一ヶ月ほどは楽しめると言うことが出来ます。
寒さにはあまり強くない品種の植物ではありますが、関東地方よりも南の暖かい地域であれば簡単な防寒を施すだけで戸外での冬越しも可能になります。しかし寒さに弱い品種であるために若干程度は葉先が痛むようなこともあるでしょう。しかし地域によっては屋外に植えて楽しむことも出来ますので広い可能性を持った園芸植物であると言えるでしょう。
-

-
コロカシアの育て方
コロカシアの原産と生息地は東南アジアや太平洋諸島です。それらの地域ではタロという名前で呼ばれていて、主食としてよく食べら...
-

-
ランタナ・カマラの育て方
ランタナ・カマラは通称ランタナで、別名をシチヘンゲやコウオウカ、コモン・ランタナといいます。クマツヅラ科ランタナ属の常緑...
-

-
トレニアの育て方
トレニアはインドシナ半島原産の植物で、東南アジア・アフリカなどの熱帯の地域を生息地として約40種が分布しています。属名t...
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
ヒマワリの育て方
野生のヒマワリの元々の生息地は、紀元前3000年頃の北アメリカとされています。古代インカ帝国でヒワマリは、太陽の花と尊ば...
-

-
アグラオネマ(Agleonema)の育て方
アグラオネマはアジア原産の熱帯雨林が生息地のサトイモ科の多年草です。インドから東南アジア、中国南部にかけて約50種類が生...
-

-
ポトス(Epipremnum aureum)の育て方
ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温...
-

-
クチナシ(実)の育て方
クチナシの特徴としては、やはり花の可憐さでしょうが、照り輝く白い色をしていて、まるで和菓子のような感じもしますが、最近は...
-

-
キャットテールの育て方
キャットテールは別名をアカリファといい、主にインドが原産地で、熱帯や亜熱帯地方を生息地としている植物でおよそ300種類か...
-

-
エラチオール・ベゴニアの育て方
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります...




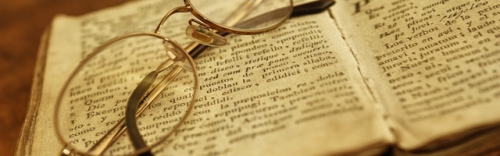





スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いていることからそれなりに日本でも親しまれてきた歴史を持っている花であるということが分かります。