タカネビランジの育て方

育てる環境について
タカネビランジは、3月もしくは9月に種をまくと、7月から8月にかけて開花となる高山性の植物です。植え付けや植え替え時期は3月の下旬頃から5月の上旬にかけてと、9月の下旬から10月の初旬にかけて適期となります。尚、肥料については、鉢植えや庭植えに関係なく、
4月から6月の下旬頃にかけてと、9月の下旬頃から10月にかけて施してあげます。タカネビランジは花崗岩帯に多く見られる小型の植物であることからも育て方のポイントとして日当たりと風通しのよい場所を選んで栽培をすることが大切です。鉢植えなどで栽培を行う時には、
芽が出て来る頃からは、日当たりが良く、風通しが良い環境の中で育ててあげます。梅雨が明けた事からは、朝もしくは午前中だけ太陽の光が当たる場所を選んだり、50%ほどの遮光を行ってあげたり、朝だけ光が当たる場所などを選んで管理をしていきます。
強い日差しと言うのは葉を焼けさせてしまい、植物が弱ってしまったり、葉の色が悪くなどの原因に繋がるので注意が必要です。自生しているタカネビランジは岩陰などでひっそりと咲いているものが多くあり、直射日光を避ける意味において、日当たり環境は栽培の上では重要な要素と言えます。
また、秋には日当たりや風通しのよい場所に置いて管理をしてあげる事で、株を大きくする事が出来ます。尚、休眠後はそのままでも良いのですが、凍結や寒風といったものは芽を傷めてしまうので、風が当たらない場所で管理をしてあげる事が大切です。
種付けや水やり、肥料について
タカネビランジの根と言うのは成長がとても速いのが特徴であり、鉢植えなどでは根詰まりを起こしてしまって植物が弱りやすくなります。それ故に、1年から2年に1度の割合で植え替えを行ってあげたり、根詰まりになっていると感じた時は早めに植え替えを行ってあげると良いです。
尚、根が多くある株については1/3程度根を剪定してあげて植え込みを行ってあげます。タカネビランジは岩場などの岩礁地帯などに自生している事もあり、水やりについてはそれほど神経質になる必要はありませんが、極端に多湿になっていたり、乾燥している場合は注意が必要です。
尚、水はけが良い用土を利用すれば、毎日1度だけ朝などに水をあげればよく、夏場などの時期については、水やりをすることで蒸れてしまう事になるので、水をあげる場合は夕方以降がお勧めです。朝などに水を与えると、日中の高温度により鉢内部が蒸されてしまい、
根を弱らせてしまうので真夏の水やりのタイミングは注意が必要です。尚、通気性と水はけが良い鉢を利用し、用土も水はけが良い物を選ぶ事がポイントとなります。鉢については、少々深めの物、鉢穴の大きい物を選んでおけば、根詰まりも防止出来ます。
特にタカネビランジは根を多く張る植物であり、大きめの鉢がお勧めです。尚、市販されている山野草用培養土が最も使いやすくお勧めですが、硬質鹿沼土小粒を主体として軽石小粒、日光砂小粒と言ったものを混ぜてあげると水はけが良い土壌を作り出せます。
増やし方や害虫について
肥料については、元肥として利用できる緩効性化成肥料を1株に対して数粒施してあげれば良いです。尚、緩効性化成肥料は春と秋などの季節は2週間に1度の割合で施し、この時に利用する肥料は窒素、リン酸、カリウムが同量含まれている液体肥料が便利です。
因みに、夏場と言うのは多肥となると株が傷みやすい季節となるため、肥料は敢えて与えずに秋になったら与えると言う事で良いのです。タカネビランジの増やし方の方法としては、株分けと種まきの2つの方法が可能になりますが、株分けは根詰まりが起きた時や2年に一度の植え替えを行う時に作業をします。
株分けのポイントは、あまり小さく株を分けるのではなく、1つの株に沢山の根が付くように、大きめに分けて上げる事です。根が多く在ることで栄養を吸収しやすくなり、生長も早くなるので、細かく分けるのではなく大きめに分けるのが株分けのコツと言えます。
種による増やし方は、花が咲いた後に出来る種を利用しますが、種を採取して冷蔵保管を行って翌年の3月頃に種まきをする方法と、取りまきをする方法が有ります。尚、どちらの方法でも、早いものですと、1年ほどで開花が可能になります。
タカネビランジは多湿になってしまうと軟腐病が発生するので注意が必要です。また、春などには芽が縮んで伸びる症状を起こしている場合は、炭素病、そうか病などの可能性が高く、症状が悪化してしまうと再生が出来なくなりますし、
そのままにしておくと感染する可能性があるので処分をするのがお勧めです。害虫については、アブラムシが萼や花の中に発生しますし、ナメクジ、ヨトウムシなどによる食害が起きる事も在りますし、梅雨時期にはハダニなどが発生するなど、その都度見つけ次第防除していくことが大切です。
タカネビランジの歴史
タカネビランジはナデシコ科マンテマ属に分類される高山植物で、花崗岩帯などが主な生息地と言われています。日本が原産の植物でもあり、本州中部地方の南アルプスなどの高山地帯に生息している高山性の植物になります。多年草の植物と言う事からも、
毎年綺麗な花を咲かせてくれるのが特徴でもあり、花色としてはピンク色、赤色、紫色などの品種が有ります。因みに、高山植物と言うのは標高が1500mや2000mと言った高山に咲く植物であり、平地での栽培は基本的には難しい、もしくは困難とされています。
しかしながら、タカネビランジは高山植物の中でも栽培が可能な品種であると言われており、園芸品種としても人気が高い植物の一つです。園芸分類においては山野草に分類されており、草丈は5cmから15cmの小型の植物で、耐寒性や耐暑性は強くも無く弱くも無いなどの理由からも、
高山植物の中では比較的容易に栽培が出来ると言われています。尚、7月から8月にかけて開花時期となりますが、タカネビランジは落葉性であり、花が枯れた後、紅葉の時期に入ると地下には翌年の芽を作り上げ、葉は枯れて落ち、休眠期となって冬越しをし、
翌年の春になると再び葉が出て来て花を咲かせると言う多年性と言われています。尚、本種と言うのは、ビランジと呼ばれる高山型の変種で有り、あまり聞きなれない名前とも言えますが、高山植物の中では山野草愛好家に人気を持っており、山梨県高山植物保護条例で定められている植物の一つになります。
タカネビランジの特徴
本州中部地方の南アルプス高山帯が生息地となるタカネビランジは、花崗岩帯に多く見られる小型の高山性の植物であり、自生しているものは登山者などでなければ見る事が出来ないと言った特徴を持ちます。花は小さな花弁を5枚広げて可愛らしい花を咲かせることからも、
山野草愛好家などに人気が高い植物であり、高山植物の中でも栽培が可能な品種、高山植物の中でも育てやすい品種だと言われています。タカネビランジは、春になると芽を出し、赤みを持つ小さな葉を沢山つけて株立ちとなります。夏になると、
5弁の赤桃色、赤色、紫色などの色を持つ可愛らしい花を咲かせ、花が咲き終えるとわき芽を次々と伸ばして行って株を形成するのが特徴です。紅葉となる、10月頃になると、地下部分では翌年の芽を形成するなどの準備を始め、やがて葉は落ちてしまい休眠状態となって冬越しをします。
尚、タカネビランジの本種と言うのは、ビランジの高山型の変種だと言われていますが、原産となる山梨県の高山植物保護条例として定められている植物でもあり、自生しているものを採取してはならない保護植物の一つと言う特徴も有ります。
因みに、ビランジと言うのは、本州中部地方の太平洋側の山地に生息しており、主に岩場に自生している植物であり、タカネビランジに似ているものの、茎部分は斜上している事や、花は桃紫色ではあるけれども小輪と言う特徴が有り、異なる花であることが解るなど区別がつくのも特徴です。
-

-
サンザシの育て方
サンザシの原産地は中国で、主に北半球の温帯を生息地としています。日本や中国に自生している種類の中には、花や実が美しいもの...
-

-
アルストロメリアの育て方
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。
-

-
チンゲンサイの育て方
チンゲンサイの原産地は、中国の華中、華南といった地域が原産地ではなかったかと考えられています。アブラナ科で原種とされるも...
-

-
ベニジウムの育て方
ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英...
-

-
オンファロデスの育て方
オンファロデスは、ムラサキ科、ルリソウ属(ヤマルリソウ属)です。オンファロデスは、北アフリカやアジア、ヨーロッパなどが原...
-

-
タカネビランジの育て方
タカネビランジはナデシコ科マンテマ属に分類される高山植物で、花崗岩帯などが主な生息地と言われています。日本が原産の植物で...
-

-
緑のカーテンに最適な朝顔の育て方
ここ数年毎年猛暑が続き、今や日本は熱帯よりも熱いと言われています。コンクリートやアスファルトに覆われた環境では、思うよう...
-

-
ホトケノザの育て方
一概にホトケノザと言っても、キク科とシソ科のものがあります。春の七草で良く知られている雑草は、キク科であり、シソ科のもの...
-

-
植物の育て方にはその人の心があらわれます。
自宅で、植物をおいてあるところはたくさんあります。お部屋に置いておくと部屋のイメージがよくなったり、空気を浄化してくれる...
-

-
ゴボウの育て方
ゴボウは世界の中でも食べるのは日本だけとも言われています。しかし、食物繊維が豊富に含まれている事からも便秘の解消などに最...




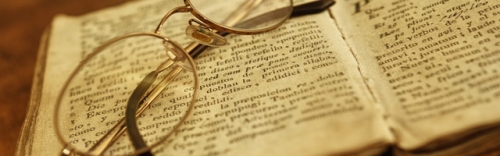





タカネビランジはナデシコ科マンテマ属に分類される高山植物で、花崗岩帯などが主な生息地と言われています。日本が原産の植物でもあり、本州中部地方の南アルプスなどの高山地帯に生息している高山性の植物になります。