ガルトニアの育て方

育てる環境について
南アフリカというと暑そうなイメージを持つかも知れませんが、ガルトニアが生育しているのは標高2,000メートルくらいの場所です。ですから、耐寒性はあり、よほどの寒冷地でない限り普通に育てることができます。手がかからないというのも特徴的なことの一つだと言えるでしょう。
植える場所として適しているのが日当たりの良い場所で水はけの良い場所です。日本の普通の庭なら問題はありません。肥料があまり多くないような土壌であっても十分に生育し、開花します。乾燥にも強いです。4月から5月くらいに植え付けると、7月から8月くらいに花を咲かせます。
地植えのままで冬を越すこともできますが、10月から11月頃に堀上をするのが一般的です。ツリガネオモトという日本名がついていますが、これは花の形によります。ガルトニアは1メートルくらいの背丈になり、ここに3センチから5センチくらいの花を咲かせます。
花の形は釣り鐘状で、下向きにつくことからツリガネオモトと呼ばれるようになったそうです。また、ヒヤシンスに似ていることもあって、サマーヒヤシンスと言われることもあります。本来は花に香りがあるのですが、
日本は気温が高いために香りがあまりしないそうです。園芸品種も育てられていて、現在では一般的なカンディガンス以外にも、ムーンビームなどがあります。ムーンビームは花を植えに咲かせ、しかも八重咲きになりますから、雰囲気はかなり違います。
種付けや水やり、肥料について
植え付けは4月から5月頃が適しています。この時期に球根を植えれば良いです。多く植える場合には株と株の間に距離を置かなければなりません。密着させて15センチおきくらいに植えることもできますし、30センチくらい開けるのも良いです。好みに応じて植え付けましょう。
地植えでも鉢植えでも育てることができて、鉢植えの場合には1個の球根を4号鉢に植えるくらいがちょうど良いです。密生させすぎると育ちが悪くなります。地植えした場合、水やりはほとんどと言って必要ありません。むしろ、水はけを良くすることを考えた方が良いです。
多湿の状態が続くと球根が腐る可能性が高くなりますから注意が必要です。鉢植え場合、春から秋までは生育していますから、この時期には水やりが必要です。用土が乾いたら太ぷりと水をやるようにします。乾燥には強いですから、もしも水やりを忘れたとしても簡単にはかれません。
しかし、花を咲かせるためには水が必要です。花を楽しむために植える人が多いでしょうから、忘れないようにたっぷりと与えます。肥料は、基本的には必要ありません。地植えの場合、わざわざ肥料をやらなくても育ちます。
鉢植えの場合には春から夏ぐらいに少しだけやります。芽が出てきてから6月くらいまで与えれば良いです。液体肥料を月に1回から2位買い与える程度で十分でしょう。元々痩せた土地に育つ植物ですから、肥料をやり過ぎないように注意するべきでしょう。
増やし方や害虫について
球根植物は、球根を分けることによって増やす場合が多いですが、ガルトニアは球根が分かれないことが多いです。ですから、球根で増やすことは難しいです。もしも分球した場合にはそれで増やすことができますから、掘り上げたときにチェックしてみましょう。
一般的には種で増やします。種を蒔いて増やす方が確実です。開花した後にはさやが膨らんできます。そして、茶色くなってくると種ができていますから、落ちないうちに採取しいましょう。すぐに蒔いても発芽しますが、春に蒔いても良いです。種から育てた場合、
3年から4年くらい経たないと花が咲きませんから注意が必要です。増やす場合には花を残しておかなければなりませんが、増やさない場合には咲き終わった花がらは早めに摘んでおくと良いです。風通しが良くて水はけの良い場所であれば、病気になることはほとんどありません。
肥料をやり過ぎたり水をやりすぎたりすると弱ることはあります。害虫についてはアブラムシがつくことがありますから注意が必要です。アブラムシがつかないように、あらかじめ防除するのも良いです。防除しなかった場合、アブラムシが発生してしまうことがありますが、
この場合には市販の薬剤を散布することによって駆除すると良いです。アブラムシがついていないかどうか常に観察しておくことは必要なことの一つです。毎日観察していれば植物の状態をチェックできますから、異常があればすぐに対処できます。
ガルトニアの歴史
ガルトニアは南アフリカを生息地とする植物で、原産はこの地域になります。ガルトニアはツリガネオモトとも言われる植物で、原産は南アフリカです。南アフリカには、現在でも3種が原種として生息しています。最も一般的で多く栽培されている種類が、ガルトニア・カンディカンスです。
それ以外にもいくつかの品種があります。多くの植物では栽培の課程で偶然に生じたものを新しい品種としていて、その中には八重咲きのものも多くあります。八重咲きというのは、植物としてみた場合には、突然変異ですから、正常な状態ではありません。
歴史的に見れば、原種があり、そして突然変異で八重咲きのものが生まれてから、それが園芸品種として育てられるというのが一般的です。ガルトニアの歴史を見ても、突然変異として生じたものが園芸品種として育てられるようになりました。
日本語ではツリガネオモトと言われることがあります。これは、花が下に垂れ下がるようになっているからです。ちょうど釣り鐘のように見えるために、こう言われるようになったそうです。花の形で言えば、最も多く栽培されているものは下を向いていますし、
全体的に見れば多くの品種がそうなっていますが、そうではないものもあります。たとえばムーンビームは花が上を向いている品種です。カンディガンス種が園芸品種としては有名ですが、それ以外には花の色がやや小さいビリディフロラ種やプリンセプス種などが有名になっています。
ガルトニアの特徴
ガルトニアは南アフリカ原産の球根で、基本的には春植えで育てます。日本で4種が手に入ります。この名前は南アフリカの研究者であるフランシス・ガルトンに由来しています。日本ではサマーヒアシンスト呼ばれることもあります。多くの品種がありますが、
ガルトニアといった場合にはガルトニア・カンディカンスを指すことが多いです。育て方は難しくはありません。そのままにしておいても花茎が立ってきます。高さは1メートルくらいになります。長い花茎を伸ばして、そこから白い花が垂れ下がるように咲きます。
ツリガネオモトと言われることもありますが、これは花の形が釣り鐘のようになるからです。一つの花茎に対して15個くらいの花が咲きます。花には香りがあるものもあります。南アフリカの植物と言うこともあって寒さには弱そうに思うかも知れませんが、実は耐寒性はかなり強いです。
日本の気候であれば、冬を超すことはできます。地植えにしていても冬を越すことができますから、栽培しやすいと言っても良いでしょう。球根で冬を越しますから、多年生植物となります。7月から8月に花を咲かせ、花の色は白から薄緑色のものが多いです。
日本の気候が最も適しているわけではありませんが、日本の気孔でも育てやすいです。耐寒性もありますし耐暑性もありますから、気候によって植物が弱ると言うこともありません。園芸品種としても育てられていて、それとともに切り花としても流通しています。
-

-
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)の育て方
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)は和名を細葉百日草といい、原産地はメキシコを中心とした南北アメリカです。リネア...
-

-
ケマンソウの育て方
ケマンソウの生息地は、森林や谷間などの半日陰を中心に広がっています。中国から朝鮮半島一帯を原産とする、寒さに強く暑さに弱...
-

-
いろんなものを栽培する喜び。
趣味としてのガーデニングについては本当に多くの人が注目している分野です。長年仕事をしてきて、退職の時期を迎えると、多くの...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
タマガヤツリの育て方
タマガヤツリはカヤツリグサ科の一年草で、湿地帯に多く見られます。生息地は日本においてはほぼ全土、世界的にみても、ほぼ全世...
-

-
ショウガの育て方
現在では日本人の食生活にすっかりと定着しているショウガですが、実は原産地は熱帯性の動植物の生息地である熱帯アジア(インド...
-

-
サルスベリの育て方
サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前ら...
-

-
キフゲットウの育て方
キフゲットウは東アジアとインド原産のショウガ科ハナミョウガ属の高さ1メートル以上になる熱帯性多年草です。日本でも沖縄県か...
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
クランベリーの育て方
クランベリーという洒落たネーミングは、可愛らしい花びらの形状を見て、鶴の頭部と同じようなイメージであることから付けられた...




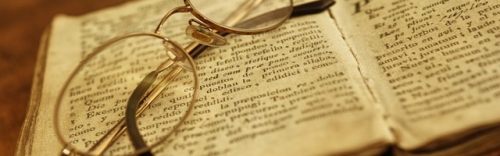





ガルトニアは南アフリカを生息地とする植物で、原産はこの地域になります。ガルトニアはツリガネオモトとも言われる植物で、原産は南アフリカです。南アフリカには、現在でも3種が原種として生息しています。