ペンツィアの育て方

育てる環境について
栽培をするにあたっての育て方として良い環境についてどういったところが適しているかです。原産の南アフリカにおいてどのようなところで咲くかとしては砂地に自生しています。どんどん根をはることができて、特に栄養分などは不要な花といえるかもしれません。花の咲き方としてはどんどん太陽に向かうようになっています。
ですから日当たりがいいところに置くのが良くなりそうです。風通しが良い所を選ぶほうが良さそうです。あまり密集して育てようとするのは厳禁になります。砂地を好むことから、乾いた土壌にしたほうが良いとされています。かと言って水が無くても育つわけではないので、それなりに水があるところで育てなければいけないでしょう。
暑さに対してはそれなりに強さを持っていますが基本的には夏にはどんどん枯れていく花になりますから特に暑さは気にする必要はありません。それよりも寒さに対してどのようになっているかを考える必要があります。寒さに対しては半耐寒性とされています。日本においては北部などでは少し寒くて外で育てるのが難しいところもありますが、
本州の南部などであればある程度冬を越すことが出来るとされています。水をやり過ぎたりするとそれによってしもができたりして傷んでしまうことがあるので、それに気をつけていれば冬も越すことができそうです。冬を越した上でその次の春に咲くことになりますから、寒すぎたり、雪がふるようなところは注意します。
種付けや水やり、肥料について
種付けに関してはいつ頃からまき始めるかですが、この花については10月ごろにまくようにします。自然の状態においては春に咲いてから花が枯れます。その時に種を持っていますからそれが落ちて再び咲く形になります。それがちょうど秋ごろになります。連続的に咲かせようとするのであれば、夏に枯れた時に種をとっておきます。
種を取るのを忘れていたとしてもそこに種が落ちていれば次の年に咲くこともありますが、そうなると雑草のようにどんどん生えてしまって密集してしまうことがあります。ある程度は管理をしながら植えるようにした方がいいでしょう。寒冷地と南部では場所も考慮します。南部であれば庭などに地植えをしても冬を越すことができます。
寒冷地だと寒さにやられてしまうことがあるので植木鉢を利用したほうが良さそうです。秋ごろに植えて寒くなるまでは外に置きますが、冬においてはフレームなどに入れるようにして越冬するようにします。水やりをどのようにするかですが、必要ではありながらやり過ぎないようにしなければいけません。乾燥気味に育てる必要があります。
他の植物の近くに育てるとき、それらの植物と一緒に水を与えてしまうことがありますが、あげ過ぎないように気をつけます。他の植物においても水をあまり必要としないものがあります。自然の雨だけで十分なものもありますからそういったものの近くであれば水を与え過ぎないで済みます。あげすぎると根腐れになります。
増やし方や害虫について
増やし方としては種まきが基本になります。多年草ではないですから枯れればそれで終わりです。でも花からは種が複数取れますから、それをうまく採取すれば増やすことができます。そのままにしていると無駄に増えてしまうことがありますから気をつける必要があるでしょう。花をきれいに咲かせるには計画的に管理をする必要があります。
発芽に対する適温としては15度から20度ぐらいとなっています。寒冷地などは冬が早く始まることがありますから、あまり寒いところであれば早めにまいておいたほうが良いこともあります。一方で南の方なら11月ぐらいでもそれなりに暖かい気温のことがあるのでその頃でも間に合わせることができるかもしれません。
用土を用意するときに気をつけることとしては水はけを良くします。赤玉土、軽石、腐葉土などを混ぜますが、軽石などの割合を増やすことで水はけを良くすることができます。周りに植える植物との兼ね合いを考えるなら他の植物よりも水はけがよりよい配合にしておくといいかもしれません。病気に関してはそれ程気にすることはありませんが、
水をあげすぎたり、水がたまりやすい状態になっていると腐りやすくなります。それを気をつけていれば健康的に育てることができます。害虫に関してはあまり気にすることはなさそうです。発生する前に蕾であったり、花が咲くことが多いです。日差しと水の管理に注意をすることで、問題なく咲かせることができます。
ペンツィアの歴史
花には花びらを豪快に開いて咲くものもあれば、こぢんまりと咲くもの、小さな花びらがたくさんあるようなキクのように咲くような花もあります。どういった花が良いか、可愛らしい、きれいと感じるかは人それぞれ異なりますが、見たことがない花であれば興味が出てくるかもしれません。
ペンツィアと呼ばれる花についてはこじんまりした花の一つになるでしょう。あまり自己主張などをすることはありませんが、非常に可愛らしく咲く花として知られています。原産としては南アフリカとされています。アフリカ大陸においても南部のほうです。アフリカといいますと砂漠があって乾燥しているような印象がありますが、
この辺りについては必ずしも乾燥をしているわけではなく、温暖なこともあって比較的たくさんの草花を楽しむことが出来るとされています。歴史において、日本にも渡来をしてきていますから育てられることがあります。いくつかの種類があるとされていて、日本に来ているものとしてはグランディフロラと呼ばれる種類になるようです。
生息地としては南アフリカの北部、ナマクアランド地方において栽培されていました。当初については切り花として栽培されることがあったようですが、今は花壇に咲かせる花としての利用が増えてきているようです。その他にはドライフラワーのように利用することも出てきています。用途としては広い範囲になっているので、これからも複数の用途で利用できるかもしれません。
ペンツィアの特徴
特徴としては、種類はキク科になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次の年にその種からまた次の花を咲かせることがあります。そのために多年草のように感じることもあるようです。花の草の丈としては40センチぐらいから60センチぐらいなのでそれ程大きくなるわけではありません。
自然によく生えている草花の中の一つに見えることもあります。花が咲く時期としては主に4月から5月ぐらいとされています。春の中でもかなり暖かくなった頃から咲き始めます。桜などだと気温がまだ寒い時から蕾などができてくることがありますが、こちらの花については暖かさが落ち着いてきた頃に徐々に咲き始めてきます。
花の色としては黄色い花がメインになります。キク科の事もあって、小さい花びらが沢山ある花です。花びらが均一についているので、まるで洋服のボタンのように見えることもあります。花の付き方は茎に対してまっすぐ上を向いています。通常のキクなどは横を向いていたりしますが、こちらの花は背丈があまり大きくなく、
花も小さいからかしっかりと植えを向いている花です。ですから生命力を感じる花でもあります。葉っぱの特徴としてはそれ程大きな葉っぱをつけるわけではありません。羽状に細かく切れ込まれた葉っぱになっています。花自体があまり大きく無く、葉っぱも非常に細いタイプのものがたくさんついています。茎などもそれ程太くありません。
-

-
ヤーコンの育て方
特徴としてはまずはキク類、真正キク類、キク目、キク科、キク亜科、メナモミ連、スマランサス属となっています。キクの仲間であ...
-

-
オカノリの育て方
オカノリの原産国は諸説ですが、中国が有力とみなされています。ある説ではヨーロッパが原産と考えられ、現在でもフランス料理で...
-

-
デンドロビウム・ファレノプシス(デンファレ)の育て方
デンドロビウム・ファレノプシスとはデンファレとも呼ばれる洋ランの一種です。着生植物の一種で、熱帯地方の木の上が生息地のも...
-

-
ハンネマニアの育て方
ハンネマニアはケシ科ハンネマニア属の多年草です。別名、メキシカンチューリップポピーとも呼ばれています。名前からも分かると...
-

-
ミヤマキンバイの育て方
バラ科のキジムシロ属であり、原産国は日本や韓国、中国の高地になります。日本では、北海道から本州の中部地方にかけて分布して...
-

-
ムラサキシキブの育て方
この植物の特徴では、シソ目、シソ科、ムラサキシキブ属となっています。英語の名前はジャパニーズビューティーベリーです。日本...
-

-
ヘレボルス・フェチダスの育て方
特徴としてはキンポウゲ科、クリスマスローズ属、ヘルボルス族に該当するとされています。この花の特徴としてあるのは有茎種であ...
-

-
バージニアストックの育て方
バージニアストックは、別名マルコミアと呼ばれるアブラナの仲間です。花がストックに似ていることからこのような名前が付けられ...
-

-
ムスカリの育て方
ムスカリは、ユリ科ムスカリ属の球根植物で、ヒヤシンスの近縁とも言える植物です。約30~50ほどの品種があるといわれ、その...
-

-
ナツツバキの育て方
ナツツバキの原産地は日本で、主な生息地は本州から九州にかけての山の中です。ナツツバキはシャラ、あるいは沙羅の木として寺院...




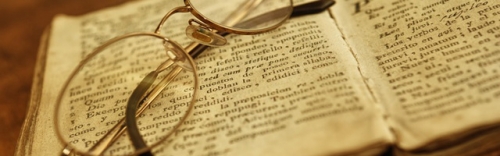





特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次の年にその種からまた次の花を咲かせることがあります。