レモンバーベナの育て方

育てる環境について
レモンバーベナは比較的、育て方がかんたんで管理しやすい植物なので、あまり特殊な環境が必要ではありません。一番大切なのは日当たりと風通しです。生息地が暖かい地方であり、乾燥気味な環境を好む植物ですので、一日中日当たりの良い場所が一番良いとされています。肥えた環境よりも痩せた環境が適してます。
しかしそれほど土壌を選ぶことがありませんので、比較的どの様な環境下でも育てることが可能だと言えます。でもじめっとした場所よりも水はけの良い土地がお勧めということは頭に留めておいて下さいね。暑さにも強く寒さにも程よく強い植物ですが、戸外で育てるのは関西よりも西が適しています。
寒い地方では、越冬することが難しいため鉢植えなどで管理するようにしましょう。一年目の冬を越えればレモンバーベナはがっしりとしたものになります。そうすれば心配もより少なくすることが出来るでしょう。最初に一年目をどう乗り切るかが、この植物を育てる最大の課題と言えるかも知れません。ハーブを寄せ植えにするのが人気の栽培方法でもありますが、その時はちょっと注意して植えるようにしましょう。
寄せ植えのもっとも大切なポイントは、美しさではなく管理方法の類似にあります。育てる環境や水やりのタイミングなど管理方法が同じでなれば、一生懸命育てていてもいずれどちらかが枯れてしまうことになります。そうならないためにも寄せ植えを行う前に、一緒に育てていけるかどうかを確認することを忘れないようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
レモンバーベナの種を収穫したり、種を購入して種まきから育てるのも良いですが、初心者なら苗を購入して植え付けることをお勧めいたします。適度にしっかりとした苗から育てる方が、失敗が少なく育てやすい傾向にあります。植え付けに時期は寒さが緩み霜の心配が無くなった時期がお勧めです。一年をとおしてなら五月から六月が良いでしょう。
植え付け方は、鉢ポットから土を崩さないように取り出します。苗が入る程度に土を掘ったら苗を静かに入れて、株の根本をしっかりと押さえてきっちりとスキマ無くおさまるようにして下さい。その後は水をたっぷりと与えて休ませてあげましょう。植木鉢などなら植え替えの直後に長時間の直射日光はお勧めできません。半日陰においてゆっくりさせてあげましょう。
一年をとおしての水やり管理ですが、乾燥気味を好むといっても乾燥しすぎると根っこが痛みます。育てる場所によって水やりのタイミングも違いますので、夏場は水やりを終えたらどの程度で乾燥し始めるかを計り、常に土の湿度をチェックしておきましょう。また冬場は乾燥気味にするよう気にかけてあげましょう。
比較的肥料などを必要としない植物ですが、あれば豊かな株になります。肥料は「緩効性」のものが好ましく。春先や花が終わった後に追肥しましょう。木の周りには「苦土石灰」夏から秋に「草木灰」を与えるのがお勧めです。追肥と土寄せ3月~9月、1~2ヶ月に1回追肥を施します。1株当たり軽く1握り(約10g)の発酵油かすなどを株の周囲に施し、土と混ぜて株元に軽く土寄せをします。
増やし方や害虫について
レモンバーベナの基本的な増やし方は「種まき」や「挿し木」です。「挿し木」、この方法が最もポピュラーなのですが、方法の一例を挙げてみましょう。伸びた枝を10㎝程度切り落とし、下葉を取り除きましょう。そしてその切り口をしたにして深く張った水に漬けます。水がしっかりあがったら用意した鉢植えなどに挿しましょう。
枝先を10cmほどきり、下葉を落とします。1時間以上水に漬け、十分水あげをしてから、湿らせた挿し床に挿します。乾燥を好みますが、発芽するまでは乾燥してしまわないように気をつけて水やりを行いましょう。しっかりと根がつけば通常の管理で大丈夫です。この増やし方の挿し木はいつでも出来るわけではなく、適した季節が決まっています。
一年をとおしてなら五月から七月の中旬まで、またそれを過ぎれば九月から十月が良い時期です。レモンバーベナは比較的害虫などに悩まされにくい植物ですが、全くないわけではありません。考えられる害虫被害は、イモムシやケムシなどによる食害です。この場合は防虫剤を用いて駆除するか、割り箸などで取り除きましょう。
さらには害虫の定番であるアブラムシにも注意しなければなりません。アブラムシにも専用の防虫剤がありますので使用するのも良いですが、食用などに利用しようと思っているなら出来るだけ避けたい方法です。防虫剤を使わない方法にアルミホイルという手段があります。
光るものにたかるという習性を利用した駆除方法ですが、アルミホイルを蜂の回りに敷いておびき寄せる方法です。また専用の粘着タイプが売られていることもあります。暑い時期には、ハダニも気をつけなければなりません。水で洗い流すか拭き取りましょう。
レモンバーベナの歴史
レモンバーベナはハーブの一種ですが、その歴史は古くさかのぼること18世紀にもなります。このハーブの原産国はアルゼンチンやチリ、ペルーなど南アメリカであり、有力な通説は1794年・18世紀ごろにチリからヨーロッパに伝えられたと言われています。随分古くから親しまれてきた植物でありとても人気のハーブです。
古代ペルー人も薬や飲み物として利用していたと言われており、長寿の効果も期待できると言われています。このようにヨーロッパ全土に広く知られたレモンバーベナですが、最も広く広まったのはイギリスの庭園です。その頃の庭にはかぐわしいレモンバーベナの香りが漂っていたと想像できます。檸檬煮近い香りのハーブはたくさん有りますが、
その中でももっともレモンの香りを楽しむことが出来るのがこのハーブでしょう。またフィンガーボールに浮かべたり、飲料用のお水に入れて香り付けしたりとその使い方様々です。ハーブティーはもちろん、媚薬などにも利用されていたという逸話も残されています。日本でもこれらが大流行した際にレモンバーベナの殺菌作用と臭い消しに着目し、広く使われていたと言います。
日本では別名「コウスイボク」や「ボウシュウボク」とも呼ばれています。このハーブはクマツヅラ科・リッピア属ですが、このリッピア(Lippia)とは、ヨーロッパの医師であり植物学者でもあったオーギユスト・リピにちなんでいます。有名な話しに「風と共に去りぬ」のヒロインの母親が愛した香りとあります。
レモンバーベナの特徴
レモンバーベナは、クマツヅラ科イワダレソウ属の落葉低木です。軽く触れるだけでもかぐわしいレモンの香りがします。この香り代々里強さを活かして調理に利用されており、魚料理や鶏肉料理の臭みを消す効果が高いハーブです。そのままのフレッシュ状態でも十分に香りがしますが、ドライにしても香りが持続することもこのハーブの大きな特徴です。
料理だけでなく人々の精神をリラックスさせる効果があります。清々しい檸檬の香りが心地よく、悲しみなどの感情を和らげてくれると言われています。また多くの人が抱えるストレスや疲労感、女性特有の症状である生理不順などを和らげる効果も期待されています。疲れを取り除きリフレッシュ効果の高い香りと言えるでしょう。
男性女性を問わず好まれる香りの一つなので贈り物にも多用されます。他にも食欲増進や消化を助けてくれるので、夕食後にレモンバーベナを使ったハーブティなどを飲むことが良いとされています。エッセンシャルオイルやアロマオイル、精油としても利用されておりその精油の成分は、リモネン・ベルベロン・ゲラニオールです。
この香りは万人に受け入れられる最もポピュラーな香りと言えるのではないでしょうか。うっすらとピンクが買った小さな花が咲き、その後に実がつくこともあります。葉の形は笹の葉のようにシャープで光沢感のある美しい緑です。60㎝から150㎝程度の低木ですが、自生しているものは3m程に成長するものもあります。
-

-
植物の栽培について アサガオの育て方
育てやすい植物の代表として挙げられるのがアサガオです。最近は色や模様も様々なものが登場しています。アサガオの育て方は比較...
-

-
トラデスカンチアの育て方
トラデスカンチアは北アメリカの温帯から熱帯アメリカにかけてを生息地とする植物です。実は日本においても似たような品種の植物...
-

-
プチアスターの育て方
キク科カリステフ属のプチアスターというこの花は、中国北部やシベリアを原産国とし1731年頃に世界に渡ったと言われておりま...
-

-
アジュガの育て方
薬草や園芸観賞用の花として、アジュガはヨーロッパ、中央アジア原産で江戸時代に伝来した歴史があります。また、日本でも数種類...
-

-
皇帝ダリアの育て方
ダリア属は、メキシコから中米に27種が分布しており、茎が木質化する3種がツリーダリアと呼ばれています。皇帝ダリアもその一...
-

-
クリスタルグラスの育て方
クリスタルグラスの原産地は南アフリカです。クリスタルグラスは植物学者によってフィシニア属のカヤツリグサ科に分類されました...
-

-
ロドリゲチアの育て方
花の特徴としてはラン科になります。園芸上においてもランとしてになります。一般の花屋さんでも見つけることができますが、ラン...
-

-
ヤブレガサの育て方
葉っぱから見ると種類が想像しにくいですが、キク目、キク科、キク亜科となっていますからキクの仲間になります。通常は葉っぱの...
-

-
セイヨウニンジンボクの育て方
学名はビテックス・アグヌス・カストゥスといいます。シソ科の植物で、原産地や生息地は南ヨーロッパや西アジアなどです。 ...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...




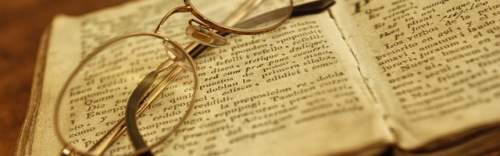





レモンバーベナは、クマツヅラ科イワダレソウ属の落葉低木です。軽く触れるだけでもかぐわしいレモンの香りがします。この香り代々里強さを活かして調理に利用されており、魚料理や鶏肉料理の臭みを消す効果が高いハーブです。日本では別名「コウスイボク」や「ボウシュウボク」とも呼ばれています。