タマガヤツリの育て方

育てる環境について
もともと駆除が必要な雑草であるため、特別な栽培環境は必要ありません。但し、湿地帯に多く生える植物であるため、湿った環境が良いと考えられます。また、生息地が世界中の暖かい地域なので、比較的暖かい地方の方が育てやすいと言えます。日本国内のタマガヤツリは日本原産であるため国内であればさほど気候は気にすることはないでしょう。
園芸種ではないため、育て方が詳しく書かれた資料はほとんど見当たりませんが、観賞用として育てるのであれば、近縁種のパピルスの育て方を参考にするのが妥当だと思われます。パピルスは水を好み、春から秋の栽培期間中は土がずっと濡れていると良いということですので、タマガヤツリを育てる際も水を切らさないようにしましょう。
また、パピルスは肥料、水、日光が十分であると非常に大きく育ちます。タマガヤツリの場合パピルスのように2mにもなることはありませんが、条件次第では1m近くまで育つことも予想されます。更にもともと雑草ですので日光を好み、葉焼けすることもありませんので、直射日光下でも大丈夫です。但し、水切れにだけは十分に注意してください。
なお、パピルスは多年草になるため冬の温度管理や霜に当たらないようにするなどの注意が必要になりますが、タマガヤツリは一年草であるため、冬越しはできません。夏から初秋にかけて、丸く可愛らしい花穂をつけた後は、種を落として枯れてしまいます。短い生命をいつくしんで育てるもの、一年草ならではの楽しみと言えます。
種付けや水やり、肥料について
日本中の水田や湿った畑に自然発生的に生える雑草の一種ですので、あまり神経質に育てる必要はないと思われます。雑草扱いの為、育て方についての資料は存在しないと考えた方が自然です。同じカヤツリグサ科の園芸種であるパピルスやシュロガヤツリ、アルボストリアツスの育て方を参考にするのがいいでしょう。
基本的にこぼれ種から育つ植物ですので、もし種が手元にあるのであれば、3~4月頃に湿った環境に蒔き、薄く土をかけておきます。5~6月頃に、元気な株を選んで植え替えを行うといいでしょう。大きく育てたいのであれば、株が育つにつれて更に大きな鉢に植え替えていくのが好ましいです。
肥料は緩効性肥料の置き肥で十分ですが、できるだけ切らさないように注意しましょう。水田や湿地に生える植物ですので、湿った環境を好みます。水はできるだけ絶やさないようにし、好ましくは水を張った水盤に鉢を漬けるなどして、水切れを起こさないよう細心の注意を払うことが必要です。なお、水盤の水が古くなると成長に悪影響を与えるほか、
ボウフラなどが発生したり腐敗して悪臭が出たりする恐れがありますので、水盤の水はこまめに変えるようにしてください。畑の雑草として位置づけられるほどに丈夫な植物ですので、水遣り以外は特に気をつけなければいけないようなことはありません。夏の日差しをいっぱいに浴びて大きく育つと、見た目も涼しげな、夏にぴったりのグリーンになるでしょう。
増やし方や害虫について
一年草なので、増やすのであれば種を取ります。約1cmになる球状の花穂が熟してくると、中に0.5~0.6mmほどの種が実りますので、花穂ごと保存しておくといいでしょう。通常はこぼれた種から自然に発芽して増えていくものですので、春になったら花穂から種のみ落として植えつけます。
害虫に関しては、カヤツリグサ科の植物には天然の昆虫摂食阻害成分が含まれていることが知られており、そのため昆虫に食害される心配がありません。ですので、涼しげな細長い葉が、昆虫の食害によってボロボロになることがなく、常に美しい状態を維持することができます。但し、前述したように、
水を切らさないための工夫として水を張った水盤に鉢をつけたままの状態にしていると、季節柄ボウフラなどが発生する恐れがあります。衛生的な面からも、水盤の水はこまめに取り換えることが推奨されます。長年、水田や畑の雑草として邪険に扱われてきたタマガヤツリですが、柔らかく細長い葉は鮮やかな緑色で美しく、カラフルな花はつけませんが、
涼しげな外観は夏限定の観葉植物にもなり得るのではないでしょうか。元が雑草であるため手間をかけなくてもすくすく育ち、病害虫も寄せ付けないという理想的な植物でもあります。小さなくす玉のような可愛らしい花穂は、熟すにつれて様々な変化を見せ、見ていて飽きないものでもあります。涼しげなグリーンを育てたいけれど、あまり手をけることができないという向きにはぴったりの植物ではないでしょうか。
タマガヤツリの歴史
タマガヤツリはカヤツリグサ科の一年草で、湿地帯に多く見られます。生息地は日本においてはほぼ全土、世界的にみても、ほぼ全世界の熱帯から暖温帯にみられる非常にありふれた草本です。カヤツリグサ科の植物には、歴史的に特に有用とされてきたものは多くはありません。古代エジプトで筆記媒体として用いられたパピルスが、唯一の有名なカヤツリグサ科の植物と言えます。
特に有用とされる特質は持たないものの、非常に身近な植物として古くから人々の生活に自然に溶け込み受け入れられてきた植物です。カヤツリグサの名称は、茎を両端から割いていくと四角い升のような形となり、それを蚊帳に見立てて遊んだことに由来することからも、古くから子供たちの遊び道具として大いに活用されてきたことを示唆します。
なお、タマガヤツリの「タマ」は、花穂がくす玉のような形の球形につくことからで、カヤツリグサ科の中でも独特の印象を与え、他の仲間との見分けも容易です。タマガヤツリは水田ではごく普通に見られる雑草ですが、繁殖力が非常に強く、強害草としての扱いです。多くの除草剤が有効とされますが、
一部効きづらい薬剤もあり、しばしば防除に失敗して大量に残ることもあります。雑草として扱われる場合がほとんどで、薬として頻繁に用いられたという記録はないとされますが、異型莎草という名の生薬として用いられることもあり、小便不通を治すとされています。また、食用として用いられたという記録もありません。
タマガヤツリの特徴
タマガヤツリの最も大きな特徴といえば、くす玉のように丸く固まった花穂です。カヤツリグサの仲間はどれもよく似ていて、専門家でも見分けるのに苦労すると言われますが、タマガヤツリはこの特徴的な花穂のおかげで他の仲間より見分けやすくなっています。カヤツリグサの名前の由来となる蚊帳の形は、茎を割いた時にできるものとされますが、
これは、穂を除いた茎の部分だけを用いて作ります。茎の部分を上下から90度の角度で互い違いになるように割いていき、どちら側からも最後まで割かずに1センチほど残したところで広げると、四角い形状が出来上がるのですが、これが蚊帳を吊った状態に似ていると、昔の人は思ったようです。
このように、子どもの遊びの友としてかなり馴染み深い植物であった考えられますが、残念ながら有名な詩歌や文芸などにタマガヤツリが謳われているという記録はなく、風流人の心をとらえるまではいかなかったようです。タマガヤツリの特長であるくす玉のような丸い花穂は、早期は柔らかな緑色で、やがて淡紫褐色に熟します。
派手な色合いではないためあまり目をひくものではありませんが、よく近づいて観察すると、一つ一つの花穂が暗紫褐色に色づき、それぞれが緑色に縁取られている様子は非常に複雑な色合いで美しく、見ていて飽きないものがあります。柔らかい黄緑色の時は美しい若草の色を、熟してきたら自然が織りなす複雑な色合いを楽しむことができます。
-

-
ユズ類の育て方
ゆず類に関しての特徴としては、まずはそのまま食べるのは少し難しいことです。レモンにおいても食べると非常に酸味が強いです。...
-

-
グミの仲間の育て方
グミの仲間はアジア、ヨーロッパ、北アメリカなどを原産地としており、幅広い地域を生息地にしています。約60種類ほどが存在し...
-

-
コリアンダーの育て方
地中海東部原産で、各地で古くから食用とされてきました。その歴史は古く、古代ローマの博物学者プリニウスの博物誌には、最も良...
-

-
なすびの栽培やナスの育て方やその種まきについて
夏野菜の中でもひときわ濃い紫が特徴なのがなすびです。日の光をたくさん浴びて、油炒めにとても合う野菜ですが、家庭でも育てる...
-

-
きゅうりの育て方
インド北部のヒマラヤ山麓がきゅうりの原産地や生息地で、現在から約3000年以上前には栽培されていたのです。その後シルクロ...
-

-
アネモネ(モナーク)の育て方
耐寒性も強いため、初心者でもあっても育てやすいのも特徴の花です。開花期が長いというのも、特徴の一つになります。原産地はヨ...
-

-
イオノプシジウム,育て方,栽培,原産,生息地
花の分類としてはアブラナ科に属します。花については庭植えとして育てられることが多く、咲き方としては1年草になっています。...
-

-
ナゴランの育て方
この植物の歴史ついて書いていきますが、まずは名前の由来についてです。ナゴランの名前は原産地でもある沖縄の「ナゴ」に由来し...
-

-
リューココリネの育て方
分類としてはヒガンバナ科になります。ユリ科で分類されることもあります。ユリのようにしっとりとしているようにも見えます。園...
-

-
マキシラリアの育て方
この花の種類としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科となっています。常緑の多年草となっているので、ずっと花を咲かせる...




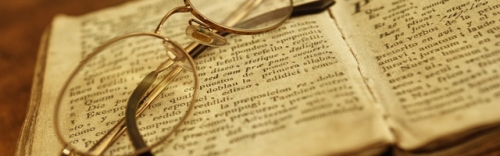





タマガヤツリはカヤツリグサ科の一年草で、湿地帯に多く見られます。生息地は日本においてはほぼ全土、世界的にみても、ほぼ全世界の熱帯から暖温帯にみられる非常にありふれた草本です。カヤツリグサ科の植物には、歴史的に特に有用とされてきたものは多くはありません。