アルストロメーリアの育て方

育てる環境について
南国といえばやはり太陽の国が多いです。栽培をする時の育て方の環境においては太陽が当たる場所が良いようです。日陰のところよりもしっかりと日がさすところに置くようにします。湿気を好むタイプもありますが、全般的に見ると水はけの良い所を好む花になります。寒いところに比べると温暖な所が良いようです。
温暖とはあくまでも心地よい暖かさであって、暑すぎるところはあまり良くないとされています。日本においては本州などではかなり暑くあることがありますが、沖縄などの南の方に行くと温暖な気候になりますから、育てるのに良い環境になるかもしれません。高温多湿の環境においてしまうと根腐れをしてしまうことがあるので、そのようなところは環境としては適しません。
寒いところになると株が凍結してしまうことがあります。寒さにはあまり強くないとされるので、やはり寒いところも適さないことになります。根の部分に関しては地中に深くまで潜った状態になっています。生育するのに不具合な季節においては花などは枯れてしまいますが根は残っています。
ですからまた気候が良い状態になればそこから新しい芽が出てきて花が咲くことがあります。根が残っていれば咲かせることができるので、根をいかに残しながら栽培するかがポイントになってくると言えるでしょう。この花においては季節によって移動をさせてあげると良いので、地植えで行うよりも鉢植えで行ったほうが良いかもしれません。
種付けや水やり、肥料について
育てる上での用土では、水はけが良いようにしておきます。小粒の赤玉土、小粒の鹿沼土、腐葉土を同じような割合で配合した土を使うことがあります。場合によっては軽石を少し混ぜて更に水はけを良くすることがあります。こうすれば根腐れをすることは少なくなるでしょう。種まきに関しては熟するようにすることが必要です。
適さない時期になると休眠状態になり、その状態でまいたとしても発芽までに時間がかかります。また発芽のタイミングもばらばらになり、咲く株もあれば咲かない株も出てきてしまうことがあります。予め熟するようにしておいて、それを一緒にまくようにすれば揃って咲いてくれます。きれいに見応えよく咲いてくれるでしょう。
植え付けにおいては鉢植えが好ましいのですが、用土の劣化、目詰まり、根詰まりをしないようにする必要があります。その方法としては植え替えを行います。デリケートな植物なので、1年から2年ごとに新しい用土に変えてあげるようにします。植え替えの作業をするのに適しているのは休眠中です。
生育が始まる直前の9月から10月、3月から5月辺りに行うのが良いとされています。鉢植えで行う場合の水やりについては水切れをしないようにします。土自体は水はけがいいように設定していますから、水をやったとしてもすぐに流れるようになっています。まめに水をやるようにしなければいけません。ねぐられをするのは嫌いますから、過剰に上げ過ぎないよにします。
増やし方や害虫について
増やすために必要なものとしては肥料になるでしょう。積極的に行うことはありませんが、芽出しの頃から開花までにおいて置き肥をしておきます。それによって土に栄養分が行き渡り、効果を得ることができます。月に数回液体肥料を行うのも成長にはいい影響を与えてくれます。花の種類によっては四季咲き性、秋に葉が茂るタイプなどがあります。
10月から11月ぐらいに追肥をするようにしておけばこれも成長にはいい影響を与えてくれます。増やす方法においては種で行うこともありますが株分けをするのが簡単で確実になります。9月であったり3月ごろに芽を確認しながら行うようにします。根だけを分けたとしてもそこから成長して花を咲かせるわけでは無いので、芽がきちんとついているかどうかを確認しなければいけません。
芽と根がセットになっている必要があります。病気に関しては土壌菌と呼ばれる病気になることがあります。根腐れ、茎腐れの原因になります。これは自分自身の育て方によって起こすことがあり、気をつけることによって対応できる場合があります。高温期において
多肥多湿の状態にしてしまうと枯れてしまうことがありますから水や肥料のあげ過ぎには注意が必要になります。害虫としてはアブラムシに注意が必要です。ガーデニングとして作るときは多の植物にアブラムシがついていてそれがこちらに広がってくることがあります。他からもつかないようにしておく必要がありそうです。
アルストロメーリアの歴史
南米といいますと情熱の国として知られています。サッカーが強い国が多いところとしても知られています。北米に比べるとどちらかと言えば発展が遅れているイメージがありますが、古くにおいては文明が栄えているなどとくとくの文化を持っている地域であることがわかります。
こちらにおいて原産になっている植物は結構あり、それが健康食品になっていることもあります。また非常に美しい花などはフラワーアレジメントの一つとして使われることが多くなります。アルストロメーリアに関しては原産が南米の花として知られています。非常に鮮やかな花を咲かせてくれるので、見た目を彩りたいときに使うことがあるようです。
幾つかに属する花で、ほとんどが南アメリカ原産となっています。こちらにはアンデス山脈の寒冷地があり、こちらにおいて自生することが多いようです。歴史としては、1700年台に南米を旅行していた人がこの花の種を採取したとのことです。その人が知り合いのスゥエーデン人の名前をとってこの花の名前にしたとされています。
日本においてはいつ頃やってきた花かといえば大正15年頃とされています。フラワーアレンジメントが盛んになってから来たのかと考えがちですが、比較的古くに日本に来ていたようです。その後日本において広められたかどうかについてはわかりませんが、最近においては花の使われ方も非常に広がっていますから、それによって知られるようになったのかもしれません。
アルストロメーリアの特徴
特徴として、ユリ目に該当します。ユリズイセン科の種類にはいる花になります。草丈に関しては50センチから1メートルほどの花になります。花の大きさは4センチ位から8センチぐらいで開ききるタイプではありません。ユリといいますと花の根元の部分がきれいに開き切らない事が多いですが、この花についても同様に開ききるタイプではありません。
花の色に関しては非常に様々です。桃色、赤、白、黄色、紫色などタイプがたくさんあります。一色だけで咲くことは珍しく、一つの花において色がかなり混ざった状態になっています。白とオレンジ色、桃色と黄色などが混ざっているので更に鮮やかさを引き立ててくれるのかもしれません。
アンデス地方を生息地とすることから寒さに関してはある程度強いと考えられていますが、実際のところは暑さや寒さに対してはどちらも強くないとされています。ですからどこにでも生えてくれる花ではありません。花に関しては多年草になっていますから、一度花が咲くようになればどんどん咲くことがあります。その点では楽しみやすい花の一つかもしれません。
南米を中心に咲いていることから、こちらの中でもいくつかのタイプがあるとされています。チリタイプ、ブラジルタイプがあるようです。生育環境に関しても必ずしも一つの地域に咲いているわけではなく、高地に咲いているものから低地に咲くもの、乾燥地に咲くものもあれば湿地に対応したものまであるとされています。
-

-
ヘチマの育て方と食べ方
ヘチマ(糸瓜、天糸瓜)は熱帯アジア原産のつる性の一年草で、キュウリやゴーヤなどと同じく巻き鬚で他物に絡み付きます。ヘチマ...
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
カキドオシの育て方
カキドオシは草地に生息する年中草です。特徴としては茎はまっすぐと伸びるのですが成長するにつれて地面に倒れます。開花すると...
-

-
植物の育て方を押さえてオリジナルな庭づくりを楽しみましょう
最近では、様々な所でガーデニングなどの園芸講座が開かれています。自分オリジナルな庭を作ることが出来るため、一つの趣味とし...
-

-
ダールベルグデージーの育て方
ダールベルグデージーはキク科の植物で黄色い花を咲かせるのが特徴です。また、キク科の仲間であることからも菊と同じ花の形をし...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...
-

-
イキシオリリオンの育て方
花については被子植物、単子葉類になります。クサスギカズラ目とされることがあります。ヒガンバナ科に属するとされることもあり...
-

-
ケラトスティグマの育て方
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科...
-

-
ヤブヘビイチゴの育て方
分類としては、バラ科キジムシロ属の多年草ということですので、バラの親戚ということになりますが、確かにバラには刺があるとい...
-

-
ウォーターマッシュルームの育て方
ウォーターマッシュルームは本来ウチワゼニクサという名前になります。生息地は湿地や河川などの水の多い場所で育つ特徴がありま...




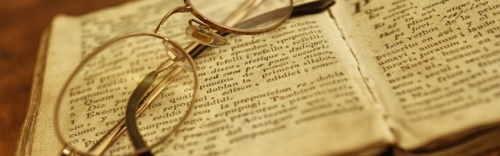





特徴として、ユリ目に該当します。ユリズイセン科の種類にはいる花になります。草丈に関しては50センチから1メートルほどの花になります。花の大きさは4センチ位から8センチぐらいで開ききるタイプではありません。ユリといいますと花の根元の部分がきれいに開き切らない事が多いですが、この花についても同様に開ききるタイプではありません。