サンキライの育て方

育てる環境について
上記でも記載したように、山に入っては必要なときだけその実を食べるというのが主流でしたので、あまり栽培されるというものでは無かったようです。お庭などで栽培される場合は、日当たりが良くまた水はけも良い環境がオススメです。出来れば山の環境に近いとベストでしょう。その特徴の一つに有機物の多さがあげられます。
植え付ける土などを作る場合は、堆肥や腐葉土などを通常よりすこしたくさん入れて作りましょう。庭植えや地植えなどではなく、鉢植えで育てる場合は、鉢を少し大きくまた深いタイプを選ぶようにしましょう。年数を重ねると根がしっかりと張り、太さも見違えるほど大きくなり立派な根になります。
十分な日当たりと適度な乾燥を好みますので、午前中などの日当たりを十分に与えられるような環境下をお勧めいたします。極度の乾燥は成長を妨げて株を痛めます。育てる環境は日当たりと水はけの良さに注意する程度であまり難しくなく、初心者でも比較的簡単に育てることが出来ると言えるでしょう。ですが、気をつけなければならないのが植える場所です。
ツルには毒性のトゲがあるということからも人や生き物が出入りする場所は避けましょう。またツルが他の植物に絡みつく可能性もありますので花壇やお庭の他の植物との兼ね合いも考えましょう。その他にも、サンキライが障害などなくツルが伸びやすいように支柱などを取り付けて、成長を促してやることも大切なポイントです。
種付けや水やり、肥料について
サンキライは極度の乾燥を嫌うため、乾燥気味に育てるのは禁物です。地植えや庭植なら植え付け当初は、土が乾いたら与えるなどが必要ですが、その後は降雨だけでも大丈夫です。しかし鉢植えなどで栽培する場合はもう少し気をつける必要があります。その他の植物でも言えることですが、真夏などは土の乾きが早くうっかりすると完全に乾燥しているということも少なくありません。
土が乾き始めたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。また開花時期などには沢山の栄養と水分が必要ですので、4月から5月などは水切れなどをおこさないように十分注意して観察しましょう。肥料なども特に必要ありませんが、植えつけ時期や花が咲く開花時期などには少し与えるのも良いでしょう。
植え付け時期なら緩効性の肥料を株もとに置きます。開花時期などは10日から20日に一回程度液体肥料を与えましょう。土が良く肥えており、環境が十分な場合は必要ありませんので、くれぐれも肥料の与えすぎには注意しましょう。種付けは、真っ赤に熟成した実のなかにあります。程よく赤く実った実を開いてみると小さな種が出て来ます。
これを植えると実生しますので、冬に花屋などで購入したサンキライの切り花やリースから良さそうな実を選び取り出して植えてみましょう。サンキライは日本各地に生息している植物なので日本での栽培は基本的に簡単な育て方で、また特段目立った注意点もありませんので挑戦しやすい植物と言えるでしょう。
増やし方や害虫について
上記でもあるように、実を植え付けることで育てることが出来ます。種まきの季節は、11月から12月が良い時期でしょう。実がふっくらしていてキレイな赤に熟成した実を選んで、まずは水洗いします。そしてその実を割ると小さな種が出て来ます。これをまた水洗いすると、トウモロコシの種ほどの大きさのキレイな茶褐色になります。
堆肥や腐葉土などが豊富な土の環境が出来上がったら、そこへ種をまきます。冬の間、土が完全に乾かないように定期的に水やりをして育てましょう。冬を越えて暖かい季節になった3月から4月下旬には小さな芽が出て来てくれます。小さな芽を大きくするにはさらに時間をかけて日当たり、水やりに気をつけて育てなければなりません。
5月下旬から6月になると葉をたくさん付けるようになり、もう安心して良いでしょう。夏を迎えることになるとツルが伸びて来ますので、支柱を用意して設置して上げます。一年を無事に越せば、落ちた実から新しく増えることもありますので、とても楽しみです。植物の大敵である病気や害虫についてですが、ほとんど心配することはなさそうです。
特に目立った害虫被害も見られませんので、安心して育てられると言えます。しかし全くないとは言い切れませんので、定期的に葉の裏やツルなどをチェックして、葉が喰われていないかやツルに虫がたくさんついていないかなど確認が必要です。葉に茶色いシミが出来ますが、このシミは成長するにつれて薄くなり消えていきますので安心して下さい。
サンキライの歴史
サンキライという名前を漢字で表記すると「山帰来」となります。その風変わりな名前の由来は、この植物に出来る実の特性にあるようです。真っ赤な候のみを食べることで、毒消しの効果があると言うことから必要になると山には入り実を食べて帰ってくると言う事から名づけられたと言われています。
根に解毒作用があり今でも生薬などで使用されているようですが、何とも直接的かつだれもが頷ける名前ですね。別名に「サルトリイバラ」「ガンタチイバラ」というものがありますが、本来はサルトリイバラが正しい名前とされています。冬になると花屋などで販売されていますが、その場合はサンキライという名前で流通しているので今ではこちらの方が通称名となっています。
サルトリイバラ(猿捕茨)の名前の由来は、ツルにあるトゲから来ているようです。その名前には、固く鋭いトゲに猿も引っかかってしまうと言う意味合いがあります。英名は「Chinaroot」で科目はサルトリイバラ科です。原産国は日本や中国、朝鮮半島、インドシナ半島などのアジアを主な生息地としています。
赤い実の姿で販売されていることが多いため、花はあまり知られておりませんが実がなるということは花もありますね。開花期は4月から5月で花の色は緑です。中国にも「山帰来」がありますが、日本の各地で生息している「山帰来」とは全く違う種類です。冬の季節が訪れるとリースなどに多く使用されているので、一度は目にした方も多いのではないでしょうか。
サンキライの特徴
サンキライの特徴は、真っ赤に実った「実」と鋭いトゲを持つツルではないでしょうか。その鋭いトゲには、毒性がありさらにはその他の植物に絡みついて成長を続けるという特徴があります。落葉低木ですが、高さは二メートル程度にまで成長します。葉は比較的丸い形をしており、光沢のある少し厚いのが特徴でしょう。形が柏餅の葉に似ていることから、代用品として使用されることもあるようです。
花は直径が7ミリ程度と小さく、色も薄い黄緑色なのであまり目立たない花ですが小さな花が集まったその様はとても可愛らしい様子です。実は最初から赤いわけではなく、出来た頃は黄緑色の爽やかな色をしています。熟成して行くにつれて真っ赤な実になりますので、とても目立つようになります。
ツルには毒性がありますが、しなやかなツルなのでリースなどに多用されています。花屋などで販売されているのは長さが50㎝程度の短いものから、2メーターほどもある長さのある状態のもの、またリース状に形作られたものまで幅広く流通しています。入手時期は、8月から12月ですが、最初はやはり黄緑色の実が主流ですので赤い実が欲しければ寒くなってから探してみましょう。
黄緑色の実の時は葉は残っている場合が多いのですが赤い実がつく頃になると、つややかな緑の葉は枯れてしまいますので、トゲの残るツルに実がついている状態がよく見られます。また、少し前まではユリ科に分類されていましたが、今ではサルトリイバラ科に分類されています。
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
ヤマシャクヤクの育て方
ヤマシャクヤクは、ボタン科、ボタン属になります。ボタン、シャクヤク、ユリといいますとどれも女性に例えられる事がある花です...
-

-
サトウキビの育て方
サトウキビはイネ科の多年草で、東南アジアや、インド、ニューギニア島などが原産と言います。また、インドの中でもガンジス川流...
-

-
バーバスカムの育て方
バーバスカムはヨーロッパ南部からアジアを原産とする、ゴマノハグサ科バーバスカム属の多年草です。別名をモウズイカといいます...
-

-
ポリシャスの育て方
特徴としてはまずはウコギ科になります。その中のタイワンモミジ属になります。原産地、生息地においては2メートルから8メート...
-

-
ハイビスカスの育て方
熱帯地方や亜熱帯地方を生息地として大きな花を咲かせているハイビスカスの種類の中には古代エジプトの3000年から4000年...
-

-
トマトの育て方について
自宅の庭に花が咲く植物を植えてキレイなフラワーガーデンを作るというのも一つの方法ですが、日常的に使う野菜を栽培することが...
-

-
ゴデチアの育て方
ゴデチアは、アカバナ科イロイマツヨイ族の植物の総称です。現在では、北米西海岸を生息地の中心としており、20種類もの品種が...
-

-
シャスタデージーの育て方
シャスタデージーの可憐な花は、アメリカの育種家である、ルーサー・バーバンクによって作り出されました。ルーサー・バーバンク...
-

-
エピデンドラムの育て方
エピデンドラムはラン科の植物であり、日本においては観葉植物としてその地位を安定させています。この植物の本来の生息地はメキ...




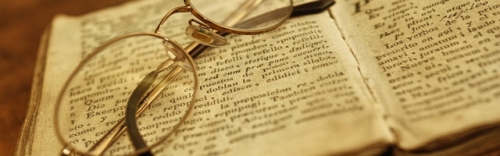





英名は「Chinaroot」で科目はサルトリイバラ科です。原産国は日本や中国、朝鮮半島、インドシナ半島などのアジアを主な生息地としています。別名に「サルトリイバラ」「ガンタチイバラ」というものがありますが、本来はサルトリイバラが正しい名前とされています。冬になると花屋などで販売されていますが、その場合はサンキライという名前で流通しているので今ではこちらの方が通称名となっています。