カロケファルスの育て方

育てる環境について
育て方において、どのような環境に置くようにするかですが、日当たりを好むことから日当たりを中心に管理をしていくようにします。しかし夏における多湿、過湿状態を好みません。あまり湿った状態になっているとそれによって弱ってしまうことがあります。ですから風通しの良い所などを用意してそちらに置くようにします。
午前中などは日差しもそれ程強い状態にはなりませんから、そういった時間を狙って日光に当てます。午後などにおいては半日陰などに置くようにします。梅雨の季節、雨が続くようなときは予め室内に入れるようにします。そして水分に当たらないようにしなければいけません。
水が必要ないわけではないですが、必要以上の水に関してはあまり良い育ち方をすることができません。少し雨に濡れるくらいなら良いですが、断続的に降るような雨の時は当てないようにする必要があります。冬の寒さに関してはある程度は対応できます。暖地であれば霜の降りないところなどで管理をすれば容易に越冬することができます。
室内なら確実に越えることが出来るでしょう。秋であったり春、冬も含めてですが日当たりに当てることで成長を促すことができます。夏とそれ以外とでくっきりわけるように管理をした方がいいでしょう。日当たりの良い所に植えるのであれば、夏には少し遮光をするなどして暑さ対策が出来るようにします。そうすることで育ちは良くなり、夏の暑さで弱ることが少なくなります。
種付けや水やり、肥料について
栽培においては生育サイクルを考えて行うようにします。秋から冬にかけて植え替えをします。冬、春、夏と鑑賞することができます。このときに管理上最もネックになるのが夏です。夏の過湿、多湿で失うことになる場合があります。用土を用意するときには水はけがしっかり取れるようなタイプにします。保水するような土になると長く水分があたりつづけることになります。
過湿状態になるので木としては弱りやすくなります。土が水はけの良いタイプになっていればそのような心配も少なくなるので、安心して育てることができます。水やりのタイミングは鉢の土が白く乾いてから与えます。手で触って乾いていると感じてもまだ中の方は乾いていません。表面が白くなっている場合は中の方もそれなりに水分が抜けていますからその時には与えるようにします。
冬において水を与えようとするときは与え過ぎないようにしなければいけません。夏の多湿もよくありませんが、冬に関しては気温が低いので水分の蒸発がありません。となると少し上げたつもりでも過湿の状態になっていることがあります。それを防ぐためにもより乾かし気味の管理が必要になります。
水を上げた日をチェックして、何日置いているなど目で見てわかる管理をしておくと確実に行えます。なんとなくで管理をすると植物が弱ってしまいます。肥料に関しては春から初夏、秋にかけて与えます。真夏であったり冬の間は与える必要はありません。
増やし方や害虫について
増やし方としてあるのがさし木になります。春の5月から6月に行うのが最適とされています。この時期にできなかった時には秋の10月くらいに行っても問題はありません。まずは挿し穂の準備をします。7センチほど切り取り、それについている葉っぱについては一番下のものを取ります。葉っぱをとった部分が埋まるくらいに用土に差し込みます。
挿し穂に関してもあまり過湿状態を好みません。多くの植物においては成長させようとするときはできるだけ水分を与える、水分を切らさないようにする事が多いですが、この植物はこの時にも水分を減らし気味に管理をしていきます。用土としては鹿沼土、パーライトなどの水はけを重視した用土にさすようにします。
根が出てくるまでにはかなりの時間がかかるとされます。秋にさしたからといってその秋に根が出てくるとは限りません。冬から春にかけてようやく出てくることもあるのでかなりじっくり待つこともあります。新芽が出てくるようになれば用土を変えるようにして育てていきます。
この時の土に関しては赤玉土の小粒を5割、腐葉土2割、パーライトを3割ぐらいにした用土を利用して使います。生育はそれほど早い方ではありません。ですから植え替えの頻度もそれ程多くなくて良いと言われています。2年から3年に1回ほどで十分でしょう。害虫であったり病気に関してはそれ程問題はありません。混みあうと蒸れてしまうので、剪定や切り戻しを行います。
カロケファルスの歴史
日本においては盆栽を趣味にすることがあります。盆栽の主類は様々ですが、植木鉢程度の小さい鉢ながら立派な枝振りの植物を育てます。木のように育つようなものでも植木鉢で育てることが出来るようになっています。他の国ではあまり見られないことのようで、現在はネットショッピングなので海外の人が日本の業者から購入することがあるようです。
購入したとしてもそれをきちんと管理したり育てないといけませんから、それ以降が少し大変になるかもしれません。盆栽のようなものはなくてもそれに近いような栽培の仕方を行うものはあるようです。カロケファルスと呼ばれる植物があります。こちらはオーストラリアが原産の植物になります。
別名としてはプラチーナと呼ばれていたり、シルバーブッシュと言われたりしています。一番わかり易いのはシルバーブッシュになるでしょう。銀色の草ですからまさにそのようにみえることもあります。カラーリーフとして日本においてお非常に人気のある種類になっています。こちらについてはいつ頃日本に来たかどうか、
いつ頃から世界において知られるようになったかについてはわからない部分もありますが、世界においてはかなり広まっていますから、かなり前から知られていた植物になるでしょう。コレが大きく育つようならあまり広まらなかったかもしれませんが、日本の盆栽のように小さい植木鉢でも育てることができたのが広まった要素になるかもしれません。
カロケファルスの特徴
見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては普通ぐらいといえるでしょう。マイナス3度以上ぐらいとされているので、関東から西であれば十分育てること、栽培することができそうです。暑さに関してはそれ程強さを持っていないため、夏の管理をきちんとしないといけないかもしれません。
木の高さに関しては、高いものでも50センチほどと言われます。こちらについては巨大化するわけではないので、自分なりに好みに合わせてもう少し小さく管理をすることもあるでしょうし、少し大きめに行うこともあるでしょう。なんとも良いこととしては常に鑑賞することができることです。花を楽しむわけではなく、木の枝ぶり、色を楽しむことになります。
シルバーブッシュとのことで銀色に見えますが、実際によく見ると濃い緑色になります。それに白い毛がたくさん生えていて、それによって銀色に見えるようになっています。出まわる時期としては秋から冬です。クリスマスに飾っていたり、新年において飾ることもあるでしょう。一度購入すれば、
その後はだいたいいつでも楽しめます。屋外で越冬させることが可能ですが、多くの場合は観葉植物として自宅の中で管理するかもしれません。生息地はオーストラリアの海岸付近になります。暑さや乾燥にはそれなりの対応をすることができますが、日本の過湿はあまり好まない植物になります。
-

-
植物の育て方を勉強する
現在は、家庭菜園などで野菜を栽培している人たちも多く存在しています。自分で手入れをして栽培した野菜を食する事ができるのは...
-

-
アサギリソウの育て方
アサギリソウは、ロシアのサハラン・日本が原産国とされ、生息地は北陸から北の日本海沿岸から北海等、南千島などの高山や海岸で...
-

-
枝豆の育て方
枝豆は大豆になる前の未成熟な豆のことです。大豆は東アジアが生息地で、自生していた野生のツル豆が中国の東北部で進化したこと...
-

-
ソラマメの育て方
世界で最も古い農作物の一つといわれています。生息地といえば例えば、チグリス・ユーフラテス川の流域では新石器時代から栽培さ...
-

-
ハナイカダの育て方
ハナイカダはミズキ科の植物です。とても形がユニークですので一度見ると忘れないのではないでしょうか。葉っぱだけだと普通の植...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
キュウリの育て方のポイント
水分を豊富に含むキュウリは、原産地はインドやヒマラヤであり、そのあたりが生息地と考えられています。栽培されていたのは、さ...
-

-
キンセンカとハボタンの育て方
冬枯れの戸外で一際鮮やかに色彩を誇るのがハボタンです。江戸時代中期に緑色のキャベツに似たものが長崎に渡来して、オランダナ...
-

-
コツラの育て方
この花の特徴はキク科となります。小さい花なので近くに行かないとどのような花かわかりにくいですが、近くで見ればこれがキク科...
-

-
カロケファルスの育て方
見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては...




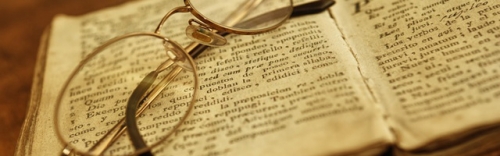





見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては普通ぐらいといえるでしょう。マイナス3度以上ぐらいとされているので、関東から西であれば十分育てること、栽培することができそうです。別名としてはプラチーナと呼ばれていたり、シルバーブッシュと言われたりしています。一番わかり易いのはシルバーブッシュになるでしょう。