ハナカンザシの育て方

ハナカンザシの種付け
霜の降りない暖地なら9月から10月に種付けをすると冬を越して春にはなを咲かせます。霜が降りる地域なら冬が終わって春が来てから3月ごろに種付けをするとその春にはなを咲かせます。しかし3月に種付けをすると花が咲くのが遅くなり、すぐに高温多湿の気候になってしまうので開花期間が短くなります。
そのためには霜が降りる地域でも霜よけをして種付けをすれば秋まきと同じように花が咲くようになります。水はけの良い土でできればアルカリ性の土に種をまきます。土は種がうっすらと隠れるくらいにかぶせます。それから初期は水きれがないように水をやるようにし、本葉が数枚見えてきたら根を切らないように10cmくらいのポットに植え替えます。
庭に地植えをしてもよいのですが、雨で多湿になってしまうのを防いだりきれいにまとなるためには鉢やプランターなどに植えるのが良いでしょう。鉢やプランターなどなら軒下に入れることができます。日光を好むのでよく日の当たるところで、雨があまり当たらないところで栽培をします。
花に水が当たると傷みやすいので、水やりをするときにも花に水がかからないようにできるだけ株元に水をかけるようにします。乾燥を好み多湿になると蒸れてしまうので土が乾いたころにたっぷりとやるようにし、土が湿っているうちは水やりはしないようにします。肥料はほとんど必要としないので培養土を用いるならそれだけで十分ですが与える場合は液肥をつきに一度くらい与えるようにします。
ハナカンザシの上手な育て方
とにかく高温多湿が苦手で、良く日が当たり乾燥した環境を好むということを念頭に置いてそのような環境のもとで栽培するようにします。また寒さに強いといっても耐寒温度はマイナス2度くらいです。それ以下の気温や霜には弱いので、飴だけでなく雪や霜にも当たらないようにすることが大切なので室内の日当りの良いところか戸外の軒下で管理するようにします。
ただ乾燥を好むとしてもまったく水がない状態では枯れてしまうので土が乾いたときの水やりは欠かせないようにします。病気や害虫に関してはアブラムシやハモグリバエがつくことがある程度ですが虫を見つけたら殺虫剤で退治をするか、虫予防の薬を事前に撒いておくとよいでしょう。
ハナカンザシを長く楽しむ
ハナカンザシは春に花が咲いても高温多湿になるころには終わってしまいます。しかし少しでも長く花を楽しむためには、咲いてしまった花はどんどん摘むようにして行きます。また花が一通り咲き終わって株の形が悪くなってきたら切り戻しをするようにします。
切り戻しをしなくても枯れるということはないのですが切り戻しをすることで、切った茎のわきから新しい芽が生えるのでもう一度咲く可能性があるのです。切り戻しの仕方は地面から10cmから15cm残して上の部分で切ります。その際に葉を残すように切ります。花が咲いていた場所からすぐ下の部分でも同じような効果があります。
切り戻しをするのは新しい芽を出させる効果があるほか株全体に風通しをよくして蒸れを防ぐという効果もあるので、ハナカンザシを上手に栽培するうえで大切なことです。ハナカンザシは種で栽培するのですが、挿し木でも増やすことができます。挿し木は切り戻した茎を2、3時間水に浸しておき、その後に土に植え付けます。
それから根がつくまでは水やりだけは欠かさないようにして日陰で保管します。元気に育って根が生えてきたら鉢などに丁寧に植え替えるようにします。はじめから鉢に植えてもよいでしょう。
ハナカンザシを育ててみる
ハナカンザシの育て方は少し難しい方なのですが、日光によく当てて、水をやりすぎないようにし、また雨や雪、霜からもできるだけ避けて育てるという育て方を守ることで枯らさないで、可愛い花を楽しむことができます。土が乾いたら水やりをするのですが、花に水がかかると傷んでくるので、水やりの仕方も花にかからないように注意をします。
そして株が茎葉が茂り風通しが悪く蒸れるようなら、切り戻しをすることで風通しを良くして、新しい芽を出させることもできます。このような育て方をしていればハナカンザシの花を長く楽しむことができます。ガーデニングの初心者の人にとっても水やりの仕方とタイミング、日当りをよくする、高温多湿を避けるという点に注意をしながらハナカンザシの栽培に挑戦してみてもよいでしょう。
ハナカンザシは種から栽培するのも楽しいですが、冬から春にかけて苗でも市販されているのでその苗から育てることもできます。日本では一年草の花ですが、本来葉多年草なので、乾燥気味で良く日が当たるという環境が合っていて高温多湿な夏を乗り越え、厳寒の冬も超えることができれば翌年の春には再度花が咲くことも期待できます。そして挿し芽や切り戻しをすることによって増やしていくこともできるので挑戦してみるとよいでしょう。
ハナカンザシの特徴
キク科ローダンセ属の多年草植物で、かさかさした感触をした花が特徴的でドライフラワーやポプリとしても用いられている花です。別名はヘリクリサムやアクロクリニウムとも言いますが、見た目も丸みを帯びたつぼみがかんざしに似ていることからハナカンザシという名前で知られていて、小さな花が冬の風に揺られている姿から「冬の妖精」とも言われています。
ちなみにヘリクリサムは「太陽の翼」という意味から付けられています。つぼみの時は赤くて咲いたら白い花になります。ピンクの花の品種もあります。花の真ん中は黄色で愛らしい花で夜になると花が閉じるのも特徴的です。しかし実は花弁がなく黄色い筒状の花を白い総苞と言われる花序全体を包み込む葉のようなものが取り囲んでいるという状態なのです。
その総苞が大きく発達して花弁のようになっているのです。ハナカンザシは寒さには強いのですが、高温多湿が苦手なので夏を越すことが難しい花なので初夏まで楽しむ花といえます。開花時期は2月から6月で一つの株から花茎がたくさん出て、その20cmから50cmの茎の先に5cmくらいの花を一個づつ付けます。
葉は披針形で互い違いに生えます。軟らかくて白っぽい緑色をし、毛が生えている葉です。花が咲いた後には実ができて熟すると破裂して種子が散布されます。生息地としては高温多湿ではない地域が良いので、本来日本はあまり生育には合わないのですが、高温多湿になる夏前までの一年草として栽培されています。
鉢植え、ドライフラワー、ポプリだけではなく寄せ植えとしても用いられますが、高温多湿で蒸れることを防ぐためには高温になる季節までが寄せ植えに適している時期で、気温が上がってきたら寄せ植えにはしない方が良いでしょう。
高温多湿が苦手で、日光と乾燥を好む植物で、土の表面が乾いてきたらたっぷりと水を上げ、土が湿っているうちは水やりはしないようにします。しかし乾燥しすぎても枯れてしまうので水やりのタイミングを見極めることが大切です。
また花に水が当たると傷んでしまうので水やりをするときには株元にかけるようにし、雨や霜もかからないように注意が必要な植物ですが、その点に注意をして育てれば可愛い花を楽しむことができ、日本では一年草で菅、上手に育てて夏を越すことができればまた翌年も花が咲く可能性もあるので、栽培に挑戦してみるのもよいでしょう。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)の育て方
タイトル:メランポジウムの育て方
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
エゴポディウムの育て方
セリ科・エゴポディウム属の耐寒性多年草です。和名はイワミツバと呼ばれ、春先の葉の柔らかい部分は食用にもなります。エゴポデ...
-

-
カラマツソウの育て方
カラマツソウ(唐松草)/学名:Thalictrum aquilegifolium(唐松草)・Trautvetteria ...
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...
-

-
キサントソーマの育て方
この植物の特徴としてはサトイモ科の常緑多年草になります。生息地の熱帯のアメリカにおいては40種類近く分布するとされていま...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...
-

-
シンボルツリーとしても人気の植物「オリーブ」の育て方
オリーブは常緑性のモクセイ科の植物で、原産国は中近東・地中海沿岸・北アフリカと考えられています。樹高は10~15mで、最...
-

-
モクレンの育て方
中国南西部が原産地である”モクレン”。日本が原産地だと思っている人も多くいますが実は中国が原産地になります。また中国や日...
-

-
カロライナジャスミンの育て方
カロライナジャスミンは、北アメリカの南部から、グアテマラが原産の、つるで伸びていく植物です。ジャスミンといえば、ジャスミ...
-

-
コンボルブルスの育て方
コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木...





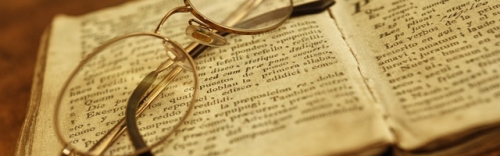





原産地はオーストラリア西南部で、砂地でよく育ち乾燥を好み自生しています。日本ではドライフラワーなどに良くつかわれていますが、寄せ植えでも用いられています。