ムクゲの育て方

ムクゲの育て方
ムクゲは一般的に落葉中の12月から3月に植えつけます。ムクゲは大変育てやすく、一度植え付けてしまうと手間が掛からない丈夫な性質をもった栽培しやすい花木です。耐寒性や耐暑性といったものがあるので育てやすいといえます。
地植えでは、日当たりや水はけの良い場所が適しています。また根が深く、横に広がらない性質なので狭い場所に植えることができる利点があります。やや明るい半日陰のような場所も育ちますが、花付きが悪くなることがあります。
夏の暑さに強い花なので日当たり重視で選んでもかまいません。日当りがよく、冬に寒風が当たらない場所を選びます。土壌は、水はけのよい土であれば特に選びませんが、夏の高温期の極度な乾燥を嫌うので腐葉土などを土と混ぜて使うほうがおすすめです。
根鉢より1回り大きな植え穴を掘り、腐葉土あるいはピートモスに、元肥として粒状肥料を与えて土と混合して植え付けます。それから、根鉢のまわりに十分に水を注ぎ、棒などでつついて根と土をなじませます。
鉢植えでも育てることができ、鉢植えは暖かくなってくる3月頃が適しています。またムクゲは、繁殖力が強いので植える場所はほかの樹木に影響しないようにある程度考えて植えたほうがいいです。
ムクゲの管理や剪定
ムクゲは日当たりがよいところ好むので、日当たりの良い場所で管理します。地植えの場合は、水やりは雨水だけで基本的には必要はありません。ですが、夏の乾燥には注意してください。極度の乾燥を嫌うので日照りなどでは適度に水をやる必要があります。
冬の寒さにも強いので北海道の南部くらいなら耐寒性があり育てることが可能です。花付きをよくするためには日当たりが重要ですので、鉢植えなども日当たりの良い場所で管理し、移動させて育成してください。
冬は、暖地でも寒風の当たらない、日当たりがよい場所が適しています。肥料は、開花する7月上旬から10月に、緩効性の化成肥料を少なめに追肥すると花つきがよくなります。または、寒肥として12月から1月に、完熟堆肥などを株から少し離してすきこむのもおすすめです。
またムクゲは丈夫な性質なので強い刈り込みにも耐えます。いろんな樹形にすることもでき、「枝を切ったことが原因で花が咲かない」という心配がなく、剪定の難しさがないのもよいところです。剪定時期は、春に枝が伸びた後に花芽をつくるので、そのため剪定は落葉中に行います。
基本となる剪定というのは特になく、どこを切ってもよいので樹形や全体のバランスを考えながら枝を切ることがポイントとなります。強めに剪定したほうが花付きがよくなることもあるようです。
剪定をせず放置しておいたとしても、ある程度はまとまった樹形になりますので、大きさを気にしないのであればほとんど剪定をする必要はありません。ですが、枝がこんで日当たりが悪くなるといったことには剪定が必要です。その場合は、枝の付け根から切り落として樹の内部までしっかりと日が当たるようにしてあげてください。
ムクゲの増やし方と病害虫
ムクゲは、うまく種付けすればたくさん増やすことも可能です。増やす方法は、さし木や種まきです。適期は、葉の出る前の3月から4月ですが、時期は二通りあります。3月頃まだ新芽が出ていない落葉期に行う「休眠枝ざし」と、初夏か秋にその年伸びた枝を使う「緑枝(りょくし)ざし」というものです。
休眠枝ざしは根付きがよく地面に直接さしておくだけで根が出ることもあるのでおすすめの時期といえます。さし木のやり方は、枝を長さ10cmから15cmに切り、先端の葉2枚から3枚を残して後は取り除きます。少し水揚げしてあげてから土にさします。
さし木の成功率を高めるためにも、土にさす前には切り口に植物成長調整剤「ルートン」を薄くまぶしてから土にさしてください。土は、赤玉土小粒を使用するのもいいですが、面倒ならさし木専用土を使ってもよいです。その後はたっぷりと水やりをして、日陰で管理します。
水きれを起こさないように管理すれば一か月くらいで発根します。種をまく場合は、秋にできたタネを採ってすぐにまく「とりまき」か、またはその種を乾燥しないように保存しておき、翌年の春3月下旬以降にまいてあげるかしてください。
ムクゲは、わりと丈夫なので病気といったものはとくにないですが、害虫というのがよくつきます。害虫には、ハマキムシ、アブラムシ、ワタノメイガ、テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)などがあります。とくに春から夏にかけて新芽や枝にアブラムシがよくつくので注意してください。
葉を食害するハマキムシの被害もあり、被害が大きいのであれば薬剤を散布して駆除するのがよいです。ほかにも、テッポウムシという木のなかに入って食い散らかす害虫の被害もあります。強い性質なのでよっぽどのことがない限り、木ごと枯れてしまうことはないですが、害虫対策は必要と考えておいたほうがよいです。
ムクゲの歴史
ムクゲはインドや中国原産とされる落葉樹です。生息地は広く、中近東になどにも分布しています。韓国の国花として知られていますが、原産は中国です。日本でも平安時代以前の奈良時代に中国から渡来しましたが、和歌山県や山口県には野生のムクゲがあったとされています。
日本では、古くから庭木や生け垣として栽培されてきました。また、「万葉集」の秋の七草のひとつとして登場する朝貌(あさがお)がムクゲのことを指しているという説もありますが、定かではありません。
アオイ科フヨウ属とされており、寒さに強いために、欧米でも夏咲きの花木として人気があります。ムクゲは、中国名を 木槿(モクキン)韓国名を無窮花(ムグンファ)別名をハチス、キハチスなどと呼ばれています。
また、ムクゲは一日花とも呼ばれ、早朝に花が咲いて夕方にはしぼんでしまう短命のためといわれています。なぜそんなかよわい花が韓国の国花なのかというと、「散って咲き、また散っては咲く生命力の強さ」または「一時に咲かず、ねばり強く咲き続ける様」が韓国の歴史と重なっているからとされています。
ムクゲの特徴
ムクゲには多数の品種があり、姿がとても似ているフヨウとも混同されがちですが、一般的には雌しべが真っ直ぐなものがムクゲ、先が上向きに曲がっているのがフヨウと区別することができます。またムクゲは多少枝分かれし、それぞれの枝を真っ直ぐ上に伸びながら成長するので、縦長の樹形をしています。
フヨウはというと、細かく枝分かれしながら成長していき、上だけでなく横にも広がるので樹形の違いをみればどちらなのかわかります。盛夏を彩る代表的な花木といえ、暑い日などに咲いているのをみると元気な気分になるというひともいます。
特徴としては、花の大きさは5cmから10cmほどで、中心に大きな雌しべとこれに付着した雄しべが多数あります。見た目は同じ仲間であるハイビスカスのような花をしています。色は一般的なものでは、白やピンクとされており、中心が赤色のものをよく見かけますが、八重咲きや花びらの形に特徴を持ったものがたくさん存在します。
たとえば、八重咲きに至っては、同じ木の花でもバラ咲きやカーネーションのような咲き方をすることがあり、進化したり先祖がえりしたり、それを見るのが楽しみの一つと思うひともいるようです。
とても風情を感じる、味わい深い花木なのでたくさんのひとに愛されています。また、同じ色合いのものでも微妙に花びらの形が違っているなど、バリエーションの多さというのもムクゲの魅力かもしれません。
ムクゲは槿皮(チンピ)という名で樹皮を乾燥させて生薬としても使われています。韓国では若葉を食し、葉はお茶として利用するようです。また花の蕾なども乾燥させれば、胃腸炎、下痢止め薬としての利用ができます。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:シャクナゲの育て方
タイトル:クチナシの育て方
タイトル:カーネーションの育て方
-

-
インゲンの育て方
豆の栽培は農耕文化が誕生したときから穀類と並んで始まったと言われています。乾燥豆は品質を低下させずに長い期間貯蔵できるこ...
-

-
オキザリスの育て方
オキザリスはカタバミ科カタバミ属の多年性の植物です。原産地は南アメリカや南アフリカですが、非常の多くの種類があり、世界中...
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...
-

-
観葉植物として人気のシュガーバインの育て方
シュガーバインは可愛らしい5つの葉からなるつる性の植物です。常緑蔓生多年草で育て方も簡単なので初心者の人にもおすすめです...
-

-
ゴンズイの育て方
この植物はミツバウツギ科の植物で、落葉樹でもあり、樹高は3メートルから6メートルぐらいということです。庭木としても見栄え...
-

-
シッサスの育て方
シッサスはオランダで品種改良をされたという歴史を持っていて、ブドウ科の植物なので葉っぱの裏側には白い樹液のかたまりが付着...
-

-
ヘリアンサスの育て方
特徴としてはまずどの種類に属するかがあります。キク科のヘリアンサス属と呼ばれる種類に該当します。ヒマワリ属としても知られ...
-

-
ノコンギクの育て方
ノコンギクの歴史としまして、伝統的にはこの種には長らく「Aster ageratoides Turcz. subsp. ...
-

-
オーニソガラムの育て方
オーニソガラムはヨーロッパから西アジア、アフリカが生息地で、約100種類ほどがある球根植物です。ヒアシンス科、オオアマナ...
-

-
マルバタケブキの育て方
マルバタケブキはキク科メタカラコウ属の植物です。原産が日本です。漢字による表記は、丸葉岳蕗です。生息地は日本と中国に分布...




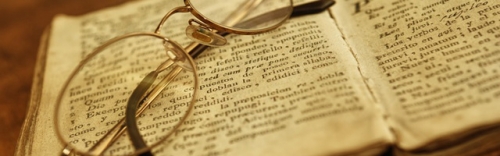




ムクゲはインドや中国原産とされる落葉樹です。生息地は広く、中近東になどにも分布しています。韓国の国花として知られていますが、原産は中国です。日本でも平安時代以前の奈良時代に中国から渡来しましたが、和歌山県や山口県には野生のムクゲがあったとされています。