テコフィレアの育て方

育てる環境について
テコフィレアの生息地は乾燥したところが中心となっています。たとえば秋から冬に雨が降ったり雪が降ったりするところで、春から夏の間はほとんど雨が降らないというような半分砂漠のような所を好んで生息します。冬になり氷点下になっても育つことができます。
氷点下になったときでも地中まで凍ると言うことはありません。球根はしっかりと寒さから守られているからです。庭に植えようと考えている人も多くなっていますが、どちらかといえば庭に植えるのにはあまり向いていません。したがって鉢のなかで栽培をするようにします。
鉢のなかで発芽をして花が開くまでは、凍らない涼しいところで育てるようにします。発芽をした後の育て方に関しては、よく日に当てるというのを心がけます。夏は休眠するようになっているので、この休眠中には鉢に植えたまま乾燥させておくようにします。
花を咲かせた後には種を作りますが、種を取らないと言うこともあります。このように種を取らない場合には球根をしっかりと太らせるために、花が咲き終わった花がらをしっかりと切り取ると言うことを行います。現在多くのところで流通している物は、栽培が行われて属食された物となっています。
それは自生地では絶滅したと考えられているからですl。チリだけではなくブラジル南部やペリーに広く分布しています。比較的暖かいところに生息していることが多いです。花は小さくインパクトがあるというような物ではありませんが、かわいらしい雰囲気があります。
種付けや水やり、肥料について
しっかりと成長させるなかで、水やりをするということはとても重要ですが、水やりに関しては、秋の涼しくなった頃から始めるようにします。そして秋から冬にかけては少し乾かし気味にしておくようにします。春に発芽をして花が開いていきますが、この時期は少し多めに水やりをするようにします。
そして花が開いた後には少しずつ水の量を減らしていきます。やがて葉が枯れて休眠になりますが、このような状態になれば水やりをする必要がありません。肥料もしっかりと与えるようにします。肥料に関しては、芽が出てから花が開いた後に、
葉が茂っている間に規定よりも少し薄めの液体肥料を与えるようにします。その回数は月に2回から3回ということになります。液体肥料でなくても置き肥でも構いませんが、このときには注意をしなければいけないことがあります。置き肥の場合には漁を少し少なめにしておきます。
10月から11月がテコフィレアの植え付けに適した時期となっています。3号鉢の場合には1球を植え、5号の鉢の場合には3球から5球植えることができます。球根の大きさが気になりますが、球根は直径1.5センチメートル程度のたまねぎのような形の物を使うようにします。
この球根を3センチメートルから5センチメートルの深さに植えるようにします。植え付けに関してはこのようなことに注意して行います。植え替えは、2年から3年ごとに新しい用土で植え替えをしていきます。
増やし方や害虫について
育てるときに使う土ですが、これは小粒の軽石と鹿沼土を均等に配合した用土がもっとも使いやすくなっています。同時に管理をする際にもとても楽になっています。4号から5号の鉢の場合には、2年間から3年間はそのままでもあまり問題はありません。
増やし方に関しては、分球で増やすことができます。したがって植え替えの時には球根を一つずつばらして植えるようにします。花が咲いた後に種が実ると言うこともあります。このようなときにはこれをしっかりと残しておき秋に種をまくようにします。
これを植えて開花するまでの期間は4年から5年が必要になります。時間がかかるようになっていますが、これは状態や種類によって異なっていると言うことを頭にいておきます。種を取らないときには球根の栄養のことを考えて花がらをしっかりと集めておくようにします。
テコフィレアの害虫や病気にはどのような物があるのかということが気になります。病気はとくに環境が悪くなければ発生すると言うことがありません。しかし肥料を与えすぎたり、水はけが悪いような環境の時には、病気になる可能性が高くなります。
したがって油断しないようにします。害虫としてはアブラムシの被害が多くなっています。アブラムシが茎や葉の部分に付くことがあるので、見つければ防除を行います。テコフィレアが害虫の被害にあっているかどうかを判断するためには、こまめに状態を確認すると言うことが必要になります。
テコフィレアの歴史
南米にはたくさんの野生生物が生息しているとされています。そのなかでテコフィレアという植物があります。これは美しい青色をしており、チリの首都であるサンティアゴ周辺の標高3000メートルのアンデス山脈に自生をしていましたが、19世紀の姿が発見されてからは、
乱獲が行われるようになりました。その後掘り出したことと共に動物にも食べられるというようなことがあり、絶滅したと考えられていました。しかしその後時代が流れ20年に私有地に自生をしている姿が発見されたのです。そしてその後保護されて保存されるようになっています。
イギリスなどと共同でチリの国立森林公社が野生復帰のために働きかけています。高さが10センチメートルになるかどうかというような小さな株に関しては、分球をするということがとても難しくなっています。現在では市場に出る量も限られています。
テコフィレアはアンデスの青い星とも呼ばれるほど多くの人に愛されています。春の早い時期に花を咲かせ、目の覚めるようなとても鮮やかな青色をしているというのが特徴です。秋に球根を植えるようになっており、流通量が少なくなっています。したがって少し高価な球根となっています。
今後増えてくるともう少し安い価格で球根を購入することができるようになります。原産地では絶滅をしたともいわれている非常に貴重な花となっています。この花は少し香りがあり夜も花が開いています。年数が経過することで花の数が増えて長期間楽しむことができます。
テコフィレアの特徴
テコフィレアはほのかに香りがする花となっています。多くの種類があり花の中心の白い部分が広がっているというのが特徴です。見た目にも大きな花で数年間は鉢のなかに植えた状態のままでも楽しむことができます。夏の間は休眠しています。
したがってこのときには鉢のままで乾燥させておきます。秋になると少し涼しくなってくるので、このときに水やりをします。球根が腐るということもなく、比較的簡単に育てることができます。草の姿はクロッカスのように見えます。しかしクロッカスとは異なっており、
2枚から3枚の葉が交互に開くようになっています。その中心部分から短い花茎が伸びて1本の花茎に対して1輪の花を咲かせるようになっています。このときの花茎は3本から4本は立つようになっています。しかしこれは球根の大きさによって異なっています。
春に花が咲いた後には6月以降は葉が枯れて休眠するようになっています。園芸分類は球根で多年草となっています。草の長さは5センチメートルから10センチメートルとなっています。花の色は青と紫で、寒さや暑さにはそれほど弱くありません。
生息地はチリを中心に広がっています。テコフィレアの花が開く時期は2月から3月と少し早めです。落葉樹で鉢植えやロックガーデンで植えられることが多くなっています。植え付けや植え替えの時期は10月から11月です。肥料は2月から4月の間に月に2回から3回液体肥料を与えるようにします。
-

-
スナップエンドウの育て方
スナップエンドウは若くてみずみずしい食感を楽しませてくれる春の食材です。このスナップエンドウはグリーンピースとして知られ...
-

-
カナメモチの育て方
カナメモチの原産は日本や中国などで、国内の生息地は伊豆半島より西側、四国や九州など比較的暖かい地域に分布しています。カナ...
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...
-

-
タイリンエイザンスミレの育て方
多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすい...
-

-
フジの育て方
藤が歴史の中で最初に登場するのは有名な書物である古事記の中です。時は712年ごろ、男神が女神にきれいなフジの花を贈り、彼...
-

-
チオノドクサの育て方
チオノドクサという植物は東地中海クレタ島やトルコの高山が原産で、現在ではヨーロッパの山々を生息地とする高山植物の一種です...
-

-
ルバープの育て方と注意点とは。
ルバープは和名をショクヨウダイオウといい、シベリア南部地方原産のタデ科の多年草です。大型の植物で高さは1メートル以上にな...
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
デルフィニウムの育て方
デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん...
-

-
マキシラリアの育て方
この花の種類としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科となっています。常緑の多年草となっているので、ずっと花を咲かせる...




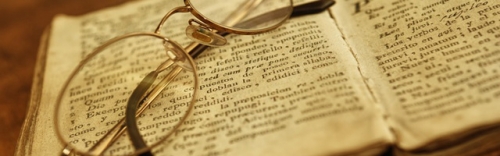





南米にはたくさんの野生生物が生息しているとされています。そのなかでテコフィレアという植物があります。テコフィレアは、テコフィレア科、テコフィレア属になります。また、その他の名前は、チリアンブルー・クロッカス,テコフィラエアなどと呼ばれています。