コヒルガオの育て方

育てる環境について
コヒルガオは太陽が良く当たる場所をとても好みます。育て方として重要なのは、日当たりが良い場所を選ぶと言う事です。そうすればグングン成長していきます。ただそれ程水分を欲する植物ではないので、あまりこまめに水やりをする必要はありません。からからに乾いたままで放置しておかなければ、それ程水の管理について慎重になる必要はありません。
適している環境としては鉢植えやプランターなどです。直接地面に植えてしまえば管理もすごく楽なのではないかと思う人もいるかもしれませんが、地面に植えるのには注意が必要です。地面であれば空き地などに自生しているのと同じ状態になるので、確かに水やりなどに関して気にする必要は全くなくなります。
しかしコヒルガオ自体の生命力はとても高い事、さらに根の生長・張り方などはとても強くなっています。そのため、周りの植物に影響を与えてしまう事が多々あるので注意が必要です。実際に栽培する時は、鉢植えで育てるのが便利です。アサガオを育てる時と同様、ツルを巻きつける事が出来るものを用意しておけば、
他の部分に巻き付いてしまう事を極力減らす事が出来ます。また鉢植えであれば必要に応じて場所移動する事も出来るので便利です。中に入れる土に関しては、出来るだけ水はけが良いタイプにしておく事が無難です。鉢の下には鉢皿を置く事、これによって種が落ちてしまって地面の所で勝手に増えて行くという事を防ぐ事が出来ます。
種付けや水やり、肥料について
コヒルガオはアサガオとは違ってなかなか種ができにくい種類の植物です。もし出来たとしても、その粒はとても小さくなっています。ただ種をまく事は可能なので、時期が来たらまいてみるのも良いでしょう。種付けの時期としては、アサガオなどと同様に春ごろが適しています。とても植物としても丈夫なのですが、やはりあまりにも暑い時期や寒い時期と言うのは適していません。
大体5月位になったら種をまきます。まく時は事前に水に一晩くらい浸しておく方が、発芽率が高くなります。水やりに関しては、それ程気にする必要はありません。アサガオの様に朝晩与える必要があるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、1日に2回も与えると与えすぎになってしまいます。
与えすぎると成長を阻害してしまう事にもつながるので、水は適宜与えるのがベストです。ただ乾燥し過ぎていると他の植物と同様に枯れてしまいます。数日に1回は水やりを行うのが良いでしょう。肥料に関しては、とても丈夫な植物なので特別用意する必要はありません。そのまま育てていたとしても十分育って行きます。
もし与える場合は、固形の費用を置肥として与えるか、非常に薄くした液体肥料を1か月に1回程度与えれば大丈夫です。それ程神経質になって育てる必要はないので、水やり、肥料に関してはコヒルガオの育って行く様子を見ながら適宜調整していく事が重要です。そうすれば過剰に与えてしまう事も十分防ぐ事が出来ます。
増やし方や害虫について
コヒルガオ自体は種が出来る植物ですが、一般的には種ではなく株分けで増やします。アサガオに良く似た植物なので種も沢山出来そうだと思われがちですが、実際にはそうではありません。なかなかできないだけでなく、できたとしてもとても小さい粒なのでうまく発芽しない事も有ります。反対に根はとても丈夫なので、株分けをすれば簡単に増えて行きます。
株分けをしなくても地面に植えておけばドンドン増えて行きます。他の植物に影響を与えずに上手にコヒルガオを増やしたいと思ったら、鉢植えのまま増やしていく事が重要です。ただ鉢自体が地面と接していると、そこから地下茎で増える事も有ります。鉢以外で育てたくないと思っている人は、鉢皿を利用します。
丈夫な植物なのでそれ程心配する必要はありませんが、害虫が付いてしまう事が有ります。有名なのがヒルガオハモグリガです。これは蛾の一種で、葉の部分を食べてしまいます。葉全体を食べるのではなく、葉肉だけを食べてしまいます。うっすらと1枚膜が残っている様な感じに見える食べた跡が発見された場合は、
ヒルガオハモグリガの幼虫がいる可能性が多々あります。多発すると葉が枯れてしまう事があるので注意が必要です。もし発見した場合は駆除を必要とします。被害が出たまま放置していると、すぐに被害が大きく広がって行きます。葉の異変に気づいたら薬剤を散布し、駆除する事が重要です。薬剤は大体1週間おき2回から3回散布すると効果が出て来ます。
コヒルガオの歴史
ヒルガオに良く似た花を咲かせる植物がコヒルガオです。一般的にはどんな場所にでも咲いている花なので、道端などで見たことがある人もいる植物です。大抵の場合は雑草として扱われてしまう事も有りますが、現在では園芸種として改良され、ガーデニングなどで楽しんでいる人もいます。つる性の多年草なので、一度そこで花を咲かせると来年、再来年も楽しむ事が出来ます。
現在、日本では花を楽しむ植物となっていますが、薬用植物としても有名です。中国では植物全体を利用する事もあります。また若葉は食する事が可能です。コヒルガオの名前は、昼まで花を咲かせているという事が由来となっています。一般的に花の名前はその花がどういう風に咲いているかで名づけられる事も多々あり、この植物も例外ではありません。
原産地はアジア東部・南部となっているのですが、日本国内本州から九州まで、様々な場所で見る事ができます。日当たりの良い場所等を探すと簡単に見つける事ができます。一見ヒルガオととても似ている植物なので区別しづらいと言う人も少なくありません。
しかし歴史的な広がり方や生息地などを見ると、両者には大きな違いがあります。また葉の形や軸の部分の様子、さらに花の大きさ等からも区別をつけることは可能です。しかしやはりぱっと見るだけだとなかなか両者の違いが良く分からないと言われる事は多々あります。そのため、以前からヒルガオと間違えられる事が多々ある植物です。
コヒルガオの特徴
コヒルガオの大きな特徴は、その花の咲き方です。アサガオやヒルガオと同じ様な咲き方をしています。またヒルガオと同様、昼ごろまでその花を咲かせ続けるのでその名が付きました。園芸種として品種改良された物は、自生している種類に比べると花弁の数は多く、大体8枚花弁となっています。もう一つの特徴は花が小ぶりだと言う事です。
こうした咲き方をする花はある程度の大きさがあるイメージがあるかもしれませんが、この植物に関してはそうではありません。大体花の大きさは直径3㎝から4㎝となっています。この大きさによってヒルガオと区別をつけることも可能です。花の色は淡いピンク色です。ヒルガオよりも色が薄いと言うので両者の違いを判断する事もできます。
あとは、花柄に縮れがあると言う事も特徴と言えます。花柄とは、花の真下の茎の部分の事を言います。この部分に縮れがある為、実際に違いを良く見なくても触っただけでもヒルガオではないと言う事は判断する事が出来ます。日当たりの良い場所を好むため、野原や道端などで見る事が出来る植物です。
多年草なのですが、現時点ではそれ程自生している個体数は多い方ではありません。茎自体は長くツル状になっています。地面を這って成長していく事も有りますが、多くの場合は他の植物などに巻きつきながら上へと延びて行きます。葉の形はホコ型になっています。ヒルガオに比べると少々長めの葉になっているのも大きな特徴と言えるでしょう。
-

-
ヘレボルス・フェチダスの育て方
特徴としてはキンポウゲ科、クリスマスローズ属、ヘルボルス族に該当するとされています。この花の特徴としてあるのは有茎種であ...
-

-
ハクサンボクの育て方
ハクサンボクの特徴としては、レンプクソウ科ガマズミ属と言われていますが、レンプクソウ科の上位であるマツムシソウ目の下位の...
-

-
スモークツリーの育て方
スモークツリーはウルシ科コティヌス属の雌雄異株の落葉樹になり、イングリッシュガーデンなどのシンボルツリーとして多く利用さ...
-

-
ラディッシュの育て方
ラディッシュとは、ヨーロッパ原産の、アブラナ科ダイコン属に分類される野菜です。ダイコンの中ではもっとも小さく、そして短期...
-

-
コキアの育て方
南ヨーロッパや温帯アジアが原産とされ、日本へは中国から伝わってきた植物で、詳しいことははっきりと分かっていませんが、「本...
-

-
ダイズの育て方
ダイズの歴史を調べてみると、はっきりとした起源がわからず、いくつかの説によって現代に伝えられていることがわかります。つま...
-

-
オキナグサの育て方
オキナグサはキンポウゲ科に属する多年草です。日本での歴史は、万葉集の随筆から江戸時代中期後期にかけて書かれた書物の中にも...
-

-
コリゼマの育て方
オーストラリア原産の”コリゼマ”。まだ日本に入ってきて間もない植物になります。花の色がとても鮮やかなオレンジ色をしており...
-

-
ドラセナ・フラグランス(Dracaena fragrans)...
ドラセナの原産地は、熱帯アジアやギニア、ナイジェリア、エチオピアなどのアフリカです。ドラセナの品種はおよそ60種類あり、...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...




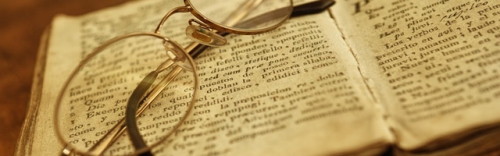





コヒルガオの大きな特徴は、その花の咲き方です。アサガオやヒルガオと同じ様な咲き方をしています。またヒルガオと同様、昼ごろまでその花を咲かせ続けるのでその名が付きました。園芸種として品種改良された物は、自生している種類に比べると花弁の数は多く、大体8枚花弁となっています。