キンカン類の育て方

キンカン類の育てる環境について
キンカンの育て方と言うのは柑橘類であるため、害虫などには注意を要します。また、鳥などの被害もあり、ネットなどを張って防御する事も大切です。そのため、育てる環境と言うのはネットを張れるようなスペースを設けられるようにしておくと便利です。
また、日当たりが良く、水はけが良い環境を好みますので、太陽の光をたっぷり浴びる場所に植え付けを行う事が大切です。尚、キンカン類と言うのは耐寒性が強いため、冬場でも枯れることなく、春先から元気に成長をしてくれます。
キンカン類の中でもネイハキンカンと言う種類は果実にビタミンAやビタミンCなどの栄養素がたっぷりと含まれており、生果で食べることでこれらの栄養素を吸収することが出来ます。疲れた時や風邪を引いた時、風邪予防などにも最適と言われています。
因みに、キンカンは接ぎ木2年目の苗の場合でも、3年目には沢山花が咲いて、多くの果実を付けますし、1年で数回花が咲くため、果実は不揃いになりがちです。これを防止する目的で、枝先に集まってつく果実を剪定してあげることが大切で、大きなものを残し、
それ以外の物は摘み取ってあげることで大きな実を甘く育てることが出来ます。また、鉢植えで栽培する場合は、1つの枝に1個から2個程度をつけるようにし、1本の木には10個から15個ほどの実がなるように剪定を行ってあげると、翌年も収穫が可能になりますし、木を長く利用出来るなどのメリットが有ります。
種付けや水やり、肥料について
植え付け3月の中旬から4月の中旬頃に行い、開花はその年の7月から8月頃で、翌年の2月から5月の中旬頃が収穫時期となります。肥料は毎年2月頃と10月頃に施してあげますが、鉢植えの場合はこれらに加えて5月頃にも肥料を施し、2月に与える肥料は寒肥で、5月や10月に与えるのは追肥となります。
また、剪定については3月から5月にかけて行います。3月の中旬から4月の中旬頃は、ちょうど気温が上昇する時期であり、植え付けには最適な季節になります。但し、キンカンは寒さに比較的強いため、暖地などでは秋に植える事も可能です。
しかしながら、一般的には春時期に植える事や初心者も春の方が成功し易いと言えます。庭にキンカン類の木を植え付ける場合は、日当たり、水はけの両方が良い場所を選び、風当たりがそれほど起きない場所を選ぶ事が大切で、風の力でついた実が落ちてしまわないようにしなければなりません。
直径と深さがそれぞれ50㎝程の穴を掘り、掘った時に出た土腐葉土や赤玉土を加えて良く混ぜ合わせて用土を作ります。また、1株あたり200gの粒状肥料を混ぜてから、穴の深さを半分もしくは2/3程になるくらい埋めてから、苗木の根を広げて植え付けます。
尚、植え付ける時は、接ぎ木の部分が埋まらないようにすること、そして浅植えにすることが大切で、支柱を立てて木に固定し、キンカンの木が倒れないようにしてからたっぷりと水を与えれば完成です。
キンカン類の増やし方や害虫について
増やし方のコツは実が出来た時に大き目な物を残して他は摘み取る事、2月に寒肥、10月に追肥、鉢植えの場合はこれに加えて5月に追肥を施してあげるなどの管理を行う事です。特に、実を多くつけたままにしておくと、実が成長不足などにより実の大きさが不揃いになってしまったり、
木がその分力が弱くなって弱ってしまい、翌年の収穫にも影響を及ぼしてしまいますし、その分木の劣化が早く起きてしまうので注意が大切です。また、キンカンなどの柑橘類というのは、春から夏場にかけて果実の成長期に入る場合などでは、この時期に水切れが起きてしまうと、
落葉が起きたり、落実が起きるなどの症状が起きるため、植え付けを行った時だけではなく、空気が乾燥していたり、土が乾燥している時などはたっぷりと水を与えてあげるのが大切です。尚、10月から12月と言うのは成熟期となるため、土が乾燥をしていても水を上げる必要はなく、
寧ろ乾燥気味にしておいた方が果実の色づきが早まりますし、甘い果実を実らせるなどの利点が有ります。また、キンカンには柑橘類特有の病害虫の発生が有ります。カイガラムシ類やハダニ類と言った害虫は柑橘類に多く発生する害虫であり、
中でもイセリアカイガラムシは発生して直ぐに殺虫剤を散布して防除が必要です。また、葉を食害してしまう、アゲハチョウの幼虫、カメムシ類においても発生し易い害虫であり、殺虫剤を使って防除しておくことが大切なのです。
キンカン類の歴史
柑橘系果物の一つにキンカンが有ります。一言でキンカンと言っても複数の種類が有り、キンカン類としてはキンカン属が4~6種類存在していると言います。食用としてのキンカン、薬用として利用するもの、観賞用などキンカン類には多種多彩な種類が有り、
これらの総称してミカン科キンカン属に分類していると言う特徴を持ちます。キンカン類は常緑性低木の果樹であり、中国から日本に伝えられたと言われており、日本に伝わったのは江戸時代だと言います。但し、これは正確には中国から伝わったキンカンも有ると言う事であり、
中には他の国から伝わった品種も存在しているとも言われています。因みに、江戸時代に清の商船が航海中に遠州灘の沖合で遭難をしてしまい、清水港に寄港し、船員が清水の人々に対し、砂糖漬けのキンカンの実を贈ったと言います。
この砂糖漬けのキンカンの中には種も入っており、その種を植えた所、発芽が行われ大きな木となり実をつけたと言われており、この時出来たキンカンが日本に広まったと言う説も有ると言います。しかしながら、この話以前から日本には中国などからキンカンが伝わっていると言う説もあり、
未だにその真実は謎に包まれていると言います。尚、現在のキンカン類と言うのは、宮崎県や鹿児島県などでのブランド品も存在しており、国内における固有種となるキンカン類も存在しています。また、キンカンは食用だけでなく観賞用としても人気が高く、庭木として植えたり鉢にいれて飾るケースも有ります。
キンカン類の特徴
中国の長江中流域がキンカン類の原産であり、中国などが主な生息地と言われています。しかし、日本国内の中でも九州の宮崎県や鹿児島県などで栽培が行われており、これらの地域も生息地として知られており、中でも宮崎県の生産量は日本一であり、続いて鹿児島県と言われています。
食用としてのキンカンと言うのは果実は果皮と一緒に食べる事も有れば、果皮の実を食べることが有るのが特徴で、生食する果物です。尚、皮の中果皮となる皮の白い綿状になっている部分(ミカンの皮を剥いた時の出て来る皮の裏側の白い部分)は苦味と甘味があり、
その両者を味わう事でキンカンの味を楽しめると言います。また、キンカンの果肉部分は酸味が強いのですが、果皮が付いた状態で甘く煮ることで、ジャムや砂糖漬け、甘露煮などの様々な加工品を作り出す事が出来ます。尚、薬用としては虫刺されの薬の原料として利用されていたり、
咳が出る時の緩和、のどの意味を和らげてくれる効果を持ち、生薬としても存在しています。キンカン類の木と言うのは2メートルほどの高さになる事もあり、枝部分には分岐が多く在る事、若い枝には短めの棘があるなど、柑橘類の特徴を持っています。
因みに、ミカンなどの木にも枝部分に棘が有りますが、ミカンほど長い棘ではありませんが、キンカンの枝にも柑橘類特有の棘が有るのが特徴です。また、春から秋にかけて白い五弁の花をつけるのも特徴で、花が咲き終わると直径2㎝ほどの実がなります。
果樹の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クランベリーの育て方
タイトル:グアバの育て方
-

-
ブルメリア・クロセア・オーレアの育て方
ユリ科という情報が多いので、ユリ科の同じような植物が近縁種ではないかということもわかります。ネギ科は、もともとユリ科だっ...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
ミニヒマワリの育て方について
一言で「ミニヒマワリ」といっても、品種改良が行なわれ、中小輪の矯性品種まで、数多くのミニヒマワリが存在しています。大きな...
-

-
イオノプシスの育て方
イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島...
-

-
ヤマボウシの育て方
木の特徴として、被子植物に該当します。ミズキ目、ミズキ科、ミズキ属とされています。サンシュ属とされることもあります。園芸...
-

-
スピロキシネの育て方
こちらについてはキンバイザサ科になっています。別にコキンバイザサ科に分類されることもあります。園芸分類としては球根になり...
-

-
クリサンセマム・ムルチコーレの育て方
クリサンセマム・ムルチコーレの生息地は、ヨーロッパ西部と北アフリカなどの地中海沿岸です。アルジェリア原産の耐寒性または、...
-

-
ヤブヘビイチゴの育て方
分類としては、バラ科キジムシロ属の多年草ということですので、バラの親戚ということになりますが、確かにバラには刺があるとい...
-

-
チャ(茶)の育て方
この植物は、ツバキやサザンカのツバキ科で、多年草の植物になります。緑茶も紅茶も烏龍茶も同じチャノキの新芽を摘んで加工した...
-

-
梅(ハクバイ)の育て方
梅は非常に色が豊富です。濃いピンクがありますがそれ以外には桜のような薄いピンクがあります。白っぽいピンクから真っ白のもの...




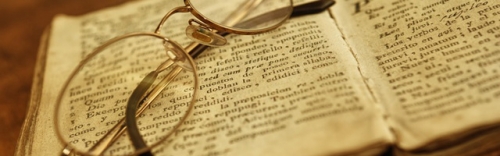





柑橘系果物の一つにキンカンが有ります。一言でキンカンと言っても複数の種類が有り、キンカン類としてはキンカン属が4~6種類存在していると言います。