デンドロビウム・ファレノプシス(デンファレ)の育て方

デンファレの育て方
もともとランはあたたかい地方の花なので、寒すぎない場所に置きましょう。あたたかい温室などがあればそこで育てるようにし最低気温を7度以上に保つようにしてください。とはいえデンファレはランの中でも比較的寒さに強い花です。
日本の寒い冬、室内でも7度以下になりそうな場合は保温性のある段ボールに入れたり、新聞紙で花全体をくるむ、ビニールなどで簡易的な温室を作りそこに入れるなどして、なるべくあたたかさを保ちつつ、あまり育てにくい環境にさせないように寒さに慣れさせるようにすると良いでしょう。
鉢植えならば、土の表面にミズゴケと呼ばれる薄い黄色や白っぽい色をした植え込み材料で覆われている場合がありますので、それが乾いてきたら水を与えるようにしましょう。この時水切れには注意するようにしてください。
寒すぎない環境にならないようにと、暖房をきかせた室内で栽培する方も多と思いますが、基本的に暖房は空気を乾かせてしまうので、本来の熱帯地方の環境に近付けるために霧吹きなどでこまめに湿度を与えてください。ギフト用などで花を付けた鉢花を贈られる方もいると思います。
花はおよそ1ヵ月という長期にわたって楽しむことができますが、栽培環境によって開花期間は前後します。花が終わるとだんだんとしおれてくるので、花の付け根部分からはさみなどで切り取ってください。花が終わっても茎は切り取らずにとっておくことで、春の芽吹きのための養分になります。
デンファレの花の咲かせ方
デンファレに限らず、ランの栽培は一般家庭において難しいものですが、2回3回と花を咲かせることは不可能なことではありません。何よりつぼみをつけ花が咲いた時の感動は他の花と比べてとても大きいものになることと思います。ランの育成において大切なことは温度の管理と水の管理です。
季節によって栽培方法を適切なものにすれば美しい花を咲かせてくれます。春、最低気温が15度以上になってきた時期には野外に出します。日差しがあまり厳しくない春ならば風通しがよく、直射日光にも半日以上当ててください。夏には葉焼けを起こしてしまう可能性があるので、20~30%ほど遮光するようにしてください。
また春から夏にかけて、最低気温が15度以上になる8月上旬頃までは液体肥料を必ず与えないようにしてください。固形肥料などの置き肥も7月上旬頃までは打ち切りましょう。こうすることで花芽を出させてあげるのです。秋になったら鉢を乾かし気味にして、少しだけ水やりを先送りにしてください。
特に注意しなければならないことが秋の長雨、水にさらさないように気をつけましょう。冬には寒さに慣れさせるために、最低気温が8度前後の寒さが2週間ほど続くような頃になったら室内に入れてください。冬の水やりは基本的に霧吹きで加湿をします。
デンファレの植え方
基本的にランは種付けでは育てにくいものです。もちろん現生種であるランは種子によって増えていきますが、一般家庭における栽培では種ではどうしても芽が出にくく、たとえ出たとしてもあまり強くない苗になりやすいです。そのため一般的には株分けが多く行われます。その際はなるべく大きな株を分けるようにしましょう。
条件としては茎が3本以上つけた状態のものを選ぶことです。このような状態のものでないと作落ちという新芽が育たずに花芽がつかないものになってしまう可能性があります。よく見られる鉢植えの中にはいくつかの株が1つの鉢に植えられているものもありますので、そのようなものの場合はそれぞれを別々の鉢に植えてみることで株をわけてみることも良いでしょう。
まずは素焼きの鉢に虫よけのためのネットをしき、そのあとで水はけを良くするための軽石を入れます。ない場合は発泡スチロールなどの破片を入れると水はけもよく保温性もよいものになります。わけた高芽、または株を1日以上水にひたして水分を良く吸ったミズゴケでくるんで植えていきましょう。
デンファレには芽、または株の向きが存在するので、よく見極めて、伸びる方向には少し余裕を持たせるようにしてあげると効果的です。あとは周囲にミズゴケを入れましょう。この時棒などを使ってぎゅっぎゅっときつく押しこむように植えてあげることが大切です。
ピンセットなどを使って下の方にもミズゴケを詰めてあげることで、着生植物としての生きていきやすい環境を作ってあげることが重要になります。植え替えた直後は直射日光に当てるのではなく、少し遮光した環境で管理しましょう。
根を出やすくするため、ミズゴケは乾かし気味に、且つ葉水という霧吹きで葉っぱに水をやることをこまめに育てるようにしましょう。植え替えの直後は根が傷んでいます。そのため根が出てきた頃には肥料をあげてよく育つようにしてください。なお植え替えの時期は5月頃が最適です。
デンファレの歴史
デンドロビウム・ファレノプシスとはデンファレとも呼ばれる洋ランの一種です。着生植物の一種で、熱帯地方の木の上が生息地のものが多く見られます。18世紀の後半、大航海時代も終わりに近づいてきた頃、各地に植民地を展開していたイギリス人達は原産地から様々な種類のランの原種を採取していました。
バラを代表とするようにかつてから様々な花の人工交配、品種改良を繰り返してきたイギリス人にとっては、やはり洋ランもその対象になったのでしょう。そこからランの人工交配が始まったのです。最初期の交配はオーリウムとノビルによるもので1874年に開花しました。
鮮やかな色彩で花付きの良いこの品種はアインスウオーシーという名前で、日本にも多くの種類が輸入されました。その後様々な改良や交配により、小型のデンドロビウム系の種類が誕生しました。日本におけるデンドロビウム栽培の歴史は江戸中期にさかのぼります。
そもそも薬草として扱われていたラン類ですが、独特の葉や花の形は観賞に値するものとして栽培されました。日本にランが輸入されたのも当時の貴族趣味として人気があったためです。本格的な交配が行われたのは昭和初期、そこから様々な品種が生まれ、デンファレもその一種です。
デンファレの特徴
鉢花や切り花として人気がある種類です。理由としては花持ちがとても良いことやそこまで花が咲く条件が厳しくはないため、年間を通しての流通がしやすいことが挙げられます。茎や葉はノビル系と大きな違いはなく、棒状の茎を伸ばし葉をつけます。まるで稲穂のように茎の先端付近にたくさんの花をつけます。
多くの種類がコチョウランに似たような花を咲かせますが、コチョウランとの違いはやや下部の花びらのサイズが小さいことが挙げられますが、全てにおいてあてはまる訳ではなく例外もあります。また近年では、エディブルフラワーという食べられる花としてもデンファレは有名で、特にアジア料理店などで多く見ることができます。
よく見られるものとして優しいピンク色をしたデンファレがあり、食卓の彩りとして重宝しています。シャキシャキとした歯触りで、オクラのような粘り気が特徴で、野菜感覚としておいしく食べることができます。しかし、一般家庭で観賞用として販売されている鉢花や切り花は農薬などの影響により食用には向かないので注意するようにしてください。
洋ランの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:デンファレの育て方
タイトル:デンドロビウム(キンギアナム系)の育て方
タイトル:アングレカムの育て方
タイトル:シュンランの育て方
タイトル:グラマトフィラムの育て方
タイトル:カトレアの育て方
-

-
バラ(シュラブ・ローズ)の育て方
バラの歴史はとても古く、恐竜が世界を支配していたころから始まります。さらに初めに文字として誕生したのは古代メソポタミア文...
-

-
ヒメサユリの育て方
ヒメサユリは高山植物として愛好家も多い日本固有の品種ですが、楚々として咲くユリは日本だけでなく世界中で古くから愛されてき...
-

-
サンチュの育て方
サンチュの歴史は、古代エジプト時代に栽培が始まったとされており、朝鮮半島では4~6世紀頃の三国時代から食されていた野菜で...
-

-
センリョウの育て方
センリョウは日本や中国、台湾、朝鮮半島、インド、マレーシアなどが原産の、センリョウ科センリョウ属の常緑性の低木です。 ...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
マンデビラの育て方
メキシコやアルゼンチンなどの中米から南米などが生息地のつる性の植物です。ディプラデニアという名前で呼ばれていたこともあり...
-

-
アリッサムの育て方
アリッサムはミヤマナズナ属のアブラナ科の植物で、日本で一般的にアリッサムと呼ばれているものはニワナズナなので、かつてはミ...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
トマトの育て方について
自宅の庭に花が咲く植物を植えてキレイなフラワーガーデンを作るというのも一つの方法ですが、日常的に使う野菜を栽培することが...
-

-
ミョウガの育て方
種類としてはショウガ目、ショウガ科、ショウガ属となっていますから、非常にショウガに近い植物であることがわかります。開花の...




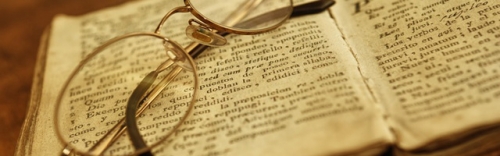





デンドロビウム・ファレノプシスとはデンファレとも呼ばれる洋ランの一種です。着生植物の一種で、熱帯地方の木の上が生息地のものが多く見られます。18世紀の後半、大航海時代も終わりに近づいてきた頃、各地に植民地を展開していたイギリス人達は原産地から様々な種類のランの原種を採取していました。