バビアナの育て方

育てる環境について
育て方としては、栽培する場所をどのように決めるかです。自宅の中において日当たりの良い所があればそちらに植えるようにします。植木鉢であれば植木鉢を日当たりの良い所に置くようにします。植木鉢の環境の方が良いとされるのは、冬の寒さにあまり強くないことです。霜が降りたりするとそれで株が傷んでしまいます。
植木鉢であれば霜が降りるときには事前に自宅内にあげることもできますし、日常的の管理も秋などとは別に行うことができます。軒下などに置いておくことで霜には当たらないようにできますから、冬の夜などにはそちらに置くことも考えるようにします。冬に弱いとされますが、庭に植えることが出来る地域としては関東から南とされます。
太平洋側なら大体どこでも庭植えが可能で、冬越も出来るとされています。もちろん常に大丈夫ではなく、異常気象などでぐんと冷え込んだりすればそれでやられることもあります。でも通常の気象状況であれば問題なく育てることができます。霜が当たったときにどうなるかですが、株が傷んで、葉っぱに関しては枯れてしまうことがあります。
でも株自体が全てが悪くなるわけでは無いので、そのまま育てることはできます。日当たり以外に大事な要素としては水はけの良い所があります。水がたまりやすいところ、ジメジメしたところなどでは育ちにくくなるので注意をします。庭に植えるときなどは、土の中身を変えるなどすることで対応しなければいけません。
種付けや水やり、肥料について
植え付けを行う時期としては9月の終わりから10月とされています。鉢植えにするときには、球根の上に土をのせるのは2センチぐらいです。5号鉢と言いますと直径が15センチぐらいの植木鉢になりますが、このタイプであれば5つぐらいの球根を植えることができます。この時の用土の配合としては赤玉土が7割、腐葉土が3割ぐらいに混ぜたタイプを利用します。
庭植えにするときは鉢植えとは少し変えます。球根の上に土をかぶせるときにおいては、3センチぐらいになります。植木鉢に植える時よりも若干多めにかぶせるようにします。球根の間としては5センチぐらいを目安に空けて置くようにします。植えるときにおいては球根の間隔を詰めすぎてしまうことがあります。そうすると水はけが悪くなることがあります。
庭植えをした時には冬の対策として防寒をする必要があります。水に関しては、土の表面が乾いてから与えるようにします。あまり水を与えすぎると茎だけがひょろひょろと伸びてしまい、倒れやすくなることがあります。当然花の状態もあまり良くなくなります。肥料については植え付けを行うときに入れておくようにします。
ゆっくり効くタイプの肥料を元肥としていれておきます。それがじっくり効いてくるでしょう。追肥をする時期としては芽が出てきてからになります。その後につぼみが出てくるまでに10日に1回程度を目安に与えていくようにします。与えるのは薄めの液体肥料です。
増やし方や害虫について
増やし方としては分球などをすることができます。花が終わって葉が半分くらい枯れてきたら掘り出します。そして軽く洗って日陰などに置いて乾かします。乾かすことができたら、風通しの良い日陰に置いておきます。網袋などに置いておくと風通しもよくなります。この時には鉢植えの土を毎年新しいものに変えるようにします。
地植えにおいては植替に関しては必ずしも毎年行う必要はありません。3年ぐらいごとに行うようにします。そうすると球根に複数の球根がついていることがありますから、それを分球して分けることができます。植え替えをするときにおいては注意としては場所を適度に変更することです。変更場所としては元々アヤメ科の花を植えていないところです。
同じ花を何年も育てていると土の状態が悪くなることがあります。この度の花はアヤメ科ですから、以前にアヤメ科が植えられていなかったところを探してそちらに植えるようにします。花が終わったあとに葉を切らないようにします。葉の光合成により球根が大きくなり、分球のための栄養がどんどん作られるようになります。
球根を育てるために花を早めに摘み取ることもあります。病気や害虫に関してはあまり心配するものは無いとされています。全くないわけではなく、もしそれらが広がってしまうと厄介なこともありますから基本的な駆除のための薬を使っておくとよいでしょう。ホームセンター等において一般的に使われているものを利用します。
バビアナの歴史
植物においては種から植えるものと球根を利用するものがあります。球根にしても最初から球根ではなく、最初は種になります。そして一旦球根ができた時はそれを乾かしたりすることで保存ができ、別のところで育てたりすることができます。球根自身は成長したり分球して複数に分かれたりすることがあるのでそれによって増やすことができます。
植物の種類によってどのような根を持つか、育て方があるかになるでしょう。この球根に関しては、動物によっては食用になることがあります。人が良く食用にするものとしてはユリなどが知られています。ユリ根として売られる事はあります。人にとっては毒になることもあるので注意しなければいけません。
アル植物においても球根をある動物が食用としていたとされています。それはバビアナと呼ばれる花になります。なぜこの名前がついたかの由来として、アフリカーンス語から来ているとされています。この言語は南アフリカの公用語の一つで、それでヒヒを意味するとのことです。
そのヒヒがこの植物の球根を掘り起こして好んで食べていたことからこの名前が付けられたとされています。言葉の由来として南アフリカの公用語が影響していることからもわかりますが、原産地としては南アフリカとされています。南アフリカの中でも南部であるケープ地方が生息地とされています。種類としては60種類ぐらいあるとされますから、非常に多くの種類を抱える花と言えます。
バビアナの特徴
花の特徴では、被子植物、単子葉類となります。キジカクシ目、アヤメ科、ホザキアヤメ属となります。この花においては旧名、もしくは別名としてホザキアヤメが使われることがあります。この種類が非常に多く、日本においてはまとめてこの名前の花として出回ることがあります。そのために同じ花の名前でも花の雰囲気が異なる場合もあります。
生息地においては別々として認識されていても、日本では同じ花のように管理されています。草丈としては30センチ位から50センチぐらいになります。花が咲くのは4月から5月ぐらいです。南アフリカですが暑い地域で育つのではなく、南の方の涼しい地域になります。そのため熱帯地域などに比べると日本と気候が近い部分があります。
その面では育てやすい花として知られています。耐暑性についてはそれなりにありますが、耐寒性はあまり無いとされます。日本の冬の寒さには少し弱いところがあります。よく知られる種類としてはケダルベルゲンシスがあります。葉っぱの形としてはあやめ、グラジオラスのような細長いタイプになります。
横に広がるわけではなく、直立するように根のあたりから生えます。葉脈が縦方向に走っているのがわかります。その部分が盛り上がっているからです。花の色としては、青紫、紫、白などがあります。種類が異なれば鮮やかな黄色の花を咲かせるタイプもあるとされています。どういった種類の花を咲かせたいかを先に選ぶ必要があるでしょう。
-

-
リョウブの育て方
両部の特徴においては、まずは種類があります。ツツジ目、リョウブ科になります。落葉小高木になります。若葉に関しては古くから...
-

-
リナムの育て方
この花の特徴としてはアマ科の植物になります。草丈としては50センチから70センチぐらいになることがあります。花の時期とし...
-

-
ミカニアの育て方
こちらについては比較的身近な花と同じ種類になっています。キク科でミカニア属と呼ばれる属名になります。育てられるときの園芸...
-

-
アークトチスの育て方
アークトチスはキク科の可愛らしい植物です。とてもかわいらしく可憐な雰囲気のある花ですが、キク科という事もありとても身近に...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
エピスシアの育て方
エピスシアはメキシコの南部からブラジル、コロンビア、ベネズエラなどを原産地としている植物で生息地は基本的には熱帯地方なの...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
マンションで育てて食べよう、新鮮な野菜
皆さんは野菜はスーパーで買う方が多いと思います。とくに都会に住んでいる方はなかなかとれたての野菜を食べる機会は少ないと思...
-

-
ディネマ・ポリブルボンの育て方
ディネマ・ポリブルボンは、中南アメリカ原産の小型のランです。主な生息地は、メキシコやグアテマラ、キューバやジャマイカで、...
-

-
野生ギクの育て方
特徴としてはキク目、キク科の植物になります。のじぎくと呼ばれるキクに関しては非常によく見られるタイプかも知れません。こち...




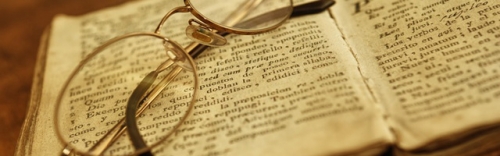





花の特徴では、被子植物、単子葉類となります。キジカクシ目、アヤメ科、ホザキアヤメ属となります。この花においては旧名、もしくは別名としてホザキアヤメが使われることがあります。この種類が非常に多く、日本においてはまとめてこの名前の花として出回ることがあります。