温州みかんの育て方

温州みかんの植え付け方
温州みかんは種付けをすることもできますが、種付けはあまり用いられません。その理由は苗の植え付けをする方が効率が良いからです。種付けをすると育つまでに時間がかかりますし、思った品種にならないこともあります。そのために、多くの人は種付けではなくて苗を植え付ける方法をとっています。
植え付けの時期は3月中旬から4月が適しています。スペースも必要で、理想的に言えば10平米から15平米があると良いです。複数の苗木を植え付けたい場合には、3メートルは間隔を開けた方が良いです。排水が悪くなると生育も悪くなることがありますから畝を作るとともに溝を作っておきましょう。植える部分についてですが、直径1メートルで深さ80センチくらいが理想的です。
まずこのサイズの穴を掘って、バークなどの有機肥料と、石灰などの肥料を土と混ぜて埋め戻し、地面から少し盛り上げておきます。植え付ける前に苗木を買ってくることになりますが、根が乾燥すると木が弱りますから注意が必要です。根が大事ですから、植え付けの時にもできるだけ広がるようにするのが良いです。マルチした植えで水をやると安定しやすいです。
温州みかんの摘果
育て方を誤ると、隔年でしか実らないこともありますから注意が必要です。毎年良い果実を安定して収穫するためには、適度な摘果が必要です。木の育て方自体はそれほど難しいものではありませんが、良い果実を得るための育て方として摘果は必須なものです。
摘果は7月中旬から8月中旬に行います。
その基準は栽培の状況によっても異なりますが、だいたい20枚の葉に1つの果実がなるような割合です。摘果するものは優先順位があって、まず傷ついたものや病害虫にあったものなどを除去します。そして、木の内側にあるものや、あるいは木の下の方にあるものは育ちが悪くなる可能性が高いですから、これも除去の優先順位は高いです。
後は、サイズが適当なものを残しておくというようにすれば良く、極端に大きいものや極端に小さいものを摘果していきます。7月から8月にこのような感じで摘果していき、8月中旬から9月中旬に渡って摘果の仕上げを行います。このときの摘果の具合で良いものがとれるかどうかに大きな影響を与えます。
まず、葉がついているものは残します。2枚から4枚くらいついているのが理想的です。果実の皮の部分が濃淡色で、しわのあるものがあれば、これも残しておきます。果実がなめらかで、緑色が薄いものは摘果した方が良いでしょう。葉に弾力のないものや、形の悪いものなども摘果します。このときにも20枚から25枚くらいの葉に対して1つの果実ができるような割合で残していきます。
温州みかんの剪定について
温州みかんは、栽培と言うよりも剪定に重きを置くべきでしょう。栽培の中で最も重要なものが選定だと考えられます。果実のできる樹木の多くは成長が早くて強いのですが、温州みかんは成長があまり早くはありません。できるだけ成長のスピードを上げるためには、あまり強い剪定はしない方が良いです。
幼木の時には、早く成長することを優先して剪定を行っていきます。明らかに変な枝以外はできるだけ残しておいた方が良いです。枝は、幹から外側に向かって伸びているのが理想的で、途中で曲がっていたり、あるいは幹の方向に伸びているような枝は落としても良いです。同じ方向に伸びている枝があれば片方を残します。幼木の時には、細い枝を残して太い枝を残すようにしていきます。
また、どれが主な枝になるのかを予想しながら、余計なものを残していくようにします。伸ばしたい枝は、あまり強く剪定せず、先端を少し切り返す程度にしておきましょう。5年くらい経てばかなり大きく育つと思いますから、これくらいの時期に主となる枝を決めます。
次に注意しておきたいのは、隔年性です。温州みかんの育て方の中では、ここも注意しておく必要があって、栽培していれば毎年実がなるというものではなくて、実のなった枝は翌年に実がならないこともあります。5年を過ぎたくらいからこのことを意識していかなければなりません。隔年ですから、実のならなかった枝は次の年に実がなりますし、実のなった枝は次の年に実がならないことが多いです。
ですから、毎年安定して収穫しようと考えているのであれば、実のなる枝と実のなっていない枝とを半分ずつ残すような気持ちで剪定していきます。木が成長してくると、細かい剪定は必要ありません。大まかな形がどのようになっているのかを意識しながら余計な枝を落としていきます。意識することの一つが木の高さです。
木は上へ上へと伸びていこうとします。伸びても収穫できるのなら良いのですが、伸びすぎると収穫が難しくなりますから、あまり高くなりすぎた枝は適度なところで短くしてやります。また、木が弱っているときには必要最小限の剪定をするというように、木の状態を見ながら剪定していく必要があります。
温州みかんの歴史
みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、東南アジアに多く見られた植物だと考えられています。それが栽培されるようになったのは中国に伝わってからだと考えられます。4,000年以上も前から栽培されるようになったと考えられるのです。
世界で見れば、現在栽培されているのは900種があると考えられていて、世界中で栽培が進んでいると言えるでしょう。温州みかんが生まれたのは日本に登場してからなのですが、これはおよそ1,200年前だと考えられています。日本に伝えられたときには、不老長寿の薬として持ち込まれたそうです。
現在のような種なしになったのは400年ほど前だと考えられています。なお、種なしというのが縁起が悪いと言うこともあって、一部の地域では栽培されていたものの、日本全国には広まらなかったそうです。温州という言葉は中国の地名で、中国でミカンの生産が盛んな地域にあやかって温州みかんと呼ばれるようになりました。
温州みかんの特徴
中国の地名にあやかった温州みかんと名付けられましたが、日本に独特のもので、中国では栽培されていません。栽培される地域は関東よりも南で、どちらかというと温暖な気候を好む傾向はありますが、少し寒いところでも栽培することは可能です。日本で食用に開発されたこともあって、品種は非常に多くあります。
そのため、品種によっていろいろな違いがあり、たとえば果実が成熟する時期が9月から12月と様々なのです。地域にあうように品種改良が進みましたから、その地域にあった品種を選ぶと育てやすいです。基本的には自家受精を行いますから、受粉の作業を行わなくても良いです。この意味では自家和合性が高いと言えるでしょう。
自家受精して結実はするのですが、種は育たないために種なしになると考えられます。希に種のあるものを見つけることがありますが、これは他の花粉を十分したものだとも考えられます。種で繁殖させることはできるそうですが、栽培と言うことを考えれば性質にばらつきが生じることや、繁殖効率が悪いことなどもあって、接ぎ木で増やすのが一般的です。
カラタチやユズなどに接ぎ木して増やされたものが現在は出回っています。日本では古くから消費量の多い果実で、1世帯あたりの購入量は1位か2位をキープしていて、日本のいろいろな地域で栽培されています。
果樹の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ブンタン類の育て方
タイトル:柑橘類(交雑品種)の育て方
タイトル:キンカン類の育て方
タイトル:イチジクの育て方
タイトル:キンカンの育て方
タイトル:バナナの育て方
-

-
レウイシア(岩花火)の育て方
スベリヒユ科であるレウイシアと呼ばれる植物は、原産が北アメリカであり学名はLewisiacotyledonで、この学名は...
-

-
アガベ(観葉植物)の育て方
アガベとは、別名・リュウゼツラン(竜舌蘭)とも呼ばれ、リュウゼツラン科リュウゼツラン属の単子葉植物の総称のことで、100...
-

-
そら豆の育て方
そら豆は祖先種ももともとの生息地も、まだはっきりしていません。 原産地についてはエジプト説、ペルシャ説、カスピ海南部説な...
-

-
ヤマハギの育て方
植物の中には生息地が限られている物も珍しくありません。しかしヤマハギはそういった事がなく、日本全土の野山に自生しています...
-

-
ステビアの育て方
ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産のキク科ステビア属の多年草です。学名はSteviarebaudiana...
-

-
カンナの育て方
原産地は熱帯アメリカで日本には江戸時代前期にカンナ・インディアカという種類のものが入ってきて、現在では川原などで自生して...
-

-
ニセアカシアの育て方
ニセアカシアは北米原産のマメ科ハリエンジュ属の落葉高木です。北アメリカを生息地としていますが、ヨーロッパや日本など世界各...
-

-
アザレアの育て方
アザレアは名前の由来がラテン語のアザロスつまり乾燥という意味の言葉です。アザレアは乾燥した地域に咲くことからこう名付けら...
-

-
バジルの育て方
原産国や生息地はインド地方といわれ、ヒンドゥー教の神に捧げる高価な植物だったのです。人々の幸福を願う意味が込められ、寺院...
-

-
ハッカクレンの育て方
ハッカクレンは、メギ科の多年草となっています。原産地は中国となっており、古くから薬用植物として珍重されてきたという歴史が...




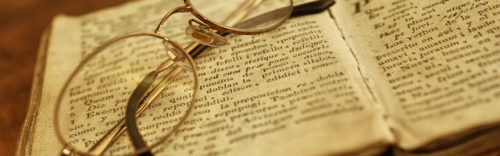





みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、東南アジアに多く見られた植物だと考えられています。それが栽培されるようになったのは中国に伝わってからだと考えられます。4,000年以上も前から栽培されるようになったと考えられるのです。