チューベローズの育て方

育てる環境について
育て方の基本となる環境において、チューベローズは花茎が約1m程度まで伸びるため、風通しの良い環境下で育てる場合には根元から倒れやすいために注意が必要で、太く生育するまでは支柱を立てることが重要です。さらに球根の育ちに左右するのが日当たりですが、通年通して日当たりの良い場所で育てることで花つき良く育ちます。
原産地同様、熱帯性の球根植物であるために寒さを苦手とするため、冬の寒波に耐えることができないために寒地よりも暖地で育てるのが適している植物です。寒地においても管理を徹底することにより、夏から秋にかけて花を楽しむことが可能で、春の植え付けまでの冬期は根を掘り上げて暖かい場所で管理することで翌年に花を楽しむことが可能です。
開花時期が初夏であることから日当たりの良い環境を好み、直射日光による葉焼けになる心配がない熱帯性の植物であるため、管理のしやすさが特徴の1つです。暖かい場所を好み、15度以上の環境下で育つものの、乾燥には若干弱いために露地栽培を目的とする場合には土が凍り、霜に当たる場所を避けて冬越しさせることが求められ、
寒地においては花が終わった後も鉢植えで管理するのが適しています。乾燥を苦手とするため、露地植えでは湿り気のある土壌を好み、水はけの良過ぎる土壌環境下では水やりに注意を払う必要もあり、日当たりや風通り、乾燥などを考慮した栽培環境を整えることで球根が大きく成長するため、花付きも良くなります。
種付けや水やり、肥料について
チューベローズはタネではなく、球根から育てる植物であり、植え付けの適期となるのが5月中旬頃の気温が高めとなる時期であり、気温が低い場合には芽が出にくくなるために気を付けたい点です。さらに球根は球径が4cmからの大きいサイズを選ぶことが花付きに関与するため、30g以上の重さがある球根が植え付けに適しています。
植える幅は15cm間隔でタネと異なり10cm程度の深さに頭が上を向くように植えます。鉢での育て方としては6号鉢に3球を目安としますが、庭植えよりも鉢植えの開花率は低いため、植え付け1週間ほど前に湿らせたバーミキュライト、または水苔と球根をビニール袋に入れ15度から30度の温度管理で生育を促した後、植え付けることで芽が出やすくなります。
チューベローズは乾燥を苦手とするため、水やりは土の表面が乾いたらたっぷり与え、水切れに注意します。鉢植えでは特に水切れしやすいため、夏時期は朝と夕方の1日2回の水やりが必要で、肥料には化成肥料と油かすを混ぜ、水持ちの良い土が適しており、追肥は花付きを促すために6月に1回、
さらに球根の栄養のために9月に1回肥料を与えますが球根植物であるため、不足する場合には液体肥料を与えることも場合により必要です。市販されている培養土を用いるだけではなく、赤玉土に培養土を合わせた堆肥をはじめ、庭植えの場合には腐葉土と堆肥を混ぜた用土や水はけが悪い場所には川砂を混ぜた肥料で栽培します。
増やし方や害虫について
甘い香りを放つチューベローズは球根植物であり、簡単に球根を分けて増やすことが可能です。球根をバラして植え付けを行いますが、親根と異なり子球は成長する前に休眠期に入るためにその年に花を咲かせないため、春まで保管した後に植え付けを行います。花が咲き終わると、地上に出ている部分が枯れ始めるため、その時期に球根を掘り上げます。
子球は室内または気温が10度を下回らない場所で、おがくずやバーミキュライトに入れて日に当てない環境下で植え付け適期となる春まで保管します。子球から増やす場合、気温が低く時期に植えると芽が出ずに根腐れしてしまいやすく、高温処理を行い発芽の成長を早めてあげることが必要になります。
植え付けは上記同様に幅と深さを球根にあわせて行い、発芽した後は鉢または庭へ植え替えを行い、開花を楽しみます。切り花として育てる場合には、葉を半分以上残し、薄い液体肥料を10月頃から枯れ始める時期までの間、2週間に1度ほど与えることにより、球根の肥大を促すことが可能で、増やす際にも適しています。
チューベローズはリュウゼツラン科でもあり、病害虫に悩まされやすい植物でもあり、特にかかりやすい病害虫となるのがアブラムシです。葉を茂らせる春先からの時期に茎や葉にアブラムシが発生しやすく、またそのアブラムシを目的にてんとう虫やアリなども招きやすいため、見つけ次第にスプレー式となる薬剤を散布して駆除を行います。
チューベローズの歴史
チューベローズはリュウゼツラン科であり学名をポリアンテスツベロサと言い、球根に由来するラテン語となる塊茎状のツベロサの意味合いがあり、名前の最後にローズと付くものの、バラとの関係性はなく、属名のポリアンテスの意味を持つ通りに白い花を咲かせます。原産地は主にメキシコであるものの、この球根植物の歴史を紐解くと、
自生する野生種が発見されておらず、生息地となるメキシコ一帯が原産地とされています。チューベローズの流通の歴史としては1629年にヨーロッパに普及し、日本においては1800年代に入り、当時はジャガタラズイセンなどの名前で呼ばれ、普及し始めた歴史が残されています。生息地一帯ではその特徴的な花の芳香が夜来香に似ていることから、
別名に月下香と名を付けており、観賞用として花を楽しむだけではなく、その花から抽出したオイルまた精水は香料として香水の材料として利用されていた歴史が残されており、花精油を抽出するためだけに栽培が盛んに行われていました。またその香りを生かし、切り花として市場に流通させるための花付きの研究、改良が行われる栽培に関する歴史的変遷が挙げられ、
古来よりフラワーアレンジメントに利用したり、レイをはじめとするコサージュなどのアイテムとして上流階級の貴婦人の方々が利用できる加工が施されていた球根植物です。日本においても1800年代を境に、女性の身だしなみとなる香水に用いるようになり、広く栽培が進められている歴史が現在も色濃く残されています。
チューベローズの特徴
チューベローズは上記で述べたように、バラと関係性の無い球根植物であり、草丈は約60cmから1m程度にまで成長し、花の開花時期は7月から9月であるのが特徴です。地際から細長い葉を伸ばし、花茎を60cmほど伸ばした先に穂状花序の花を付けるのですが、花茎は光沢があり、太めで数枚の葉を付け、
花は属名のポリアンテスの意味通りに乳白色となる花を下から2輪ずつ咲かせます。蝋細工のような厚みのある花びらでロウト型であり、付け根は筒状で先端は6つに分かれた状態で咲き開くのがチューベローズの花の特徴です。さらにこの花の特徴は、別名にもなるその芳香にもあり、月下香の名前の通りに夕方から香りを漂わせるのですが、
その香りは夜の間も続くために月下香と言う名で呼ばれており、日が高くなる昼間には香りを抑えて咲き開くのがこの花の香りの特徴でもあります。香りの成分は香水またポプリに利用されており、切り花やレイに利用されています。品種には多く普及されている八重咲きの品種だけではなく、
一重咲きや草丈の低い品種、葉っぱに斑が入っている園芸用に改良された品種などもある球根植物です。春に球根を植え、葉を繁らせた後に夏から花を楽しむのが一般的な栽培方法の特徴でもあり、チューベローズの球根は小さなサイズでは長期間かけて花を咲かせる特徴があり、球根が大きいほど開花が揃うのが特徴の1つであり、花の楽しみ方に品種やサイズによって違いがあります。
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
アセロラの育て方
アセロラの原産国は西インド諸島や中央アメリカなど温かい熱帯気候の地域です。別名「西インドチェリー」とも呼ばれています。そ...
-

-
ハナイカダの育て方
ハナイカダはミズキ科の植物です。とても形がユニークですので一度見ると忘れないのではないでしょうか。葉っぱだけだと普通の植...
-

-
マリモの育て方
また日本以外はどうかというと、球体のものは、アイスランドのミーヴァトン湖やエストニアのオイツ湖などで確認をされているとい...
-

-
シラーの育て方
シラー(Scilla)とは、ユリ科の植物で別名はスキラー、スキラ、スキルラと呼ばれております。学名の「Scilla」は、...
-

-
植物栽培の楽しみ方について。
私たちは、身近に植物が生息しているのを知っています。いわゆる雑草は、育て方を教えなくても、年から年中、切っても切っても生...
-

-
ゆりの育て方
ゆりは日本国であれば古代の時期から存在していました。有名な古事記には神武天皇がゆりを摘んでいた娘に一目惚れして妻にしたと...
-

-
すなごけの育て方
特徴は、何と言っても土壌を必要とせず、乾燥しても仮死状態になりそこに水を与えると再生するという不思議な植物です。自重の2...
-

-
ナスタチュームの育て方
黄色やオレンジの大きな花をつぎつぎと咲かせるため、ハーブの利用だけでなく観賞用としても人気のナスタチューム(ナスタチウム...
-

-
ミヤマハナシノブの育て方
この花はナス目に該当する花になります。ハナシノブ科、ハナシノブ属に属します。高山などをメインに咲く山野草で、多年草です。...




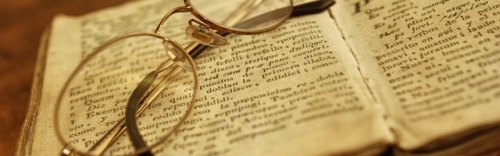





チューベローズはリュウゼツラン科であり学名をポリアンテスツベロサと言い、球根に由来するラテン語となる塊茎状のツベロサの意味合いがあり、名前の最後にローズと付くものの、バラとの関係性はなく、属名のポリアンテスの意味を持つ通りに白い花を咲かせます。