ニガナの育て方

育てる環境について
またこの植物の仲間はたくさんあり、どれも似ているので、なかなか素人には区別がつかないのですが、シバリという名前が付いているものや、ニガナの上にシロバナとかホソバとかノとかカワとかついた名前で生息していたりします。変種ということのようですが、それぞれの環境に合わせて形態を変えていくことができる順応性の高い植物とも言えるようです。
また姿はまったく似ていませんが、ムラサキニガナという植物もあるようで、こちらは食べるとよくないようですので注意する必要があります。最も形がまったく違うので間違えることもない植物ですが、名前にニガナとついているので、その点は注意する必要があるかもしれません。
またシバリという花の場合には、非常に繁殖力が強く、いくら取り除いてもまた生えてくるということで、花は美しいのですが、農家にとっては厄介な雑草ということのようです。育てるということでは、鉢植えなどで育てて、庭には植えないようにするのが良い植物です。取り除くのが大変になりそうな植物ということです。このシバリ系の植物では、ジシバリとオオジシバリがあり、多くはオオジシバリのようで、
農家にとっての強害雑草ということでは、このオオジシバリが多いということでした。美しい花でも雑草ということですが、美しければ人に好かれるということでもないのも皮肉です。そのように色々な種類の植物があるのが、この系統の植物ということになります。また雑草に共通している注意点としては、やはり繁殖力を注意するということのようです。
種付けや水やり、肥料について
また花も白いものもありますので、栽培をしたいような時にも、色々な種類を調べてから、栽培するということが良いようです。また観賞用に育てる場合には、カラスバニガナが良いかもしれません。花は同じように黄色なのですが、茎が黒いということで、名前もカラスとなっているだけあります。
カラスのような色の葉ということでしょうが、この植物をみると誰でも驚くのではないかというような植物です。またもともと雑草なので育てるのにも楽で、強いということでも初心者向きですし、色もシックなので、面白さもあるという植物です。よくこのような植物が存在するものだという感じで驚く植物です。
この植物は4月から7月に花が咲き、最初は鮮やかな黄色ですが古くなると緑に変色するということです。またもともと雑草なので、雑草化しないように花を摘み取るようにします。そのような点も注意点です。環境はもちろん雑草だったので、選ばず、とても育てやすい植物ということです。また育て方ということでは、耐寒性もある植物なので、関東以西では問題なく育つということでした。
このカラスバの場合には、土はこだわらないようですが、日当たりが良くないと、このシックな黒の色が出にくいということもあるようなので、できるだけ日が当たるような場所で育てると良いということです。また病害虫も心配なく、肥料も無理に与えなくてもよいという事で、放任してもよい植物ということです。そのような植物も栽培では珍しいです。
増やし方や害虫について
このカラスバは育てるのは簡単ですが、どこに植えるかとか、どこに置くかとかが難しい植物ではあります。珍しい黒いということ以外には、なかなか観賞用ということでも、あまり勧める事ができないということで、黒と黄色ということでも難しい配色です。これが黒と白でしたらまた違うのでしょうが、ファッションでも黒と黄色の衣服は殆ど見ません。
ですのでガーデニングでの、この植物は珍しさだけが特徴ということになります。その他の種類では、沖縄の食べられるホソバワダンという植物がありますが、こちらは葉を食べますので、サラダや和え物、また味噌汁に入れても良いということです。葉も若いほうが柔らかいので、できるだけ若いうちに葉を摘み取っておくということで美味しく食べることができます。
こちらはインターネットなどでもレシピがありますので、楽しみながら栽培できる簡単な苦菜ということになります。このようにガーデニングや家庭菜園でも利用できる面白い植物群ということですので、それぞれの用途で利用すると楽しめるとも言えます。また人に育てやすいということは、繁殖力が旺盛ということの裏返しということも、これらの雑草からは学ぶことができます。
ガーデニングでも初歩としては、それらの繁殖力が旺盛な植物から育てて、経験を積んでいくというのもテクニックのひとつかもしれません。その点でもこれらの植物も一度試してみるのも面白いということになります。ただ繰り返しますが、雑草化だけは注意する必要がある植物でもあります。
ニガナの歴史
ガーデニングでは、色々な植物を育てることができるということが魅力ですが、育てられる種類は日本でも豊富にあり、どれを選べばよいかも迷いながら、その時に育てたい植物を育てていくうちに、庭の整理がつかなくなるということもあります。そのような時にも区分けをして色々な育て方をしてみるというのも面白いですが、
例えば野草なども花の美しいものも多いので興味も持ちやすくなります。また日本に自生している植物なので、自然に育つという初心者には特に扱いやすい植物です。繁殖力がある場合注意するということですが、そうでない場合には、庭で育てるのも面白いということになります。鉢植えでもプランターでも育てられるのでガーデニングを楽しめます。
そのような野草の中ではニガナも興味深い野草です。この名前はいろいろな植物の名前になっていて、苦い菜ということなので、本来のこの植物ではなく、味が苦いからそう呼ばれているものもあり面白いのですが、本来のニガナは、歴史的にみると江戸時代ぐらいから、文献でも見え始めている植物で、それ以前からあったのでしょうが、
目立たない雑草として扱われていたのでしょう。しかし黄色い可憐な花を咲かせるので、ガーデニングでも楽しめそうな野草ということになります。苦菜とあるので食べられそうですが、食用としては別種の沖縄の植物ぐらいで、本来のこの植物はあまり食べられるような植物ではないということのようです。食べた人がいたから味もわかるのでしょうが、食用にも利用できるようです。
ニガナの特徴
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道端や田畑などや山や平野などでも普通に見ることができます。親しみやすい植物ということですが、名前がわからないながらも見たことのある人も多い植物でしょう。
高さは40センチから70センチぐらいで、名前の通り白い苦い汁が出てきます。また根から長い茎が出てきて、そこに黄色い5弁の花が開きます。実際には舌状花ということですが、タンポポやひまわりなども舌状花ということのようです。花は5月から7月頃咲くということですので、その頃楽しめるということになります。
環境としては日当たりの良い草地や林などのはずれなどの場所で見られますが、それほど繁殖しているという感じはなく、慎ましく咲いているという花でもあります。あまり目立たないので今までも文化的にもとりあげられなかったのでしょう。そのような意味では少々気の毒な野草でもあります。
また食用ということでは、茹でて水にさらして、胡麻和えなどに使うと、ほろ苦くて美味しいということのようですが、また漢方薬ということで健胃や鼻詰まりにも使う地域もあるようです。苦味の成分が効果的なのかもしれません。
いずれにしろ食べられる菜ということになります。よくニガナのレシピということであるのは沖縄のニガナの場合が多いようで、こちらはキク科の多年草のホソバワダンという植物のようで、同じキク科ですが本来のニガナとは別の種類です。
-

-
クレピスの育て方
クレピスは学名で、モモイロタンポポ(桃色蒲公英)というキク科の植物です。ただし、クレピスの名前で呼ばれることも多いです。...
-

-
自宅で植物を育てよう
部屋に植物があると生きたインテリアにもなり、その緑や花の華やかな色は日頃の疲れやストレスへの癒やしにもなります。ただ、生...
-

-
タイリンエイザンスミレの育て方
多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすい...
-

-
フユサンゴの育て方
リュウノタマ、フユサンゴとも呼ばれているタマサンゴは、ナス科ナス属の非耐寒性常緑低木です。ナス科は、双子葉植物綱キク亜綱...
-

-
コウリンカの育て方
コウリンカはキク科の山野草で、50センチくらいに成長し、7月から9月頃には、開花時期を迎えます。2007年に環境省のレッ...
-

-
緑のカーテンを育てよう
ツルを伸ばし、何かに巻き付く性質を持つ植物で作る自然のカーテンのことを「緑のカーテン」と言います。直射日光を遮ることがで...
-

-
アメリカネズコ(ベイスギ)の育て方
特徴としては、裸子植物になります。マツ綱、マツ目、ヒノキ科です。属はスギではなくクロベ属、ネズコ属と言われることもありま...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
ミムラスの育て方
種類としてはゴマノハグサ科、ミムラス属となっています。園芸分類としては草花として扱われます。生息地においては多年草として...
-

-
ランタナの育て方
一つの花の中にとても多くの色を持つランタナは、とても人気の高い植物で多くの家の庭先で見かける可愛らしい花です。ランタナ(...




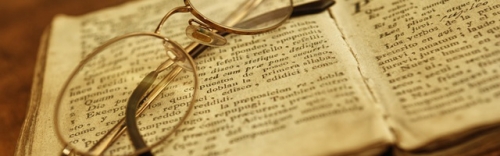





ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道端や田畑などや山や平野などでも普通に見ることができます。親しみやすい植物ということですが、名前がわからないながらも見たことのある人も多い植物でしょう。