メコノプシスの育て方

育てる環境について
メコノプシス・グランディスを育てる際には、気温の管理をきちんとしてあげなくてはいけません。ですので、必要に応じて、一箇所ではなく、複数箇所で太陽の位置などをきちんと確認して育てる事をおすすめ致します。特に、真夏の直射日光は、メコノプシス・グランディスは嫌いますので、当たらないように配慮をしてあげなくてはいけません。
また、真夏の気温が25度以上になってしまいますと、花がつかない可能性があります。そういった場合には、室内で育てられる環境を作ってあげて、できる限り高温多湿にならないようにしてあげましょう。ですので、メコノプシス・グランディスを育てるのに向いている環境は、風通しのよく、高温多湿になりにくいところが最適だと言えるでしょう。
もしも、家の庭などで育てたいという事であれば、朝日はしっかりと当たって、その後の日中はできる限り日陰の場所が良いでしょう。夕方あたりに、西日が当たれば、尚良い場所になります。花を植える前に、お庭の太陽の動きをきちんと見て、どこが育てる場所に適しているかどうかというのを確認してから植えると確実です。
メコノプシス・グランディスは、幻の花と呼ばれるくらい、繊細な花になります。その名の通り、なかなか育てる事が難しいと言われておりますので、安易な気持ちで育てないようにしてください。せっかく育てるのであれば、簡単にからせてしまわないように、責任を持って最後まで育てるようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
メコノプシス・グランディスは、ヒマラヤの青いケシと呼ばれるように、高山で育つ花になります。ですので、一般的な土地で育てる場合には、環境に気をつけてあげなくてはいけません。では、どのようにして育ててあげれば良いのでしょうか。まず、基本的には肥料が大好きな花になりますので、花をよくつけるためにも、春先に1株に対して、
1握りの骨粉をあげるようにしましょう。肥料はそれだけで十分です、液肥など色々ありますが、与え過ぎてしまいますと、かえって軟弱に育ってしまいます。そうする事で、夏に蒸れてしまう原因を作ってしまい、枯れてしまう可能性があります。逆に、何も肥料をあげないままでおりますと、それはそれで花はつきません。
大変難しい花になりますので、肥料の与え過ぎには気を付けるようにしましょう。また、春先に株がコロリと根元から落ちてしまう可能性があります。そういった時は諦めてすぐに捨ててしまうのではなく、そのまま優しく植え直してあげてください。そうする事で、また新しい芽を出してくれる可能性があります。
また、ある程度育てていて、元気が無くなってきてしまったら、ハイポネックスのごく薄くした液肥を水代わりに与えてみましょう。そうする事で、元気になる可能性があります。メコノプシス・グランディスは、元々が育てにくい花になります。ですが、株が落ちてしまったからといって、難しいからといってすぐに諦めて捨てるのではなく、最後までしっかりと育てるようにしましょう。
増やし方や害虫について
メコノプシス・グランディスは、昔は育てるのが難しいということで、なかなか園芸店などに出回ることもありませんでしたが、最近は春先になると開花見込みの株が売られるようになりました。ですので、開花見込みの株を購入して、育てるというのも良いでしょう。メコノプシス・グランディスを育てるということであれば、絶対に配慮しなくてはいけないのが、気温の管理になります。
北海道などの寒い地域であれば、露地上であったとしても、十分に育てることができます。冷涼な地域であれば、幻の花と言われていたとしても、比較的簡単に育てることができます。ですが、気温が高くなってしまうことで、株が衰弱してしまい、枯れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
冷暖房設備がしっかりと整っている環境で育ててあげるのであれば、問題ありませんが、そういった設備もなく、普通に庭などで育てたいと考えているのであれば、絶対に直射日光に当たらないようなところで育ててあげてください。極端な話ではありますが、あまりにも高温多湿になるようであれば、日陰で育てることをおすすめ致します。
そして、育てている最中に害虫などが発生しないように、きちんと花の様子を観察することも大切になってきます。必要に応じて、殺虫剤などを撒いてあげるようにしましょう。ですが、あまりにも薬が強すぎてしまいますと、その影響で花自体が弱ってしまう可能性がありますので、できる限り薄くしてあげることが大切です。
メコノプシスの歴史
ヒマラヤの青いケシと呼ばれる、メコノプシス・グランディスは、その名の通り、原産地がヒマラヤ山脈かチベット、ミャンマーなどになります。標高3000から5000メートルにもなる、高山が生息地となりますので、一般的にあまり見かけることは無いでしょう。小さいものですと、30センチ前後の可愛い花ですが、成長することで中には150センチにもなるものもあります。
そんなメコノプシス・グランディスの特徴は、何よりもその青い花になります。10センチ程度の花は、大きな空色で、まさにヒマラヤンブルーと呼ばれるにふさわしい花です。また、最も栽培するのが難しい花と呼ばれるメコノプシス・グランディスは、幻の花とも呼ばれております。ですので、ガーデニングを始めたばかりの初心者の人は、
なかなか育てることができないでしょう。もしも、育ててみたいということであれば、きちんとした知識をつけて、育て方を学んでから栽培をするようにしましょう。また、育てる際には、夏の気温が25度を超えないように調整しないといけないといった、相当の配慮が必要になります。
ですので、一般的に何も考えずに外で育ててしまっては、絶対に花はつかないでしょう。日本の気候にはなかなか向いていない花のために、一般的な園芸店や花屋には売っていない可能性があります。ですので、花が欲しいということであれば、事前にインターネットで探して、売っているかどうかというのを確認すると良いでしょう。
メコノプシスの特徴
メコノプシス・グランディスの特徴は、先ほども述べました通り、幻の花と呼ばれる程栽培が難しいということです。特に、気温の管理をしっかりと行いませんと、せっかく育てようとしましても、すぐに枯れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。ですが、きちんと育てますと、綺麗な空色で可愛らしい花が咲きます。
ですので、是非育てたいということであれば、しっかりと育て方を学んで、失敗しないように配慮をしましょう。また、メコノプシス・グランディスは、開花した株はその年で枯れてしまうといった特徴があります。ですので、開花した時点で、1本しかなく、その種が衰弱してしまいますと、冬を越せなくなってしまう可能性が高くなります。
ですので、もしも開花した時点で、その花が衰弱してしまい、枯れてしまうかもしれないと感じましたら、その時は1番花が咲いたら、茎の根元から切ってしまいましょう。少し残酷な気もしますが、株の衰弱を防ぐことにより、秋までに株の横から子株が増えてきます。そうする事で、きちんと冬腰をする事ができますし、何よりも子株が増える事で、
1本しかなかった花も複数に増えますので、株が弱りにくくなります。また、根元から切ってしまった花は、そのまま捨ててしまうのではなく、切り花として楽しむ事ができますので、決して酷ではありません。正しくメコノプシス・グランディスを育てるために、判断を間違えないようにしましょう。そうすれば、綺麗な花を楽しむ事ができますよ。
-

-
コチレドンの育て方
コチレドンはベンケイソウ科コチレドン属で、学名をCrassulaceae Ctyledonといいます。多肉植物の仲間の植...
-

-
ヤグルマ草の育て方
ヤグルマギクとも言われていて、キク科ヤグルマギク属のひとつですが、ハーブでもあり、花も鮮やかなのでファンもたくさんいる矢...
-

-
ハツユキカズラの育て方
ハツユキカズラはキョウチクトウ科テイカズラ属で、日本の本州以南と朝鮮半島が原産の植物になります。名前の由来は、葉に入った...
-

-
アリストロキアの育て方
アリストロキアの特徴と致しましては、花の独特な形状があります。数百種類にもなるそれぞれの形状は個々で異なりますが、そのど...
-

-
ノースポールの育て方
ノースポールは別名クリサンセマム・パルドーサムとも呼ばれる花です。北アフリカに自生しているレウカンセマム・パルドーサムを...
-

-
オドントグロッサムの育て方
オドントグロッサムはラン科の植物で様々な品種が含まれています。オンシジウムに近い植物で花弁が大きくて、斑紋が入っているも...
-

-
アガベ(観葉植物)の育て方
アガベとは、別名・リュウゼツラン(竜舌蘭)とも呼ばれ、リュウゼツラン科リュウゼツラン属の単子葉植物の総称のことで、100...
-

-
プシュキニアの育て方
プシュキニアはトルコやレバノンの辺りを生息地としている高原に咲く花として知られている花です。球根が取れる花であるという特...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...
-

-
アボカドの育て方・楽しみ方
栄養価も高く、ねっとりとした口当たりが人気のアボカド。森のバターとしてもよく知られています。美容効果もあり、女性にとって...




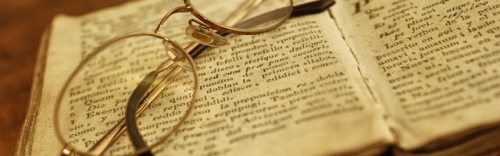





ヒマラヤの青いケシと呼ばれる、メコノプシス・グランディスは、その名の通り、原産地がヒマラヤ山脈かチベット、ミャンマーなどになります。標高3000から5000メートルにもなる、高山が生息地となりますので、一般的にあまり見かけることは無いでしょう。