キンバイソウの育て方

育てる環境について
育てる環境としては、元々の種が中部地方の山岳部によく見られること、そしてそれ以外の地名のついた種は、それよりも北部で見られることから、寒さに対する耐久性はあるものの、暑さにはさほど強くないと言われています。そのため、夏は半日陰になり、直射日光に当たらないよう注意する必要があります。
低~亜高山帯の湿った場所に自生しているため、乾燥にも弱く、多少湿気があるところがよいとされています。高山植物は、この種にかぎらず、気温が低い場所、ところにより極寒の地で、栄養分の乏しい土壌で育ってきており、栽培に関しても、そもそもの生息地などを意識して環境を整えることが重要です。
しかしその一方で、通常栽培するような場所をすべて高山地帯にすることは不可能で、且つ、従来よりも暖かいまたは暑い場所での栽培になることがほとんどのため、土壌や肥料などを調整し、日当たりなども考慮に入れながら、育てる土地に併せて、調整していく必要があります。
育てるきっかけは人それぞれですが、自生している場所に行き、実際に見られたことがあり興味を持たれた方は、その時にみた環境そのものですし、また、自生しているものを見たことがない場合(植物園での鑑賞も含む)は、機会があれば、自生しているところ見に行くのもオススメですし、
また今では多くの愛好家たちが写真を撮影しインターネットのブログなどにアップロードしてあるため、ブログを探すか、検索エンジンの画像検索機能などを使い、実際の環境などを確認することをオススメします。ブログの場合、登山の状況なども併せて書いてありますので、画像単体よりは参考になるかもしれません。
種付けや水やり、肥料について
主に、宿根草の状態のものを購入して育てます。植え付けでも鉢植えでも構いません。土壌に関しては、一般的に売られている高山植物用の土で問題はありませんが、鹿沼土、腐葉土、火山レキなどを混ぜて作っても大丈夫です。火山レキが手に入りにくい場合は、鹿沼土、腐葉土、砂利などでも構いません。鹿沼土の他に赤球などを使用することができます。
腐葉土は必須ではありませんが、多少の有機物が環境の変化を助けてくれます。根腐れに注意が必要なため、腐葉土を用いず、水はけの良い環境で育てる方も多くいらっしゃいます。いずれにしても、一般で販売されている専用土が最も適しています。水やりは、土が乾いた時に与えます。植え付け直後は多少多めに与えて問題ありません。
根付いたあとは、乾燥させないようにします。通常の自然の雨だけでも問題ありませんが、晴れた日が続くなどした場合で、地面の表面が乾く場合には、水やりを行います。また、水やりにより、温度を下げる効果もあるので、日中に水やりをすると効果的ですが、夏の多湿は避けます。肥料の与え過ぎは、根腐れを起こす原因となります。
肥料を与える時期は、開花前の3月頃で、植え替えや株分けも同時期に行います。3月から4月に植え付けをします。高山植物については、人より育て方が異なり、一般的な見解を統一することが難しいため、市販の用土を用いて、根腐れに注意し育てることで問題ありません。特に、キンバイソウは栽培が難し部類ではないため、育てる過程で、ご自身の土地柄にあった育て方を探しだすのが肝要です。
増やし方や害虫について
増やし方は、植え替え時の株分けが多いですが、種から育てられる方もいらっしゃいます。どちらでも好みの方法で、増やしていくことが可能です。株分けの時期は、地上部が枯れている時期に行うか時期を決めて3月頃を目安に行います。育てる地域により育ち具合が異なることから、常に観察をして、適切な時期を見分けて行います。
種を採り蒔きする場合には、専用の市販の用土を使用することで発芽率が一定になります。専用の市販の用土を用い、かなり高い確率で暖かい地域に入る関東周辺で発芽することが確認されているため、それ以北の環境を好むこの品種については、関東以北でも比較的高い確率で発芽する可能性があります。
病害虫に関する被害はほとんど報告されていないため、そこまで神経質になる必要はありませんが、万が一何かしらの病害虫の影響が確認された場合には、防除するなど早めに対応をします。また、ひとつの品種にかぎらず、いくつかの種類を混色することにより、害虫の被害が軽減することが報告されています。
基本的な害虫対策は一般的な対応と同じで、雑草を放置しない、花がらをこまめに摘み取るなどをしますが、この品種の場合開花の期間が1週間程度となっています。株と株の間を適度に開け、風通しをよくします。このように育て方が確立されていない反面、高山植物としては栽培が比較的優しい分類に入ります。
状況に応じた、多少の配慮は必要ですが、これは他の植物にも言えることであり、慣れないうちは市販のもので対応し、慣れてきた段階で、自分なりの土壌配合や肥料の与える時期を見分けていく必要があり、これが高山植物を育成する上での一つの楽しみでもあります。
キンバイソウの歴史
キンバイソウの歴史は、文献が少なく、定かなものはありませんが、原産は日本であると考えられています。国内にあるキンバイソウは、キンバイソウの名前がつくものがあり、エゾキンバイソウやシナノキンバイ、レブンキンバイソウなどで、いずれも、キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。
過去どのような形で進化してきたのかは謎ですが、それぞれに特性がありながらも、キンバイソウの特徴を持ち合わせているので、ちょっとした環境の変化に対応し、それぞれが独自の進化を遂げてきた可能性があります。このような独自の進化は、一朝一夕ではならず、かなり長い年月をかけて変化してきたものだと考えれています。
一つ例を上げると、レブンキンバイソウの生息地である礼文島は、今から1万年前の氷河期の時代から徐々に気温の上昇に伴い、海面が上昇し、島を取り巻く環境が変化したとされています。それ以前の氷河に囲まれた時代に植物が自生しているわけはなく、キンバイソウのどの種かは不明だが島に根付き、
この地独特の進化を遂げ、まさに島の名前である礼文(レブン)を冠にすることができました。漢字では、金梅草と書き、別名としては、トロリウスと言います。苗自体は、トロリウスの名前でも売られておりますが、キンポウゲ科トロリウス属で、実際の属性自体は異なっています。このように同じような名前の種族や同じと言われながらも違う属性のものがあり、歴史的にもまだ研究の浅い分類の植物になります。
キンバイソウの特徴
金梅草の特徴としては、名前の由来にもなった、梅の花のようなで、黄色くなるところにあります。黄色を金と当て字を使用するところが日本人が草木愛でる奥ゆかしさを表現しています。開花の時期は夏で、7月頃から9月頃に見られます。一般的には、中部地方から近畿地方にかけて分布しているとされていますが、独自の進化を遂げている、
シナノ、エゾ、レブンなどを含めると北海道から近畿地方にかけて生息しているという説もあります。また、一見、シナノ、エゾ、レブンなどと区別がつきにくいことがあることから、冠がつかない学キンバイソウ、学術名:Trolliushondoensisが北海道から近畿地方にかけて生息しているとは必ずもとは限りませんが、
可能性として、進化を遂げなかった、Trolliushondoensisそれぞれの地域に残っている可能性もあるからです。これは、今後の研究に判断を委ねるしかないですが、梅のような黄色い花が咲くことにはかわりはありません。花弁のように見えるものは、萼(がく)で、中心部の雄しべのような箇所になります。
高さは、40cmから100cmほどで、葉は、のこぎりのようにギザギザしています。この葉は、同じキンポウゲ科に属しているトリカブトにも似ており、トリカブトと間違えられることもあります。開花後には、袋果の集合体の実をつけます。実は熟した後、自然に割れて、中の種子が地面に落ち、次の世代へと命をつなぎます。
-

-
マンリョウの育て方
江戸時代より日本で育種され、改良も重ねられた植物を古典園芸植物と称しますが、マンリョウもこのような古典園芸植物です。 ...
-

-
パキフィツムの育て方
パキフィツムは、メキシコ原産の多肉植物です。ベンケイソウ科パキフィツム属の植物は、多肉植物の中でも、肉厚な種類として有名...
-

-
マーガレットの育て方
マーガレットは、大西洋に浮かぶカナリア諸島が原産で、もともとの生息地です。17世紀は、ヨーロッパにおいて色々な花の改良が...
-

-
ダイコンの育て方
大根は冬になると鍋料理の具材やおろしなどをして食べたり、収穫後に干してたくわんなどの漬物にするなど色々な調理方法が在りま...
-

-
チシマギキョウの育て方
チシマギキョウは、キキョウ科ホタルブクロ属に属している多年草のことを言います。キキョウ科は、真正双子葉植物の科で大部分が...
-

-
メカルドニアの育て方
メカルドニアはオオバコ科の植物で原産地は北アメリカや南アメリカですので、比較的暖かいところで栽培されていた植物です。だか...
-

-
サフィニアの育て方
この花の特徴としては、キク亜綱、ナス目、ナス科、ペチュニア属に属する花になります。元々ペチュニアが原種ですが、日本の会社...
-

-
エキノプスの育て方
エキノプスはキク科ヒゴタイ属の多年草植物の総称で、この名前の由来はギリシア語で「ハリネズミ」を意味する「エキノス」と「~...
-

-
ナスタチウムの育て方
ナスタチウムはノウゼンハレン科ノウゼンハレン属の一年草です。ブラジルやペルー、コロンビアなどが生息地となり、葉と花と種に...
-

-
ティアレ・タヒチの育て方
ティアレ・タヒチのティアレとはタヒチ語で花という意味があります。つまりティアレ・タヒチはそのままタヒチの花という意味の名...




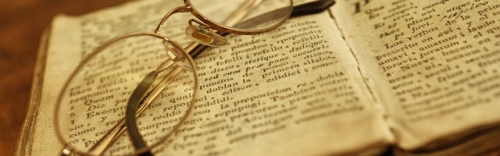





キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。過去どのような形で進化してきたのかは謎ですが、それぞれに特性がありながらも、キンバイソウの特徴を持ち合わせているので、ちょっとした環境の変化に対応し、それぞれが独自の進化を遂げてきた可能性があります。