シェフレラ・アルボリコラ(Scefflera arboricola)の育て方

シェフレラ・アルボリコラの育て方
非常に丈夫な植物ですので、特別なケアは必要ありません。直射日光の当たらない、明るい所に置いてあげると元気な葉が育ちます。前述の通り耐陰性がありますので、日陰気味でも育てられる植物です。比較的寒さにも強い方ですが、
霜に当たったりすると株を傷める原因になりますので、屋外で育てている場合でも、冬場は室内にて管理してあげる方が無難です。水やりは土が乾いて表面が白くなってきたらたっぷりと与えるようにします。あまりたくさん水を与えすぎると根腐れの原因になります。
室内管理で受け皿を使用している場合、受け皿に溜まった水は必ず捨てて下さい。秋から冬にかけては水やりの回数を徐々に減らしていきます。若干乾燥気味にすると越冬しやすくなります。成長が早い植物ですが、茎が柔らかいので、
支柱を立ててあげると綺麗な樹形に育ちます。大きくなりすぎた場合は下の方を15センチ程残して切り戻してあげると、そこからまた新しいわき芽が伸びてきますので、綺麗でまとまった木に仕立て直すことが出来ます。生育期にあたる5〜9月頃には肥料を与えると、
より元気のいい株に育ちます。観葉植物用の液体肥料や置き肥料などを与えてあげます。成長性が高いのであまり大きくしたくない場合は、肥料は控えめにしましょう。冬場は成長が止まり気味になりますので、肥料は与えなくても大丈夫です。
シェフレラ・アルボリコラの栽培の注意点
根が伸びるスピードが早いので、根詰まりには十分注意してあげましょう。鉢の底から根が伸びてくると根詰まりを起こしてしまっていますので、植え替えをしてあげる必要があります。赤玉土と腐葉土を6:4の割合で混ぜたものを使用します。
水はけを良くするためにパーライトか川砂を混ぜる際は、赤玉土、腐葉土、パーライトを5:3:2くらいの割合で混ぜてあげましょう。自分で作るのは不安な場合は、市販の観葉植物の用土を利用しても大丈夫です。植え替える際は根腐れを防ぐために鉢の底に軽石などを敷いてあげましょう。
株を丁寧に鉢から取り出し、古い土を3分の1ほど軽く落としてから新しい用土に植え替えてあげましょう。5〜7月頃の暖かい時期がベストです。放置しているとどんどん成長してしまう植物です。定期的に剪定してあげることによって、葉の詰まった綺麗な樹形に整えることが出来ます。
成長した後の形をイメージしながら剪定をしてあげることが大切です。時々ハダニなどの害虫がつくことがあります。葉水をしっかりしてあげることである程度予防することも出来ますが、もし害虫が発生してしまった場合は早めに駆除をし、観葉植物用の殺虫剤などを散布してあげましょう。
シェフレラ・アルボリコラの増やし方
シェフレラ・アルボリコラは比較的簡単に増やすことが出来ます。主な栽培方法としては挿し木や茎伏せ、取り木などがあります。挿し木をする際には、元気のいい枝を使用します。切り戻しした際に落としたものを使用するのもよいでしょう。
あまりたくさんの葉が付いていると、そこから水がどんどん蒸発してしまいますので、数枚の葉を残して、後は取り除きます。30分ほど水で薄めたメネデール液に切り口を浸しておくと、発根が早まります。鉢に挿し木用の用土を入れ、切り口にルートンを塗ってから挿してあげます。
挿し木用の用土には肥料は入れないようにして下さい。発根して、新芽が出てきたら適切な用土に植え替えてあげます。茎伏せで増やす場合は、節を含んだ枝を利用します。ある程度太さのある枝を横向きに栽培用ポットなどに入れ、茎の表面が出るように植えておくと、小さめの株が育ちます。
その為ミニ観葉植物や、ハイドロカルチャーなどで育てたい場合などに向いています。節ごとに株が出ますので、一度にたくさんの株を増やしたいときにもお勧めです。取り木で増やす方法は以下の通りです。カッターなどで、数センチほどの幅で茎の表皮を剥いであげます。
節の下の部分から発根するので、その部分を剥いであげるのがベストです。皮を剥いだ部分に水を十分に含ませた水苔を巻き付け、その上をビニールでしっかりと覆っておきます。その際、水の代わりに薄めたメネデール液を利用すると発根率が上がります。
乾かないように常に湿らせておきましょう。暫くすると根が生えてきます。せっかく出た根を傷つけないように丁寧に水苔ごと切り離し、用土に植え替えてあげましょう。取り木は、大きめの株に育てたい場合に向いています。大株になったシェフレラ・アルボリコラは花を咲かせ、実をつけることがあります。
淡黄色の種がなることもありますので、種付けにて増やしてみるのも楽しいかもしれません。あまり一般的には流通しておりませんが、まれにインターネット通販はオークションサイトなどでも種子が販売されていることもありますので、興味のある方はチェックしてみられるといいでしょう。
シェフレラ・アルボリコラの歴史
台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低木ですが、その中でもシェフレラ・アルボリコラと呼ばれるものが一般的に「カポック」と呼ばれ、親しまれている種になります。
ホンコンと呼ばれる品種が最もメジャーです。若干丸みを帯びた葉が特徴的です。レナタは、ホンコンと葉の形が異なります。魚の尾ひれのような形に先端が分かれた形になります。他にも葉が分かれていないリサという品種もあります。たくさんの品種が出回っているので、選ぶ楽しみもある植物です。
シェフレラ・アルボリコラの特徴
初心者の方にも育てやすく、非常に人気の高い観葉植物です。一枚の茎に8〜10枚ほどの葉が付きます。葉は少し厚みがあり、固くしっかりしています。光沢があり、品種によっては黄色や白の斑模様が入っているものもあります。葉が茂った様はとても見応えがあり、魅力的です。
その人気の高さから一般的な園芸店やホームセンターで手軽に手に入れることができます。大きさも様々で、ミニ観葉植物から大きめの鉢植えのものまで置き場所に合わせて選べます。ハイドロカルチャーでも育つので、土を部屋に置きたくないという方にもお勧めです。
値段も比較的安価です。また、樹形も様々なものがあります。大きく広がったものや、支柱を立てて整えてあるものなどがありますので、置き場所に合わせて選んでみるとよいでしょう。栽培も他の観葉植物に較べて容易です。自宅でも簡単に増やすことが出来るのも人気ポイントの一つです。
観葉植物の入門編として、まさにうってつけの植物と言えます。何と言っても暑さ、寒さに強く、環境適応能力が高いので育てやすい特徴があります。日光を好む植物ですが、耐陰性もありますので、日陰気味でも育ちます。
暖かい地方では冬場でも5度以上であれば屋外でも育てることが可能です。常緑性があるため、一年中美しい葉を楽しむことが出来ます。葉だけでも非常に趣きのある植物ですので、どんなインテリアにも合わせやすく、和室でも洋室でもマッチします。
ある程度の高さまで成長しますので、広いフロアなどでもしっかりと存在感を出すことが出来ます。その為、レストランや病院などの公共の場でも人気が高く、たくさんの観葉植物が並んでいる中でもメインとなり得る植物です。大事にすると20年以上元気に育っている例もあるほど丈夫な植物です。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オスモキシロンの育て方
タイトル:シェフレラの育て方
タイトル:カラテアの育て方
タイトル:アフェランドラ・スクアロサ‘ダニアの育て方
タイトル:アカリファの育て方
-

-
ポリゴラムの育て方
ポリゴラムはヒマラヤを原産とする多年草です。タデ科の植物で、別名でカンイタドリやヒメツルソバとも呼ばれます。和名のヒメツ...
-

-
ダチュラの育て方
ダチュラといえば、ナス科チョウセンアサガオ属、あるいはキダチチョウセンアサガオ属の植物のことです。しかし、この区別に関し...
-

-
プチヴェールの育て方
プチヴェールは、1990年に開発された、歴史の新しい野菜です。フランス語で「小さな緑」と意味の言葉です。アブラナ科である...
-

-
カーネーションの育て方
母の日の贈り物の定番として、日本でも広く親しまれているカーネーションですが、その歴史は古くまでさかのぼります。もともとの...
-

-
チョウノスケソウの育て方
植物の特徴としては、被子植物、双子葉植物綱になります。バラ目バラ科バラ亜科なのでまさにバラの仲間の植物といえるでしょう。...
-

-
初心者でもできる、へちまの育て方
へちま水や、へちまたわし等、小学校の時にだいたいの方はへちまの栽培をしたことがあると思います。最近は夏の日除け、室温対策...
-

-
アジサイの育て方
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるもの...
-

-
ポトス(Epipremnum aureum)の育て方
ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温...
-

-
ヒメリュウキンカの育て方
ヒメリュウキンカの原産はイギリスで、生息地は山野の湿った草原や川沿いの林床などです。原産はイギリスではありますが、自生地...
-

-
ロベリアの育て方
ロベリアは熱帯から温帯を生息地とし、300種以上が分布する草花です。園芸では南アフリカ原産のロベリア・エリヌスとその園芸...




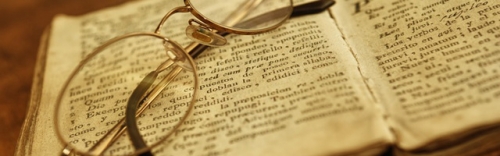





台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低木ですが、その中でもシェフレラ・アルボリコラと呼ばれるものが一般的に「カポック」と呼ばれ、親しまれている種になります。