カラテア(Calathea ssp.)の育て方

カラテアの育て方を学ぼう
水はけが良く、通気性の優れた用土が向いています。赤玉土を5、ピートモスを3、川砂を2の割合で混ぜ合わせた土もしくは観葉植物の培養土に川砂をその量の1割程度混ぜて使うのもありです。肥料は液体肥料を10日に1度の間隔で与えるようにするか、
遅効タイプの粒状の肥料を2か月に1度土の上に置き肥しましょう。水やりは春から夏にかけては水切れしないように土の表面が乾いたらたっぷりとあげるようにします。カラテアが湿った状態は大好きですが、だからといって水を与え過ぎてしまうと根腐れを起こしてしまいますので適量を守ります。
夏は高温期ということで特に土が乾燥しやすいので注意が必要です。逆に冬はほとんど生育がしないので水は控えめが良いです。土が乾燥していると気づいてから数日おいて水を与えるようにするのがベストな方法といえます。
育てるのは明るい日陰、例えば木陰があるような場所ですといいです。完全な日陰は株が弱ってしまうきっかけになりますのであまり良くありません。冬は10度以下になると生育が鈍ります。できるだけ12度以上を保てるようにします。
秋頃になると冷えてくる日も出てきますから室内にとりこんで、レースのカーテン越しに日光があたるようにするといいです。冬場のカラテアには霧吹きが必需品です。乾燥しやすい冬場は毎日葉に霧吹きで水をかけてあげると元気に育ちます。
カラテアを栽培する上でのコツは?
カラテアは害虫であればカイガラムシやハダニ、病気であれば黒斑病や斑点病が春から秋にかけて発生しやすいので時々株や葉の様子を細かくチェックしてみましょう。カラテアの葉の裏側についてそこから汁を吸って傷めてしまうハダニは高温乾燥期に発生しやすく、
葉水をすることで予防できますが、ひどいと枝枯れを起こしてしまうカイガラムシは一度発生すると成虫の場合薬剤がほとんど効果をなさないので古い歯ブラシなどを使ってこそぎ落とすしかありません。この時には葉を傷つけないように気をつけます。
しかもカイガラムシの悪影響はそれだけでは終わりません。カイガラムシの排泄物をえさにして黒いすすのようなカビが生えてしまうすす病というものが発生してしまうことがあるのです。すす病になってしまうと植物にとってはとても大切な光合成ができなくなってしまうので命取りになりかねません。
すす病を改善するためにはその原因となっている害虫を完全に退治するしかありません。つまりこの場合はカイガラムシということになります。カイガラムシは幼虫であれば薬剤が有効ですから退治しやすいです。この段階で見つけたらすぐに薬剤を使いましょう。
株が鉢いっぱいになるほど大きくなっていたり、冬に寒さで傷んだりしてしまった株は5月中旬から7月下旬にかけての間に植え替えしてしまいます。鉢から抜いた株の古い土を3分の1程落とし、株と鉢とのバランスを考えて一回りか二回りほど大きな鉢に植えつけましょう。
またもし下葉が傷んでしまったものはカットしておきます。傷んでいると葉が黄色く変色したりしているのですぐにわかります。葉水をすることはハダニの予防以外でも葉の水分の蒸散を抑えることもできますから忘れないようにして行なうほうがいいです。
冬場などに室内に取り込んだ時には暖房の風が直接カラテアにあたらない場所に置いてあげることも大切です。暖かい国で育ったといってもさすがに暖房は熱過ぎますし、株が枯れてしまう原因になりますので避けましょう。
種付けで増やすことができるのか?
カラテアは一般的に株分けや挿し芽などで増やしていきます。株分けは6月から7月頃に行います。株を鉢から抜いたら、新芽が2つ以上、葉っぱが5、6枚で一株になることを目安にして地際の茎をナイフなどで切ってから手で裂くようにして分けます。
株分けをした直後は根が傷んでしまってるので、特に乾燥に弱い状態です。ですから根づくまでは霧吹きなどで葉や茎にこまめに水を与えて湿度を高く保つようにすることが大切です。新しい芽は数週間ほどで出てきますから少しずつ一般的な育て方に移行するようにします。
挿し芽は高芽が出る品種に施すことができます。高芽をハサミなどで切ってからその株元にミズゴケを巻きつけ、そのまま鉢に植えます。1か月ほどで発根するまでは明るい日陰で管理し、ミズゴケを乾かさないようにします。
発根したら、あとは親と同じ用土で鉢に植えつければOKです。種は花を楽しめる鉢植え品種を選んで採取してみるのがいいでしょう。また種は市販でも販売されていますので、そこから手に入れて育ててみてもいいかもしれません。
カラテアの種は茶色をしていて、俵形のような形をしています。カラテアの花言葉はいろいろありますが、例えば温かい心や強い思いというものがあります。また温かい心とつながる母性という花言葉もあります。
カラテアの歴史を知ろう
カラテアの名前はギリシャ語のかごという意味があるカラトスが由来となっています。これは南アメリカの先住民達がカラテアの葉を使ってかごを使っていたことにちなんでいます。また花穂の形をかごに見立てたからだという説もあります。
原産や生息地は熱帯アメリカで、日陰にも強いのでインテリアとしてもとても人気があります。カラテアにはいくつかの品種があり、例えばカラテア・ランキフォリアは和名もあり、ヤバネシワヒメバショウといいます。昭和初期に日本へ渡来しています。
以前はカラテア・インシグニスと呼ばれていましたが、これは誤称で誤ってそのまま流通していたのです。また観葉植物として人気があるのがカラテア・マコヤナです。こちらの和名はゴシキヤバネショウといい、昭和30年頃に渡来しています。カラテアはクズウコン科カラテア属に属しています。
トラフヒメバショウと和名で呼ばれているのはカラテア・ゼブリナ・フミリオで、これは明治時代末には日本に渡来しています。見た目がそっくりなものにマランタという植物がありますのでこれと間違えないようにしましょう。マランタも同じくクズウコン科で南アメリカが原産なのです。
カラテアの特徴
カラテアは熱帯アメリカにおよそ20種が分布しています。多年草で、30cmから1mほどの草丈があります。自生しているのは薄暗い林の下で、いかにも熱帯の植物らしい葉の模様が美しいことで人気の観葉植物となっています。
カラテアの葉は地際から軸を伸ばし、その先に楕円形や卵型の葉を付けます。この葉の模様は品種によって違います。茎は這うように横に伸びていき、立ち上がることはありません。花茎は地際の葉の付け根から伸びて花穂を付けます。
苞と呼ばれる葉の一部が密生しているのですが、花はその間から見えているという感じです。育てやすさは5段階でいえば3段階目ほどで普通ですが、暖かい国で自生している植物なだけに寒さにはあまり強くありませんから、その辺りはしっかりと管理してあげる必要があります。
植えるのは5月から8月頃にかけて行います。明るい日陰が大好きで、1年を通して生まれ故郷である熱帯アメリカのように高温多湿の環境を作ってあげることで葉が枯れません。病気や害虫はいくつかのものが発生することがありますので、よく注意して見つけ次第処置するようにしましょう。虫も病気もせっかく育てた株をだめにしてしまいます。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アオキの育て方
タイトル:フィロデンドロンの育て方
タイトル:アロエの育て方
タイトル:トックリランの育て方
タイトル:フィロデンドロン・セロウムの育て方
-

-
ツキヌキニンドウの育て方
ツキヌキニンドウはアメリカ原産のツル性の植物で、5月頃から10月頃までの春時期から秋口にかけて、細長く先端部分が開いた、...
-

-
ギョリュウバイの育て方
ギョリュウバイはニュージーランドとオーストラリアの南東部が原産のフトモモ科のギョリュウバイ属に分類されている常緑樹で、日...
-

-
シラーの育て方
シラー(Scilla)とは、ユリ科の植物で別名はスキラー、スキラ、スキルラと呼ばれております。学名の「Scilla」は、...
-

-
マツの育て方
マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にあ...
-

-
クンシランの育て方
クンシランはヒガンバナ科クンシラン属で、属名はAmaryllidaceae Clivia miniata Regelとい...
-

-
リンコスティリスの育て方
リンコスティリスはラン科の植物ですが、生息地は熱帯アジア地方に分布しています。主にインドやタイ、マレーシア、中国南部が原...
-

-
コマツナギの育て方
この植物は背丈が高く40センチから80センチまであり、マメ科コマツナギ属の落葉小低木に分類されています。同じマメ科に属す...
-

-
ルリマツリの育て方
「ルリマツリ」は、南アフリカ、オセアニア原産のイソマツ科プルンバゴ属常緑小低木です。半つる性の熱帯植物であり別名「プルン...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
アガスターシェの育て方
アガスターシェは、初心者でも簡単に育てる事のできる、シソ科の花になります。別名が沢山ありまして、カワミドリやアガスタケ、...




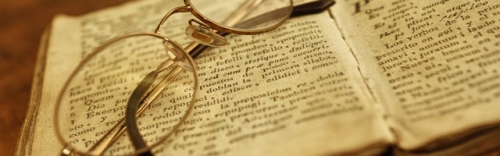





カラテアの名前はギリシャ語のかごという意味があるカラトスが由来となっています。これは南アメリカの先住民達がカラテアの葉を使ってかごを使っていたことにちなんでいます。