サギゴケの育て方

サギゴケの植えつけ
サギゴケは、種ではなく苗で流通していますので、種付けではなく苗の植え付けをします。種や苗を扱っている実店舗では手に入りにくいので、ネットから苗を購入するのが、おそらく一番簡単に手に入るでしょう。
春から開花が始まりますので、その前の3月~4月半ばくらいまでに植え付けを行います。丈夫な植物ですので、あまり神経質にならずに植え付けましょう。湿地では自らどんどん茂るほど丈夫ですので、基本的にあまり肥料は必要ありません。
開花時期に花が咲いていれば、特に肥料はやりません。ただ、葉の色が薄くなったりした場合は、一般の植物の与える量の半量くらいの肥料を施してやります。肥料は緩効性化成肥料でも液体肥料でもどちらでも使えます。緩効性化成肥料なら粒状のものを枝元にばらまいてやり、液体肥料なら2週間に1回くらいのペースで与えましょう。
用土は、市販の山野草用の土などで良く育ちます。ポイントは水はけと水持ちがよいことです。庭に植える場合に、水はけが悪いようであれば、川砂・赤玉土・腐葉土等を混ぜて水はけを良くして上げましょう。
サギゴケの育て方と管理
サギゴケは本来、田んぼや畔などに繁殖する湿地の植物です。ですから、とにかく乾燥を嫌います。とても丈夫な植物ですが、極端な乾燥にさらされると枯れてしまいます。特に花が咲いていない時期には雑草のように見えて、水やりを怠りがちになりますが、乾燥する冬の間などきちんと水をやってあげましょう。
そうはいっても、土が乾いていたら水をやる程度で、水やりの頻度は普通でかまいません。この点を気をつけてあげれば、冬も簡単に越してくれる育て方の難しくない多年草の植物です。
日当たりが良く水はけと水持ちの良い場所が、植えるには最適の場所です。明るい日陰でもそれなりに成長しますが、花付きが悪くなる可能性がありますので、日当たりがよい場所が合っています。
また、良く茂りますので、放っておくとどんどん広がっていきます。グランドカバーとしてとても優秀ですが、適度に切り戻しをしながら、広がりすぎないように管理しましょう。
肥料は一般的な植物より控えめに施しましょう。成長する時期に肥料をやると良く育つのですが、とても丈夫な植物で乾燥さえ気をつけていれば自分でどんどん茂っていきますので、きちんと成長して花付きも良ければ肥料はいりません。
育て方としては、正直、花が付いていない時期は雑草のような見ばえなので、整然とした庭や、メインの花を引き立てるような寄せ植えなどにはあまり合いません。このため、イングリッシュガーデンのような自然風の庭に植えたり、鉢植えにしてサギゴケだけで楽しむのも良いでしょう。
庭に植えるなら、地を這う性質を利用して、グランドカバーや土止めとして活躍します。耐寒性があると共に耐陰性もあるのですが、花を上手に咲かせたいならぜひ日当たりの良い場所に植える、または鉢を置くようにします。
サギゴケは色々な花色がありますので、一色だけで楽しむのも良いのですが、白やピンクの花色のものを混ぜて植え付け、花を咲かせてあげると、花の時期は華やかになってきれいです。
見映えを重視した園芸植物と比べると、ルックスで負けてしまうかな、というような地味な植物ですが、とにかくその丈夫さは折り紙付き、育て方も乾燥さえ気をつければ、初心者でも安心して育てられる品種です。
なんといっても日本の気候に適応した日本原産の植物ですし、多年草で毎年花を咲かせてくれますから、春の花咲く時期を楽しみに育てるのも良いでしょう。一般的に、白色のものをサギゴケ、紫色のものをムラサキサギゴケと呼んで、一般では流通しています。
サギゴケの種付け、栽培
サギゴケは苗で流通していますので、種付けはしません。このため、増やす場合にも種を取って種付けするのではなく、株分け、挿し木、根伏せ等で増やして栽培します。栽培は、花が終わり夏の厳しい暑さが和らいだ頃、9月終わり~10月半ば頃が適しています。
栽培方法ですが、株分けで増やすのが一番簡単でしょう。這うように絡み合って成長していますので、それをほどくように株分けします。株を分けたものをポットに植え替えてやりましょう。
乾燥を嫌いますので、水はけと水持ちの良い土を用意してあげます。サギゴケはポットで育苗してから植え付けを行うと、とても良く育つので、ここで栽培したものを花の咲く春前に植え付けしてあげると、良く育ちます。
丈夫ではありますが、冬の乾燥に気をつけつつ、翌春の開花を楽しみに栽培しましょう。サギゴケの株分けはそれほど難しいことはなく、水はけと水持ちの良い土に植え替えてあげること、乾燥を嫌うので土が乾いてきたら水をきちんとあげることで、簡単に増やすことができます。
サギゴケの病害虫
サギゴケは湿地に自ら繁殖する、雑草に近いとても丈夫な植物ですので、病害虫に神経質になる必要はありません。病気はまずありませんので、心配しなくても問題ありません。害虫もこれといったものは発生しません。
サギゴケの歴史
サギゴケは日本を原産とする多年草です。本州、四国、九州などが生息地です。日本以外だと、台湾や朝鮮半島南部で見ることができる植物です。サギゴケは主にゴマノハグサ科、あるいはハエドクソウ科に分類されます。サギシバと呼ばれることもあります。
日本の気候に適応した結果、湿地の植物として、日本の田んぼや畔などに自生するようになったのが、サギゴケとしての歴史です。とても丈夫で良く茂ります。花が咲かない時期の見た目は雑草のようで、サギゴケと分からないで引き抜いてしまうほど、私たちの生活に身近に存在している植物です。
名前の由来は、サギゴケの花が鷺が飛んでいる姿に見えたことからそのように呼ばれるようになりました。また、コケと名前につきますが、上述したとおりゴマノハグサ科の植物でコケの仲間ではありません。これは、地面を覆うように成長していく様子が苔のように見えたことから名付けられたという由来があります。
サギゴケの特徴
サギゴケは春になると花を咲かせます。初夏頃までが花の咲く時期です。色々な花色があり、薄紫色、ピンク色、白色などがあります。花びらの上唇には切れ込みが入り、中央に毛の生えた黄褐色の部分があります。
雌しべの柱頭がふたつに分かれており、触れると閉じるのですが、これは花粉を積極的に取り込んで受粉を促す役割があると考えられています。葉は、切れ込みが深い濃い常緑色で赤い葉脈が目立ちます。花が終わっても冬になっても緑の葉は茂り、一見、雑草のように見えるほどです。
高さは3センチ~8センチくらいで背が低く、名前の由来となった苔のように地面に這って伸びて20センチ以上になります。葉がたくさん付きますが、最盛期には花もたくさん咲かせてくれます。耐寒性はそれなりにあり、関東より南であれば簡単に冬を越します。
日陰でもそれなりに育ちますが、開花を促すには日当たりの良い場所に植えて上げた方が、良く花を咲かせます。また、湿地を好む植物ですので、乾燥には弱いです。水はけと水持ちの良い場所に植えてやり、極端に乾燥させないようにします。
花が咲かないと雑草のような見た目のため、メインにするには難しい花です。這うように成長しますので、優れたグランドカバーになるのですが、何しろ野趣があるため、寄せ植えやきれいに整った花壇などには使いにくいです。自然風の花壇にはよいでしょう。丈夫で良く茂るため、それほど手をかけずに育てられる点は利点です。
こちらのコチョウランの育て方もかなり参考になる記事です♪
-

-
ステルンベルギアの育て方
ステルンベルギアの名前の由来は19世紀に活躍したオーストラリアの植物学者であるシュテルンベルク氏に因んだものです。他にも...
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
ニゲラの育て方
地中海沿岸から西アジアが原産の一年草の植物です。ニゲラの仲間はおよそ15種類がこの場所を生息地としています。この中でもニ...
-

-
ペラルゴニウムの育て方
和名においてアオイと入っていますがアオイの仲間ではありません。フクロソウ科、テンジクアオイ属とされています。よく知られて...
-

-
キンシバイの育て方
初夏から本格的な夏を迎える時期に、黄金色をした花を咲かせるキンシバイは中国原産の半落葉性の低木です。半日陰でも育つ丈夫な...
-

-
フェスツカ・グラウカの育て方
フェスツカ・グラウカは、ヨーロッパ原産の、イネ科の植物です。寒冷地などに多く自生している、細い葉が特徴の植物で、6月から...
-

-
ユズ(実)の育て方
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くら...
-

-
大きなサツマイモを育て上げる
サツマイモは特別な病害虫もなく農園での育て方としては手が掛からないし、家族でいもほりとして楽しむことできる作物です。
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
カラタチの育て方
今から約1300年前に伝来していて、和名の由来はからたちばなという言葉が略されたとする説が実在しています。ただ、からたち...





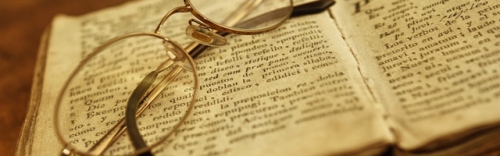





サギゴケは日本を原産とする多年草です。本州、四国、九州などが生息地です。日本以外だと、台湾や朝鮮半島南部で見ることができる植物です。サギゴケは主にゴマノハグサ科、あるいはハエドクソウ科に分類されます。サギシバと呼ばれることもあります。