スターチスの育て方

スターチスの育てる環境について
スターチスの栽培環境として、キーポイントとなるのは、太陽の光具合と水 はけにつきます。庭に植えるのであれば、太陽の光がたっぷりと浴びることができるポジションに植えてあげましょう。それでいて、水はけも良い場所が、ベストポジションとなります。
木枯らしが吹き冬がやってくると、外の気温もグッと下がることになります。真冬にもなれば、霜柱が登場して株がいつの間にか持ち上げられれるケースもあります。この状態を見つけたら、すぐに作業に土地掛かりましょう。持ち上げられた株をそのままにして放置した場合、
いつの間にか干からびていた、ということになりかねません。干からびてしまったら、結果として枯死ことになります。そんな最悪の状態を回避するためにも、株が持ち上がっているのを見つけたら、即座に植え直し作業に取り掛かりましょう。直に土 に植えるのではなく、
鉢に植える場合は、鉢を置く場所に気を使って育てます。おひさまの光がよくあたって、それでいて風通しが抜群のゾーンに置いて管理します。室内であれば、窓際のポカポカとおひさまの光が暖かく、風も入ってくる場所に置いておけば、スターチスにとっても、
快適な環境でのびのびと成長することができます。室内の温度も下がる冬になったら、凍らない場所においてあげます。外に置くときでも、軒下などで凍りつかない場所を選びます。花壇に植えることもできる花ですが、長いあいだ雨に当たったりするのには弱いです。
種付けや水やり、肥料について
スターチス植えつけやの植え替えに適した時期は、季節も程よい過ごしやすい、10月から11月にかけてになります。植え 替え作業を行うときの注意点は、根の部分をうっかり切ってしまわないことです。気温にも左右されるところがありますから、
本格的に寒さ到来の冬が来てしまう前に植え付け作業を完了させます。そして、根をしっかりと張らせてあげましょう。これは寒い冬が来てからの、霜柱に対する予防対策でもあります。霜柱は見た目は、冬が来たなと季節の移り変わりをしんみりと感じられる光景でもありますが、
草花にとっては深刻です。なぜならば、冬に霜柱になることによって、スターチスの株も持ち上げられてしまうことがあるためです。まさに、スターチスにとっては死活問題とも言えるでしょう。そんな意外と深刻な状態を回避するためにも、根はしっかりと張らせて、
我が身を守ってもらいます。万が一、植 え付け作業が遅くなってしまったら、ポット苗で春までの期間はフレームの中で管理するなど対策を取りましょう。3月頃から4月にもなれば寒さは和らいできますから、その頃になってから、植え付け作業に取り掛かると良いです。
庭に植えた場合は、特に水屋視しなくても平気です。しかし鉢植えであれば、水やりは必要になります。表土が渇いたな、と察知したら、水はたっぷりとあげましょう。栄養分としては、緩効性化成肥料を使います。鉢植えは10月と11月、あとは3月と5月に肥料をあげます。庭に植えている場合は、10月から11月くらいに施してあげます。
増やし方や害虫について
スターチスを育てるに当たり、害虫対策もしておく必要があります。主に害となる虫の代表選手は、アブラム シの存在です。草加を育てるにあてり、登場品度も高い害虫ですが、スターチスを差建て帝國あたり、メインで登場しやすい害虫になります。
とくに9月から7月の期間は要注意です。生育期間は大事な時期ですが、この期間に発生するのがアブラムシです。もしも見つけたら、その時点で防除を行います。発生を事前に防ぐためには、立て込み過ぎの隙間のない育て方ではなく、風通しの良い環境を作りましょう。
風通しが良くなることで、アブラムシが発生するのも、少しは減らすことになります。大量に発生してしまうと、花を痛めてしまう要因にもなりますから、発生する前から対策をとることです。病気では、立枯病には注意が必要です。根詰まりをしたり、湿気が多くなったりする、
9月から7月の期間は要注 意です。うっかり肥料が切れてしまっていると、下葉の枯死してしまったときに、この病気が起こる可能性があります。立枯病を防ぐためにも、風通しを良くすることは必要です。また、水はけも良い状態にしておきましょう。
枯れ葉は、病気の発生源にもなりますから、気がついたらできるだけ取り除くように心がけることです。増やすのは、タネまきで行います。9月から10月は、タネまきにも最適な時期です。バーミキュライトによる細粒での覆土にして、少しだけタネの顔が見える暗い薄くしておくのがポイントです。
スターチスの歴史
スターチスの花の原産地は、ヨーロッパであり、地中海沿岸地方を生息地としています。いかにも洋風な見た目の花は、日本へ伝わってきた時期としては、ほかの品種の花よりもあとのことです。今でこそ日本国内では、多くの花を楽しむことができますが、このスターチスがやってきたのは、
明治時代よりあとのことです。様々な洋風の花が日本へやって来る中で、遅い渡来となりました。タネがわたってきたのは、1910年くらいから1920年代になります。全て欧米方面より、日本へ導入されたものです。栽培としては、種子からの育て方でした。
スターチスの科目分類としては、イソマツ科であり、常緑多年草になります。メリクロン由来品種がメインになてきているのは、形質がどれ も均一性がないためです。メリクロンというのは、洋蘭などの栽培にも用いられる方法です。新しい芽が出てきて、
その中から成長点をピックアップして無菌培養基で増やすといった方法です。スターチス箱花が未収して咲き誇るタイプの花です。この小さな花たちは、通常の花びらのように、1枚ごとに散っていくタイプの花ではありません。お花屋さんで成果を見ることもありますが、
室内でドライフラワーとして見かけることもある花です。花をカットして放置してみると、いつの間にかしぼんでいるため、花がなかにあったのかさえわからないような状態です。しかしドライフラワーでは、ガクのない状態で、カラーだけが残っている状態になります。
スターチスの特徴
とてもカラフルなカラーであることと、花の形状もスターチスの特徴です。スターチスの仲間には、半低木になるものもありますし、多年草や一年草などさまざまです。シヌアツム種は、一年草または二年草になります。カラーは白やピンク、ブルーなど色鮮やかで目にも楽しませてくれます。
日持ちも良いのも特徴的で、ドライフラワーにも適していますし、切花でも利用されることの多いタイプです。ニーズもありますから、栽培される割合も多くを占めています。ボンデュエリ種はせいしつがシヌアツム種ともよく似通っています。黄色の萼があり、
シヌアツム種として扱われることが多いです。ラティフォリウム種やベリディフォリウム種などは、扱いは多年草になります。原産地は世界中の海岸とされており、砂漠であ ったり荒地でも姿を見ることがあるタイプです。草丈としては10cmから150cmくらいのあいだで、
種類によっても長さは異なります。開花は、5月から7月あたりが見ごろとなります。カラーの鮮やかさは特徴的で、白やレッド、イエローやパープル、ピンク色など美しい色が揃っています。耐寒性としては、やや弱い部分があります。
気温が高すぎるのも得意な方ではありません。お日様の光は好きですが、土を超えた暑さには弱いです。なんといっても特性として、開花期の長さが挙げられます。切花にしても、できるだけ手入れが楽な花を選びたい時にも、ベストチョイスな花と言えるでしょう。
-

-
エゾエンゴサクの育て方
エゾエンゴサクとは北海道や本州の北部の日本海側の比較的湿った原野や山地に古くから生息してきたという歴史があります。生息地...
-

-
イオノプシスの育て方
イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島...
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...
-

-
セキショウの育て方
元々はサトイモ科に属していました。しかし実際の姿とサトイモの姿とを想像してみても分かる様に、全くサトイモとは性質が違いま...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
ガマズミの育て方
ガマズミはその名前の由来がはっきりとわかっていません。一説によるとガマズミのスミは染の転訛ではないかというものがあり、古...
-

-
ホウセンカの育て方
ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているよ...
-

-
オンシジウム育て方
オンシジウムの一種で特にランは熱帯地域で種類も多くさまざまな形のものが見られることが知られています。それらを洋蘭と呼び、...
-

-
ディケロステンマの育て方
ディケロステンマは原産が北アメリカ西海岸のワシントン州西部からカリフォルニア州中部に分布しています。別名をブローディア・...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...




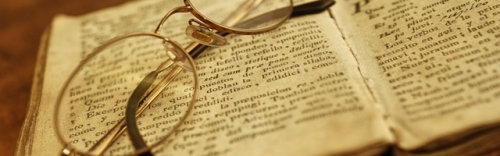





スターチスの花の原産地は、ヨーロッパであり、地中海沿岸地方を生息地としています。いかにも洋風な見た目の花は、日本へ伝わってきた時期としては、ほかの品種の花よりもあとのことです。