ムラサキサギゴケの育て方

育てる環境について
実際生えているのを見ると、少し湿ったところでよく見かける事が出来ます。切り拓かれた場所や田んぼの畦など、日当たりが良くしかも湿った場所に群落を作る傾向にあります。ムラサキサギゴケは平地や低山に良く見られます。サギゴケは本来、湿地で繁殖をする植物になるので、とても乾燥を嫌います。
ムラサキサギゴケ自体は、大変丈夫な植物ですが、極端に乾燥している場所での生育となると枯れてしまいます。特に花が咲いていない時期には、雑草のようにも見えてしまうのでついついミスやりを忘れてしまいがちになってしまうので注意しましょう。また、乾燥する冬の間など出来る限りきちんと水をあげるようにしましょう。
しかし、このムラサキサギゴケは冬もしっかり越す事が出来る野草になるので、育て方も比較的簡単になります。日当たりが良く水はけと水持ちの良い場所を好みます。明るい日陰でも成長しない事はありませんが、花付きが悪くなってしまう可能性があります。その為、出来るだけ日当たりがよい場所で育てるようにしましょう。
それほど手間をかけずに育てる事が出来る野草です。他の花と一緒に鉢植えに寄せ植えをして楽しむ人も多数います。このムラサキサギゴケがたくさん咲いているのを見ると、本当にきれいで見とれてしまう存在です。土の状態は、あまり乾燥させてしまうと大変なのでそこだけは気をつける必要があります。また、他の植物より比較的丈夫なので是非しっかり育ててみましょう。
種付けや水やり、肥料について
ムラサキサギゴケは、種ではなく苗で流通している事が多いので、種付けではなく苗の植え付けをする方が良いでしょう。インターネットなどでも入手することが出来ます。春から花が咲き始まりますので、その前の3月から4月半ばくらいまでに植え付けを行うようにしましょう。
大変丈夫な植物ですので、あまり神経質にならずに植え付けする事が出来ます。湿地では自らどんどん成長していく野草なので肥料の心配はいりません。耐寒性が強く、初心者でも育てやすいので是非挑戦してみましょう。見ごろの季節に花が咲いていれば、特に肥料をやらなくても良いでしょう。ただし、葉の色が薄くなったりした場合は肥料をあげる必要があります。
あげる場合でもそれほど多い肥料が必要ありません。一般の植物の与える量の半量くらいの肥料をあげるだけで大丈夫です。肥料の種類は緩効性化成肥料でも液体肥料でもどちらでも構いません。緩効性化成肥料をあげるのであれば粒状のものを枝元まいていきましょう。液体肥料なら2週間に1度くらいのペースで与えれば大丈夫です。
何もしなくても良く茂る野草です。特に成長期に肥料をあげるととても育ちます。きれいに花が咲いている状態であれば、得に肥料の心配はいらないでしょう。水やりは、そんなに頻繁にあげなくても大丈夫です。土が乾いていたらあげる程度にしてさえすれば丈夫の育てる事が出来るでしょう。それほど慎重にならなくてもしっかり育つ野草です。
増やし方や害虫について
増やす場合は、種を取って種付けする方法ではなく、株分けや挿し木、根伏せ等で増やして栽培をした方が良いでしょう。栽培する場合は、花が終わり夏の厳しい暑さが和らいだ頃から始めましょう。9月の終わり頃から10月の半ばくらいが一番適しています。そのままの状態にしていると、どんどん広がっていくので適度に切り戻しをしながら広がりすぎないように注意しましょう。
色々増やす方法はありますが、株分けで増やす方法が一番簡単でお勧めです。這うように絡み合って成長してるので、それをほどきながら株分けをしていきましょう。そしてその株分けしたものをポットに植え替えてやりましょう。ムラサキサギゴケを栽培する場合はポットで育苗してから植え付けを行うと、大変良く育ちます。
冬の乾燥さえ気をつければ、翌年の春には開花を見る事が出来ます。何よりも水はけと水持ちの良い土壌さえ用意することが出来れば、後はそれほど手をかけなくても育てる事が出来るでしょう。大変丈夫な野草ですので、害虫や病気など特に心配する必要はありません。
害虫も特に発生しない野草なので安心して初心者でも育てる事が出来るでしょう。管理もしやすく、また増やすのも簡単な野草なので、花をどんどん増やして庭先を彩ってみましょう。小さな薄紫色の花がきれいに咲き誇り、お庭を楽しい空間に変えてくれるでしょう。また鉢植えにたくさん咲かせても大変きれいに見える花なので、是非上手に育ててみましょう。
ムラサキサギゴケの歴史
ムラサキサギゴケは、日本を原産とする多年草になります。本州や四国、九州などが生息地です。他に、台湾や朝鮮半島南部でも見る事が出来ます。見ることができる植物です。名前の由来は”鷺のような形の花を咲かせ、苔のように地べたを覆う草”という事から来ていると言われています。
鷺は白い色をしている鳥なので、白花を咲かせるものが”サギゴケ”、紫色の花を咲かせるものを”ムラサキサギゴケ”と呼ぶようです。このサギゴケの歴史は言い知られていません。万葉集などの他の和歌集でも名前が詠まれておりません。江戸時代の”本草綱目啓蒙”に「サギゴケ」の名前が書かれていますが、このサギゴケなのかどうかは定かではないようです。
野山に咲く野草で、同種のトキワハゼに似ています。しかしトキワハゼは地面を這わないのでこの違いがあります。可愛らしく小さな紫色の花を咲かせ咲いているムラサキサギゴケ。花言葉は「追憶の日々、あなたを待っています」です。何とも言えない少し寂しげな花言葉ですね。優しい色合いで道端を飾り、
あまりの小ささについつい見落としてしまいがちですが、草むらなどに群生しているとその紫色が大変美しい花になります。4月から6月にかけて開花し、一斉に咲き誇ると本当に可愛らしく見えてしまいます。湿ったあぜ道などでも見かける事が出来る花になります。なんだか見つけると心がホッとする、そんな印象さえ与えてくれる野草ではないでしょうか。
ムラサキサギゴケの特徴
ムラサキサギゴケの特徴は、葉が根もとに集り、草丈は4cmから7cmくらいになります。倒卵形または楕円形の形をしています。根元の葉の間から、花茎をのばして薄紫色の小さな花を咲かせます。花冠は唇形になっており、長さ2cmくらい。上唇は2裂、下唇は3裂しています。雄しべ4個と雌しべは上唇に沿ってついており、
雄しべ4個のうち、2個が長くなっています。湿性の高い田んぼや畔道などに生育しており、多くの場合群生しているのを見る事が出来るでしょう。春になると、長さ10cm前後の花茎を立て、茎頂にまばらに長さ2cmくらいの花を咲かせます。成長期間は2月~6月頃です。種子とほふく茎で繁殖します。
あぜ道などでたくさん群生しているのを見るととても癒される存在です。花が終わる頃からほふく茎をあちこちに伸ばし、節から根を下して増殖していきます。名前に”コケ”という名前が付いていますが、コケの種類ではありません。本州から九州まで、幅広い地域で見る事が出来る野草です。あまり大きくならないので、園芸用としても重宝されます。
また寄せ植えをして鉢植えを楽しむのも良いでしょう。花が終わる頃から,匐枝を伸ばして這いまわるのが特徴でしょう。繁殖力も強く、どんどんその数を増やしています。実際歩いていても、あまりに小さな花なので気付かない人もいるかもしれません。しかし、そんなムラサキサギゴケが好きで自宅で栽培している人もいるでしょう。
-

-
プチヴェールの育て方
プチヴェールは、1990年に開発された、歴史の新しい野菜です。フランス語で「小さな緑」と意味の言葉です。アブラナ科である...
-

-
ハシカンボクの育て方
ハシカンボクは日本が原産とされる植物です。漢字で書くと波志干木となりますが、その名前の由来はわかっていません。また別名を...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
エリカの育て方
ツツジ目、ツツジ科、エリカ属生息地は、ヨーロッパ、アフリカに600種類以上が分布する、常緑樹です。分布、自生している範囲...
-

-
オクラの育て方について
夏になれば栄養満点のオクラの栽培方法のコツです。オクラは北海道など一部の地域を除きかなり育てやすい野菜の一つです。スーパ...
-

-
アツモリソウの育て方
この花はラン科の花で、アツモリソウ属ということですが、ガーデニングではラン科の植物は非常に人気があり、この植物も人気が高...
-

-
マトリカリアの育て方
花の特徴は、キク科のヨモギギク属とされています。タナセツム属に入ることもあります。園芸分類としては草花に属します。形態と...
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
鉢植え植物を上手に育てるポイント
鉢花は花が咲いているものやつぼみの時期に購入するとその時から観賞することができ、苗から栽培するのと比べると誰でも簡単に楽...
-

-
カトレアの育て方
カトレアは、肉厚の葉とバルブと呼ばれるやや太った茎をもつ洋ランとされ、生息地は、熱帯、亜熱帯地域の南アメリカ周辺で中南米...




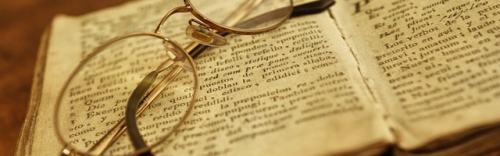





ムラサキサギゴケは、ハエドクソウ科のサギゴケ属になります。和名は、ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)でその他の名前は、サギシバなどと呼ばれております。