スナップエンドウの育て方

育てる環境について
スナップエンドウを含むエンドウの仲間は比較的寒い環境には強いという性質があります。生育適温は15~20℃であり、その範囲であればよく育ちます。温度がマイナス4℃でも絶えることが出来る強さがありますが、暑さには弱いという性質があり、
28℃以上になると生育が悪くなる傾向があります。収穫時期が5月から6月にかけてになりますのでその時期に30℃を超える地域では生育に適さないということがあるかもしれません。育てる場合の注意としては連作の問題があります。育て方の注意事項としてはこの様な問題を意識しておく必要があるでしょう。
連作障害がありますので5~6年間は同じ場所に作付しないようにすることが重要であると言えます。連作に弱い代表的な作物ですので注意をするのに加え、酸性土壌が苦手であるという特性がありますので種まきの一週間前くらいに苦土切開をまいて耕しておくとよいでしょう。
酸性土壌を良い具合に改善してくれる効果が期待できます。スナップエンドウを含むエンドウの仲間は秋の種まきのタイミングが非常に重要です。早すぎる時期に種まきを行ってしまうと冬になるまでに大きくなりすぎてしまうという問題につながり、
結果として病気になったり虫が付きやすくなってしまうという問題があります。そのため適切あタイミングに種まきが出来るように工夫を凝らす必要があります。病気や虫が付いた場合には薬を使用し開ければ対処できないケースも多く、工夫したいところであると言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
種付けを行う前に土壌づくりをしておくことが望まれます。その理由としてはスナップエンドウを含むエンドウの仲間は酸性土壌が苦手であるという特徴があるためです。そのため種まきの前の段階で土壌を改善するために苦土石灰と堆肥を混ぜて工作を市、
化成肥料を加えておくことが有効であるとされています。種付けには瓶の底を使って40センチくらいの間隔をあけながら種をまいて行くとよいでしょう。壱カ所に3~4粒程をまいたら土をかぶせます。この時上にかける土が浅すぎると根が浮き上がってしまったり、
種皮をかぶったままの状態で発芽してしまうため注意が必要であると言えるでしょう。発芽して7~8センチの大きさになったら状態の悪いものを間引いて壱カ所に2株と言う状態にまとめるとよいでしょう。春になるとん美始めてきますので化成肥料を追加して土寄せも一緒に行っておくとよいでしょう。
その後鶴が伸びてきたら支柱を立てて挙げると育ちやすくなります。その後は長さいたら化成肥料を追加してあげるとよいでしょう。つるが沢山育ちますが、あまりに多いと成長を阻害しますので必要のないつるは間引いて風通しや日当たりを良くするのも有効に機能します。
その頃になるとスナップエンドウが実ってきますので、実が太ってきたら収穫の時期を迎えたと判断することが出来るでしょう。スナップエンドはこの様なタイミングですが、エンドウの種類によって収穫時期に違いがありますので注意するとよいでしょう。
増やし方や害虫について
エンドウは生命力が強くどんどん育つという性質がありますが、収穫を多くしたいという目的があるのであれば収穫に対してマイナスに働くものは積雪に間引いて行くことが有効かつ必要なことであると考えられます。上手に対応してスナップエンドウの収穫量を増やすためには、
その様な対処が必要であると言えるのです。例えばスナップエンドウを摘心竹刀で栽培すると側枝が多く伸びて非常に大きく育つように見えますが、そのままの状態にすると見た目ほど収穫が良くないという結果につながります。これは枝が置くなりすぎてに当たりと風通しが悪くなってしまったがゆえに、
育ちも悪くなってしまうという問題なのです。そのため側枝が育ち始めたら適当に間引いて整理してあげることで日当たりと課税とお市を確保することが出来ます。これは非常に面倒なことですが、そうしてあげることで寄り多くの実をつけることにつながる大切なことなのです。
また弦に関しても親つるには沢山の花が付きますが、子つる、孫つるとなるに従って花が付きにくくなります。そのため子つるは早めに間引いて親つる一本の環境を保つのも工夫の一つです。害虫や病気についてはいくつかの種類が知られています。
華美に起因するものと蒸しに起因するものがありますので、それぞれの状態を的確に把握して対処することで問題の回s決につなげることが可能になります。時として農薬の使用をした方が良い場合もあるため、害虫や病気に対しては適切な対処をしましょう。
スナップエンドウの歴史
スナップエンドウは若くてみずみずしい食感を楽しませてくれる春の食材です。このスナップエンドウはグリーンピースとして知られている未熟な豆をさやごと食べることが出来るように改良された品種であり、その歴史は1970年代にアメリカから導入されてからのことですので、
それほど古いものではありませんが、そのルーツは古代ギリシャまで様上ることが出来ます。そのルーツとはすなわちエンドウ豆のことを指します。このエンドウ豆の歴史は非常に古く、古代ギリシャの時代にはすでに栽培されていたと言われており、世界最古の豆と呼ばれています。
その証拠の一つとして古代エジプトの王であるツタンカーメン王の王陵発掘の際に豪華な副葬品と一緒にエンドウ豆が発掘されているのは非常に有名な話として伝えられています。そのため少なくとも3000年の歴史をエンドウ豆は持っているということが出来ます。
スナップエンドウはその様な歴史の深い品種なのです。スナップエンドウ自体は近年になって日本に入ってきた新しい品種ですが、エンドウ豆自体については中国から9~10世紀に入ってきたと考えられています。本格的に栽培され始めたのは江戸時代に入ってからであり、
さやえんどうとして知られるようになりました。どちらもそのルーツとしては同じ植物であり、広い生息地を持った植物の一種として今も世界的に栽培されています。スーパーなどで見かけた際にはその様な深い歴史があるものであることを思い出してみると良いでしょう。
スナップエンドウの特徴
スナップエンドウを含むエンドウの仲間はエチオピアから中央アジアにかけての地域を原産としているという仮説が存在しており、15~20℃という比較的冷涼な気候を好む植物として知られています。寒さに強いのが売りであり、簡単に冬越しすることが出来るのが特徴であると言えます。
その中でもスナップエンドウはさやと未熟な豆を食べる種類であり、近年非常に人気が高まってきているものであると言えます。さやは肉厚で実には甘みがあります。栄養価にも優れており、タンパク質、カロテン、ビタミンC、ビタミンB1などを豊富に含んでいる緑黄色野菜です。
昔から食べられているグリーンピースなどと同じ種類の未熟な豆として知られています。収穫できる時期は4月から6月にかけてであり、春の野菜として多くの人に愛されている食材として知られるようになってきています。日本においてはアメリカから導入された品種として知られており、
甘みが豊かな食材として人気が高くなっています。肉料理の付け合わせやサラダなどの用いられますが、さっと塩茹ですることによって生まれる味わいはさやいんげんとはまた異なった方向性で様々なあ料理に応用されています。調理に特別な工夫を必要としておらず、
扱いやすい食材として非常に人気が高くなっているという特徴があります。食用にする場合にはあまり長時間加熱するのではなく、適度に抑えておくことが勇往であると言われています。そうすることによって色どりを鮮やかに残すことが出来ます。
-

-
アスパラガス(観葉植物)の育て方
アスパラガスの原産地というのは、南ヨーロッパ地中海沿岸あたりと言われています。ロシア南部やウクライナ、ベラルーシの一体が...
-

-
ディサの育て方
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ラン...
-

-
アフェランドラの育て方
アフェランドラはキツネノゴマ科でアフェランドラ属に属します。ブラジル、ベネズエラ、エクアドルなどの熱帯、亜熱帯アメリカを...
-

-
ブルーデージーの育て方
ブルーデージーは、キク科フェリシア属であり、このキク科フェリシア属は熱帯から南アフリカあたりを原産として約80種類が分布...
-

-
クロコスミアの育て方
クロコスミアは、モントブレチアやヒメヒオウギズイセンと言った別名を持つ球根植物の多年草の植物です。ヒメヒオウギズイセン(...
-

-
プランターで栽培できるほうれん草
ほうれん草の生育適温は15~20°Cで、低温には強く0°C以下でも育成できますが、育ちが悪くなってしまうので注意が必要で...
-

-
トックリラン(Beaucarnea recurvata)の育...
トックリランは、スズラン亜科の常緑高木でトックリランという名前は、幹の下部が徳利のような形に膨らんでいることが由来してい...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...
-

-
セネシオ(多肉植物)の育て方
植物としては多年草に分類されます。キク科に属しており、つる植物という独特な分類になっています。これは種類が非常に豊富にあ...
-

-
マツムシソウの育て方
マツムシソウは科名をマツムシソウ科と呼ばれており、原産地はヨーロッパを中心にアジア、アフリカもカバーしています。草丈は幅...




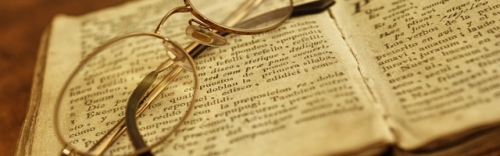





スナップエンドウは若くてみずみずしい食感を楽しませてくれる春の食材です。このスナップエンドウはグリーンピースとして知られている未熟な豆をさやごと食べることが出来るように改良された品種であり、その歴史は1970年代にアメリカから導入されてからのことですのでそれほど古いものではありませんが、そのルーツは古代ギリシャまで様上ることが出来ます。