ローズマリーの育て方

種付けに関して
種付けをする場合は、4~5月頃に蒔きます。発芽までは1ヶ月ほどかかり、その上初期の生育は遅いので、種を蒔いた年の秋ごろになっても10cmくらいにしか成長しませんが、冬を越し、2年目を迎える頃には急激に生長します。他にも苗を購入して植える方法もあります。
苗を選ぶ際には、下葉が枯れていないかや、病気や虫の付着がないかなども確認し、根が回りすぎているようなものは避けるようにして、根元がしっかりしているもの、葉の色が濃いものを選ぶと良いでしょう。苗を植えつけるのは、購入してからなるべく早い方が良いので、土はハーブ用のものを事前に準備し、ポットから苗を取り出したあと、根を軽くほぐしてあげてから植え込みます。
庭植えする場合には、ローズマリーの性質上、酸性土を嫌いますので、種付けの1週間くらい前から苦土石灰を土に混ぜ込み、中和するようにします。鉢植えをした際に、水はけが悪い場合は川砂を混ぜておきます。ローズマリーは根張りがとても良いので、種付けをした後は2年に1回は植え替えが必要です。その際には根鉢を崩さないよう、植えるようにしましょう。
ローズマリーの育て方
ローズマリーは、水はけが良い場所を好みますので、水分を多くやり過ぎてしまうと痛んでしまいます。育て方としては、土が乾いている状態の時には、たっぷり水分をあげますが、まだ湿っている様な状態の時には水はあげないようにしなくてはなりません。肥料をあげる場合には春と秋に10日に1回くらいの割合で液体のものをあげます。肥料を与えないからと言って枯れる事はありませんが、成長が早くなります。
ですが、夏には暑さで成長が止まるので、肥料は与えないようにします。置き場所については日当たりの良い場所で育てるようにしましょう。真夏の直射日光の中でも育ちます。多少の日当たりの悪さは問題ありませんが、湿気が多いと株の生育が衰えてしまい、弱ってしまう場合がありますので、乾燥している日陰は影響がほとんどありませんが、湿度が高い日陰には注意が必要です。
寒さに対しても気温が0℃くらいまでは問題なく成長しますので、室内に移動させたり、防寒措置を行う必要はありません。植え替えを行う場合は春が最も適していますので、3月~5月に行うようにします。秋の場合は9月から10月が最適でしょう。地植えをする場合の育て方は、株と株の間を50cmから90cm空けるようにするのが理想とされています。育て方で気を使う部分は他の植物に比べ少ないので育てやすいでしょう。
栽培する上でのポイント
ローズマリーを栽培する際には、立性のものと這性があるので、育てる環境の広さを考慮した上で、栽培するようにしましょう。ロ増やし方に関しては、立性・這性共に挿し木で増やす事になります。若い枝を5月中旬~6月中旬までの間に収穫し、2節ずつになるように切り揃えます。切り口になっている下部を水に30分程度浸し、水揚げをさせた後で、挿し木用の土に挿すようにします。
およそ20日が経過する頃には初根しますので、その後30日くらい経過したところで十分に初根できていることを確認しポットに植え替えする作業に入るようにします。鉢替え作業をする際のポットの大きさは一気に大きなものに移すのではなく、少しずつ成長に合わせてポットの大きさも変えていくようにします。
ローズマリーの様に乾燥気味の環境を好む植物は、鉢が大きすぎてしまうと土が多すぎるため、根が吸収する水分よりも土の保水力の方が上回ってしまい、表面上は乾燥しているように見えていても、実際の鉢の中は湿っているという状況が続いてしまい、枯れてしまう原因にもなります。
その場合、また移し変えなくても、梅雨の間は水やりを減らすようにし、葉が茶色く変色してしまった場合には早めに剪定するように心がけると、ローズマリーは元々強い植物ですので、復活する可能性も十分あります。挿し木をする場合は若い枝の方が初根がしやすく、生育スピードも早くなります。逆に古い枝を使用すると、初根はするものの、生育までの時間が若い枝と比べると倍になります。
料理などに使用する場合の収穫に関しては、1年を通して収穫する事ができます。生の葉を利用する場合は、軽く水で洗い流してから、葉だけを使用するようにしましょう。また、乾燥保存する場合は、花が開花する直前に枝ごと収穫し、日陰になる場所に束ねてつるします。気温が0℃以下になる冬場は、1月頃に株の根元に新芽が出ている事を確認してから全体の二分の一程度にカットし、枯れ葉や細い枝などを除去します。
この時、霜柱で根が浮くことのないよう株の周りを藁などで覆うようにすると良いでしょう。秋頃に苗を寝付けした場合は、この方法で冬の間にしっかりと根が張ります。2年目以降の栽培方法に関しても、花が咲いた後2週間ほどした、ら早めに切り取ることで1シーズンで2~3回花の開花を楽しむことができます。
ローズマリーの歴史
その歴史は古く、古代エジプト時代の墓からローズマリーの枝が発見されているように、人間との関わりは非常に古くからとされています。ヨーロッパの人々には、生活に深く馴染みのある植物として、神話や伝説を初めとして結婚式や葬儀年中行事として使用されている事を初め、家庭料理や人名にまで使われています。他にも薬、香料、縁起物などその使用用途は多岐に渡ります。
ローズマリーには属名があり、その名はロースマリヌスと言い、この植物の古代ラテン名に由来し、海の露と言われています。元々、古代ローマ人やエジプト人の間では、万能薬として認知されていました。ヨーロッパ地方では魔除けの聖木として知られていた事から、花嫁が身に付けるという習慣もありました。
ギリシャでは頭の働きを良くするとされ、受験を迎えた学生などは、頭にローズマリーの花を飾って、合格を祈っていたようです。それだけではなく、ハンガリーでは女王が若さを保つ為に使用していたという伝説も残っており、このため、現代でも、若返りのハーブとして使用されており、日本には江戸時代に渡来し、色々な用途に使用し、日本各地で栽培されています。
ローズマリーの特徴
ローズマリーは、ハーブの中でも特に美しい花を咲かせる植物とされています。生息地は名前の由来の通り海岸に近い所とされ、成長すると60cmから150cmくらいまで育ちます。、葉は、3cmくらいで、短くツヤがあります。先端は細く、針のようになっており、上の部分は濃い緑色、下のほうは白っぽい色をしています。
花は秋から冬にかけて葉の付け根に淡紫色の花を咲かせて、満開の時期には枝がたくさんの花でうめ尽くされます。現在ではこのほかにも葉のふちの部分に黄色い縁取りの入る品種や、コンパクトにまとまるもの。花の色もピンクのものなど品種改良されたものもあります。乾燥や強い陽射しにも強く、病害虫にも強い植物です。
また、立性這性という上に伸びて背が高くなるタイプと、クリーピングタイプと言われる這性の枝が長くなると地面を這うように成長するものの2つに分かれています。薬用に使用されていた事もあり、殺菌・抗菌・抗酸化作用も持ち合わせています。
料理に使用される際には、生で使用する場合と乾燥させて使用する場合があります。原産は地中海沿岸地域の中でも特にフランスや、ユーゴスラビアの西部沿岸地方の石灰質の丘陵上に広く分布しています。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
タイトル:ダリアの育て方
タイトル:ゆりアジアティックハイブリッド系の育て方
タイトル:ハイビスカスの育て方
タイトル:アーティチョークの育て方
-

-
ゲンノショウコの育て方
この植物の原産地と生息地は東アジアで、中国大陸から朝鮮半島を経て日本全国に自生しているということですので、昔から東アジア...
-

-
キンセンカとハボタンの育て方
冬枯れの戸外で一際鮮やかに色彩を誇るのがハボタンです。江戸時代中期に緑色のキャベツに似たものが長崎に渡来して、オランダナ...
-

-
ハナモモの育て方
ハナモモというのは、中国が原産地で鑑賞をするために改良がなされたモモですが、庭木などにも広く利用されいます。日本へ入って...
-

-
コレオプシスの育て方
コレオプシスはアメリカ大陸、熱帯アフリカにおよそ120種類が分布するキク科の植物です。園芸用としては北アメリカ原産種が主...
-

-
ハランの育て方
ハラン(葉蘭)はスズラン亜科ハラン属の常緑多年草です。名前に蘭という漢字を使用しますが、ラン類ではなく、巨大な葉を地表に...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)の育て方
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)は和名を細葉百日草といい、原産地はメキシコを中心とした南北アメリカです。リネア...
-

-
クガイソウの育て方
クガイソウは、日本でも古くから知られていた植物で、昔の植物の書物にも載せてあるくらいですから、相当有名な薬草だったという...
-

-
園芸初心者でもできる枝豆の育て方
枝豆の育て方のポイントは以下のようになります。枝豆の生育適温は25~28度で、高温には強いですが、低温と霜には弱いので、...
-

-
タカネビランジの育て方
タカネビランジはナデシコ科マンテマ属に分類される高山植物で、花崗岩帯などが主な生息地と言われています。日本が原産の植物で...




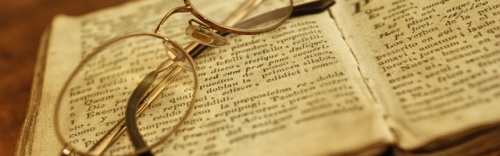





その歴史は古く、古代エジプト時代の墓からローズマリーの枝が発見されているように、人間との関わりは非常に古くからとされています。ヨーロッパの人々には、生活に深く馴染みのある植物として、神話や伝説を初めとして結婚式や葬儀年中行事として使用されている事を初め、家庭料理や人名にまで使われています。他にも薬、香料、縁起物などその使用用途は多岐に渡ります。