トサミズキの育て方

育てる環境について
トサミズキの育て方は、花がしぼんでも花は摘みません。花の根元から新芽が出てくるので、しぼんだからと花を摘んでしまうとこの新芽までなくなってしまいます。日当たりを好む品種です。半日蔭でも生育はしますが、花つきが悪くなる可能性があります。
寒さには弱いので、東北や北海道では庭植えすると枯れてしまします。その場合は鉢植えにして管理することをおすすめします。それ以外の地域では、戸外でも越冬が可能です。剪定の仕方は、花後は5月、冬の整枝は1~2月に行います。トサミズキは放任しても形よくまとまりますが、
放任しすぎると3mにも成長するので、通常は1m程になったら剪定を行います。若木のうちはあまり剪定の必要もなくひこばえや徒長枝を整理する程度でかまいません。ただ根元から多数の新梢が発生してくるので、枝数が多くなりすぎたら元から切ってすっきりさせるとよいでしょう。
小さい庭では主枝を2~3本程度に整えると見た目がよくなります。花後の剪定では長い枝や樹冠からはみ出す枝を整理し、落葉期には樹形を整える作業を行います。あまり刈り込みすぎると花芽を落とすことになるので、不要な枝は間引くように剪定します。
日当たりを好むので、日当たりの良い場所で育てます。耐陰性があるので、午前中の日光が良く当たる半日蔭でも育ちます。水きれを嫌うので、鉢植えは鉢土の表面が乾けば与えます。夏はよく乾くので毎日水やりします。庭でも雨が降らず乾きすぎる場合は水を与えます。
種付けや水やり、肥料について
用土は一般的な土で、市販の花と野菜の培養土または、赤玉土7腐葉土3を混ぜたものを使います。庭植えするときには、元肥としてあらかじめ庭に堆肥と鶏糞を混ぜ込み、根に肥料があたらないように土を入れてから根鉢を入れて埋めます。一般的には、庭に植えることが多い種類です。
庭に植えてしまって根付けば、水やりしなくても十分生育する木です。比較的乾燥に強い品種ですが、強い乾燥では枯れたり、生育不良を起こすので、夏の日照りが続く場合は水を与えます。また鉢植えの場合は、土が乾いたら水をあげるようにします。
地植えよりも水の渇きが速いので注意が必要です。ただ水をあげすぎても根腐れの原因となるので、土が乾くまでは水はあげないようにしてください。肥料は2月に感肥として堆肥と鶏糞と油粕を混ぜたものを周囲の土に混ぜ込みます。ただ花つきに問題がなければ寒肥はあげなくても問題ありません。
翌年の花芽のために5月か9月に油粕と骨粉を混ぜたものを周囲にまきます。鉢植えは2~3年に1回を目安に植え替えが必要です。根鉢の周りを3分の1から2分の1くらいこわして、新しい用土で植え替えをします。植え替えの時期は2月中旬から3月頃に行うのがよいでしょう。
葉先が枯れた場合は、水分不足が原因です。適切な水管理を怠ると葉先枯れの症状が出るので、乾燥を防ぎ多湿で根が吸収しないなどの状態にならないように注意が必要です。また肥料の高濃度障害によっても葉が枯れる場合があるので、肥料の分量も適切な量にする必要があります。
増やし方や害虫について
植え替えは落葉時期に行います。葉っぱがある時期に植え替えをすると枯れることがあるので、葉が落ちてから行います。鉢植えの植え替えの場合は、2月または3月の花が咲く前の落葉時期に行うのが良い時期です。トサミズキは、根がよくはる品種なので、根づまりを起こしやすく2~3年に1回の植え替えが必要になります。
枝が混みすぎると、葉の表に白いカビの生えるうどんこ病が発生することがあります。うどんこ病は葉に白い斑点がぽつぽつでき始め、そのうち葉全体が白くなるもので、他の病害と容易に区別できる症状です。21度が適温なので真夏や真冬には自然に治癒してしましますが、
うどんこ病をそのまま放っておくと葉の表面がどんどん白くなり、生育不良を起こしてしまいます。予防のために枝葉を剪定し、風通しと日当たりを良くすることが必要です。
増やし方には、さし木、株分け、種まきがあります。さし木の場合、通常春ざしを行います。
前年の枝を1月下旬から2月に採取しておき、3月中旬から下旬にかけてさします。夏ざしは、当年枝の半熟成枝を6月中旬から7月上旬にさしていきます。春ざしを行うときには赤玉土など肥料分のない土を使います。
株分けの場合、根元からひこばえが出ているときに、十分発根しているのを確認して分けていきます。種まきの場合、秋に入って熟した種を採取しておいたものをとりまきします。春まきの場合は、種を乾燥させないように翌春まで貯蔵しておきます。
トサミズキの歴史
トサミズキの生息地は、四国の高知県です。高知県(土佐)に自生することからトサミズキ(土佐水木)と呼ばれるようになりました。原産国は日本です。暖帯植物で、九州南部から中国、近畿まで連続的に分布しています。「ミズキ」と名前がついていますが、
ミズキ科ミズキ属の「ミズキ」とは別の科です。「ミズキ(水木)」は春期発芽前に幹枝を傷つけると多量の水分を出すことからその名がついたと言われています。しかしこのトサミズキは枝を切っても水が滴り落ちることはありません。このことからも「ミズキ」とは品種が違うことがわかります。
日本では、農作業に当たって植物の開花状態や語呂を気にしていたため、「満木」と書いてミズキとしていたという説もあります。3月から4月頃に花が咲き、一つのつぼみから1.5㎝くらいの黄色く小さな花が7~10個集まって咲きます。
これが長さ9㎝くらいの花序になって下に向かって咲く姿はとても美しいものです。黄色い花と赤いおしべのコントラストが美しく人気のあるポイントです。次第に黄色い花粉が目立ち、赤くなっていきます。ぶら下がるように咲く黄色い花は、とても優雅に咲き、
トサミズキの花言葉「清楚」、「愛」、「伝言」、「優雅」がまさにぴったりあう花を咲かせます。日本原産のトサミズキですが、日本だけでなく外国でも高く評価されています。また花だけでなく葉の形状も美しい樹なので、盆栽として楽しむ人も多くいます。
トサミズキの特徴
トサミズキ(土佐水木)は四国に分布する落葉性の樹木です。高知県(土佐)の蛇紋岩地帯や石灰岩地などに野生のものが多くみられることからこの名前が付きました。早春から明るい黄色の花を咲かせ、庭木や盆栽、切り花として広く親しまれてる木でもあります。
高さは放っておくと数mとなり、若い枝は分岐点でジグザグに曲がるので、ある程度の高さになると剪定が必要になります。また丸いたまご型の葉が特徴で、表面には散毛があり、裏面には葉脈状に軟毛が多くあります。おしべの先端が暗い紅紫色をしているのも特徴です。
葉の形状は「ミズキ」の仲間に似ていますが、マンサク科で、早春に葉の展開に先立って穂状の花序を出します。花弁は5枚のヘラ形で、おしべは5本、春を告げる花として植栽されています。花が終わると新芽が出てきます。マンサク科は、双子葉植物の科で、
世界の亜熱帯から暖帯にかけて27属80-90種が分布しています。この中のトサミズキが日本で自生しており、庭木として古くから栽培されています。枝が少なく軽快な樹形です。置き場所は日当たりの良い場所が望ましいですが、東北、北海道以外では戸外で越冬も可能です。
ただ真夏に1日中光が照り付けるような場所は枯れてしまうので注意が必要です。落葉樹なので冬は葉を落として越冬します。あまり剪定を必要としませんが、樹形が乱れたり、高くなりすぎた場合には剪定を行う方がよいでしょう。また丈夫な木なので、病気や害虫の心配はほとんどいりません。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニセアカシアの育て方
-

-
キリンソウの育て方
キリンソウとは、ベンケイソウ科に属している多年草のことです。生息地は、シベリア東部や中国、朝鮮半島などが挙げられます。タ...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
ヤブジラミの育て方
分類はセリ科でヤブジラミ属ですが、原産地及び生息地ということでは中国から朝鮮半島、台湾、日本言うことで東アジア一帯に生息...
-

-
アセロラの育て方
アセロラの原産国は西インド諸島や中央アメリカなど温かい熱帯気候の地域です。別名「西インドチェリー」とも呼ばれています。そ...
-

-
マクワウリの育て方
マクワウリと言えば、お盆のお供えには欠かせない野菜です。メロンの仲間で、中国や日本で古くから栽培されるようになりました。...
-

-
植物を元気いっぱいに育てるには
どれを選ぼうか迷うほど園芸店などにはたくさんの植物が並んでいます。好みの花色や珍しさで選ぶとうまく育たないこともあり、植...
-

-
スギ(杉)の育て方
スギが日本に登場したのは200万年前頃で、縄文時代や弥生時代には、すでに日本全国に広く分布していました。日本人が日本人に...
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...
-

-
植物の栽培、育て方のコツ。
植物を育てるのは生き物を飼うのよりはだいぶ気楽にできます。動かないので当然といえますが、それでもナマモノである以上手を抜...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...




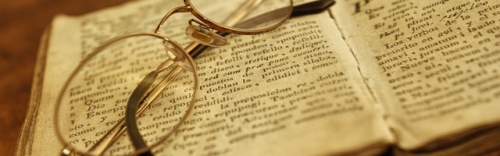





トサミズキの生息地は、四国の高知県です。高知県(土佐)に自生することからトサミズキ(土佐水木)と呼ばれるようになりました。原産国は日本です。暖帯植物で、九州南部から中国、近畿まで連続的に分布しています。