モナデニウムの育て方

育てる環境について
モナデニウムは日当たりのいいところが好みの植物です。ですのでできるだけ日当たりがいい場所で保管することが大事になってきます。そしてモナデニウムは根張りが弱い植物です。ですので、冬の季節は断水をしたりしますが、あまり与えないでいると、細根が枯れてしますことが起こってしまったりします。
そうなると再生をするにも時間がかかってしまいます。だからできるだけ断水するとしても月に一回ぐらいは水を与えてあげると根が枯れる心配がないです。そして水を与えるときには、土を軽く湿らせる感じに与えるといいです。また肥料を与える時は、不足しない程度に成長期の夏などには気をつけておかないといけないです。
与える肥料に関しては、液肥などがよくて薄めたものなどがいいです。また土に混ぜ込んでおくなども効果的です。そして気温に関しては、モナデニウムは夏には強いですが、どうしても寒さには弱くなってしまいます。それに休眠中などになるので、できるだけ寒い時期になってきたら、室内で管理してあげるといいです。
室内の暖かい場所で管理してあげて、また暖かくなってきたら、室外で育てるといいです。そして冬場は室内に移動させますが、それでも日の光を当ててあげるのも大事です。日の光を当てることによって、強く丈夫になります。だから冬の休眠中であっても時々は、昼間など気温が比較的高くなるときに、日の光をしっかりと与えてあげることによって、強い植物に育っていきます。
種付けや水やり、肥料について
モナデニウムの水やりに関しては、基本的には乾いたらたっぷりとした水を与えてあげます。あまりまだ乾いてない状態で与えすぎてしまうことだけは気をつけてあげるといいです。そして成長期の時はモナデニウムの場合は夏になります。だから夏になったら、土が完全に乾いた状態になったときに水をたっぷりと与えてあげることが大事です。
しかしもしも日光の光がたくさん当たるところであれば頻繁に水を与えてあげてもかまわないです。だから置く場所はモナデニウムは明るい日当たりのいいところが好みですので、明るいところに置いてあげて水分を与えてあげるようにします。そしてどんどん気温が下がってきて、夏が終わりに近づいてきたら、今度は水の量や回数などを減らしていってあげます。
減らしたり、回数を少なくしたりしないと、今度は与えすぎになってしまったりします。だからできるだけ気温の下がりはじめから徐々に減らしていきます。そして寒くなってくると、葉が枯れ落ちてきます。枯れ落ちてきたときには、あまり水を与えないで、春までは断水気味にしていきます。
完全に断水をしてしまったりすると、どうしても根が枯れてしまいます。だからまったく与えないのではなく、月に一回程度水を与えたりして時々は様子をみてあげるといいです。根が枯れてしまったりすると、なかなか再生するのにかなり時間がかかってしまったりします。また肥料に関しても不足しすぎないように気をつけてあげます。
増やし方や害虫について
モナデニウムはさし木にして増やすことが可能な植物です。大きくなってきてしまって、そろそろ切りそろえたいと思ったときにさし木にするといいです。時期的には6月ぐらいに行なうのがちょうどいい感じになっています。そして6月ぐらいにカットしたときに、切り口から液がでてきます。この液は触ってしまったりするとかぶれの原因になったりしてしまいます。
だから切り口は触らないようにして、洗い流すのが大事になってきます。そして肥料分をほとんど含まない土で通気性や保水性が高い鹿沼土に植えるといいです。そして挿した直前には水をたっぷりと与えて、その後は乾いてきたら水をあたえるようにしておけば大丈夫です。できるだけ発根をしてしっかりするまでは管理をきっちりとして、乾燥しすぎないようにしてあげるといいです。
そして乾燥してしまう前に水を与えますが、また与えすぎてしまうと根ぐされをして発根できない状態になってしまいますので、気をつけないといけないです。そしてモナデニウムは風通しのよい一年中、日光の光があたる場所で育てることが大事です。だからしっかりと日の光があたる場所に置いておくことが大事です。
あまり日の光があたらない場所にあると、細く長く伸びていってしまいます。また他にも害虫の心配が出てきてしまいます。あまり日の光にあたらないで育てていると、風通しもあまりよくない状態になってしまって、害虫が発生してしまいます。害虫の発生を防ぐためにも日当たりにはきをつけます。
モナデニウムの歴史
モナデニウムは日当たりのいいところで栽培をします。そして育て方は土が乾いたらたっぷりの水を与えてあげます。塊根タイプの植物でケニア周辺が主な原産地になっていて、暖かい場所で育っている植物になっています。標高の低い乾燥した草原などが生息地になっています。そしてモナデニウムはユーフォルビアの仲間になっています。
だから個性的な形をしています。あまり有名な植物ではないので、変ったものを育ててみたいという方にとってはぴったりの植物です。そしてユーフォルビアの仲間ですので、葉や幹を切ったり、傷つけてしまったりしたときに、白い液がでてきます。この白い液は触ってしまったりするとかぶれてしまう原因になります。
だからお手入れをする際には手袋などをして触るようにするといいです。さし木などをしたり切り戻しをしたりする際には、白い液を直接触らないようにして、またすぐに洗い流すといいです。そして夏などは野外で日当たりのいいところに育てることがおすすめですが、冬になってきたら、室内に移動させることがいいです。
野外でも育てることができる場合もありますが、あまり寒くなってしまう場合は外に出さないほうがいいです。冬は暖かい室内で管理してあげることが大事です。そして気温も上がってきたら、モナデニウムの成長期になりますので、しっかりと日の光をあててあげて、害虫の被害を合わないようにしっかりと風通しのいいところに保管してあげるようにするといいです。
モナデニウムの特徴
モナデニウムは日当たりがいい環境で育てます。一年中日当たりのいいところに置いておくのがよくて、また風通しのいいところで育てるのがいいです。だから日の光を浴びて育っているのかどうかによって、成長がかなり変ってきてしまいます。あまり日の光を浴びないで育ってしまうと、茎が長く伸びて成長してしまいます。
だからあまり長く伸びて成長してしまったりすると、細く長くで弱々しかったりしますので、伸びすぎてしまったときには気って分岐させてあげてもいいです。そしてあまり伸びすぎないように日光の光が十分当たる場所に変更してあげるといいです。また風通しも大事になってきます。
風通しが悪くなってしまったりすると、どうしても蒸れてしまったりしますので、害虫の被害にあいやすくなってしまいます。植物が弱ってしまったり、また枯れてしまったりする原因になってしまうので、風通しも一年を通じてしっかりとできる環境で育てることが大事になってきます。そして水やりに関してはあまり与えすぎてはいけないです。
与えすぎてしまうと、根腐れの原因になってしまったり枯れてしまいますので、水分は上げすぎは注意が必要です。だから夏場などの成長期になってくると、土が乾いたらしっかりと水を垂れるまで与えておきます。そして水はけのいい土に植えておくことも大事になってきます。また今度は冬場になってきたら、あまり与えないで、ほとんど断水状態にして管理をしていきます。
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
トケイソウの仲間の育て方
トケイソウの仲間は中央アメリカから南アメリカにかけてが原産地とされています。生息地は熱帯地域が中心で、現在では世界中に数...
-

-
アデニウムの育て方
アデニウム/学名・Adenium/キョウチクトウ科・アデニウム属です。アデニウムは、南アフリカや南西アフリカなど赤道付近...
-

-
ナツメ(実)の育て方
この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べる...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
リュウビンタイ(Angiopteris lygodiifol...
かたまりから葉が四方八方に突き出たようなユニークな形で成長していくリュウビンタイは、その基部が竜のうろこのようであること...
-

-
ソラマメの育て方
世界で最も古い農作物の一つといわれています。生息地といえば例えば、チグリス・ユーフラテス川の流域では新石器時代から栽培さ...
-

-
カンパニュラの仲間の育て方
カンパニュラはラテン語で「釣鐘」を意味しています。和名もツリガネソウだったり、英名がベルフラワーだったりすることから、ど...
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...
-

-
ナスの育て方
インドが原産の植物といわれ、中国でも古くから伝わる植物でもあります。栽培の歴史は数千年を超え、農業に関する世界最大の古典...




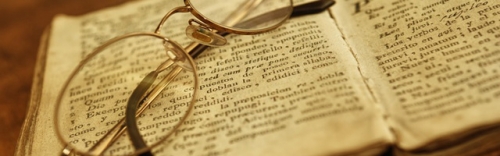





モナデニウムは日当たりのいいところで栽培をします。そして育て方は土が乾いたらたっぷりの水を与えてあげます。塊根タイプの植物でケニア周辺が主な原産地になっていて、暖かい場所で育っている植物になっています。標高の低い乾燥した草原などが生息地になっています。そしてモナデニウムはユーフォルビアの仲間になっています。