ハオルチアの育て方

育てる環境について
育てる環境に関しては乾燥地帯が一番適しているので、家で園芸用として育てる場合にも水のやり過ぎには注意をしなければなりません。外に植えて育てる場合には夏の強い日差しや西日をなるべく避ける事ができる場所で栽培をすることが重要で、乾燥や暑さに強い植物なのですが、
直射日光などには弱い傾向があるので、暑すぎる場所を避ける事が大切です。またハオルチアのような多肉植物に関しては、あまり世話をしなくても良いと思われがちなのですが、実際は鉢の植え替えや肥料などにも気を配る必要があるので、ある程度の基礎知識は必要となります。
花が咲いている2月から6月までの時期には色などの変化が見られるので、ハオルチアの状態などが把握できるのですが、その時期が終わってしまうと緑色のまま鉢植えの中で育つので、肥料をやるタイミングなどが難しいのですが、花が咲いている時期には栄養分を必要とするので、
その時期にしっかりと世話をすることで、次の年にもきれいな花を咲かせることができます。また大きく育ってしまった場合にはそのままにしておくこともできるのですが、なるべく植え替えなどをして根を張るスペースを大きくすることが重要です。
これらの植物は鉢の大きさに合わせて成長するので、小さなカップなどで栽培している場合にはそのままの大きさを維持することができるのですが、ある程度は大きくなるので、大きな鉢に植え替えるなどの処置が必要になる可能性もあります。
種付けや水やり、肥料について
この植物は種まきをしたり、根ざしや葉ざし、株分けをするなどして増やすことができる植物なのですが、これらに適した時期としては3月から5月の暖かい季節と9月から10月の秋のはじめくらいの季節が良いとされています。多肉植物なので夏の暑さに強いという印象が強いのですが、
実際にはあまり強くはないので春や秋などの気候が安定している時期に株分けなどを行います。群生している場合には植え替えをするときに一部分を切り取って株分けをすることができるのですが、そのまま植えてしまうこともできます。種まきで増やす場合に関しては原種に限られていて、
ほとんどの場合は株分けなどによって、増やされています。水やりに関しては春と秋の生育が盛んな時期には土の表面の乾燥具合を見て水を与えていきます。夏と冬は休眠期にあたるので、土が湿りすぎていると根の部分が水分を吸収できないので腐ってしまうことがあります。
最近ではインテリアとして室内のエアコンで温度調節されている部屋で栽培することがあるのですが、この場合には一年中が生育期となるので、土の表面が乾いたら水やりをしなければなりません。肥料に関しては生育期に化成肥料や液体肥料を少量与えることが必要になるのですが、
水はけの良い用土を使っている場合にはあまり必要ではありません。用土に関しては鹿沼土の小粒と赤玉土小粒、ピートモス、川砂、くん炭などを配合してものを使用するのが一般的となっています。
増やし方や害虫について
増やし方は様々なバリエーションがあるのですが、株分けをするのが一番簡単なので初心者の場合には鉢替えの時に株分けをすることができます。多肉性植物の場合には基本的には病気になることが少ないとされているので、病気の心配をする必要がないのですが、
害虫に関してはカイガラムシやアブラムシ、ネジラミ、キノコバエなどの数多くの種類の害虫が根の部分や茎の部分に付着する可能性があるので、気をつけて見ておく必要があります。とくに湿り気の多い環境で育てている場合には用土の中にキノコバエの幼虫が発生してしまって、
根や茎が被害にあって、栄養分や水分の吸収ができなくなって、枯れてしまうこともあります。カイガラムシは基本的には茎の部分に付着するのですが、薬剤などが効きにくいので歯ブラシなどを使って、少しずつ落としていきます。
アブラムシに関しては少なければあまり害がないのですが、増殖してしまうと、葉の部分などを変色させるので、注意が必要で、また感染性の最近などによって植物を弱らせることもあるので、数が多くなったら駆除をする必要があります。ネジラミは栽培をする段階で根の部分を、
清潔にしておく必要があるのですが、発生した場合には枯れてしまうことがあるので、薬剤などを使って駆除を試みる必要があるのですが、効果が十分でない場合には一度根の部分を洗浄する必要があります。その場合には植えている土や鉢なども全て交換する必要があります。
ハオルチアの歴史
ハオルチアはもともと南アフリカ地域の原産のユリ科の多肉植物で、水分が多くなると生育できないことが多いので日本で栽培をする場合にはアフリカの乾燥している土地のように水分を少なめにして育てることが基本になります。現在では様々な品種のハオルチアが販売されていて、
中国などでも人気の観葉植物となっています。アフリカの乾燥地帯を生息地としているこの植物は育て方難しいので初めて多肉植物を育てる場合には経験者などのアドバイスを聞く必要があります。サボテンなどと同様に水分があまりに多いと根の部分が腐ってしまって、
地面からの水分の吸収ができなくなるので、夏の暑い時期以外は乾燥させたままでもほとんど問題がありません。アフリカから日本に入ってきたハオルチアですが、日本の温暖で湿潤な気候はあまり生育には適していないので、外で育てる場合には天気などにも、
気をつけて雨の日にはベランダなどに移動させるなどの対処が必要となります。南アフリカからナミビア南部にかけて100種類以上が自生しているとされているのですが、歴史的にはイギリスの植物学者が発見してヨーロッパに紹介したことがきっかけで、
観賞用に品種改良などが行われてきたので、この学者の名前から属名が付けられています。またハオルチアは品種によってはユリ科として分類されている場合もあります。また多年草なので寒さなどに気をつけて育てることで何年も楽しむことのできる観葉植物です。
ハオルチアの特徴
ハオルチアの特徴としては手頃なサイズの多肉植物であるということで、これによって多くの愛好家によって栽培がされていて、日本でもミニチュアサイズのハオルチアなどを部屋のインテリアとして用いている家庭も数多くあります。
またホームセンターなどでも小さなサイズのものが比較的安い値段で売られているので、おしゃれなカップなどで栽培をする若い女性も増えています。ユリ科の多肉植物なのですが、基本的には乾燥地帯の植物としての性質を強く受け継いでいるので、多年草なのですが、
水をあげ過ぎたりすると根が腐ってしまって枯れてしまうこともあります。ハオルチアという植物は白やピンクの花が咲くので、開花期の2月から6月くらいまでは小さな花を楽しむことができます。それ以外の季節には変化が殆ど無いので、
上手に栽培出来ているのか心配になることもあるのですが、乾燥には非常に強いので水やりなどをしなくても空気中の水分だけで十分に育っていきます。また根の部分も水分の量に合わせて長くなるので、生命力の強さにまかせておくだけでも長持ちさせることができます。盆栽などとしても楽しむことができるのですが、
初心者の場合はインテリアの一部として他のサボテンなどと一緒に園芸用の植物として栽培することが多いので、植物をこまめに世話をするのが苦手な人にとっては非常に楽な観賞用の植物となります。しかししっかりと成長させるためには植え替えを行ったり、肥料をやる必要があります。
多肉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エンレイソウの育て方
タイトル:トリテレイアの育て方
タイトル:エケベリアの育て方
-

-
キンギョソウの育て方
キンギョソウはもともとは多年草ですが、暑さで株が弱り多くが一年で枯れてしまうので、園芸的には一年草として取り扱われていま...
-

-
ソラマメの育て方
世界で最も古い農作物の一つといわれています。生息地といえば例えば、チグリス・ユーフラテス川の流域では新石器時代から栽培さ...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
フルクラエアの育て方
フルクラエアはリュウゼツラン科の植物で原産地は熱帯や亜熱帯地方の乾燥地帯なので日本には自生していません。またこの品種には...
-

-
カツラの育て方
カツラは日本特産の植物で大昔である太古第3紀の頃から存在します。日本とアメリカに多く繁茂していましたが、次第にアメリカに...
-

-
チョコレートコスモスの育て方
チョコレートコスモスは、キク科 コスモス属の常緑多年草です。原産地はメキシコで、18世紀末にスペインマドリードの植物園に...
-

-
スカビオーサの育て方
別名を西洋マツムシソウといいます。英名ではピンクッションフラワーやエジプシャンローズ、スイートスカビオスなどあります。ス...
-

-
クサギ(ソクズ)の育て方
こちらは被子植物、真正双子葉類です。シソ目、シソ科に該当します。クマツヅラ科に該当するとの話もあります。栽培上においては...
-

-
メロンの育て方
園芸分野では実を食用とする野菜、「果菜」とされています。青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物や果実に分類されて...
-

-
サンギナリア・カナデンシスの育て方
サンギナリア・カナデンシスとはケシ科サンギナリア属の多年草の植物です。カナデンシスという名の由来はカナダで発見されたこと...




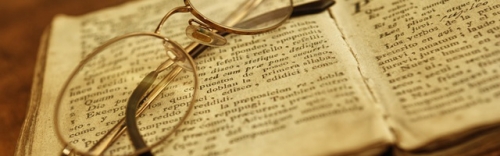





ハオルチアはもともと南アフリカ地域の原産のユリ科の多肉植物で、水分が多くなると生育できないことが多いので日本で栽培をする場合にはアフリカの乾燥している土地のように水分を少なめにして育てることが基本になります。