プセウデランテムムの育て方

育てる環境について
プセウデランテムムは日当たりの良い土地から半日陰の土地まで、幅広い条件化の環境で生育できます。ポイントは保水力の高い土を好むことです。排水性の良い土壌の場合でも、保水性を改善することが可能ですから、水はけの良い土地であれば、水がたまらない程度に、
しっとりと保水能力が発揮されるような土壌に改善すると良いでしょう。土壌の改善には、ピートモスやミズゴケが大変役に立ちます。バークと呼ばれる木片を土に混ぜ合わせても、保水力を向上させられます。半日陰でも生育しますが、必ずしも耐陰性が高いというわけではありませんので、
花の色を鮮やかにしたい場合や、カラーリーフを観賞したい場合には、日光不足にならないように注意しましょう。光合成によって作られる栄養分が、プセウデランテムムでは重要な役割を果たします。鉢植えで栽培する場合は、土を多めにして深くするなど、
保水力の向上を工夫すると良いでしょう。熱帯性気候や亜熱帯性気候が原産の植物ですが、真夏の高温には弱い面があります。耐暑性は普通です。耐寒性は、弱いので、越冬には注意しましょう。鉢植えやプランターであれば室内に移動して、常に室温が5度以上に
維持できるように管理するのが理想的です。地植えにしている場合は、温室効果の得られるように、大きめの植物用カバーを被せておくと越冬させやすくなります。温室に限らず、室内で日当たりの良い環境であれば、無理なく越冬させることが可能です。
種付けや水やり、肥料について
プセウデランテムムは水を好む常緑性の植物です。とくに春から秋にかけては成長期ですから、水やりを、こまめに行うように心がけましょう。保水性を高い土に改善しておくと、より効果的です。夏は毎日、水やりを行うのが理想的です。水やりに適した時間帯は
、夏ならば朝と夕方です。
保水性の高い土に、日中に水を与えてしまうと、水分が高温化してしまうことがあり、根に負担がかかってしまいます。比較的に涼しい朝のうちに水やりを済ませておくと、水分が早くに吸収されますので、土の中の水分が必要最低限になりやすく、日当たりが良い場所であっても
高温化してにくいというメリットがあります。肥料は液体肥料よりも置き肥のほうが適しています。液体肥料は吸収が良いのですが、即効性が強すぎて長持ちしにくいからです。プセウデランテムムの栽培では保水性の高い土壌が求められますので、粒状の化成肥料などを置き肥しておくことで、
ゆっくりと栄養分が土壌の水分に溶けて浸透していきます。ゆっくりと時間をかけて、栄養分が浸透して根から吸収されますので、急激な栄養過多になりにくいメリットが得られます。肥料の栄養分の基本は、窒素、リン酸、カリウムです。これら三要素が、
ほぼ等分となるようなバランスで置き肥すると良いでしょう。開花期間が長い品種で、具体的にはラクシフロルム種などは、リン酸を多めに与えても良いでしょう。リン酸を多めにすることで、開花期間が長くなっても、花冠の色が鮮やかなまま維持されます。
増やし方や害虫について
プセウデランテムムは、挿し木で増やすことが可能です。挿し木を行うには、初夏から夏の間が最適な時期です。挿し木にするときは、切り口から雑菌が入らないように注意しましょう。切り口から雑菌が入らないようにするには、土を選ぶことがポイントです。
赤玉土や鹿沼土だけを使用し、挿し木をすると成功しやすくなります。栄養分の高い腐葉土を使用してしまうと、発根しにくく、発根する前に枯れてしまうことがあります。挿し木をするときは、プセウデランテムムの枝を10センチメートル以内に切り、葉を少なめにして水分の蒸発を抑制します。
発根し、ある程度まで成長し葉が増えてきてから、腐葉土も含んだ培養土などの保水性の高い土に植え替えします。プセウデランテムムは害虫がつきにくいほうですが、カイガラムシにだけは注意しましょう。カイガラムシが繁殖してしまうと、葉がベトベトしてくるなどの被害が発生します。
カイガラムシが繁殖してしまう要因は、風通しの悪さです。通気性が改善されれば、カイガラムシが発生したとしても、被害は小さく済みます。プセウデランテムムは、病気にかかりにくい植物ですから、カイガラムシ対策をしておくだけでも一年を通して美しい常緑性の葉を観賞できます。
プセウデランテムムが茂ってきたら、枝を剪定して風通しを良くし、剪定した枝を切り揃えて挿し木にすると良いでしょう。すでに生育中のプセウデランテムムの土と、剪定した枝を挿し木する土を別々にするのが、上手に育てながら増やしていくコツです。
プセウデランテムムの歴史
プセウデランテムムは、キツネノマゴ科プセウデランテムム属の植物です。常緑性の植物です。熱帯気候と亜熱帯気候の地域が原産であり、東南アジアや南太平洋地域に生息地が存在しています。かつての大航海時代に、ヨーロッパからの渡航者が香辛料を発見していったことに伴い、
南太平洋各地で観賞用の植物として人気となり、本国へ持ち帰り広まっていきました。寒冷気候のヨーロッパでは、持ち運んでみたものの育成が困難であることも多く、越冬できなかったりしたため、独自に品種改良されることもありました。温室での栽培は成功しやすかったため、
温度管理と湿度管理によっては栽培しやすい熱帯植物として認識されるようになりました。近年では、世界中の熱帯地域と亜熱帯地域に、およそ120種類のプセウデランテムムが自生していることが確認されています。育て方は決して容易とは言えないのですが、
エアコンの普及や、一戸建て住宅における断熱材の普及により、越冬が可能になってきました。温室での栽培には適しており、植物園では多種多様なプセウデランテムムが栽培されています。住宅環境の改善や、建築資材の改善によって、屋内の温度管理と湿度管理が容易になったことも、
プセウデランテムムが世界中に広まっていった原因となっています。現在では、ラクシフロルム種とリラキヌム種とアトロプルプレウム種などが家庭での観賞用としても親しまれており、気軽に鉢植えでも栽培可能な品種としてはレティクラツム種とオヴァリフォリウムが知られています。
プセウデランテムムの特徴
プセウデランテムムは常緑性の植物です。一年を通して、鮮やかな緑色の葉を茂らせています。白色と紫色を中心に、熱帯性気候を連想させる鮮やかな色彩の花を咲かせます。開花期間が長いのが特徴で、気候条件が良好であれば、長い期間にわたって花を観賞できます。
葉は対になって生えるスタイルで、披針形と呼ばれる形をしています。披針形とは、平たくて細長く、先端が尖っている状態の形です。先端が尖っている分、根元のほうが広がっています。日本では、笹の葉に似ている形として知られています。プセウデランテムムは、
品種によって異なる花の付き方をするのも特徴です。ラクシフロルム種は、濃い赤紫色の花を咲かせます。花径は3センチくらいで花冠は筒状を形成しており、筒状の花冠は先端で5つに裂けて広がり、星の形になります。リラキヌム種は、淡い青紫色の花を咲かせます。
花冠は、やはり筒状なのですが、4つに裂けて広がるのが特徴です。アトロプルプレウム種は、淡い紅色もしくは赤紫色と形容される色の花を咲かせます。花冠は筒状で、先端は4つに裂けます。葉が全体的に紫色を帯びているのが特徴で、紅色や紫色の斑模様が入っているのが特徴です。
アトロプルプレウム種のプセウデランテムムは、色味がかった葉がカラーリーフと呼ばれて親しまれています。カラーリーフが美しい品種は、熱帯性気候だけでなく亜熱帯気候や、積雪の少ない温帯気候の地域でも、庭木として栽培されていることがあります。
-

-
スズランの育て方
春を訪れを知らせる代表的な花です。日本原産のスズランとヨーロッパ原産のドイツスズランがあります。ドイツスズランは、草姿お...
-

-
ツルコケモモの育て方
原産地は北アメリカ、東部で、果樹・庭木・花木として植えられることが多いです。耐寒性は強いですが、耐暑性は弱いです。ツルコ...
-

-
ツルムラサキの育て方
ツルムラサキがどこに自生していたのかというのは、詳しくは分かっていないのですが、熱帯地域が原産だろうと考えられています。...
-

-
デンドロビウム・ファレノプシス(デンファレ)の育て方
デンドロビウム・ファレノプシスとはデンファレとも呼ばれる洋ランの一種です。着生植物の一種で、熱帯地方の木の上が生息地のも...
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...
-

-
ウスベニヒゴスミレの育て方
ウスベニヒゴスミレはガーデニングでも適した植物と言われていて、専門家も性質も強く園芸的にも優れていると太鼓判を押している...
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...
-

-
アルケミラ・モリスの育て方
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケ...
-

-
栽培が簡単な植物の育て方
花も植物も育てたことがない人にとっては、花壇いっぱいの花や植物の栽培はとても難しいもののように思われることでしょう。しか...




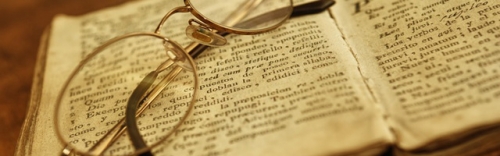





プセウデランテムムは、キツネノマゴ科プセウデランテムム属の植物です。常緑性の植物です。熱帯気候と亜熱帯気候の地域が原産であり、東南アジアや南太平洋地域に生息地が存在しています。