アリウムの育て方

育てる環境について
種類によってその性質は若干違いますが、全体的に耐寒性は非常に強い植物です。そのため、防寒対策を行う必要はありませんが、真冬の凍結などが起こるような場所では球根が持ちあげられる可能性があるので、藁などで凍結を防ぐようにします。
逆に夏の暑さにはあまり強くありませんので、25度以上で乾燥するような状態はあまりよくありません。生育中は乾燥させないように注意が必要です。葉が枯れて休眠状態に入れば水やりは必要ありませんので、乾燥していてもそのままで大丈夫です。
土は酸性の土壌を好みませんので、植え付けを行う数週間前から石灰を土に混ぜ込み、中和させておく方が良いです。種類によって若干の違いはありますが、基本的には日当たりの良い場所を好みますので、生育期には日当たりの良い場所で栽培してあげる方が良いですが、
比較的丈夫な植物ですので、あまり小まめに手入れをしなくてもしっかりと成長してくれます。小球性のものは比較的球根が強いので数年間土に植えたままでも問題ありませんが、大球性の種類は梅雨の雨により、水分を吸収しすぎてしまい枯れるおそれがあるため、掘り起こして乾燥した場所で保管してあげる必要があります。
ギガンチウムは大球性のアリウムですが、比較的腐りにくい球根ですので、それ以外の大球性の種類を栽培する際には注意が必要です。鉢植えの場合は水はけの良い土壌を用意し、6号くらいの大きさの鉢に大球性の球根なら一つ、小球性なら3つ程度が目安です。
種付けや水やり、肥料について
自然界にも自生している植物ですので、育て方はあまり難しくはありません。生育期間は極端な乾燥状態を嫌いますので、土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげます。が夏の休眠状態のときは水分を吸収しすぎないように水を与えなくて大丈夫です。
葉が枯れてきたら休眠に入る合図ですので、枯れた葉を取って放置します。但し、大球性の球根の場合は長期間の雨などで球根から水分を吸収し、腐ってしまう可能性があるため、掘り起こす作業が必要です。肥料は球根を植える前にゆっくりと効果が出る粒状の肥料を土に混ぜ込みます。
その後花を咲かせるまでは液体肥料を定期的に与えます。水はけの良い土壌を好み、酸性の土壌を好みませんので、植付け数週間前に石灰で中和しておきます。土は小粒の赤玉土、腐葉土、川砂を6:2:2の割合で混ぜます。土質によって水はけが悪いようであれば、配合の割合を少し変えても良いです。
植えかえは秋です、気温が少し下がってくる9~10月頃に鉢植えの場合は6号程度のサイズで、小球性の球根であれば3つ、大球性であれば一つ植えます。小球性であれば横の感覚は約15センチほどで、深さは球根の高さ1個分と同じ程度の深さに植えます。ギガンチウムなどの大球性の球根であれば、横幅30センチ感覚程度です。
大球性であれば、球根のうえに土が5センチほどかぶる程度の深さで大丈夫です。庭植えの場合も同じ感覚で問題ありませんが、土壌環境と日当たりは育てる上で重要なポイントになりますので、事前に土の状態と場所をしっかりと考えてから植えます。
増やし方や害虫について
種まき、もしくは分球のどちらかで、増やすことが出来ます。気温が上がってくると葉が枯れて休眠状態になりますので、その6~7月頃に土を掘り起こし、親球の周りに出来ている小球を分けます。小球性の種類は分けやすいのですが、大きいものは分球しにくいため、種まきで増やします。
しかし、9~10月頃に種まきを行うのですが、種まきから開花の時期まで5年~6年程度の期間が必要になります。また、種まきで育てた種類は湿度の高い状態を嫌いますので、湿度には注意が必要です。最悪の場合枯れてしまう恐れもあります。
種まきの場合は長期間の時間が必要になる上、種を再度増やすことが難しいため、園芸初心者には少し難しいかもしれません。害虫は主にアブラムシが発生することがあります。頻繁に手入れを行うのであれば、水を吹きかけるか、タオルなどで拭き取ることも可能ですが、
あまり数が多いようであれば、ホームセンターなどでアブラムシ専用の薬剤を購入し散布してください。春頃に発生することが多い害虫ですが、あまり放置をすると植物そのものに影響を及ぼします。またウイルス性の病気等を媒介することもありので、発見した場合は出来るだけ早期に対処することをおすすめします。
病気はモザイク病やさび病などにかかることもあるようですが比較的病気にはかかり辛い植物ですので、そこまで神経質になる必要はありません。但し、モザイク病などは一度かかってしまうとそこから分けた球根から成長したアリウムは確実にかかりますので、やはりある程度の注意は必要です。
アリウムの歴史
原産地は北アフリカやアメリカ北部、ヨーロッパ、アジアなど世界中です。アリウムは聞きなれない植物かもしれません。しかし、野生では700種類のアリウムがあるとされています。その種類は非常に多いのですが、鑑賞用に育てる種類は比較的少ないと言えます。
食用の種類が非常に多く、タマネギ、ニンニク、ラッキョ、ネギなどもアリウムの一種ですので、普段から頻繁に目にする植物です。北半球だけでも300~400種類存在していると言われますが、正確な数は判明しません。アリウムという名前そのものの定義によって判断が変わるからです。
その名前の由来もラテン語の「におい」や「ニンニク」からきていると言われています。ユリ科の植物で実際に日本でも山や森などに入れば野生種が多く見られますが、これらも古い時代に日本に渡来したものと考えられています。その経路がはっきりしないのもアリウムという種類が非常に多く分類が正確ではないからと言えます。
たとえば、タマネギやニンニクなどは古代エジプロ王朝の時代から労働者に対し配給されていたもので、何千年も昔から存在したと言えますし、ニンニクなどは中国から8世紀ごろに渡来したと考えられています。食用のアリウムは記述の通りニンニクやタマネギが代表の植物ですので、
比較的その歴史は古く、文献も多く存在しますが、鑑賞用のものや、野生種等は正確な伝来経路は把握されていません。裏を返せば、タマネギは日本で、野生種が確認されていないことから、もともと日本にあったものではないということが分かります。イランでは8000年前から栽培されていたという記録がありますので、アリウムそのもの歴史は非常に古いものと言えます。
アリウムの特徴
タマネギやニンニクなどの食用ではなく鑑賞用のアリウムについて記述いたします。一般的な園芸で言われるアリウムは切り花に用いられることが多く、球根から成長する多年草です。花の色は白やピンク、紫、黄色など様々で、その種類によって1メートル程の丈に成長する種類もあります。
生息地は世界中で、園芸用に楽しまれているアリウムも種類が様々で、大きい者から小さいもの、花が目立つものであれば、フラワーアレンジメントのポイントとして利用されることも非常に多い植物です。中でもギガンティウムなどは有名な種類で、比較的大きく成長します。
球根も6センチ~8センチと大型で、約10センチにもなるの大きな球状に咲く花は非常にきれいで、花壇などにも好んで植えられます。逆にネアポリタヌムなどの小さな球根から育つものもあります。大きさはギガンティウム程大きくなく、20~30センチほどまで成長し、白い花を15~20くらい咲かせます。
花が咲くのは4~7月の比較的暖かい季節ですが、非常に耐寒性が強く、9~11月頃の秋に植え、冬の寒さには十分耐えることができます。種類によって秋には芽が出る種類もありますが、比較的夏の暑さにはあまり強い種類ではないため、25度以上の高温な場所や、
乾燥しすぎている状態も成長しません。野生でも平気で自生する植物ですので、園芸で用いるには比較的容易ですし、花自体は鮮やかな色のものが多いので、花壇に植えるのも最適です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アリッサムの育て方
-

-
モミジアオイの育て方
モミジアオイは、ハイビスカスの仲間で、花は、非常に鮮やかな赤色で、花弁も大きく、よく似ています。いかにも夏の花という感じ...
-

-
ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存...
-

-
家庭菜園で甘くておいしいトマトを作る方法
家庭菜園を始める際、どんな野菜を作りたいかと聞けば、トマトと答える人は多いようです。トマトは見た目もかわいく、野菜なのに...
-

-
アルテルナンテラ‘千日小坊’の育て方
園芸店や生花店などでは千日小坊という常緑多年草が売られています。これはペルーやエクアドルといった中米原産の植物です。アル...
-

-
キュウリの育て方のポイント
水分を豊富に含むキュウリは、原産地はインドやヒマラヤであり、そのあたりが生息地と考えられています。栽培されていたのは、さ...
-

-
オリエンタルポピーの育て方
オリエンタルポピーは地中海沿岸からイラン等の西南アジアが原産地のケシ科ケシ属の仲間です。スイスの遺跡から種子が発見されて...
-

-
ディオスコレアの育て方
観葉植物として栽培され、日本でも人気を集めているのがディオスコレアであり、特に普及しているのがディオスコレアエレファンテ...
-

-
ハーブで人気のバジルの育て方
近年、ハーブは私達の生活に身近な植物になってきています。例えば、アロマテラピーなど香りで癒しを生活に取り入れたり、食事に...
-

-
チャービルの育て方
チャービルはロシア南部から西アジアが原産で、特に、コーカサス地方原産のものがローマによってヨーロッパに広く伝えられたと言...
-

-
カミソニアの育て方
カミソニアとは北アメリカの西部を原産とする植物であり、62種類もの品種があります。アカバナ科ですが、開花後に枯れてしまう...




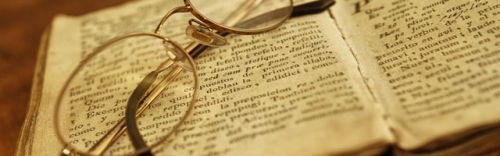





原産地は北アフリカやアメリカ北部、ヨーロッパ、アジアなど世界中です。アリウムは聞きなれない植物かもしれません。しかし、野生では700種類のアリウムがあるとされています。