ディフェンバキアの育て方

育てる環境について
最低気温が13度以上ある場合は屋外で栽培することができます。春から秋頃にかけては半日陰に置いておきますが、真夏は葉が茶色く焼けてしまう葉焼けを起こす可能性がありますので置き場所には気をつける必要があります。秋頃になれば日光を十分にあててあげるほうが株が丈夫になります。
冬はできれば13度以上あるほうが良いですが、どうしても低い場合でも最低10度はある環境に置いてあげることが大切です。室内に置いておく時も日がよくあたる場所が良いです。しかし夜になると窓際は気温がぐんと下がってしまうので夜になったら部屋の真ん中辺りに移動させてあげましょう。
また寒いからといって暖房の風に直接あたってしまうような場所は乾燥してしまい、葉が傷んでしまうので避けます。土は水はけの良いものがいいのですが、冬は室内栽培になりますので、水はけの良さのためによく使われる腐葉土よりはピートモスを使うのがオススメです。
例えば用土の合わせ方として小粒の赤玉土を5、ピートモスを3、バーミキュライトを2の割合であわせるようにするのが良いのではないでしょうか。ピートモスはカビも生えにくいです。植え付けは5月から8月頃まで行うことができます。
根詰まりを防ぐために2年に1度は植え替えをしたほうがいいです。植え替えをする場合も植え付けと同じく5月から8月頃が良いでしょう。植え替えする時は鉢から株を抜き、土を3分の1程度落としてから一回りほど大きな鉢に新しい土を入れて植え替えます。
種付けや水やり、肥料について
水やりは秋頃までは土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげるようにします。空気中の湿度もできれば高いほうが良いです。冬は土の表面の乾きを感じてから3日ほど置いてから水を与えるようにするのが良いです。冬の間は生育が鈍るので水やりも控えめで大丈夫です。
またこまめに葉水をしてあげるようにするとより元気に育ってききます。肥料は秋頃までは与えないと葉が小さく育ってしまいますし、耐寒性がますます低くなってしまいます。ですから月に1度程度でいいので錠剤型の肥料を置き肥として与えるようにしましょう。
またこれと同時に10日に1度は液体肥料を与えるようにもします。花などの場合は種つけをさせて種によって増やしていくことも多いですが、ディフェンバキアのような観葉植物の場合は種付けさせるというよりも挿し木にしたり、とり木にしたりして増やしていきます。
挿し木用に使うものは仕立て直しをした時に切り落としたものを利用するのが良いでしょう。仕立て直しは丈が伸びすぎてしまっていたり下葉が落ちてバランスが悪くなってしまった場合に行ないます。雑菌が切り口から入ってしまうことがありますから、切り口の表面を乾かしておくようにします。
カットした時に切り口から白い液が出てきますが、これがかゆみや痛みの原因になる液なので触らないように気をつけておかなくてはいけません。茎ざしや茎伏せをすることもできますから、茎が余分に余っている時には挑戦してみるといいです。
増やし方や害虫について
害虫は観葉植物なだけにハダニが発生しやすいので気をつけましょう。高温で乾燥するような時期になるとハダニが出やすいです。ハダニは葉などの汁を吸って株の生育を邪魔してしまいます。ハダニを除去するためには湿らせたティッシュなどを使って葉を擦り、ハダニをとってしまいます。
その時は葉を傷つけないようにします。ただしこれは数が少ない場合にできることであって、あまりにひどい場合は薬剤を散布して駆除をする必要があります。増やし方は種まきよりも挿し木やとり木などで増やしていきます。挿し木の場合、葉がついているものであれば鉢植えにそのまま挿すとすぐに楽しむことができます。
葉がついていない場合でも2節から3節分ほどにカットして土に挿しておくことで節部分から小さな芽が出てきて育っていきます。乾燥させないようにするのがポイントで、順調にいけば3週間ほどで発根します。とり木にする場合は2cmほどの幅に皮をぐるりとはいで、
その部分を湿らせた水ゴケで巻いておきます。さらにその上から乾かないようにビニールなどで保護して上下を縛っておきます。3週間ほどしてビニールをはずし、根が出てきているか確認を行ないます。もし根が出てきているようであればその部分の下で
カットして水ゴケなども取り外し、鉢に植え替えます。もし水ゴケがはずれないようであれば無理にはずさないようにしてそのまま植えてしまってもかまいません。これを行なうのは5月から8月頃です。このように育て方は慣れてしまえばそれほど難しくもありません。
ディフェンバキアの歴史
ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウというものがあります。原種は約30種ほど存在しており、常緑性なことから主に観葉植物として人気があります。
英名には口がきけなくなる茎という意味があるダム・ケーンや口がきけなくなる植物という意味があるダム・プラントとなっていますが、これにはディフェンバキアの葉茎から出るシュウ酸カルシウムなどを含んでいる汁が皮膚に触れると痛みやかゆみがでてしまい、
さらに口に入れてしまうと激しい痛みのあまりにしばらく口をきけなくなるという症状が出るということが関係しています。ですから株分けなどして増やそうとする時や茎をカットする時などは汁が手などにつかないように手袋をするなどして工夫をしなくてはいけません。
caneというのは一般的にはサトウキビや竹などの節がある茎のことをいうのですが、ディフェンバキアの場合も葉が落ちてしまうと茎が棒状で節がところどころ見えるからcaneと呼ばれています。学名もそのままDieffenbachia ですが、こちらはドイツの植物学者である
ディッフェンバッハ氏が由来となっています。古くからある観葉植物ですが、株が大きめのタイプと小さめのタイプの2種類があります。主な種はマクラータ種とアモエナ種です。園芸品種のほとんどがこの2つのどちらかを中心にして改良されたものになっています。
ディフェンバキアの特徴
ディフェンバキアは葉が卵型をしており、葉の色は明るい緑から暗緑色をしています。緑一色ではなく、白やクリーム色の斑模様が入っていることが多いです。特徴として葉の軸部分は茎をくるりと囲むようにして出てくるということがあります。
花茎は葉の付け根部分から出てきて花が集まっている肉穂花序というものがつきます。花序と呼ばれる棒っぽいものには上のほうに雄しべ、下のほうに雌しべがついており、仏炎苞というものが花序を包んでいます。その高級な見た目からお祝いごとの時などにも観葉植物として贈られることが多いです。
ディフェンバキアはどちらかといえば花を観賞するよりもその葉の美しさを観賞するものです。どちらかといえば鉢植えで育てるもので、小鉢から中鉢くらいに植えるのがベストです。草丈は30cmから2mほどになるものまであります。育てやすさは5段階でいうところの2くらいなので、
比較的育てやすいといえます。初心者の方も栽培に挑戦してみるのも良いのではないでしょうか。ディフェンバキアに近い仲間には同じサトイモ科のフィロデンドロンやアグラオネマなどがあります。耐暑性はそれなりですが、耐寒性はかなり弱く、冬でも10度以上の気温がなければ枯れてしまいますので、
冬は室内で育てるようにしたほうが良いでしょう。10度以下になるとせっかくの葉の美しい色が失われ、黄色くなっていきます。葉が落ちてもなんとか越冬することもありますが、これが5度以下になってしまうと株そのものが枯れてしまうので注意します。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カラジウムの育て方
タイトル:パキポディウムの育て方
-

-
レシュノルティアの育て方
レシュノルティアは世界中で見ることが出来ますが、生息地であるオーストラリアが原産国です。この植物は世界中に26種類あると...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
バージニアストックの育て方
バージニアストックは、別名マルコミアと呼ばれるアブラナの仲間です。花がストックに似ていることからこのような名前が付けられ...
-

-
ユッカ(Yucca)の育て方
ユッカは丈夫で、育て方もそれほど難しくありません。日当たりを非常に好むため、できるだけ日の当たる場所で栽培します。特にユ...
-

-
アロエの育て方
日本でも薬草として人気のあるアロエはアフリカ大陸南部からマダガスカルが原産地とされており、現在ではアメリカのテキサス州や...
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
ネモフィラの育て方
北アメリカで10数種類以上分布し、花が咲いた後に枯れる一年草です。草丈はあまり高くなることはないのですが、細かく枝分かれ...
-

-
ロータスの育て方
「ロータス」は、北半球の温帯、主に地中海付近の島国を原産として約100種類もの品種が存在するマメ科ミヤコグサ科の多年草で...
-

-
ヤマアジサイの育て方
ヤマアジサイは、アジサイ科、アジサイ属(ハイドランジア属)になります。また、その他の名前は、サワアジサイと幅れたりします...
-

-
ラッセリアの育て方
この花については、オオバコ科、ハナチョウジ属とされています。科としてはゴマノハグサ科に分類されることもあるようです。原産...




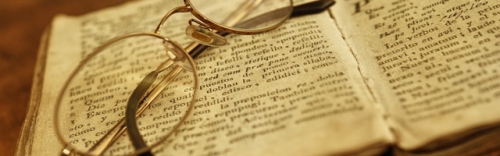





ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウというものがあります。原種は約30種ほど存在しており、常緑性なことから主に観葉植物として人気があります。