マサキの育て方

種付けや水やり、肥料について
栽培は挿し木と種撒きと両方できます。タネまきは秋~冬に熟した果実を採ってすぐに撒くか、乾かさないように貯蔵しておいて春になってから撒きます。一般的には挿し木を行います。梅雨の時期に赤玉土などに適当に挿していると増えます。一般的には庭木にするものなので、基本的に自然雨だけで十分です。
鉢植えの場合は、鉢の土の表面が乾いてきたときに、たっぷりと水を与えるというペースで十分です。肥料はあまり必要としない植物です。与える場合には、二月頃に寒肥として油粕と化成肥料を少々あげれば良いでしょう。生育を早くしたい場合は秋にも同様に肥料をあげます。生長が非常に早いので年に2から3回刈り込みを行って樹形を整えるようにします。
刈り込みは春から秋にかけて適宜行いますが、新しい枝の出はじめる時期と真夏の間は避けるようにします。また花や実を楽しみたいという場合には、花が咲く直前の刈り込みも避けるようにしてください。6月の梅雨の時期には、枝葉が込み合っていると蒸れてしまって、病害虫が発生しやすくなってしまうため、梅雨に入る前に枝を適当に落として風通しをよくしておくと良いでしょう。
木が若いうちは、どんどん勢いよく伸びてしまう間延びした枝部分は、早目に付け根から切り落とすようにします。他は好みの樹形に刈り込んでいけば大丈夫です。樹形の整っている株は、はみ出た部分をバッサリと刈り込んで樹形を整えていきます。刈り込みに強いので、時期さえ間違わなければ多少短く刈り込んでしまっても枯れることはまずありません。
増やし方や害虫について
育て方としては、非常に発根しやすい挿し木がお勧めです。梅雨時に挿し木をすると簡単に増やせます。赤玉土や庭土に挿し木をして日陰で管理すれば、どんどん増やせます。春~梅雨時期にうどんこ病が発生することがあるので要注意です。うどんこ病は糸状菌のカビの一種で、前の年から樹上で冬越しした菌が発生源となって、比較的涼しくなる時節に発生することが多いです。
大体3から4月ごろから発生して広がり、梅雨に最盛期を迎え、夏に少しおさまりますが、秋に再び広がります。この病気の予防策としては、茂りすぎた枝を間引いて、風通しと採光をよくすることが大切です。害虫としては、カイガラムシ類、ユウマダラエダシャク、ツノロウムシ、ルビーロウムシの他、数種類に注意する必要があります。
これらの虫は、いずれも樹液を吸い、木の樹勢を弱らせます。さらに虫の排せつ物が葉や枝に堆積し、黒いすす状のカビを発生させることによって、すす病になることがあります。こうなると見た目だけでなく光合成を妨げてしまいますので、木がだんだんと弱ってきてしまいます。
虫の成虫は体がロウ質で覆われているものも多いため農薬が効きにくいのですが、見つけたら竹べらなど樹皮を傷めないものでかき落とすと良いでしょう。接触毒性の薬剤を散布するのが有効です。ユウマダラエダシャクは黒色のシャクトリムシで、群生して夜に葉を食べてしまいます。食べる量が少ない若齢幼虫のうちに捕殺するか薬剤散布を行うようにします。
マサキの歴史
マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicusで、Euonymusはニシキギ属を意味しており、japonicusが日本のものであるという意味です。またEuonymusはギリシャ語の「良い評判」というのが語源となっています。漢字では、柾や正木と記されます。
別名、オオバマサキ、ナガバマサキ、コバマサキ、ボウシュウマサキ、ヤクシママサキと呼ばれています。大きいものでは5メートルほどに成長する低木で、常緑で斑入りの品種がよく流通しており、庭木として植えられています。花は6月前後に咲き、冬に綺麗な赤い実をつけます。
大気汚染にも強く、剪定にも強く管理が楽で、密生することから、生け垣や庭木としてもよく用いられています。主に葉や樹形を楽しむ庭木です。耐陰性が強く、海岸近くの林などにも多く自生しています。日本における名前の由来はハッキリとはしていませんが、常緑なので真青木から転訛して「マサキ」となったという説があります。
古い時代から身近な常緑樹であったようで「古事記」の中に、すでにその名が記されています。また江戸時代の本草書「本草綱目啓蒙」にその名が現れています。俳句では「柾の実」が秋の季語となっています。葉っぱが金色に輝く黄金柾,金正木などを始めとして、斑入り黄覆輪柾をはじめ、葉っぱのふちや中央部に斑が入るものなど、多くの品種が作り出されています。
マサキの特徴
正木の樹高は1から5メートル程度まで成長します。若い茎は円く、緑色です。葉は、短い葉柄をもって対生しています。葉身の部分は倒卵円形から楕円形となっており、長さは3から8センチ、幅は2から4センチ程度です。葉は厚く革質で、強い光沢があります。葉先部分は鋭頭になっており、その基部は円形からくさび形、縁には低い鋸歯があります。
品種によっては斑入りのものもあります。黄緑色で小さい花が目立たないようにひっそりと咲きます。花が咲くのは、大体6月から7月にかけて、その年の枝の上部分の葉腋から、集散花序を付けます。秋になって果実が熟すと、3から4つに裂けてオレンジ色の仮種皮におおわれた種子が出てきます。種子も含めて食用にはできません。
また日照不足や乾燥、塩害、煙害、刈り込みに強いことが特徴で、生垣や街路樹などに用いられることが多いです。上手に管理・剪定された生垣は遮蔽効果、美観の点でも優れていると言えるでしょう。強い剪定に耐えるので、庭の縁取りのような低い生け垣から、境界になるような高めの生け垣、あるいは球形に刈り込んで玉物仕立てにしたり、
変わったところでは串にダンゴが刺さっているように見える2段の球形仕立てなどにも出来たりします。もちろん枝を切る作業を最小限に留めておいて、自然に近い樹形でも楽しむことが可能です。マサキの葉を餌とする昆虫としては、蜂によく似たガの一種であるミノウスバがよく見られます。成長した葉も集団で蚕食するので、部分的に葉が食い尽くされて食害箇所が目立つことがあります。
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...
-

-
カマッシアの育て方
カマッシアの原産は北アメリカ合衆国の北西部です。生息地も北アメリカ合衆国を中心に6種類が分布されています。カマッシア・ラ...
-

-
シャンツァイの育て方
シャンツァイはコリアンダーと言うセリ科の一年草で、中華料理などで利用される野菜です。コリアンダーと言うのが学名であり、シ...
-

-
オシロイバナの育て方
日本に入ってきたのは江戸時代に鑑賞用として輸入されたと言われており、当時この花の黒く堅い実を潰すと、白い粉が出てきます。...
-

-
ポーチュラカの育て方
ポーチュラカの原産地はメキシコや南アメリカといわれています。日本には1980年代にドイツから入ってきたとされています。高...
-

-
おいしいトマトを作りましょう
トマトにはさまざまな種類があります。大きなトマトからプチトマトまで、収穫のサイズも種類によって変わってきます。以前は病気...
-

-
イヌタデの育て方
イヌタデの特徴としては、タデ科の植物であり色のついた花がゆらゆらと揺れているのが特徴の一つとして挙げられるでしょう。上記...
-

-
マルバタケブキの育て方
マルバタケブキはキク科メタカラコウ属の植物です。原産が日本です。漢字による表記は、丸葉岳蕗です。生息地は日本と中国に分布...
-

-
サラセニアの育て方
サラセニアは北アメリカ大陸原産の食虫植物です。葉が筒のような形に伸びており、その中へ虫を落として食べることで有名です。生...
-

-
セリの育て方
特徴としては種類がどのようになっているかです。キキョウ類、セリ目となっています。別名としてシロネグサとの名前がついていま...




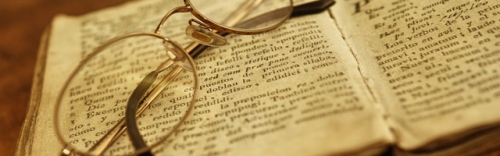





マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicusで、Euonymusはニシキギ属を意味しており、japonicusが日本のものであるという意味です。別名、オオバマサキ、ナガバマサキ、コバマサキ、ボウシュウマサキ、ヤクシママサキと呼ばれています。