クロガネモチの育て方

育てる環境について
クロガネモチは育て方が比較的簡単で、生息地が日本の風土に合っていますので、育てる環境に関してはそれほど心配することはありません。鉢植えでも庭植えでも育てることができますが、寒さにはやや弱いため、特に寒冷地では北風の強いところや頻繁に凍結するようなところは避けたほうがよいでしょう。
直射日光にも強いため、日当たりのよいところに植えると色合いのコントラストもはっきりしますし、樹木自体もすくすくと成長します。ただ、日陰でも多少のことであればきちんと成長します。育てるときの心配はそれほどありませんが、年数がたつと丼損生長して、
幹が太くなったり根が広い範囲に張ります。そのため、庭植えをするときには、建物の基礎や塀の基礎が傷つく恐れがありますので、少し距離をとって植えるようにしたほうがよいでしょう。用土は水はけがよく、有機質の多い土のほうがよく成長します。
配合するときには、中粒の赤土2に対して完熟腐葉土や樹皮堆肥を1の割合で混ぜたものなどを使用するとよいでしょう。放置しておくとどんどん成長しますので、徒長枝やバランスの悪くなった枝はもとから切り落としましょう。古い枝を間引くことで、
形を整えながら実をたくさん実らせることも可能です。剪定しすぎたからと言って成長に影響があることはほとんどありません。むしろ、葉が茂りすぎると日光が届かないこともありますし、重みで枝が折れることもありますのでこまめに剪定しましょう。
種付けや水やり、肥料について
種まきは成長するまでに時間がかかりますのであまり行いませんが、鳥が運んでくることもあるように、実ができてからすぐにまくと芽を出すようになります。基本的には株を植えつけることになりますが、庭植え、鉢植えのいずれでも、5~6月の暖かくなり始めた時期が適しています。
ただ、冬以外であれば大体どの時期に植えても枯れる心配はありません。やせた土地でも育ちますが、どちらかといえば肥沃な土地を好みますので、堆肥を混ぜておいたり培養土を使用するとよいでしょう。肥料は植え穴や鉢土の底に、有機質肥料か緩効性化成肥料を元肥として入れておきます。
移植のために株を掘り上げるときには、この根鉢を大きめにつけることで移植後も育ちやすくなります。水やりは、鉢植え、庭植え共に、植え付けてから2年の間は土の表面が乾いたときにたっぷりと与えるようにしましょう。庭植えの場合には、2年以上経過したら
自然の雨で十分育ちますが、例年よりも雨が少ないときには、土がひどく乾燥する前にたっぷり与えましょう。やや湿潤な環境のほうが育ちやすいため、あまり乾燥すると春の落葉時期以外に葉が落ち始めます。この時にはしっかり水やりをしましょう。
肥料は、2月にリン酸やカリを含んだ化成肥料を与えましょう。クロガネモチは、窒素分を控えることで花つきや実つきがよくなります。鉢植えの場合には、3月にリン酸の含有率が高い化成肥料を株元に追肥するのもよいでしょう。
増やし方や害虫について
クロガネモチは比較的増やしやすい品種ですので、種まきでも接ぎ木でも株を増やすことができます。種まきを自力で行う時には、11~12月に赤く熟した果実から種を取出し、流水で果肉を洗い流します。その後、乾燥させないように湿らせた砂と混ぜてビニール袋などで密封し、冷蔵庫で保存します。
翌年の3~4月に再度種を水でよく洗い、まきます。種まきでは、雄株と雌株ができますので、3~4年も成長すれば接ぎ木をするときに台木として使えます。発芽した苗は鉢上げして育て、将来的に接ぎ木をするときに使用しましょう。接ぎ木は、3月下旬から4月上旬に、
上記で育てた雄株から穂木をとって行います。台木は株元から5~10cmに切り詰め、穂木は雌株の、前年枝から2芽以上つけた5~8cmのものを用意し、切リつぎします。ついだ部分はつぎ木テープを下から巻き上げて固定し、鉢ごとにビニールなどに入れて密閉し、乾燥を防ぎます。
慣れてくればそれほど困難な作業ではありませんが、手早くやることで成長しやすくなります。クロガネモチを栽培するうえで、病気では特に気にするものはありませんが、害虫ではツノロウムシなどが発生します。これはカイガラムシの仲間で、成虫は白く厚いロウ質に包まれています。
そのため、農薬が効きにくくなっている反面、移動はできません。見つけた時には樹皮を傷めないように、竹べらなどで掻き落としましょう。この虫は樹液を吸い、排泄物が葉や枝に堆積していきますので、大発生すると木の成長が弱まり、
やがて黒いすす状のカビが発生し、すす病となります。6月ごろに幼虫が発生し、成虫になるまでの間は移動しますが、この時期はロウ質に覆われていませんので薬剤散布も有効です。
クロガネモチの歴史
クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生していたとも、朝鮮などから持ち込まれたとも言われています。この木は中国では樹皮や根の皮などを、止血や鎮痛、風邪、扁桃腺炎などの治療に用いていたため、
大切に育てられていました。また、樹皮は染料にもなりますし、とりもちも作ることができるため、日本でもとりもちを多用していた時期にはこの木から採取していました。一方で、西洋ではクリスマスリースに使用する柊の系列として扱われており、クロガネホーリーと呼ばれています。
日本や中国でも縁起の良い樹木として庭木などに使用されていることがありますが、これは名前が金持ちに通じるところからきています。移植することもそれほど困難ではないため、盆栽として育てている家庭もありますし、野鳥が種を運んで庭などに生えることもあります。
また、排気ガスに強いことから、都内の公園樹や街路樹として用いられることもあります。丈夫なため昔は農機具として使用されたこともあり、日本人の生活に店切に関わりを持っていました。なお、この名前の由来は、葉柄と新しい枝が紫黒色を帯びること、
葉が乾くと黒鉄色になるモチノキであるということなどからつけられているといわれています。ライターなどで葉をあぶった時にも黒っぽい色に変色するなど、他の植物とは若干異なる特徴を持っている樹木でもあります。
クロガネモチの特徴
クロガネモチの特徴は、秋から冬にかけてつける小さな赤い実です。この時期には開花する花が少ない中で、濃い緑色と鮮やかな赤い実のコントラストがとてもきれいで、庭に彩りを与えます。また、常緑樹ですので実のつかない時期でも灰白色の木肌と濃い緑の色合い、
紫色を帯びる葉柄などが鑑賞に向いており、好まれています。雌雄異株ですので実を鑑賞したいときには雌株が必要ですが、育てるときに種まきではなく、雄株に雌株の枝をついでいるものがほとんどですので、増やすときには気を付けましょう。
ちなみに、雄株でも花は咲かせますが、実がつきません。花は淡い紫の小さいもので、開花後に実ができます。高さは10~20mまで成長することもあります。葉は互い違いにつき、革のような質感で厚みもあり、楕円形で様々なサイズになります。刃先は鋭く、縁はギザギザのない形です。
小枝や葉柄は紫色を帯びており、色合いのコントラストが特徴的です。樹皮は灰白色で滑らかさがあり、皮目がついています。育て方が簡単で、都市の排気ガスなどが多い環境でも生育できる強さがありますが、逆に鳥が実を食べたことによって、植えていないところから発芽することもあります。
ただし、クロガネモチは種からある程度大きい樹木まで成長するには10年近くかかりますので、大体はまだ小さいうちに種が飛んだことに気がつきますので、大きな力を入れなくても抜くことができ、庭木のバランスを保っています
-

-
エイザンスミレの育て方
エイザンスミレは多年草のスミレの仲間ですがこのスミレ属は広く世界中で愛されている花です。エイザンとは比叡山を指し、この比...
-

-
アイスランドポピーの育て方
ポピーというケシ科はなんと26属250種も分布しており、ケシ科ケシ属でも60種の仲間が存在します。ケシ科は麻薬成分モルヒ...
-

-
サラセニアの育て方
サラセニアは北アメリカ大陸原産の食虫植物です。葉が筒のような形に伸びており、その中へ虫を落として食べることで有名です。生...
-

-
ベルフラワーの育て方
ベルフラワーはカンパニュラの仲間で、カンパニュラはラテン語の釣鐘を意味する言葉から由来しており、薄紫色のベル状のかれんな...
-

-
ダイコンの育て方
大根は冬になると鍋料理の具材やおろしなどをして食べたり、収穫後に干してたくわんなどの漬物にするなど色々な調理方法が在りま...
-

-
カタセタムの育て方
カタセタムの科名は、ラン科、属名は、カタセタム属になります。その他の名称は、クロウェシアと呼ばれることもあります。カタセ...
-

-
葉ネギの育て方
ネギの原産地はアジアの北部だとされています。元々の生息地はこのあたりで、中国の西部、あるいはシベリアあたりのものが栽培さ...
-

-
ミラクルフルーツの育て方
小さな赤い果実のミラクルフルーツは、あまり甘くなく、食した後、しばらくは、酸味のあるものを食べると、甘く感じ、とてもおい...
-

-
園芸初心者でもできる枝豆の育て方
枝豆の育て方のポイントは以下のようになります。枝豆の生育適温は25~28度で、高温には強いですが、低温と霜には弱いので、...
-

-
アエオニウムの育て方
アエオニウムはアフリカ大陸の北西の北アフリカに位置するカナリー諸島原産の植物です。生息地は亜熱帯を中心に多くく見られる植...




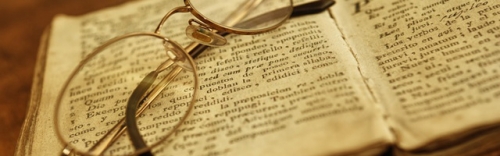





クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生していたとも、朝鮮などから持ち込まれたとも言われています。