コノフィツムの育て方

育てる環境について
ハマミズナ科(メセンの仲間)の中でも、コノフィツムは「冬育成型」の植物として扱います。小型の植物なので、庭植えには向きません。多少の霜であればあたっても問題ありませんが、株が傷んでしまうこともあるので、できるだけ冬は室内に取り込むか、もしくは防寒対策を行います。
コノフィツムの品種はいろいろありますが、どの品種も色を明るく育てるためには明るい光を必要とします。理想の生育温度は、8〜25℃です。冬であれば、暖房で室内気温が35℃まで上がっても耐えることが出来ます。気温が上がり、休眠に入る梅雨明け〜夏にかけて、風通しの良い日陰に移動させます。
この時には水やりは控えて、休眠させます。確実に休眠させるならば、全く水を与えずに断水したほうが良いです。水を与えてしまうと、根腐れを引き起こす原因になります。休眠期の扱いについてです。コノフィツムは乾燥にも耐えられるように進化していますが、
あまりにも乾燥させすぎると太い根まで死んでしまったり、茎が枯れる原因になります。すると生長期に入ってもスムーズに生長をスタートすることが出来なくなります。これを防ぐためには、月に2回ほど軽く潅水(水を注ぐ)します。
培養土が少し湿り気を帯びるくらいで良いです。与えすぎるとかえって腐る原因になるので気をつけましょう。用土にはできるだけ水はけの良いものを用います。小粒鹿沼土:小粒赤玉土:ピートモス:川砂:くん炭=2:2:2:2:2の割合で配合してあげると良いです。
種付けや水やり、肥料について
種まきは花後の種を採取して10〜11月にまきます。植え替えについては、他の多肉植物よりは頻繁な作業は必要ありません。ただし、株の生育が良くない時や、株が群生して鉢に対して大きすぎると感じた場合には植え替えるようにします。
植え替え可能な時期は10〜12月ですが、最適な時期は生育期の最初の10〜11月です。株分けする場合には根が出てくるまでに時間がかかるので、早めに済ませておくのがおすすめです。水やりについては、6〜9月頃の夏の休眠期には、基本的には完全に断水させるようにします。
ただし一部の園芸情報では、あまりに乾燥させ過ぎると生長に影響するという報告もあるので、月に1〜2回は潅水させるようにします。ほとんど乾燥気味で夏越しさせるのがポイントです。秋になって最低気温が20℃を下回る頃になると、新芽が動き始めます。
この時期になったら、徐々に水を与えるようにします。いきなりたっぷりあげずに、徐々に水やりの量を増やしていったほうが良いです。その後本格的に生育期に入ったら、たっぷりと水を与えるようにします。そして春になって表皮が黄色くなって休眠期に向かう頃には再び水の量を減らしていきます。
肥料はどうしても必要というわけではありませんが、与えるならば秋〜春にかけての生育期に緩行性化成肥料か、もしくは液体肥料を少量施すと良いです。休眠期に肥料を与えても意味がありませんし、場合によっては腐る原因にもなるので止めましょう。
増やし方や害虫について
種まきか株分けで増やすことが可能です。種で増やす場合には、花後についた果実が枯れたら、種を採取して保存しておきます。まき時は10〜11月です。交配種から採れた種だと、親とはまた違った色の花が咲くことがあるので楽しめます。
株分けで増やすならば、群生している株を選んで、10〜12月の植え替え時に株分けをすると良いです。群生している株を分けることで、もとの株を元気に生長させることにもつながります。つきやすい害虫には、カイガラムシ、アブラムシ、ネジラミ(サボテンネコナカイガラムシ)、
ナメクジ、などがいます。カイガラムシやアブラムシは蕾や花、ネジラミは根の部分に発生しやすいです。ネジラミは小さな小判形の虫で、重篤な被害は引き起こさないものの、増えることがあるのでオルトランを培養土に混入させて駆除します。ナメクジは開花期に花弁や蕾につくことがあります。
捕殺するか、駆除スプレーで駆除するようにします。コノフィツムの育て方で一番苦労するのは、球体が腐ってしまうことです。原因となるのは、細菌やカビによるものですが、発病のメカニズムはよくわかっていません。品種によっても腐りやすいものとそうでないものがあります。
腐敗が起こりやすいのは、春〜梅雨の時期です。また、休眠期に表皮で覆われた状態で中身が腐敗することもあります。腐敗を防ぐには、生育期間中にしっかり生長させて新球の形成をしっかりしておく、休眠期は水をほとんど与えないで管理する、などに気をつけることが大切です。
コノフィツムの歴史
コノフィツムは、アフリカ南部(南アフリカ・ナミビア南部)が原産の生息地の多肉植物です。日本に入ってきたのは大正末期〜昭和初期の頃で、1931年(昭和10年)には業者のカタログや雑誌などにも名前が登場していました。1935〜1940年(昭和10〜15年)頃が戦前の輸入の最盛期で、
この頃には約80種類余りが栽培されていた記録があります。戦争により輸入が一時中断されましたが、その後1955年頃になって戦争を生き残った品種が出回り始めました。さらに1960年になると再び輸入が再開され、徐々に交配された品種などが作られていきます。
1970年の頃までには約300種類近くが株や種子の形で輸入され、愛好家を増やしています。コノフィツムは多肉植物で、丸く、ユニークな形が最近では人気を集めています。多肉植物は最近になってブームがきている植物で、室内での観賞用などによく用いられます。
もともとは日本の花壇などでよく見られるマツバギクの近縁種で、植物学上はハマミズナ科に属します。かつてはツルナ科、ザクロソウ科、メセンブリアンテマ科、などと呼ばれていた時代もありました。ハマミズナ科の植物は一般的に葉が多肉化するという特徴があり、
これにより水分の蒸発を抑え、乾燥に耐えられるようになっています。コノフィツムは一対の葉が著しく多肉科するのが特徴で、ほとんど球状になっています。愛好家の間では、葉は「対」ではなく「頭」という単位で数えられています。
コノフィツムの特徴
ハマミズナ科コノフィツム属に分類されている多肉植物です。葉の見た目が特徴的で、一芽一芽が単幹の葉から成り立っています。複数の芽が集まり、クッションのようになります。ハマミズナ科の植物は、全体的に「メセン(女仙)類」や「メセンの仲間」と呼ばれています。
約120種類以上の属、2000種類近くの原種が含まれています。栽培方法で「冬育成型」と「夏育成型」に大きく分け、このうちの「冬育成型」がコノフィツムにあたります。コノフィツムはメセン科の特徴として、脱皮をするというユニークな特徴も持っています。
年に1回休眠に入る前に外側にある古い葉が枯れ、それがそのまま保護層になります。そして、生育期の秋になるとその中から新しい芽が、まるで脱皮をするような形で出てきます。園芸用には、主に秋に小さめの鉢物で出回ります。花色は赤紫、オレンジ、白、など様々な種類があり、
これらはほとんどが日本で作られたものです。また、巻き花、縮れ花、などの変わり咲き種もあります。株の形状も様々で、足袋型、鞍型、丸形、に分けられています。葉の色は緑が多く、他にクリーム色、褐色、などもあります。株分けで増やすことが可能なので、
いろいろな品種を収穫できるというお得感がある植物です。耐寒性、耐暑性は品種によって違うので一概には言えません。ただし、だいたいの品種が耐寒性は普通〜やや弱い、耐暑性はやや弱い〜弱い、という性質を持っています。
-

-
ナツハゼの育て方
ナツハゼはジャパニーズブルーベリーや山の黒真珠と呼ばれており、原産や生息地は東アジアです。日本はもちろん朝鮮半島や中国な...
-

-
オキナワスズメウリの育て方
この植物は被子植物に該当します。バラ類、真正バラ類のウリ目、ウリ科になります。注意しないといけないのはスズメウリ属ではな...
-

-
パボニアの育て方
パボニアはブラジルが原産の植物で、赤い苞が鮮やかな低木の熱帯植物になります。尚、この植物はアオイ科、 ヤノネボンテンカ属...
-

-
家庭菜園の栽培、野菜の育て方、野菜の種まき
家庭菜園ではプチトマトやゴーヤなど育てやすい野菜を育てるのが人気です。ですが、冬野菜でもある大根の栽培でも、手軽にするこ...
-

-
コトネアスターの育て方
コトネアスターはほとんどがインド北部またはチベットを原産としています。生息地はこれらの国に加えて中国まで広がっています。...
-

-
オステオスペルマムの育て方
オステオスペルマムは南アフリカを生息地としているキク科の草花です。従来は「ディモルホセカ」の仲間に入っていたのですが、形...
-

-
ホリホックの育て方
この花については、アオイ木、アオイ科、ビロードアオイ属になります。見た目からも一般的な葵の花と非常に似ているのがわかりま...
-

-
ブラサボラの育て方
ブラサボラはカトレアに近い仲間でカトレア属やレリア属などの交配にも使われる植物で原産地は中央アメリカやカリブ海沿岸、南ア...
-

-
フクジュソウの育て方
雪に覆われたり、冬の間は殺風景な庭に、どんな花よりも早く顔を出して春の訪れを知らせてくれる、それがフクジュソウです。フク...
-

-
ボケの育て方
ボケはもともと中国原産の落葉低木です。梅と比べてもかなり木の丈が低く、コンパクトな印象で春の花木として人気があります。 ...




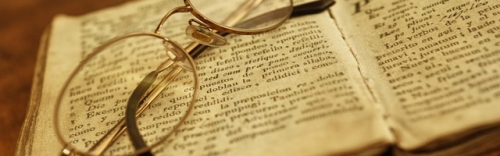





コノフィツムは、アフリカ南部(南アフリカ・ナミビア南部)が原産の生息地の多肉植物です。また、ハマミズナ科コノフィツム属に分類されています。