オオアラセイトウの育て方

育てる環境について
オオアラセイトウは日当たりがよく、水はけもよく、肥沃な土地を好みますので、育て方もそうした環境に注意して植え付けることが必要です。もともと野生のこの花が咲いている環境を見てみると、斜面になった線路脇、畑の小道、田んぼのあぜ道など、大変日当たりがよく、水はけがいいところだということがわかります。庭植えする場合でも日当たりと水はけを確保して植え付けるようにしましょう。
その際には水はけをよくするために、赤玉土と腐葉土を混ぜ合わせたものを使います。肥沃な土地を好むので牛糞や化学肥料などを鋤込んだものが最適です。日当たりは一日中日が当たらなくても、午前中の日光が当たる東向きの敷地などでも十分育てることができます。また朝日が当たらなくても西日が当たる環境でも育てることができます。
ただし全く日が当たらないような暗い環境では茎が徒長してしまい花付きが悪くなってしまうことがありますので注意が必要です。全く日が当たらなくても、北向きの明るい日陰であればオオアラセイトウは育てることができます。またこの植物は日本では一年草として扱われますが、
環境が合えば熟した種が飛び散り、毎年同じ場所に紫色の可愛い花を咲かせることができます。草丈が30セントメートルから60センチメートルとかなり高めなので、ボーダーガーデンの後ろの方の植物として育てることもできます。基本的に強健なので初心者でも育てやすい植物と言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
オオアラセイトウの栽培で注意することは水やりです。特に水はけが良い土地を好むので、水はけのよい土壌を作って植え付けるのが育て方の基本ですが、その分水切れもおこしやすくなってしまうので注意が必要です。暑さに弱く特に夏の高温多湿や直射日光でダメージを起こしてしまう上に、水切れしやすく、葉がチリチリになってしまうことがありますので水切れを起こさないように頻繁に水やりをする必要があります。
特に花が咲く前の3月から4月にかけては十分な水やりをすることで丈夫に花を咲かせることができますので、一日1回は水やりをしましょう。密集させて植え付けて群生を楽しむような育て方をするので、たっぷりと水をやらないと水を奪い合って枯れてしまいます。鉢栽培をする場合はさらに水切れに対する注意が必要です。
水やりをするときは鉢底から水が染み出るのを確認してたっぷりやるようにすると、根が鉢全体に回って丈夫な株にすることができます。また肥料に関しても欲しがる植物です。植え付けの際に緩行性のつぶ状肥料を混ぜ込んでやると丈夫に育ちます。または牛糞などを植え付けのさいに鋤込みましょう。
また、花の前には液肥を希釈したものを水やり替わりに与えることで花つきが良くなります。その際には窒素分が少なくリン酸やカリウムが多い液肥を選ぶようにしましょう。花の色を美しく保ちます。このようにオオアラセイトウは水や肥料を好む植物ですので、適宜施肥や水やりをしましょう。
増やし方や害虫について
オオアラセイトウの増やし方は種まきです。もともと年越しをする植物でしたが、日本では夏の高温多湿を乗り越えることができずに一年草として扱われるケースが多いので、種まきをして株を絶やさないようにするのが良いでしょう。種は実が熟した8月から9月に取れますので、サヤごと保管して次の年の2月頃に撒きます。
この種は環境さえ合えば、自然に熟した種が飛び散って撒き散らされるので、庭に絶えず紫色の花を咲かせ続けることもできます。基本的に強健な植物ですので、環境さえ合えば自然に育ち増えていくことができます。鉢栽培の場合には種が熟してきたら茶こしなどの紙パックを取り付け、十分熟してから採取できるように工夫しましょう。
採取した種は保存して2月ころにバーミキュライトか赤玉土のような清潔な土に植え付けましょう。春になると芽が出てみるみる間に草丈30センチメートルまで育ち、紫の美しい小花を房状に咲かせることができます。オオアラセイトウにつく害虫にはアブラムシがあります。小さなアブラムシは殺虫剤をスプレーすることで駆除することができますが、
テントウムシなどの天敵が来るようでしたら、あまり気にせずにそのまま育てても良いでしょう。ヨトウムシなどは一晩でオオアラセイトウの葉や花を食い荒らしてしまうので、見つけ次第捕殺しましょう。ヨトウムシは夕方から夜にかけて出てくるので、食害されたらそのタイミングで探してみるのが効率的です。
オオアラセイトウの歴史
オオアラセイトウは別名ショカツサイとも言われる中国原産のアブラナ科の植物です。紫色が美しい小花はその昔三国志で有名な軍師、諸葛亮孔明が広めたという伝説があり、それからショカツサイという名前がつけられました。戦に明け暮れて食料が乏しい中国の戦国時代にこの花が広められた歴史の理由は、この植物の若い葉が食用として利用できたからと言われています。
葉は野菜と同じように食べることができ、おひたしや炒め物として貴重な食料になっています。また、アブラナ科の植物ならではの特徴として、その種を絞って油を取ることもできるため、大変有効活用された歴史があります。中国の全土に栽培され広まっていたこの植物は江戸時代に日本に持ち込まれました。
もともと花の美しさというよりも葉を食料にする目的や種から油をとる目的で持ち込まれたこのオオアラセイトウは、日本の風土にもしっかりと馴染み、今では日本全土に野生化して自生しているのが見られます。日本では紫金草という美しい名前で呼ばれることもありました。
幼虫がこの植物を好んで食べるスジグロシロチョウという蝶が多く見られるようになったなど日本の生態系にも影響を与えるほど一般的な植物となりました。群集して咲いている姿は紫の霞がかかったようで大変美しく庭に好んで植える方もいますが、道端や田んぼのあぜ道、川原などにも多く見られる野草といった植物にもなっています。今では日本の春を彩る植物の一つです。
オオアラセイトウの特徴
オオアラセイトウは中国原産で中国全土を生息地としているアブラナ科の植物です。自然開花の時期は春のさかりの4月から5月、群生して美しく咲くと紫の花が霞が買って見えるような美しい花です。知恵の泉という花言葉を持つこの花は紫の色以外は菜の花によく似ているので菜の花の紫版と誤解される方もいますが、全く別の品種になります。
江戸時代に日本に持ち込まれたものが全国に野生化して広がっています。草丈は30センチから50センチほどで本来は越年する多年草ですが、日本では質道や高温といった環境から一年草として扱われることもあります。畑の周りや緑道などに咲いていて野生化しています。直立して茎が枝分かれして先に房状の花をつけます。
花は3センチ前後でやや大きく、紫色の4枚の花弁が十字の形に開きます。地面際の葉は羽状に深く切込が入り、茎葉は6センチメートルほどです。果実は先端に細長い突起をつくりその中に黒褐色の実を付けます。実が熟すと種が弾け飛び周囲に撒かれます。花が美しく花持ちも良いのでしばしば切花としても利用されています。
今ではほとんど食用とされることはなくなりましたが戦後の食料の少ない時期には、新芽や若い葉が食用として用いられました。またその熟した種からは油がとれたということもあり、江戸時代から盛んに栽培されてきたものが現在では日本全土を生息地とする野生種のようになっています。育てやすく花が美しいのが魅力です。
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
オキナグサの育て方
オキナグサはキンポウゲ科に属する多年草です。日本での歴史は、万葉集の随筆から江戸時代中期後期にかけて書かれた書物の中にも...
-

-
アルテルナンテラ‘千日小坊’の育て方
園芸店や生花店などでは千日小坊という常緑多年草が売られています。これはペルーやエクアドルといった中米原産の植物です。アル...
-

-
パパイヤの育て方
パパイヤはメキシコ南部から西インド諸島などが原産と言われており、日本国内においても熱帯地方が主な生息地になっており、南国...
-

-
ドクゼリの育て方
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
ペンツィアの育て方
特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次...
-

-
レモンの育て方
レモンの原産地や生息地はインドのヒマラヤ地方とされ、先祖とされている果物は中国の南部やインダス文明周辺が起源です。そして...
-

-
ツルニチニチソウの育て方
夾竹桃(きょうちくとう)科に属しているツルニチニチソウは、学名を「Vinca major」「Vinca」といい、ツルニチ...




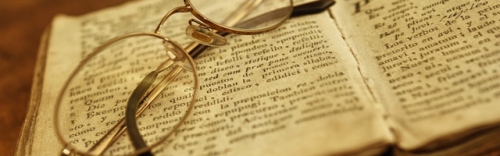





オオアラセイトウは別名ショカツサイとも言われる中国原産のアブラナ科の植物です。紫色が美しい小花はその昔三国志で有名な軍師、諸葛亮孔明が広めたという伝説があり、それからショカツサイという名前がつけられました。戦に明け暮れて食料が乏しい中国の戦国時代にこの花が広められた歴史の理由は、この植物の若い葉が食用として利用できたからと言われています。