センペルビウムの育て方

育てる環境について
育てる環境は春秋生育型の多肉植物ということを考えて栽培を行う必要があり、3月から6月頃までと9月から11月くらいの期間に生育をするので、この期間に肥料や水分をしっかりと与えて生育することが必要になります。この品種は全般的に寒さには強いのでたとえ霜が降ったとしても
根の部分が傷むことがありません。しかし高温多湿に弱い性質なので梅雨から夏にかけては風通しの良い場所でわずかに日が当たる程度の日陰で育てる必要があります。真夏の気温には弱いのでそれ以外の時期は戸外の日当たりの良い場所で管理をして、
雨などが当たっても枯れることがありません。秋の終わりにかけては紅葉し始めて、春を迎えて暖かい気候になってくると生育期の美しい発色が戻ってきます。庭植えにする場合には夏の暑い時期の高温多湿の状態に耐えることができるように水はけが良くて、
ある程度の日陰になる場所を選ぶ必要があります。しかしセンペルビウムは基本的には強い品種なのである程度の陽の光や湿度では傷んだりすることがありません。鉢植えにする場合には鹿沼土や赤玉土、ビートモス、川砂、くん炭などを配合した土を使うと株が元気に育ちます。
植え替えは2年から3年に1回程度行う必要があり、生育期ならば何月に行っても大丈夫です。一番良いとされる時期は生育期の直前か初期の状態で、株分けや挿し木によって、増やすことができるので、環境によって株分けと挿し木を選ぶことができます。
種付けや水やり、肥料について
水やりは春と秋の生育期には用土の表面が乾燥したら十分に与える必要があります。用土が乾燥していないのにもかかわらず水を与えてしまうと、土がずっと湿度を保持してしまうので、根の部分が傷んでしまう可能性があります。センペルビウムは非常に強い品種なのですが、
根の部分が衰えてしまうと美しい色が出なくなるので、観賞用の植物として見栄えが非常に悪くなってしまいます。また梅雨明けから夏の暑い時期は休眠期なので、この時期に水分を与えすぎると用土の湿度が高いままになるので、細菌によって根腐れを起こしてしまいます。
根腐れが起きるとその部分を切除する必要があるのですが、気が付かないで放置しておくと全体が枯れてしまうことがあります。冬の休眠期には空気が乾燥している状態なので戸外で栽培をしていても十分に生育していきます。肥料については春と秋の生育期に緩効性化成肥料を与えたり、
液体肥料を少量施します。それ以外の時期は休眠期なので肥料を与えないようにする必要があります。センペルビウムという植物は花茎の整理をする必要があり、春頃から花茎がどんどん伸びてしまうのですが、花を咲かせたものは枯れていくので、
花が咲く前に整理をして、子株の生育ができる環境を整えておく必要があります。この植物は美しい葉の色を観賞するものなので、花をつけて生育状態が悪くなると葉が変色してしまうので、花茎を整理することが非常に重要な作業になります。
増やし方や害虫について
増やし方は株分けの場合には群生しているものならば植え替えをするときに株分けをするだけなので、難易度が非常に低くなります。挿し芽をする方法としては伸びているランナーの先にできている子株を剪定して、切った芽で挿し木をすると根が生えてきて、
鉢植えができるようになります。種まきをすることもできるのですが、品種によってはできない場合もあります。原種を栽培している場合には種まきで増やすことができるとされています。非常に強い植物なので問題となるような病気はほとんどないとされているのですが、
害虫に関しては様々なものがあり、カイガラムシやアブラムシ、ネジラミなどが多いとされています。葉や茎に寄生してしまうカイガラムシやアブラムシは養分を吸い取ってしまうので、全体的に体力を衰えさせてしまいます。大量に発生した場合には効果を長期間維持することができる薬剤を使ったり、
歯ブラシなどで物理的に除去する方法があります。ネジラミはサボテンなどの多肉植物に特有の害虫で、培養土の中の根の周辺に白い楕円形の袋を作ることで繁殖をしていきます。またウジ虫のような虫が繁殖することもあるので、これらが増えてしまうと
吸水ができなくなるので、体力が衰えてしまうので、葉の色が変色したり、最悪の場合には枯れてしまうことがあります。ホームセンターやガーデニングの専門店で市販されている薬剤があるので、汚染された土を捨てて根の部分を水洗いするなどしてから使用します。
センペルビウムの歴史
センペルビウムはヨーロッパの中部や南部、コーカサス、中央ロシアの山岳地帯に分布している植物で、ヨーロッパやアメリカでは栽培用の品種として人気のある園芸品種として流通をしていますが、原産地が寒い山岳地帯なので、寒さには非常に強い品種が数多くあります。
生息地が山地であることから育て方としては湿度や気温などに気をつけることが必要なので、ある程度の経験が必要とされているのですが、山岳地帯の気候を考慮すると管理の方法もわかるので、品種によっては難易度が低いものもあります。
寒さには非常に強いので日本全国で栽培することができるのですが、暑さに弱い品種も多いので夏には直射日光を避けられる場所での栽培が基本になります。またセンペルビウムは園芸用品種として様々な品種が作られていて、その数は1000種類以上ともいわれています。
常緑性の植物なのですが、中には落葉するものがあるので、どのような品種を栽培しているのかをしっかりと把握して育て方の情報をチェックしないと育てることが難しい植物です。ヨーロッパやアメリカでは古くから栽培されていた品種なので、いつ頃日本に入ってきたかはあまりはっきりとは知られていないのですが、
趣味で楽しむことのできる植物なので、昭和の頃から栽培されていたと考えられます。永遠に生きるというラテン語から名前が付けられていて、その名の通り非常に繁殖力が強い多肉植物なので、温度や湿度の管理をしていれば枯れることはありません。
センペルビウムの特徴
特徴としては寒さに大変強いということですが、ほとんどの品種が春から秋にかけて開花するタイプなので、国内では山野草などとしても流通しているのですが、多肉植物なので品種によっては株からランナーが伸びてその先に子株を付けて群生するものがあります。
葉の色は赤や紫、茶色などがありますが、これらの色の中間色の品種も数多くあるので、好みに合わせたり、インテリアに合わせて栽培をすることができます。栽培難易度に関しては品種によって異なるので、初心者でも育てやすいものや温度管理が非常に難しい物など
様々なバリエーションがあります。常緑の植物で非常に強い性質なので全体が枯れてしまうことはあまりありません。色が多様なので、センペルビウムのいろいろな品種を集めて鑑賞することもできるので、趣味の園芸を楽しむことのできる多肉植物として日本でも非常に人気が高くなっています。
草の高さは2センチから8センチなのですが、茎の部分が伸びるとこれ以上の長さになります。盆栽向きの植物として流通しているのですが、多様な植物なので品種をしっかりと把握しておかないと盆栽として鉢に収めることが難しくなることもあります。
開花期が2月から7月となっているのですが、花に関しては小さいのであまり目立たないのですが、咲かない場合には株が弱っていることが考えられるので栽培方法を見直す必要があります。また生育がうまくいくとランナーが伸びて群生を始めるので育て方には注意が必要です。
-

-
キジムシロの育て方
被子植物で、バラ目、バラ科、バラ亜科となっています。特徴としては、梅に似ているだけあって属以外は梅と同じです。被子植物で...
-

-
かぼちゃの栽培の方法を教えます。
かぼちゃの栽培場所ですが、出来るだけ乾燥気味の土地で、水はけと日当たりが良い所を選びます。ウリ科の作物は連作障害が出やす...
-

-
カラミンサの育て方
カラミンサはシソ科のハーブで白やピンク、淡い紫色の小さな花をたくさんつけることで人気となっている宿根植物で葉の部分はハー...
-

-
イチゴノキの育て方
マドリードの旧市街の中心地には、「プエルタ・デル・ソル」(太陽の門)と呼ばれている広場が有ります。この広場はスペイン全土...
-

-
みつばの育て方
みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になってい...
-

-
キュウリを種から育てる方法
花と野菜の土をポットに準備します。ポットにキュウリの種まきをします。キュウリの種は扁平な中央部がやや膨らんだ長円形です。...
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...
-

-
ワケギの育て方
原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地で...
-

-
ハバネロの育て方
ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられ...
-

-
家で植物を育ててみましょう
植物はそこにあるだけで人を癒してくれます。緑は安らぎ、穏やか、やさしさなどを想像させ、またマイナスイオンによる空気浄化効...




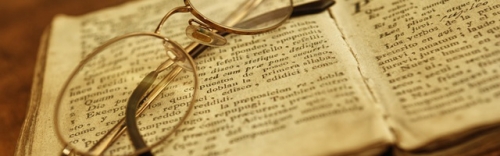





センペルビウムはヨーロッパの中部や南部、コーカサス、中央ロシアの山岳地帯に分布している植物で、ヨーロッパやアメリカでは栽培用の品種として人気のある園芸品種として流通をしていますが、原産地が寒い山岳地帯なので、寒さには非常に強い品種が数多くあります。