アケビの育て方

アケビの育てる環境について
栽培する場合は、一般的に苗木を販売しているお店や苗木商などで購入することになりますが、挿し木を使用する方法で大量に育てることも可能です。11月~2月は植え付けや植え替えを行う時期になります。育つと4月頃に開花し、秋になると実を結びます。
日光が必要なので、庭などに植えるときや、鉢植えなどにするときも、日当たりの良い場所を選びます。またアケビは雌雄同株なのですが、自家不和合性をという特徴があるため自家受粉をすることができません。つまり1株では実を結ぶことができないので、受粉用に必ず別種のアケビと一緒に育てる必要があります。
したがって、もう一つの種類を適宜選んで植えてください。また育て方としてアケビはつる性の植物なので、アケビだけでは育てられません。そのため棚などの施設が必要です。現在の主流は平棚仕立てです。土壌や天候が適した地域の範囲は広いのですが、品質の高い実をつけさせるには、日当たりが良いこと、肥沃な土壌であること、排水の良いゆるい傾斜地といった条件が見られます。
剪定されていない自生のアケビも果実を多くつけているので、時に剪定をする必要はありません。剪定によって花芽を落とすなど、かえって傷めてしまうこともあり、そうなると花が咲かなくなる可能性もあります。
したがって特に場所や見た目の問題が無ければ、剪定はしないほうが良いでしょう。剪定を行う場合、枝葉が伸び、花芽がついていることがわかる春が良いとされています。花芽が付いていない枝を適宜落として樹の形を整える程度の剪定にとどめましょう。
アケビの種付けや水やり、肥料について
通常は種から育てることは行っていません。「アケビ」「ミツバアケビ」「ゴギョウアケビ」があり、この中から二種類を適宜選択して植える必要があります。 庭に植える場合は、植える場所にあらかじめ準備が必要です。庭の土に、赤玉土と腐葉土とを同程度を混ぜます。
またもし水はけが悪い土壌なら、川砂を混ぜて苦土石灰で中和させましょう。その後環境が適していれば、早ければ2年、遅くとも4年程度で結実します。実がなるまでの期間は長いのですが、実がなった後は安定した収穫が見込めます。
もしできるだけ多くの実を得ようとする場合、樹から広がる枝があまり大きくならない性質があるため、平棚仕立てにすることと、10アール当たり200本程度を植栽するなどし、その後間引きするなどしてあまり密集させない方が良いとされています。
鉢の場合も、同様の土を使うと良いでしょう。水やりに関しては、鉢植えの場合、 鉢の土の表面が白く乾いたら、鉢の底の穴から水が少し流れ出るくらいの量を与えます。庭に植えた場合は、土質にもよりますが、
水はけが良すぎるのでなければ水やりは降雨だけでよく、通常はほとんど必要ありません。ただし、苗木や植えつけ直後だった場合は、多めに与えます。肥料は庭植えの場合、2月と10月に有機質肥料か速効性化成肥料を与えてください。
また鉢植えの場合は2月、5月、10月同じ肥料を与えることで、生育を助けることができます。また植え付けや植え替えは、11月~2月が良いとされています。根詰まりを防いだり、通気をよくするなどの理由で2~3年に1回は鉢植えも植え替えしたほうが良いでしょう。
アケビの増やし方や害虫について
一般的には、苗木を購入してくるかつぎ木を行います。時期としては2月上旬から3月上旬の休眠期が適切です。6月ごろに緑枝ざしを行い新梢を使います。5~7cmの長さに切り、上葉だけを半分に切って残し、下葉を全て取り除きます。1~2時間水あげし、その後、肥料を使用した土に挿し木してください。
その後挿し木から発根したら鉢にも移せます。また生育中の剪定として、庭植えの場合は一枝あたり育ちのよいものを2果ほど残します。樹の高さが2~3mになったら、20~30果を目安に残し、他は摘果します。鉢植えの場合は一鉢5~6個を残し、他は摘果します。
この際、位置が偏り過ぎないように気をつけましょう。病気としては、うどんこ病、黒点病、すす病の病害が多く見られます。この中で、うどんこ病は特に果実の収穫量に大きな影響がありますので、もし見つけた場合は防除を徹底する必要があります。
もし怠った場合、非常に大きな被害が出てしまいます。主な害虫はアブラムシ、カメムシ等が挙げられ、これらにより大きな被害を受ける事もあります。これらの被害を予防するには、日当たりの良い場所であることと風通しを良くする必要があります。
通常の生育には剪定が必要ではないのですが、害虫のためには剪定を適切に必要があります。また、アケビには病虫害に対して有効であることを示す登録農薬がありません、したがって果樹用の農薬を年間十回程度散布することで対策を行っているケースがあります。
アケビの歴史
アケビはまず中国の歴史に現れます。中国で最古の薬物学と書と言われている「神農本草経( しんのうほんぞうぎょう)」という本に記載されていることから、西暦500年頃にはすでにお薬として使われていたことがわかります。
日本では明治時代に広く知られた折衷派の漢方医である浅田宗伯先生が書いた古方薬議という本に記載があります。この頃にはすでに広く医薬品として日本でも利用されていたことがわかります。その効能は、熱を下げるなどの効果がありました。
また、医薬品だけではなくその蔓が実用品のための素材として使用されていました。古代中国では蔓を編んで「葛籠(つづら)」を作るための材料として利用されていました。日本でもアケビの蔓の利用はとても歴史が古いことがわかっています。
奈良の正倉院にアケビの蔓で編んだ「御書箱」という入れ物が残っていることからもわかります。ちなみにこの「御書箱」は筆・数珠・仏様など、特に大切なものを奉納するための入れ物として利用されていました。また有名な昔話である「舌切り雀」にも葛籠が出てきますが、これもアケビで作られたと言うことになります。
名前の由来はいくつかあります。たとえば熟すと実縦に裂けたように開くことから「開け実(あけみ)」と呼ばれ、これが変化して「あけび」になったという説があります。さらに他の説として、実が熟して割れた様子が、人があくびをしているようにも見えることから、「あくび」が変化して「あけび」と呼ばれるようになったという説があります。 も
う一つは赤い実を表す、「赤実(あかみ)」が訛って「あけび」になった説もあります。漢字では、「通草」もしくは「木通」と書きます。由来は蔓に空洞があり、ここを空気が通ると思われていたことによります。
アケビの特徴
原産、および生息地は日本、中国、韓国などの東アジアなど広い範囲になります。アケビは秋の味覚の1つとも言われています。大きさは長さが10cmくらいの紫から朱色といった種類があります。熟すと表面の皮が割れて中身が出てくるので、この実をそのまま食べることもできてしまいます。
その実は乳白色をしたゼリーのような食感で、甘味があります。小さな種がたくさん入っているので、全体を食べてから種だけを出すようにして食べます。皮は炒め物や揚げ物などにも使われるなどするので、ほとんど捨てるところがありません。
またアケビのツルが非常に丈夫なので、ザル、籠、椅子、入れ物、生け垣といったさまざまな素材に使用されています。現在の産地は山形県がとてもシェアが高く、全国の生産量150tのほとんどが山形で生産されています。アケビを食べる場合は、実の中にあるゼリー状の半透明の果肉を食べます。
甘さは強くありませんが、ほんのりした甘さが特徴です。昔から中の果肉部分だけでなく皮の部分も料理して食べる習慣があります。皮を使用した肉詰め、炒め物、天ぷら、素揚げといった料理方法が伝統的に行われています。
また、アケビの芽は春の山菜としても親しまれています。東北や信越地方では「木の芽」というと「アケビの若芽」のことを言います。また山形県の代表珍味としても知られています。
アケビは傷みやすく、傷つきやすいので丁寧な取り扱いが必要です。昔の人はアケビを食べて疲れをとったというほど、滋養強壮に効きます。また乾燥させた実は腎臓炎の予防薬としても効果があり、現在も一部で利用されています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クロトンの育て方
タイトル:イヌマキの育て方
タイトル:アセロラの育て方
-

-
ミニカボチャの育て方
ミニカボチャをはじめとするカボチャの原産地は、インド地方やナイル川の沿岸地域、南米大陸北部のペルー、アンゴラなど様々な学...
-

-
カリブラコアの育て方
カリブラコアは南米原産です。1825年にメキシコの植物学者であるセルバンテスとヴィンセンテによりナス科カリブラコア属が新...
-

-
エリゲロン・カルビンスキアヌの育て方
エリゲロン・カルビンスキアヌはロッキー山脈からメキシコにかけてまでの北アメリカを原産とし、現在生息地を世界中に広げている...
-

-
ブーゲンビレアの育て方
今ではよく知られており、人気も高いブーゲンビレアは中央アメリカから南アメリカが原産地となっています。生息地はブラジルから...
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
マンリョウの育て方
江戸時代より日本で育種され、改良も重ねられた植物を古典園芸植物と称しますが、マンリョウもこのような古典園芸植物です。 ...
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...
-

-
パンジーの育て方について
冬の花壇を美しく彩ってくれる植物の代表格は、なんといってもパンジーです。真冬の街にキレイな彩りを与えてくれる植物としては...
-

-
アキザキスノーフレークの育て方
オーストリア、ハンガリーなどの南ヨーロッパ西部を原産国とするアキザキスノーフレークは、この名の通り、秋に咲くスノーフレー...
-

-
銀葉アカシアの育て方
まず歴史的にもミモザという植物は、本来は銀葉アカシアなどの植物とは違う植物です。もともとミモザとはオジギソウの植物のこと...




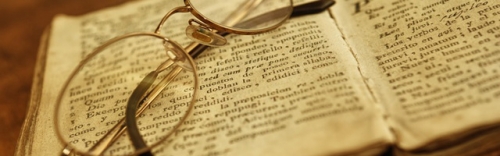





アケビはまず中国の歴史に現れます。中国で最古の薬物学と書と言われている「神農本草経( しんのうほんぞうぎょう)」という本に記載されていることから、西暦500年頃にはすでにお薬として使われていたことがわかります。