コレオプシスの育て方

育てる環境について
コレオプシスの育て方としては日当たりと水はけの良い所であれば栽培は容易にできます。種類によっては荒れ地のような場所や砂利混じりのやせ地でも育つことがあります。ただし日陰や湿地では上手く育つことはできません。種や品種によって性質の強さや増えやすさに多少の違いは出てきます。
日当たりや風通しが良く、水はけがよければある程度は成長します。日当たりが悪いと花付きが悪くなります。コレオプシスは寒さに強いため、寒冷地でなければ防寒する必要はありません。寒冷地だと冬に落葉します。土質はあまり選ぶ必要はなく、市販されている花と野菜の土で十分植え付け可能です。
一年草タイプは花後に枯れてしまうので一度植え付けたら植え替えする必要はありません。多年草タイプはよく育つのであh地がいっぱいになったら遥か秋に株分けをかねて植え替えを行いましょう。根詰まりを起こしたり、芽が込みすぎたりすると生育が悪くなり、花も少なくなるので気をつけることです。
咲き終わった花は摘み取るほうがいいでしょう。草丈が高くなるものは倒れないように支柱を立てておくことが必要になります。この支柱も軟弱なものを使用すると倒れてしまうので気をつけましょう。コレオプシスは草丈が高い割には根が浅いので
しっかりとした支柱を使うほうがいいでしょう。品種によっては耐暑性がやや弱く夏に枯れてしまうこともあるので好みのものを見つけて育てましょう。日当たりのよい場所を好みますが、若干暑さに弱い部分もあるので午後から日陰になるような場所が最適ではないでしょうか。
種付けや水やり、肥料について
コレオプシスの生息地がアメリカ大陸ということもあり、どちらかというと乾燥を好む傾向にあります。多湿を嫌い、水をやり過ぎると腐って枯れてしまうので、土が乾くまでは水をやり過ぎないようにしましょう。特に鉢植えの場合は真夏などの蒸発が激しい時期は
朝と夕方の二回、しっかりと水やりをしなければなりません。だからといってやり過ぎは厳禁です。肥料は切れてしまうと花が咲かなくなるので春から秋にかけては肥料を切らさないように液肥を毎月二回か三回はやるようにします。ただし、こちらも肥料のやり過ぎになると花が咲かなくなりますので
様子を見て肥料の頻度を調節したほうがいいでしょう。草丈の高いものは肥料を抑えて生育を抑えたほうが倒れにくくなり、草姿のバランスもよくなります。草丈が低く、開花期の長いものは4月から6月と、9月から10月に月一回置き肥をするか、月3・4回の液肥を施すといいでしょう。
植え付けの際にゆっくり時間をかけて利くタイプの肥料のほうが向いているように思えます。地植えの場合はあまり必要ではありませんが鉢植えやコンテナの場合は肥料が切れてしまうとそれ以上花が咲かなくなることもあります。
様子を見ながら少しづつ肥料を与えるといいでしょう。肥沃で湿潤な土に植えていれば、基本的に雨水だけでも育つことができます。直射日光の下では水やりの回数を多めにしておきます。半日ほどは日陰のほうが土の乾きも少なく、適している場所といえるでしょう。
増やし方や害虫について
一年草タイプは種から、多年草タイプは株分けで増やすことが可能です。種まきの時期は秋頃で発芽温度は20℃前後です。気温が高い時に蒔くと発芽しにくいので早蒔きしないように気をつけます。発芽して本葉が数枚出てきたら庭や鉢に植え付けます。
複数株まとめたほうが見栄えするので庭植えの場合は20センチほどの感覚で植えつけるのがいいでしょう。鉢植えの場合はやや詰め気味にしたほうが花が咲いた時にボリュームがあります。株分けは生長を早める直前の早春、もしくは花が咲き終わったあとの晩秋が適しています。
大きく育った株は掘り上げて根をほぐしながら子株に分けてそれぞれを植え付けるのがいいでしょう。害虫については春先から新芽やつぼみにアブラムシが発生します。葉や茎を駄目にしてしまうので見つけ次第駆除しましょう。春や秋の低温時期に長雨が続くとべと病が発生することがあります。
べと病にかかると葉に黄色い斑点ができて黒ずみ、枯れてしまいます。被害にあった葉は早めに取り除き、殺菌剤を散布するほうがいいでしょう。日当たりや風通しが悪いと発生しやすくなるので、水はけをよくしたり、
枝を間引いたりコンパクトにするための枝先の剪定をするといいでしょう。日頃の観察が大切で、常に害が広がらないように注意して早めの対策や防除が効果的です。また、同一品種を多く植えるのではなく、様々な品種にハーブなどを加えて混植することで害虫の対策にもなります。
コレオプシスの歴史
コレオプシスはアメリカ大陸、熱帯アフリカにおよそ120種類が分布するキク科の植物です。園芸用としては北アメリカ原産種が主に栽培されています。様々な種類があり、一年草と多年草があります。一年草であるキンケイギクはアメリカのテキサス原産で日本に入ってきたのは明治10年頃、
ハルシャギクは北アメリカ中西部で江戸時代後期に渡米されたとされています。多年草のグランディフロラ北アメリカ中央から南部にかけて広く分布しており、オオキンケイギクは北アメリカ、日本にトライしたのは明治時代と言われています。
他にも北アメリカ東部原産のロセア、南アメリカ原産のアウリクラタなどがあります。その、どれもがアメリカ原産で江戸時代や明治といった頃に観賞用目的で導入された花です。丈夫な性質で手間もかからないことから現在の日本でも園芸用として幅広く栽培されています。
しかしオオキンケイギクは繁殖力が強く、大きな群生になり他の花を駆逐するために2006念に特定外来生物に指定されていることから栽培や販売、運搬、輸入などすることを原則法律で禁じられています。明治期に渡来、とありますが現在一部地域では
戦後渡来説のほうが有力だという声も上がっています。これは戦時中に南方の戦場から帰還した軍用機の機体や、搭乗員の服に種子が付着して渡来、飛行場周辺に根付き戦争が激化した20年初夏頃に花が咲いた、という言い伝えがある地方も存在するそうです。
コレオプシスの特徴
コレオプシスは花が咲いた後に種ができて枯れてしまう一年草タイプと枯れずに冬を越して毎年花を咲かせる多年草タイプがあります。一年草タイプの代表としてはハルシャギクやキンセイギク、多年草タイプにグランディフロラやイトバハルシャギク、ロセア、
栽培が禁止されているオオキンケイギクがあります。今まで一番ポピュラーだったのが、栽培禁止になったオオキンケイギクでした。おそらく一番目にしていたものも、このオオキンケイギクではないでしょうか。特定外来生物に指定されてからは他の品種が目立つようになってきています。
開花時期は春から秋で種によって違いはありますが黄色や赤褐色で一重咲き、八重咲きがあります。細い花茎に菊のような花をぱっと咲かせて群れる姿はコスモスやヒデンスにも似ています。丈夫で手間がかからないので花壇や鉢植え、切り花など様々な用途と色々な場所で見ることがあります。
品種によって色は様々で黄色や赤紫、ピンクや白といった色があります。見た目の印象は野性的で、細長い葉を茂らせる花です。先程も記述したように丈夫な性質であり、荒れ地などでも成長しますが肥料過多や過失に弱い面もあるのです。
葉はコスモスのように羽状に分かれており、石畳の隙間などにこぼれ種で増えたものを見かけることが多くなっています。草丈は30センチから1メートルほどで、花色は様々あります。枝は分枝してたくさんの花をつけていることがほとんどです。
-

-
サカキの育て方
サカキは日本・朝鮮・台湾・中国に自生する、比較的温暖な地を好みます。葉の形で先が鋭くとがっているものは神の宿るよりしろに...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
ゲンノショウコの育て方
この植物の原産地と生息地は東アジアで、中国大陸から朝鮮半島を経て日本全国に自生しているということですので、昔から東アジア...
-

-
ケストルムの育て方
ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとさ...
-

-
キンギョソウの育て方
キンギョソウはもともとは多年草ですが、暑さで株が弱り多くが一年で枯れてしまうので、園芸的には一年草として取り扱われていま...
-
雪割草の育て方
さまざまな種類がありますが、その中でも小さくて可愛らしいイメージがあるのが雪割草で、キンポウゲ科ミスミソウ属の多年草の園...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...
-

-
コダチアロエの育て方
アロエの種類は約300種類にものぼり、大変種類が多い植物になります。日本で良く見られるアロエは”コダチアロエ”と呼ばれ、...
-

-
みつばの育て方
みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になってい...
-

-
パボニアの育て方
パボニアはブラジルが原産の植物で、赤い苞が鮮やかな低木の熱帯植物になります。尚、この植物はアオイ科、 ヤノネボンテンカ属...




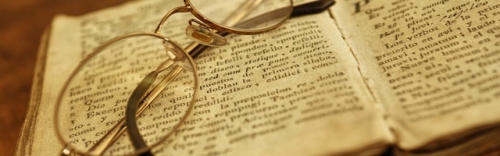





コレオプシスはアメリカ大陸、熱帯アフリカにおよそ120種類が分布するキク科の植物です。園芸用としては北アメリカ原産種が主に栽培されています。様々な種類があり、一年草と多年草があります。一年草であるキンケイギクはアメリカのテキサス原産で日本に入ってきたのは明治10年頃、ハルシャギクは北アメリカ中西部で江戸時代後期に渡米されたとされています。