ヘゴの育て方

ヘゴの育てる環境について
日本の南部から台湾、東南アジアにかけて野生種が生育しています。耐陰性の高い植物ですが、ある程度日光が当たる方がよく育ちます。家庭で育てる場合には、やわらかく間接光のあたる窓辺、半日陰、などの場所が適しています。ヒカゲヘゴについては、明るい場所を好むので直射日光があたる場所に置いても構いません。
湿度が高い場所を好み、乾燥を嫌うので、強い風があたるような場所は避けるようにします。冬越しさせるためには、室内の明るくて暖かい場所で管理します。最低でも5℃以上に保ち、空気が乾燥しないように加湿しましょう。用土は基本的な小粒赤玉土:腐葉土=7:3もしくは5:5の割合で混ぜたものを使えば良いです。
乾燥してしまうと枯れてしまうので、葉や茎を乾かさないように管理しましょう。これには、じょうろや霧吹きなどを使って葉や茎に直接水をかけてあげると良いです。また、気根が乾燥すると枯れてしまう原因になるので、こまめに葉を湿らせるように気をつけましょう。シダ植物が元気に育つ環境をあげてみると、通気性が高い、
土中や葉の周囲の空気が常に入れ替わり酸素が次々に供給される、温度が高い、湿度が高い、という条件があります。日本は高温多湿の環境ではありますが、室内などで育てていると暖房や冷房によって乾燥してしまう場合もあります。湿度を高めるために、ミズゴケを湿らせて幹に巻きつけるという方法もあります。ただし、受け皿に水を溜めると根腐れの原因になるので避けましょう。
ヘゴの種付けや水やり、肥料について
5〜7月にかけてが植え付けや植え替えの適期です。2〜3年に1度、成長に応じて一回り大きなサイズの鉢に植え替えるようにします。植え替える時には、鉢の底に大粒軽石などを入れ、水はけを良くします。用土は小粒赤玉土:腐葉土=7:3or5:5で配合したものを用います。
植え替えの時に茎を乾燥させてしまうと、その後生育不良になる恐れがあるので、直射日光や強風が吹いているような場所は裂けて作業を行うように気をつけます。できるだけスピーディに手際良くやるのがコツです。5〜6月は気温が上昇するのでおすすめの時期です。
鉢土と幹を乾燥させないように、たっぷりと水やりを行う必要があります。水やりのポイントは、幹の先端部分を中心にして、株全体を濡らすように湿らせるのがコツです。じょうろで上からまいても良いですし、下が濡れると困るような場所ならば、霧吹きなどで十分に湿らせるようにします。
冬場も乾燥しやすいので、鉢土の表面が乾いてきたら水を与えます。冬場も他の時期と同様に、葉や幹を乾燥させてしまわないように管理します。ここでひとつ、霧吹きを使う時の注意点です。霧吹きを使うとたくさん水がかかったように錯覚してしまいますが、
実際にはそれほど量がかかっていないことも多いです。なので、少し多めにかけてあげるようにしましょう。肥料は、5〜9月の成長期に3大栄養素(チッ素・リン酸・カリ)が等量含まれているものを施します。規定量を置き肥として与えれば良いです。花の最盛期には、リン酸が多めの液体肥料を施すと花付きが良くなります。
ヘゴの増やし方や害虫について
シダ植物は胞子で増えますが、家庭での育て方では胞子で増やすことは難しいです。一般家庭ではまず繁殖は不可能です。葉や新芽の部分にカイガラムシが発生することがあります。見つけたら薬剤散布か歯ブラシなどを使ってこすり落とすようにします。早めに駆除しないと葉が萎縮して見栄えが悪くなるので、注意しましょう。
カイガラムシの成虫は殻をかぶったり、体がロウ物質で覆われているので、駆除しづらい害虫です。歯ブラシでこすり落とす時には、葉を傷つけてしまわないように注意が必要です。薬剤による駆除では、幼虫のうちに退治してしまうのが一番です。卵から孵化したばかりの幼虫は薬剤に弱いので、
オルトランなどをかければすぐに撃退することができます。他には、成虫になるための脱皮を阻害してしまう薬剤を使うのも良い方法です。この成分はブプロフェジンと呼ばれるもので、成虫になるのを抑えることで被害を最小限に抑えることができます。成虫に対しては、産卵数を減らす、卵が孵化しないようにする、などの作用もあります。
カイガラムシは吸汁性の害虫で、こういう系統の害虫の排泄物はしばしば、すす病の原因になります。すす病にかかると葉が黒くなり、見栄えが悪くなります。排泄物は、テカテカ光ったり、ベトベトとした粘着性を帯びているので、見たり触ったりすればわかります。カイガラムシが排泄物を落としているようであれば、まずは本体を駆除することに専念しましょう。
ヘゴの歴史
南西諸島、台湾、フィリピンを原産とする熱帯植物です。世界的には、熱帯〜亜熱帯にかけて約800種類が分布しています。大型の種になると、野生では高さ7〜8mに育ちます。日本では一般的には沖縄や鹿児島などの南部を生息地としています。日本で流通量が多いのは奄美大島以南の南西諸島原産のヒカリヘゴです。
茎の部分がヘゴ材という材木に使われてきた歴史があり、ランや観葉植物を植え付ける時の資材や支柱として使われてきました。現在では乱獲により自生数が減っています。ヘゴの種類によっては、新芽を食用として使えるものもあります。属名のCyatheaceae(シアテア)は、
ギリシア語では「コップ」「盃(さかずき)」を意味するキアトアに由来しています。これは、葉の裏についている胞子のう(胞子を作り収納する袋状の器官)の形が、まるでコップのような水を入れる形になっていることからきています。東南アジアや中南米では茎や根の塊に彫刻を施して、土産物としていたことがあります。
また、ゼンマイ状に伸びた新芽を採取して山菜として食することも出来ます。茎の部分はでんぷん質に富むため、かつてニュージーランドなどを中心として、広い地域で原住民が食用としていた歴史もあります。ただし、今では乱獲により数が減り、ワシントン条約付属書2類に掲載されているため、土産物や食用として使うのは注意が必要なこともあります。日本では沖縄や鹿児島で原生林を見ることが出来ます。
ヘゴの特徴
ヘゴ科ヘゴ属のシダ植物です。野生種は最大7〜8m近くにまで伸びる熱帯性の植物です。原産地は南西諸島、台湾、フィリピンなどで、日本では沖縄や鹿児島の限られた地域で見ることが出来ます。家庭で栽培した場合にはそれほど大きくならず、丈はだいたい0.5〜2mくらいです。
一般的に園芸品種として流通しているのは、ヒカゲヘゴ(Cyathea-lepifera)という品種で、明るい場所の生育が適しています。ヒカリヘゴの名の由来は「日陰をつくるヘゴ」からきています。乾燥を極端に嫌い、土はもとより、茎が乾燥してしまっても枯れてしまうので、水やりには注意が必要です。
熱帯性の植物であるため、耐寒性は弱いです。耐暑性もそれほど高くなく、普通といったところです。常緑性なので、暖かいところで育てれば常に緑を楽しむことが出来ます。見た目は原始的で、茎がすっと立ち上がり、大きく伸び、直径50cmほどの太さに成長します。茎の上から放射状に葉が伸びて、細かく裂けて鳥の羽のような形になります。
茎の表面には気根と呼ばれる細かい根が絡み合い、木の幹のような硬さになります。ここがヘゴの最大の特徴でもあり、この茎の部分を使ってヘゴ材という材木として用います。主にランや観葉植物の植え付けの時の資材や支柱に用いられます。野生種は乱獲によって数を減らしています。中には新芽の部分を食用にできるものもありますが、園芸用として出回っているものに関しては食用には適さないことが多いです。
-

-
ポリゴラムの育て方
ポリゴラムはヒマラヤを原産とする多年草です。タデ科の植物で、別名でカンイタドリやヒメツルソバとも呼ばれます。和名のヒメツ...
-

-
スプラウトの育て方
スプラウトの歴史はかなり古いとされています。5000年も前の中国では、すでにモヤシが栽培されていたとの説があります。モヤ...
-

-
フェンネルの育て方
フェンネルは原産が地中海沿岸だとされています。かなり古い歴史があり、最も古い記録では古代エジプトや古代ローマでも栽培され...
-

-
ナンテンの育て方
ナンテンはメギ科ナンテン属の常緑低木です。原産は日本、中国、東南アジアです。中国から日本へ古くに渡来し、西日本を中心に広...
-

-
ブーゲンビレアの育て方
今ではよく知られており、人気も高いブーゲンビレアは中央アメリカから南アメリカが原産地となっています。生息地はブラジルから...
-

-
ベニバナの育て方
ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...
-

-
トリカブトの育て方
トリカブトは日本では”鳥兜”または”鳥冠”の由来名を持っています。この植物の花の形が舞楽で被る帽子の鳥冠に似ている事から...
-

-
ヒベルティアの育て方
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にも...
-

-
ラセンイの育て方
”ラセンイ”は畳の原料である「イグサ」と同じ種類の植物になります。葉っぱが退化し、くるくるとらせん状にうねうねと曲がって...
-

-
マリモの育て方
また日本以外はどうかというと、球体のものは、アイスランドのミーヴァトン湖やエストニアのオイツ湖などで確認をされているとい...




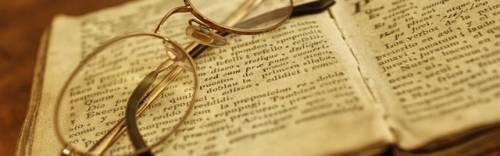





ヘゴ科ヘゴ属のシダ植物です。野生種は最大7〜8m近くにまで伸びる熱帯性の植物です。日本では一般的には沖縄や鹿児島などの南部を生息地としています。日本で流通量が多いのは奄美大島以南の南西諸島原産のヒカリヘゴです。