ラッカセイの育て方

育てる環境について
上記にも述べたように、ラッカセイは日本国内にも全国的に知れ渡る有名な生産地があります。近年は輸入品も多いので購入してから食べる人も多いですが、実は比較的育てやすい植物だと言われています。初心者が家庭菜園で挑戦してみても育てやすい植物でしょう。
しかし、育ちやすいとは言っても、植物の好む環境やそれぞれの作業に適した時期など基本的情報は知っておかなければなりません。ラッカセイの収穫時期は秋頃です。逆算すると種まきの時期は5月上旬以降にしましょう。暖かい気候も必須です。日本全国どこでも栽培できる植物ではありますが、
日本は南北に細長い地理のため、山地や内陸部、北と南などそれぞれの土地で気候は全く変わってきます。当然のことながら地域によって時期に多少の誤差が出てきます。自分の住む地域の気候を考慮した上で種まきの時期や収穫の時期を調節しなければなりません。また、種まきの数週間前ぐらいから石灰や肥料を撒いて土壌を整えて種まきの準備をしておきましょう。
畑の土壌が栄養分を多く含んでいるかどうかなど土地によって元々の土の状態が異なるため、土の状態に合わせて量を判断しなければなりません。実が付いたと信じて楽しみにして収穫を待っていたにも関わらず、収穫した時に中身が無かったということもよくある話です。石灰はこのような中身のない状態での実の生育を防ぐ効果があります。初めての人ならば、ホームセンターなどで尋ねてみると良いでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ラッカセイの種は撒く前に水を吸収させておくのが良いです。そして植えた時にもたっぷりと水を与えましょう。一部では発芽するまでの水やりは避けるのが良いという人もいます。また、種まきの時に一緒に肥料をやるのが望ましいですが、豆類という植物の特性上少なめにして撒くのがコツです。一か所に数粒ずつ種まきをし、多めの土で覆います。
種まきから数日すると発芽を確認することができるでしょう。発芽を確認したら間引きして栄養分をよく吸収できるようにしてやります。この時期から水やり開始です。毎日水やりをするのではなく、土壌が乾燥していると判断した時に適宜水を与えます。どの植物でも当てはまることですが、陽射しの強い時間にやると、水が温められてお湯の状態になります。
これは植物にとっては非常に良くありません。朝方か夕方にするのが良いです。水やりのし過ぎもやはり良くありません。特にラッカセイは夏場に生育する植物なので、気を付けましょう。枝が伸び始めたら再び肥料を加える人もいますが、花が咲いてから肥料をやるという人もいます。発芽してから数十日すると花を咲かせるので、
植物の状態を見てタイミングは見計らうべきです。植物にとって良かれと信じて疑わずに肥料を多くやりたい気持ちはわかりますが、肥料も多すぎるのは禁物です。また、土の中に潜っていく植物なので土を柔らかくしておき、土寄せをしましょう。そして収穫時期までは気長に待ちましょう。早すぎても遅すぎても期待するような収穫ができないことがあります。
増やし方や害虫について
育てやすい植物として有名だとしても、枯らしてしまうこともあります。特に、豆類に関しては共通で連作は良くないとされています。知らずに連作にしてしまうと、害虫が発生する要因を自分で作ってしまっていることになります。少なくとも数年あけるのが理想的です。植物の葉によく虫が付いているのを見たことがある人も多いでしょう。
害のない虫ならば良いのですが、ほとんどは緑の葉を食って穴をあけてしまいます。ラッカセイも葉を害虫に食われることがありますので、普段から観察をしっかりしておかなければなりません。見つける度に駆除して終わるだけでいい種類の虫もいますが、しっかりとした防虫対策が必要なものもあります。
また、知らないうちに病気にかかっている場合もあります。多くの場合、水をやりすぎたことが原因で引き起こされます。湿気が多すぎてカビが発生してしまう場合や他にも様々な病気があります。植物にとって水はとても大事な物ですが、必要な量を知って与えなければ逆に害になってしまいます。プランター栽培の場合、
栽培開始の時点で発泡スチロールをプランターに敷くなど排水対策をしっかり施しておくと病気にかかる確率は低くなります。無知によって植物を枯らしてしまうのはとても残念なことです。植物を育てるのならば、事前に育て方の基本情報をよく調べ、基本を忠実に実践していく過程で、自分の住む土地や気候に合うように試行錯誤を加えていくのが良いでしょう。自分の判断だけで栽培するのは失敗を招く元になります。
ラッカセイの歴史
ビールのおつまみとしてもおやつとしても皆から愛されている気軽に食べられる食べ物の一つにラッカセイがあります。漢字でも表記されることがあるものの姿や形からして元々日本に生育していた植物だと考える人はあまりいないでしょう。今では日本国内で生産されていますし、有名な生産地もありますが、歴史を遡ってみれば日本での歴史はまだあまり長いとは言えません。
元々は南アメリカが原産地のようです。中世の頃、世界中で人々の交易や往来が盛んになると共に、ヨーロッパやアメリカなど各地に伝播していき、今では生息地は世界規模になっています。あまり有名ではないですが、日本では南京豆という呼称も残っています。南京とは中国のことを指し、中国から日本に伝わったものだということが容易に想像できます。
沖縄が琉球王国として栄えていた頃は、琉球王国とやり取りのあった国はたくさんあるようです。ラッカセイ栽培の沖縄での歴史は日本本土よりも古いようですが明確なことはわかりません。日本本土で本格的に広がったのは明治時代になってからです。文明開化と共に海外との交流も増え、種を容易に入手できるようになりました。
政府がアメリカから種を入手して栽培を勧めたそうです。明治時代や大正時代を通して、人々の栽培の努力によって根付いてきたラッカセイですが、戦争などによって一時姿を消し、終戦と共に需要は復活するものの農地改革などの政策によって昔よりも農地や生産量は減少し現在に至ります。
ラッカセイの特徴
ラッカセイは植物としての特徴もあれば、栄養価における特徴も注目するべきでしょう。植物としての特徴は、とても怪奇的で面白いです。他の植物では実をつけるために花を咲かせ、付け根に実ができて膨らんでいきます。ラッカセイは夏頃に花を咲かせるものの花托から伸びた蔓が地面に潜り込み、地面の中で実をつけて膨らんでいきます。
固い殻も特徴の一つです。他の植物には見られません。ラッカセイを漢字で書いた時にその生育的特徴をよく表していると言えます。また、栄養価に関して、栄養価はとても高いのが特徴と言えるでしょう。食べ過ぎると鼻血が出るという噂を聞いたことのある人もいるかもしれません。
この噂の根拠は確かではないですが、実際に食べ過ぎると不都合な点はあります。カロリーがとても高いです。植物ですし、一つ一つの豆は小さいため深刻に考える人はいないでしょうが、ダイエット中で代替食として食べる人やお酒と一緒におつまみとして好んで食べている人などは想像以上にカロリーを摂取しているかもしれません。
美味しいのでついつい食べ過ぎてしまうこともあるでしょう。カロリーの高さ以外に良い点もあります。コレステロールを抑制する成分が含まれていますし、ビタミンEなど生活習慣病予防に役立つ成分も含まれています。二日酔いにも良いとされるので知っておくと生活の色々な場面で役に立つことがあるでしょう。過剰摂取には気を付けるべきですが、適度な量の摂取は健康のためにもお勧めの食べ物だと言えます。
-

-
ファレノプシス(コチョウラン)の育て方
学名はファレノプシスですが、和名をコチョウランとも言い、日本でランと言えば、胡蝶蘭を思い浮かべるくらい有名で、人気がある...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
ミヤコワスレの育て方
ミヤコワスレ日本に広く生息している花ですが、もともとはミヤマヨメナという植物を指しています。日本では広く分布している植物...
-

-
ルッコラの育て方
ガーデニングブームとともに人気になっているのが家庭菜園です。自宅に居ながらにして新鮮な野菜をたべられるというのも人気の秘...
-

-
植物の育て方について述べる
世の中に動物を家で飼っている人は多くいます。犬や猫、爬虫類などを飼って家族と同然の扱いをして、愛情深く飼育している場合が...
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...
-

-
リクニス・コロナリアの育て方
花の特徴として葉、ナデシコ科、センノウ属となっています。いくつかの花の名前が知られていて、スイセンノウの他にはフランネル...
-

-
プリムラ・オブコニカの育て方
プリムラ・オブコニカはサクラソウ科サクラソウ属に分類される植物で、和名は常磐桜と呼ばれています。中国西部が原産の多年草に...
-

-
アッツザクラの育て方
アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザク...
-

-
コリアンダーの育て方
地中海東部原産で、各地で古くから食用とされてきました。その歴史は古く、古代ローマの博物学者プリニウスの博物誌には、最も良...




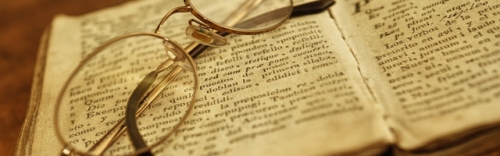





ラッカセイは、マメ科になります。和名は、ラッカセイ(落花生)、その他の名前は、ピーナッツと呼ばれています。ラッカセイは植物としての特徴もあれば、栄養価における特徴も注目するべきでしょう。植物としての特徴は、とても怪奇的で面白いです。