レブンソウの育て方

育てる環境について
育て方として良い環境としてはどういったところが好まれるかですが、1年を通して風通しと日当たりの良い所となります。原産地の礼文島においてなぜこの花が咲いたかの理由は、非常に風が強いこと、風が強い上に大きな木が育っていないことがあげられます。これくらい風が強ければ当然風通しは抜群でしょうし、木々がなければ日当たりも良くなるでしょう。
島などであれば斜面などがあるでしょうから、そういったところで咲くことができます。もちろん木が育たない程の強い風が必要なわけではありません。一定の風通しがあれば十分育てることが出来るでしょう。この植物としては北海道の北の方で自生していますが、栽培種としてどんどん都市部において咲かせられています。
栽培がしやすいことがわかってどんどん植えられています。そのときにあまりこの環境は良くないとして言われるのが夏の直射日光です。都市部になってくると北海道に比べてかなり気温も高くなります。日差しも強くなります。そうった日差しにあうと葉が日に焼けてしまうことがあります。
花の時期としては終わっていますが、葉っぱをきれいに育てるなら遮光をすると良い場合があります。少しぐらい焼けても問題ない人はそのままにしても良いですが、株を傷めるぐらいになることもあります。都市部の冬は乾燥していてそれが芽を傷める原因になることがあります。寒さには強いですが乾燥にはあまり強くないのでその対策が必要になります。
種付けや水やり、肥料について
種付けをしていく場合において用土をどのように配合するかですが、まずは植木鉢選びから行います。植木鉢といえばどれも一緒のように感じるかもしれませんが、素材が異なれば性質も異なります。扱いやすいのがプラスチック製なのでそれでばかり植えている事があるかもしれません。プラスチックはそれなりに丈夫ですが通気性があまりありません。
それに対して素焼きタイプは落とすと割れるので扱いは注意が必要です。でもそれなり通気性があるとされています。空気に対する通気性、水分に対する通気性があります。そのために通気性を重視する場合には必要になります。この花においては通気性と水はけが良くなるタイプを選ぶようにします。この花については根の成長が早いです。
植木鉢の大きさとしては、根株よりも2回りほど大きいタイプを用意するのが良さそうです。用土については、水はけの良い土を選びます。鹿沼土を4割、日光砂を4割、軽石を2割の配合にします。水やりを行うときとしては、春と秋は朝のみ行います。夜は夜に1回行います。
冬に関しては休眠状態になるので水やりをどうするかが問題になります。冬においても乾かしすぎるのは良くなく水切れしてしまうことがあるので与えるようにします。肥料はタイミングを考えて与えます。春の芽出し、花のあとの4月下旬から6月下旬があります。内容としては液体肥料を2週間に1回ほど与えるようにします。春と秋に置き肥を1回ずつ行うこともあります。
増やし方や害虫について
増やし方においては、種まきが行えます。花が咲いた時に準備を始めます。花の上部と下部を摘んで引っ張ると受粉してくれます。これをしないと受粉がうまく行かずにその後の実がならないことがあります。受粉ができたら結実するのを待ちます。色づいてきたら中から褐色のたねを取り出します。種をまくのはその時です。
発芽までどれくらいかかるかですが、2週間ぐらいから1箇月ぐらいまで幅があります。取りまき以外にも翌年の春にまく方法もあります。この時は種を冷蔵庫にいれておきます。野菜室などが温度としては調度よいでしょう。これについては翌年の3月ぐらいにまくようにします。本葉が4枚くらい出てきたら通常の株に移植するようにします。
開花までは2年ぐらいになります。株分けをすることができます。植え替えの時期において、ちょうどいい株があるときに分けることが可能になります。少しむずかしいこともあるので、株数に余裕のあるときに行うとよいでしょう。一つしか株がないのに挑戦をしてうまくいかなければ株がなくなってしまいます。
さし芽は誰でも簡単に出来る方法です。芽出しをした後にわき芽をカッターなどで元の部分から切り取ります。それを培養土にさしておきます。数箇月ほどで発根し、開花株になるまでには1年ぐらいになります。病気は根詰まりに気をつけます。根の成長が早いために対応しなければいけません。害虫はアブラムシ、ヨトウムシなどが出てきます。
レブンソウの歴史
日本において旅行に行きたい場所としては東京や京都などの都市部があげられます。そしてそれ以外となると南の島である沖縄、そして北の北海道があります。北海道においては冬はかなり厳しい環境になりますが、夏でもそれ程暑くありません。梅雨がないとして知られて、さわやかな夏を過ごすことが出来るとされています。
都市部もありますが、都市部を離れると広い畑などが地平線の向こうまで続くような景色を楽しむことができます。北海道においては歴史としては決して新しくありません。元々はアイヌ族が暮らしていたところで、近年になって開拓が進められています。北海道には北の方に島が2つあり、観光地として知られています。その一つに礼文島があります。
この礼文島の名前がついている植物としてレブンソウがあります。原産としては北海道の礼文島になります。生息地に関しては礼文島の他に北海道において見られることがあるようです。非常に美しい花ですが、日本のその他の地域、また大陸などでも同じようなものが見られないとのことで固有種となっています。
これは礼文島が風が強くて木が生育しない草原だからこその植物といえます。ではなぜこのように呼ばれるようになったかですが、もちろん礼文島を中心として見られるようになったためとされています。野生での生息地が非常に狭いですから、それだけに非常に珍しい状態になっています。レッドリストにも乗っている植物になります。
レブンソウの特徴
この植物の特徴として、バラ目、マメ科、オヤマノエンドウ属になります。園芸上においては山野草として区分されます。生え方は多年草ですから、冬でも枯れることなく残ります。草丈は大きい物で25センチ位です。開花する時期としては、4月下旬くらいから6月ぐらいになります。
これは栽培をしているときであって、北海道などで自生しているタイプになると6月下旬から7月ぐらいの開花になります。花の色としては印象的な紫色が多くなります。ちょっと変わった桃色っぽい紫などもあります。非常にまれに白やピンクの花をつけることもあります。北の最北端で咲く花から分かりますが耐暑性としては少しありません。
耐寒性としてはそれなりにあるとされています。落葉性なので、季節によって葉っぱは落ちます。草丈がこの花の全長のほとんどを占めていて20センチぐらいあります。そしてその上部に端が付きます。一本の花柄において数個の花を咲かせます。風が強い高原に咲いても、かなり上部な茎があるのでまっすぐに伸びています。
花もまっすぐ植えを向いて咲きます。雪が解けてくると徐々に茎から小さい葉っぱをつけるようになります。葉っぱは羽状葉になります。花を咲かせたあとは実ができます。マメ科とのこともあって小さなえんどうのような果実を付けます。やはりえんどうのような種がその中に入っています。冬に関してはそのまま生えているよりも休眠している状態と言えるでしょう。
-

-
ポテンティラの育て方
この花の科名としてはバラ科になります。キジムシロ属、ポテンティラ属ともされています。あまり高くまで成長することはなく、低...
-

-
観葉植物を育ててみよう
初めての人でも比較的簡単に栽培することが出来る観葉植物の育て方について記述していきます。まず、観葉植物と一口に言っても、...
-

-
ペチュニアの育て方
ペチュニアは花がタバコの花に似ているためブラジルのグアラニ語で タバコを意味するの「ペチュン」という言葉が花の名前の由来...
-

-
コエビソウの育て方
コエビソウはメキシコを原産とする植物です。キツネノマゴ科キツネノマゴ属の植物で、常緑の多年草でもあります。低木ではありま...
-

-
アフェランドラ・スクアロサ‘ダニア’(Aphelandra ...
アフェランドラという植物は、熱帯や亜熱帯地域が生息地で、亜熱帯アメリカが主な原産地でその他にもブラジルなどに生息していま...
-

-
ヤマホタルブクロの育て方
キキョウ目キキョウ科キキョウ亜科ホタルブクロ属の植物で、花の色は紫色や白い色のようです。学名はカンパニュラ・プンクタータ...
-

-
リンコスティリスの育て方
リンコスティリスはラン科の植物ですが、生息地は熱帯アジア地方に分布しています。主にインドやタイ、マレーシア、中国南部が原...
-

-
クリスタルグラスの育て方
クリスタルグラスの原産地は南アフリカです。クリスタルグラスは植物学者によってフィシニア属のカヤツリグサ科に分類されました...
-

-
フウランの育て方
原産地は日本(関東南部・以西)、朝鮮半島、中国南部です。ラン科のフウラン属に分類され、日本では江戸時代から園芸植物として...
-

-
観葉植物として人気のシュガーバインの育て方
シュガーバインは可愛らしい5つの葉からなるつる性の植物です。常緑蔓生多年草で育て方も簡単なので初心者の人にもおすすめです...




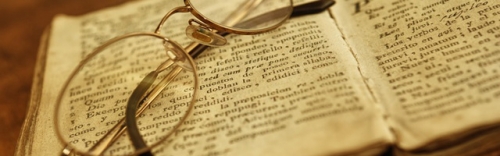





この植物の特徴として、バラ目、マメ科、オヤマノエンドウ属になります。園芸上においては山野草として区分されます。生え方は多年草ですから、冬でも枯れることなく残ります。草丈は大きい物で25センチ位です。開花する時期としては、4月下旬くらいから6月ぐらいになります。