コルディリネ(Cordyline)の育て方

コルディリネの育て方
耐陰性がある品種もありますので、そういった品種であれば部屋の中の明るさでも問題はありません。ただし真夏の直射日光にあたりすぎると葉の色彩が落ちてしまいます。真夏は明るさがある日蔭がベストです。
そういった場所が確保できない場合には、遮効率が50%程度の日焼けネットを貼って、その下に置くようにしましょう。部屋に中の場合には、カーテン越しの光や、窓からの距離を取るなどするとよいでしょう。温度に関しては、さほど気にする必要はありません。
真夏は明るい日蔭、それ以外の季節は日にたっぷり当てる、これが基本です。水やりは、土が乾いたら与えるとし、まだ土がしまっている状態で水やりを繰り返せば、根ぐされを起こしてしまうこともあります。冬は頻繁に水やりを行う必要はありません。
3日に1回ほど様子を見て、乾いていたら与える程度で大丈夫です。乾いている程度が冬は根ぐされの心配がありません。肥料は成長が著しい5月から9月あたりは液体肥料を週1程度で与え、固形肥料は2カ月に1度程度。その時期以外には、特別与えなくても大丈夫です。
鉢植えでも庭植えでも、水はけと水持ちが良い土壌を好みます。葉にほこりがたまりやすいといった特徴があります。水分を含ませたティッシュや柔らかい布で葉の表面を拭いてあげるとよいでしょう。水道水を葉の上からかけると、
水道水の成分が乾いた時に白く残ってしまいます。見た目が良くありませんので葉に掛けないようにしたいところではありますが、そうするとハダニの繁殖を防ぐことが難しくなります。マメに葉を拭くようにするか、殺ダニ剤を使うかの選択になります。
栽培上の注意点
庭植えの場合にはさして注意も必要ありませんが、鉢植えの場合には、すぐに根が育って、鉢の中が太い地下茎が巻いてしまいます。根詰まりを起こしてしまえば、新しい葉は出てきません。葉の色彩が悪くなり、下の方から徐々に葉も落ちてしまいます。
そういったことを避けるためにも、植え替えは2年に1度を目安として行いましょう。植え替えには5月から7月が適しています。鉢から抜いて回りについている土を3分の1程度落とし、伸び過ぎている根を3分の2程度にまで切ります。
新しい土を入れた鉢に植え替えます。植え替えた後しばらくは成長も遅くなりますが、この時期は陽のあたる場所は避け、明るめの日蔭で管理します。新しい葉が出てきたあたりで、通常通りの日が当たる場所に移しても差し支えありません。
コルディリネの種付け
コルディリネは種付けを行わず、挿し木や取り木で増やします。挿し木が比較的簡単です。適している時期は5月から7月。点目の部分を7枚から10枚程度葉が付いているところでカットします。それをそのまま鉢の土に挿し、管理します。
もし葉が邪魔になるようであれば、抑えつけないように配慮しながら輪ゴムで止めてもかまいません。直射日光が当たらない明るい場所を選びましょう。根が出るまでには1カ月以上かかります。根が出てくれば通常通りの明るい場所に移します。
この時に葉を束ねていたのであれば、外すのを忘れずに。下の葉が落ちて上の方だけに葉が付いてしまってスタイルが悪くなってしまったコルディリネは、点目を挿し木にし、葉が付いていない茎は節ごとに3センチほどカットして茎伏せを行うと、また新たな根や芽がでます。
茎伏せは土に半分の径が埋まるような格好で寝かせて行います。生命力が大変強い種ですので、あまりマメに面度を見なくても、しっかりと根が出てきます。どんどん増やすことができ、それもコルディリネを育てる楽しみの一つです。
コルディリネの病気や付きやすい害虫
コルディリネはハダニが付きやすい植物です。ハダニが付いてしまうと葉の色彩が落ち、成長も悪くなりますし、新しく出てきた葉につけば、それが奇形を起こしてしまうこともあります。葉の様子がおかしいと感じた時には病気を疑う前に、ハダニの可能性を考えてみましょう。
ハダニは水を嫌いますので、乾いている時に霧吹きで水をかけるなどすれば、かなり予防できます。ただし水道水の成分が乾いた時に白く残ったりしますので、見た目が悪いと感じるなら、殺ダニ剤の散布になります。カイガラムシが付いてしまった時には、なかなか薬も効きません。歯ブラシなどで落して駆除するといった方法が確実です。
ナメクジが葉を食べてしまうこともあります。隠れやすいのは葉と葉が重なっている部分や、葉の付け根です。葉が食べられている様子があれば、そういった場所から探してみましょう。見つけたら駆除します。ナメクジの誘殺剤が市販されていますので、そういったものを使うのも有効な手段です。
コルディリネの歴史
熱帯性の樹木であり、東南アジアやオーストラリア、またニュージーランドなどを原産国として、約20種が分布しています。ハワイやポリネシアも生息地とし、コルディリネ・テルミナリス・ティーはハワイアン・グッドラック・プラントと呼ばれています。
神聖な木と考えられ、古くから伝わる儀式に用いられたり、フラダンスの腰みのに使われたりしています。食用としても使われています。この「グッドラックプラント」の名前が日本では「幸福の木」と訳されて紹介されましたが、
実は日本に持ち込まれたのはドラセナ属のD. fragransであり、コルディリネ・テルミナリス・ティーではありません。誤認されたまま、「幸福の木」として定着していました。実際に「幸福の木」と呼ぶならば、コルディリネ・テルミナリス・ティーでなくてはならなかったのです。
コルディリネの特徴
属名は「コルジリネ」「コルディリーネ」とも言われていますが、これがギリシャ語のコルディレから来ています。コルディレは棍棒といった意味ですので、その名の通り根茎は太く棒状です。多くが途中で枝分かれをしない単幹種です。
日本名は千年木(センネンボク)です。笹に似た細長い楕円形の葉を持ち、1メートルから3メートルに育つ低木です。園芸品種は葉の色を楽しむものが多く、赤紫に蛍光赤色が縦に入るアイチアカ、濃いグリーンを赤紫で縁取るレッドエッジ、薄い緑にピンクや赤、薄黄色といった模様が見られるトリコロールといったものが人気があります。
寄せ植えによく用いられいるナナ・コンパクタは、高さが抑えられた品種です。その反対に庭植えなどに用いられる大型の品種もあり、ニュージーランド原産のアウストラーリスは高さが10メートルまで育ち、同じくニュージーランド原産のインディビーサは8メートル、
オーストラリア原産のストリクタは少々低く、2メートルから3メートル程度に育ちます。それぞれの高さに応じて葉も大きく、長く育ちます。アウストラーリスの葉は1メートルほどの長さにまで育ち、インディビーサは1.5メートルほどで肉厚、ストリクタは50センチ程度で幅広です。
ストリクタには葉に白筋が見られるスバルや若い葉が紫色に染まるグランディスといった園芸品種も持っています。原産地から見ても耐寒性は弱く、屋外で育てる場合には、コルディリネ・アウストラリスのような寒さに比較的強いとされているものでも、5度を下らない気候であることが必要です。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:バオバブの育て方
タイトル:ゲッキツの育て方
タイトル:アレカヤシの育て方
-

-
手まりかんぼく(スノーボール)の育て方
手まりかんぼくとは、名前からも分かるように手毬のような花が咲く肝木(かんぼく)です。原産地は朝鮮半島だと言われています。...
-

-
八重咲きコンロンカ(ハンカチの花)の育て方
またハンカチの花という名称もあり、遠くから見るとハンカチがたくさん舞っているように見えるのでハンカチの花と命名されたとい...
-

-
ブリメウラ・アメシスティナの育て方
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、南ヨーロッパを原産とした鉱山植物です。花の宝庫と呼ばれ大自然あふれる山脈、ピレネー山脈...
-

-
ミズナの育て方
水菜の発祥地は静岡県小山町阿多野といわれており、JR御殿場線、駿河小山駅近くに水菜発祥の地を記した石碑が立っています。静...
-

-
アマドコロの育て方
アマドコロは、クサスギカズラ科アマドコロ属の多年草のことを言います。クサスギカズラ科は、クサスギカズラ目に属する単子葉植...
-

-
植物の育て方について
今年はガーデニングで野菜を育ててみようと思っている初心者の方におすすめな野菜の1つがプチトマトです。今まで植物を育てたこ...
-

-
カタセタムの育て方
カタセタムの科名は、ラン科、属名は、カタセタム属になります。その他の名称は、クロウェシアと呼ばれることもあります。カタセ...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
チャ(茶)の育て方
この植物は、ツバキやサザンカのツバキ科で、多年草の植物になります。緑茶も紅茶も烏龍茶も同じチャノキの新芽を摘んで加工した...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...





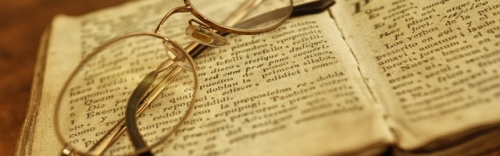





屋内で育てる場合には鉢植えになりますが、葉の色彩を落とさないためにも、日に充分当ててあげることが必要です。5度を超え、霜が降るような心配がない時期であれば、屋外に置いてもよく育ちます。